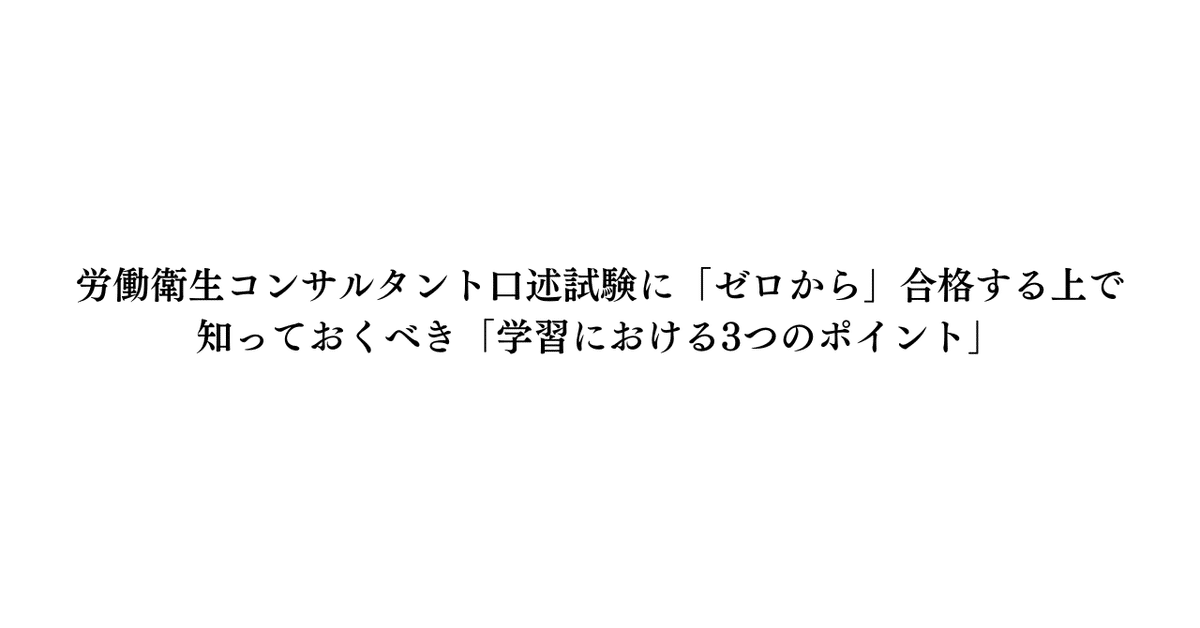
労働衛生コンサルタント口述試験に「ゼロから」合格する上で知っておくべき「学習における3つのポイント」
労働衛生コンサルタント口述試験の勉強を「そろそろ始めようかな」と思ったところで、初学者ですと「で、どこから手をつければいいんだ?」となるのではないでしょうか。
私が試験を受けた当時、断片的に口述試験の「過去問」を掲載しているサイト、ブログなどもありましたが、「で、結局、何を勉強したらいいのよ?」ということがなかなか分からず、まずはそこを調べるところからスタートしました。
今回は、そんな「労働衛生コンサルタント口述試験では、何を、どこまで、どのように勉強を進めたらいいのか」という3つのポイントについて書いてみたいと思います。特に初学者・産業医の実務未経験といった方で、試験をこれから控えていらっしゃる方にお読みいただければ幸いです。
ポイント1 試験範囲について
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十四条2項には、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の口述試験における「科目」として、「一 労働衛生一般」および「二 健康管理」と記載されています。
なんともシンプルな内容ですが、この「労働衛生一般」と「健康管理」とは、筆記試験についての記述で、次のような範囲であると規定されています。
・労働衛生一般
労働衛生概論 健康管理の概論 労働生理概論 作業環境管理の概論 人間工学概論 化学物質の管理 作業管理の概論 労働衛生保護具 労働衛生教育 労働災害の調査及び原因の分析 安全管理概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
・健康管理
労働生理学 産業心理学 労働衛生学 健康診断及び面接指導等並びにこれらの事後措置 作業環境の管理方法 作業方法の管理 健康の保持増進対策 救急処置 快適な職場環境の形成
となっています。
少し学習の進んだ方ですと、上記を見て次のようなことを押さえておく必要がある、とおわかりになると思います(初学者でまだ全くもって勉強が進んでいなかったら、チンプンカンプンで当然ですので、サラリと目を通すだけで結構です)。
「労働衛生一般」
・作業環境管理、作業環境、健康管理(いわゆる労働衛生の3管理)
・リスクアセスメント
・化学物質による健康障害防止対策(SDSなど危険有害性化学物質情報の伝達、リスクアセスメント、化学物質へのばく露防止対策、新規化学物質の有害性調査)
・呼吸用保護具などの労働衛生保護具、換気装置
・作業環境測定の方法、評価、事後措置、管理区分
・許容濃度と管理濃度
「健康管理」
・職業性疾病予防対策(石綿、粉じん、電離放射線、酸素欠乏症、高気圧障害、騒音障害、振動障害、職場における腰痛予防対策、熱中症予防対策)
・メンタルヘルスケア(4つのケア、一次予防、二次予防、三次予防、ストレスチェック制度、メンタル不調者への対応・復職支援)、THP
・過重労働による健康障害防止対策
・職場における感染症対策、BCP
・受動喫煙防止対策
これらすべてを学ぼうとすると、『労働衛生のしおり』で言いますと(これがいわゆる「教科書」になります。まだご購入していないようでしたら、ぜひ買ってください)、160ページほどの内容になります。
あと、「統計」データおよび法令問題も出題される可能性があり、さらに分量としては増えるということになります。
かなりの広範囲であり、なおかつ理解して覚える量も多いです。初学者・未経験者ですと「どこから手をつけるべきか…」「どこを重点的に覚えるべきか…」と途方に暮れてしまうと思います。
そこで、どのように学習を進めていけば最もコスパがいいのか、その点について以下では解説したいと思います。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
