
金融アナリストから学ぶ資産運用の鉄則
★高齢期の資産運用について3つの段階
金融アナリストの「山崎元(はじめ)」さんという方がいらっしゃいました。
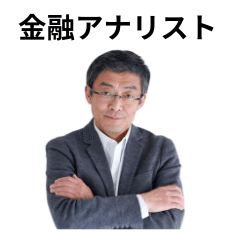
残念ながらお亡くなりになりましたが、
とてもわかりやすい解説で、しかも金融アナリストでありながら、
顧客本位の優しい対応が魅力的でした。
その山崎さんは、ある講演会で
高齢期の資産運用を3つの段階と
3つの原則について、お話しされていたことがありました。
まず、高齢期を3段階に分けます。
高齢準備期(40歳~60歳)、
高齢前期(60歳~75歳)、
高齢後期(75歳以上)の3段階です。
そして、それぞれの段階で
やるべきことを示していただいていました。
たとえば、高齢準備期(40歳~60歳)では、
金融リテラシーを高め、資産形成を始めながら、
リタイア後の生活立案、
セカンドキャリアの準備をしていくのです。
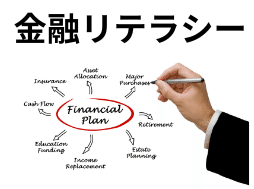
これについては、
2021年5⽉ファイナンシャル・プランニング技能検定2級の「個人資産相談業務」で、以下の問題が出題されています。
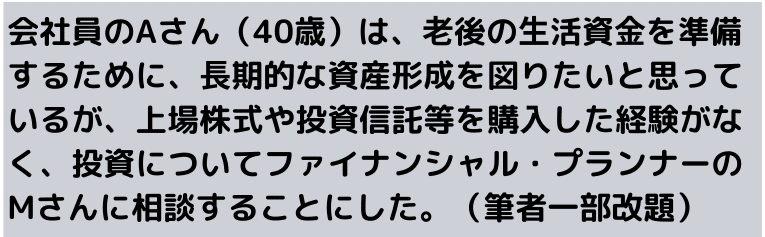
ファイナンシャルプランナーの試験では、
40歳の会社員がよく登場します。
つまりは、山崎さんのおっしゃるように、
40歳は資産形成において、
どうしても始めておかなければならない年齢だと
示唆しているということでしょう。
実際に、30代の方でも、
将来に向けた資産形成について、
相談にいらっしゃる方もいます。
資産形成に早すぎるということはありません。
そして、60歳~75歳の高齢前期では、
蓄積してきた資産の運用と取り崩しを始めます。
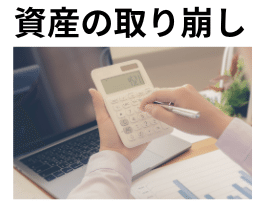
75歳以上の高齢後期では、
自分で資産を運用できなくなったときのことを考え、
次の世代へとつないでいくということです。
これが、高齢期の資産運用について3つの段階です。
★高齢期の資産運用について3つの原則
あと、3つの原則についてですが、
山崎さんは資産運用の原理原則は
生涯を通して変わらない、とおっしゃっています。
その3原則とは、
「人間のリスクに備える」
「計画的に損をせずに資産を取り崩す」
「正しい運用法を終生続ける」の3つです。
一つ目の原則、「人間のリスクに備える」とは、
どのような資産運用でも、
わからないことには手を出さないこと。
とくに「無料で相談」「親身に相談」
をしてくれる人に対しては、警戒すること。
二つ目の原則、
「計画的に損をせずに資産を取り崩す」
についてですが、
たとえば、分配金、配当を受け取れるようにしている方がいます。
できれば、
金融機関に分配してもらうのではなく、
自分で計画的に取り崩す方がいいのです。
または、必要な時に必要な額を取り崩すことです。
なぜかというと、
分配してもらわず再投資してもらった方がいいですし、
必要なときに自分で取り崩した方が手数料が少なくすみます。
小さなことかもしれませんが、
できるだけ損をしない、
ということは原則であると考えてください。
3つ目の原則の
「正しい運用法を終生続ける」については、
そもそも「正しい運用法」とは何かという問いにぶつかります。
山崎さんは、正しい運用法を、
「守りではなく、適切なリスクをとること」と述べています。
守りは、攻めがあってはじめて
機能するということなのでしょう。
たとえば、1000万円を単に銀行に
預けるということは、今や「守り」とはいえません。
銀行に円で預ける、ということは、
円に投資していることと同意ですので、
円安に向かえば1000万円はその価値が下がっていきます。
そうではなく、NISAで積み立てておく、
米ドル建てや米国国債を購入するなど、
「適切なリスク」を取り、お金に働いてもらうのです。

このようなことを親子で考えながら、
親子で資産を運用していくことが大切です。
山崎さんは、親御さんの資産に年を取らせないよう、
サポートすることが支援になると話しています。
とはいえ、資産の話はかなり繊細なので、
親御さんとのコミュニケーションを深めながら、
少しずつゆっくりと進めていくのがいいでしょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
よろしければ下記のサイトもご覧ください。
●X(旧Twitter):https://x.com/gracia4041
●Instagram:https://www.instagram.com/gracia_okane/
●当社の新刊
