
<第4回>超初心者が作文を練習するには何から始めれば?【文章の書き方入門講座】
こんにちは。戦略マスター頼朝です。
今回は「文章を書きたいけれど、いざ書くとなると書けないんだよなぁ」とお悩みの方に向けて、お勧めの練習方法をご紹介します。
お題(テーマ)が与えられても、いざ原稿用紙やスマホの画面、あるいは、パソコンの画面に向かったところで、なかなか言葉が出て来ませんよね。
でも、それはむしろ自然なことなので、心配はいりません。
せっかく「文章を書いてみたい」という素敵な思いを抱いたのですから、諦めずにやってみましょう。
戦略マスター頼朝@文章術でブランディング/リーダーシップ論(@6VQGPJH3FHYoZn6)さん / X (twitter.com)

私は長年学習塾の教室長をやってきました。
そのキャリアの中で小中高生向けに英数国理社の主要5教科を教えてきましたが、作文や小論文については論文指導講師として小中高生及び大学生、社会人の方を対象に10,000通を超える添削指導をしてきました。
その経験から申しますと、最初は多くの方が文章を書くことに苦手意識を持っていらっしゃいます。
しかし、正しい文章の書き方を学んで練習していくうちに、文章を書くのが楽しくなっていく人もまた多いです。
そのため、「文章を書いてみたい」という素敵な思いを大事にして取り組み続ければ、誰でも文章を書けるようになります。
それでは行ってみましょう❗️
1.超初心者向けの作文練習法とは?
そもそも文章を書くには、次の4つの要素が必要です。
◯お題(テーマ)
◯テーマに関連する題材(出来事・見聞きした事実)
◯自分なりの意見(結論 *学びや気づきも含む)
◯理由や根拠
これらの文章に必要な4つの要素が入っていれば、それは立派に文章として成り立ちますし、きちんと内容が伝わります。
また、伝えたい内容が読者にとって分かりやすくなるように、4つの文の要素をどういう順番で並べて書くかを考えることを「構成(文章の内容の組み立て)」と言います。
相手に伝わりやすいように構成をきちんと考えることも、文章を書くための作業として大切なことです。
なお、この構成をどのようなものにするかは、文章の目的や伝える相手によって異なります。
構成のやり方については、別の記事(第7回・第8回・第9回)で詳しくご説明しています。
しかし、「文章に必要な4つの要素は分かったけれど、構成まではよく分からないよ。」と思われる初心者の方は多いと思います。
大丈夫です。心配は要りません。
文章に必要な4つの要素が入っていて、しかも、自然に構成までできてしまうタイプの文章があるからです。
それこそが作文練習の第一歩としてお勧めしたい「手紙文」です。
超初心者の段階では、「文章を書く」=「手紙文を書く」と考えてください。
手紙文には文章を書くのに大切なことが全て含まれているからです。
「誰に」「どんな用件を伝えたいか」がはっきりしていることが伝わりやすい文章を書くためのポイントですが、手紙文はこれらをイメージしやすいです。
つまり、
◯「誰に」=伝えたい相手
◯「どんな用件を」=伝える目的・内容
がはっきりしていることで、
文章に必要な4つの要素はもちろんのこと、構成も自然な流れでできるようになり、相手に伝わりやすい文章になるのです。
皆さんも、ご家族やお友達にメールやLINEなどでメッセージを送る時には、伝えたい相手と目的・内容がはっきりしているだけに、書くべき文章の内容も思い浮かべやすいと思います。
逆に、伝えたい相手と伝える目的・内容がはっきりしていないと、どんなに書き慣れた人でも文章を書きにくいのです。
さらには、手紙文には一定の書き方の型があるため、その型にのっとって書けば、構成についてあれこれと悩まなくても済みます。
そのため、超初心者のうちは、一定の型の通りに書けばすらすらと書ける手紙文の練習から始めるのがちょうど良いでしょう。
もちろん、厳密に手紙文の型の通りに書かなくても良い場合もありますが、超初心者のうちは型に合わせて書けば文章が成立してしまうメリットを活かしましょう。
以上より、超初心者の方が文章を書く練習をするには、手紙文を書くことから始めるのがお勧めです。
まずは手紙文を書く練習をすることで、伝えたい相手と何を伝えたいかをはっきりさせるための作文のコツを身につけていきましょう。
かなり文章が書きやすくなるはずです。

2.手紙文の書き方
2-1.「誰に」宛てて手紙を書くかを決める
手紙文を書くには、まずは「誰に」宛てて手紙を書くのかを決めましょう。
自分のメッセージを伝えたい相手がいるからこそ、伝えるべき内容を具体的にイメージできるようになるからです。
そして、伝えたい相手を決める時には、なるべく身近な人を対象にするのが良いでしょう。
父や母、おじいちゃんやおばあちゃん、あるいは、一番の親友でもいいです。
伝えたい相手が身近な人であればあるほど、伝えたい内容も思い浮かべやすくなります。

2-2.伝えたい内容(メッセージ)を決める
伝えたい相手が決まったら、次に、その相手に対して一番伝えたい内容(メッセージの中心点)を決めましょう。
相手に伝わりやすい文章を書くためには、結局何を一番言いたいのかをはっきりさせることが必要です。
自分だけが内容を分かっているのでは伝わりません。
メッセージの中心点は何なのかが相手に分かるように書く必要があります。
例えば、ある情報とそれに関する自分の気持ちや意見を伝える場合であれば、
◯いつ
◯誰が
◯どこで
◯何を
◯どういうわけで
◯どうしたか
◯どうしたいか
◯どうしてほしいか
などをはっきりさせて、相手に伝えたいものです。
また、あれもこれもとたくさんメッセージを詰め込んでしまいますと、かえって伝えたい内容がぼやけてしまって、相手からすれば一番言いたいことは結局何なのかがよく分かりません。
したがって、手紙文を書くポイントは、伝えたいメッセージの中心点を明らかにして文章を書くことです。
これができるようになりますと、将来的には、伝える相手が一人の場合でも大勢の場合でも、伝わりやすい文章を書けるようになります。

2-3.手紙文の型にのっとって文章を書く
前述のように、手紙文の良いところはあらかじめ一定の型があることです。
つまり、文章の組み立てである構成が型として既にありますので、それにのっとって書いていけば、支離滅裂な文章になることはほぼありません。
超初心者の方であっても、手紙文の型通りに書いていけば文章として成立しますので、とても書きやすいと思います。

それでは、手紙文の型とはどのようなものでしょうか?
手紙文の型は、大きく分けて3つの部分から構成されます。
これは、用事があって相手の家を訪問した時の会話の流れと同じなので、イメージしやすいと思います。
①前文(「はじめ」にあたる部分)
いきなりメッセージの中心点から書き始めてしまいますと、相手にとっては唐突に感じますので、まずは挨拶から書き始めるのが通常です。
・季節の挨拶
・相手の様子(元気かどうか)をたずねる
・自分の近況(最近の出来事や体調の良し悪し)を伝える
前文はいわば、出会いの挨拶の役割を果たす文章と言って良いでしょう。
(例1)小学4年生の子が書いた手紙
だんだん夏が近づいてきて、暑い日が増えてきましたが、おばあちゃんはお元気ですか。
私は転校した学校の生活にも慣れてきて、元気でやっています。
②本文(「中」にあたる部分。主文)
前文で挨拶を済ませてお互いの距離が縮まったところで、いよいよ用件を伝えるために本文を書いていきます。
相手の家を訪問する時も、何かしら伝えたい用件があるからこそ伺うわけですよね。
したがって、本文では、相手に一番伝えたい内容を書きます。
前述した通り、本文を書くポイントは、伝えたいメッセージの中心点を明らかにして文章を書くことでしたね。
そのため、本文では、メッセージの中心点を明らかにするために、文章に必要な4つの要素(テーマ、題材、結論、理由)を盛り込んで書くようにしましょう。
本文はいわば、相手に用件を伝える役割を果たす文章と言って良いでしょう。
(例2)小学4年生の子が書いた手紙
さて、今度の私の誕生日に、お父さんとお母さんがディズニーランドに連れて行ってくれます。
前からとても楽しみにしていたので、最近では一番うれしいです。
ディズニーランドに行ったら、色々な乗り物やパレードを見て面白い体験ができたらいいなと思っています。
そこで、おばあちゃんもぜひ一緒に来てほしいです。
忙しいとは思いますが、家族みんなでディズニーランドに行く方がもっと楽しめると思うからです。
もしよかったら、一緒にディズニーランドに行きましょう。
ただ、もしおばあちゃんが忙しくて来れないようでしたら残念ですが、それでもお元気でいてくれたらうれしいです。
私も学校の勉強や苦手なことができるように元気にがんばります。
③ 末文と後付け(「おわり」にあたる部分)
本文で一番伝えたいことを書き終えたら、手紙文の締めくくりとして結びの挨拶を書きます。
この手紙文の最後に結びの挨拶を書く部分のことを「末文」といいます。
用事があって相手の家を訪問し、一番伝えたい用件を伝え終えたら、何も言わずにそのまま立ち去ることはないですよね。
別れの挨拶の言葉を相手に伝えてから帰るはずです。
末文はいわば、「一番伝えたいことを伝え終えましたので、これで帰ります。お元気で。また会いましょう。」という別れの挨拶の役割をする文章です。
最後に、日付と差出人、相手のお名前(敬称)を書いて手紙文を書き終えます。
この部分のことを「後付け」と呼んでいます。
日付は、いつ書いた手紙なのかが分かるようにするために書きます。
差出人は、通常は自分の名前を書きます。
差出人に自分の名前を書くことで、その手紙を書いた人が自分であることを示し、かつ、それに対して責任を負うことを表明します。
相手のお名前は、この手紙が誰に宛てて書かれたものなのかをはっきり示すために書きます。
(例3)小学4年生の子が書いた手紙
これからもっと暑くなってくると思いますので、おばあちゃんも体を大切にしてくださいね。
それではまた、お元気でいて下さい。
◯年△月×日 あきより
おばあちゃんへ
以上ご説明してきましたように、手紙文には書くべき内容と順番の型が伝統的に決まっています。
したがって、手紙文の型の通りに書いていけば、相手に意味が伝わる文章を書くことができます。
文章を書き慣れない人にとっては、伝えるべき相手と伝えたい内容のイメージが湧きやすく、しかも、構成があらかじめ決まっている手紙文を書く練習をすることで、文章の書き方が無理なく上達していくでしょう。

3.他人が書いた手紙を参考にしてみる
「超初心者は手紙文を書くことから始めたら良いことは分かったし、手紙文の書き方も理解できたけど、まだイメージがわかない。」という人もいらっしゃるかもしれませんね。
手紙文の具体的なイメージを持つためには、他人が書いた手紙を参考に読んでみるのがお勧めです。

もちろん、他人の手紙を許可なく勝手に読むのはだめです。
ただ、過去の小説家や偉人などが書いた手紙は出版されていますので、まずはそれらを参考に上手い手紙の書き方を真似してみましょう。







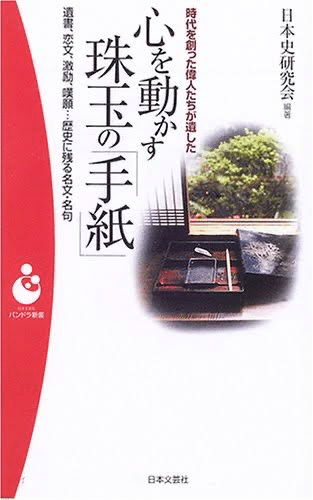

インターネットで検索しても、手紙の書き方と例文などが出てきますので、それも参考にしてみましょう。

どんな芸事もそうですが、文章の書き方が上達するには、上手い人の書き方の真似をして自分の文章に取り込むインプットが大切です。
色々な人の手紙の書き方を参考にしていく中で、「この人の手紙の書き方は好きだなぁ」と思うものが見つかったらしめたものです。
まずは、その人の手紙の書き方のどんなところが好きなのかを分析して、真似していきましょう。
そして、真似するだけでなく、少しずつ自分のオリジナルの味を加えていくようにすると、文章の上達も早いでしょう。
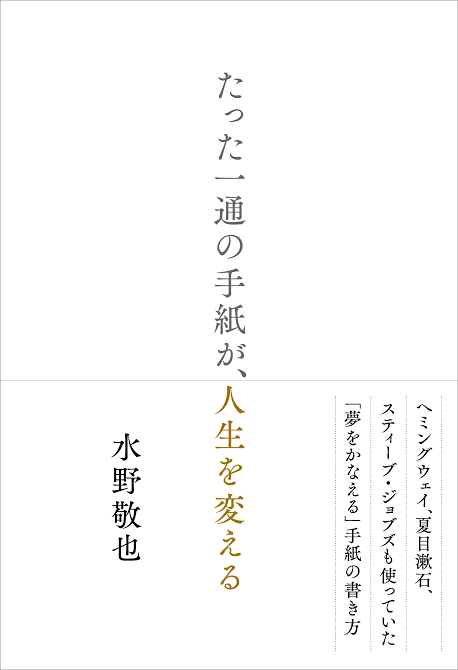

最後までお読みいただきまして、どうもありがとうございました。
今回の記事が、文章を書きたいという素敵な気持ちがせっかくあるのに、どういう風に書き方の練習を始めていけばいいのかが分からなくて困っている方のお役に立てたなら嬉しいです。
これからも、論文指導講師の経験を生かして、文章の書き方や書く習慣についてお役立ちできるような記事を書いていきたいと思います。
この試みに共感して下さる方は応援して頂けますととてもありがたいです。
それでは、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
戦略マスター頼朝
