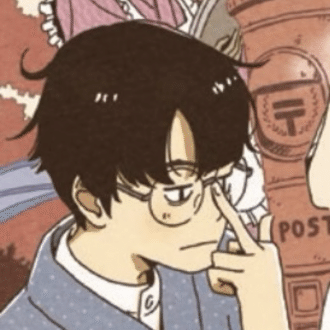note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第50話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。父親の周一の動向を探るため、周一を尾行することに。
声の正体は、門から顔を覗かせた太ったおじさんだった。
手ぬぐいを首もとにまき、しきりとひたいの汗をぬぐっている。白い半袖のシャツは汗でべったりとはりついていた。
一体、どう言いぬけようかと思案していると、制する間もなくバシャリが勝手に口を開いた。
「周一ですよ。周一の尾行ですよ」
尾行という言葉にたまげたのか、おじさんは目を大きく見開いた。
「尾行とは、ずいぶんとおだやかじゃないな。周一とは、誰のことだい?」
「周一を知らないのですか? 周一といえば、水谷周一ですよ」
「ああ、水谷さんのことかい?」
「ご存じなんですか?」
「ご存じも何も、水谷さんにはうちで働いてもらってるからな」
驚きのあまり思わず目をしばたたいた。
「働いてもらってるって……じゃあその工場は?」
向かいにある建物を指さすと、
「うちの工場だよ。俺は、あそこの社長だ」
おじさんは目を細めた。その声色にはかすかな自慢がにじんでいる。
「あんたらは水谷さんの何かね?」
どうしようか少しためらったが、わたしは正直に打ち明けた。
「わたし、水谷の娘なんです……」
おじさんは目を見張った。
「へえ、水谷さんにこんな大きなお嬢さんがいたのかい。あの人、仕事のこと以外、一切口を利かないから知らなかったよ」
警戒を解いたのか、途端に声色がやわらかくなった。
「水谷さんに用事かい? 呼んできてやろうか?」
「いえっ、あの、その大丈夫ですわ……」
あわてふためいたので舌がもつれる。その態度で何かを察したのか、おじさんが提案した。
「そうかい。じゃあ立ち話も何だから事務所に寄るかい? ここから歩いて数分の場所だから」
バシャリが飛びつくように言った。
「行きましょう。早くここから脱出しましょう。暑くてかないません」
「そうだな。今日は特別暑いからな」
おじさんはわらいながら手で顔をあおいだ。まっくろに汚れたとても大きな手だった。
以前工場だったところが手狭になったので場所を変え、今は事務所として使っていると、おじさんは歩きながら説明してくれた。
五分ほどして見えてきた事務所は板壁の平屋で、その前に、駄菓子屋でよく見かける大きめの縁台が置かれていた。
「中はちらかってるからお客さんとはいつもここでしゃべるんだよ」
おじさんは照れたように頭をかき、わたしたちに座るようにうながす。
「それに、こう暑くちゃ外のほうが涼しくてね」
と、おじさんはまた手ぬぐいで汗を拭くと閃いたように言った。
「そうだ。出前でかき氷でも頼むかい? ごちそうするよ」
「お願いします!」と、バシャリがかぶりつくように言った。わたしは遠慮しようかと考えたけれど、この暑さはたまらない。
お言葉に甘えて、一緒に頼んでもらった。
しばらくして出前もちがやって来た。おかもちからかき氷を三つとりだし、縁台に置く。山盛りのかき氷があらわれた途端、涼やかな気分になる。
「やっぱり暑いときはこれだ。さあ、二人も食べて」
おじさんはそのひとつを手にすると、早速食べはじめた。
「いただきます」と、バシャリがスプーンを手にとり、口に運びかけた寸前で急ブレーキをかけたようにその動作を止めた。わたしは目をぱちくりさせた。
「どうしたの?」
「危なく罠にかかるところでした」
と、バシャリは安堵の息をもらした。そして腹まきをとりだし、注意ぶかく身にまとった。
「腹まきを装着せずにこんなものを食べたらと考えるとぞっとします」
そしてかき氷を口に含み、その感激を吐き出した。
「これほど冷たい物質を安全に体内に吸収できるとは、腹まきの偉大さには頭が下がる思いですよ」
その奇妙な言い回しに、おじさんは面食らったようだ。無視してわたしもかき氷を一口食べた。氷の冷たさとみぞれの甘味で、疲れが嘘のように消えていく。
かき氷を食べ終えると、ようやく一息ついた。頃合いを見はからい、わたしはおずおずと尋ねた。
「あの……父はこちらで働いてるんですか?」
「ああ、そうだよ」
おじさんは手ぬぐいで口元をぬぐった。
「水谷さんの会社とうちは取引させてもらってるんだけど、六年前に水谷さんが、夜だけでいいから、うちで働かせてくれないか、と言ってきてね。
それからの付き合いかな。近頃は、家電の売れ行きがいいから、夜でも工場を動かさないと出荷が追いつかなくてね。水谷さんみたいに腕のいい人に来てもらえて大助かりだ」
と、快活にわらう。
「それにしても水谷さんも大変だよ。昼も夜も働き詰めだろ。休日も別の工場で働いてるって、うちのやつらが言ってたしさあ。まあ、いろいろ事情があるんだろうな……」
語尾を弱めると、おじさんはわずかに背中を丸めた。
喫茶店でお父さんを見たときの光景がよみがえる。あの女性に渡していた封筒……
わたしはぱっと立ち上がり、勢いよくお礼を言った。
「すみません。かき氷までごちそうしていただいてありがとうございました。ほらっ、もう行くわよ」
「もうですか? わかりました」
バシャリもしぶしぶ立ち上がり、腹まきの位置を調整した。
「あと、すみません。このことは……」
と言いかけたのを、おじさんが手で止めた。
「ああ、わかってるよ。水谷さんには内緒にしておくから」
「ありがとうございます」
わたしは深々と頭を下げた。
第51話に続く
作者から一言
縁台で食べるかき氷も昭和という感じがします。工場の近くに氷屋があって、出前でもってきてくれるという設定です。
周一は遊んでいたのではなく、夜も工場で働き詰めの毎日を送っていました。
いいなと思ったら応援しよう!