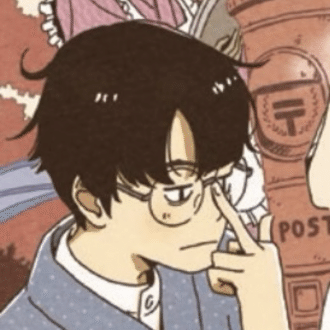note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第49話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。父親の周一の動向を探るため、周一を尾行することに。
銀行の仕事を終え、わたしは急いで北品川に向かった。すでに仕事帰りの人間がちらほら見える。
急がないとお父さんが会社を出てしまう、とわたしはさらに足を速めた。
中学校を通り過ぎると、企業の工場が建ちならぶ地帯に入る。やがて、お父さんの会社の工場が見えてきた。
木造二階建ての大きな工場だ。その周囲をぐるっと塀が囲っている。ちょうど終業時間らしく、門からはぞろぞろと作業服姿の人たちが出てきた。
あたりを見回すと、塀の一角にバシャリがいた。
帽子を目深にかぶり、身をかくしながら門を凝視している。その箇所だけ、別世界のように目立っている。
道行く人はバシャリを気味悪そうに眺めながら通り過ぎていった。
わたしはその背後から声をかけた。
「……一体、何をしてるのかしら?」
バシャリは振り向いた途端、ぱっと顔を輝かせた。
「おお、幸子遅かったですね。ですがご安心ください。周一はまだ出てきていませんよ」
「誰がそんな目立つ見張り方をしてって頼んだのよ。見つけてくださいって言ってるようなものだわ。
それに、その腹まきは絶対外してってあれだけ言ったでしょ」
つい、声が大きくなる。
周りの人たちがちらちらとわたしたちを盗み見ていく。恥ずかしさで目をふせると、バシャリが弁解するように言った。
「私も腹まきを外そうかと思ったのですが、すでに腹まきと私は一心同体、いわば切っても切り離せない関係へと進展したのです。
腹まきも、私とは一時も離れたくなさそうですし……」
「……いいから、外しなさい」
ささやくように、でも有無を言わせないように、目に力を込めた。
バシャリはぶるっと体をふるわせ、「はいっ! ただいま」と、腹まきを外した。わたしたちは門が見える電信柱の陰に身をひそめ、今か今かと待ち構えた。
その数分後、お父さんがあらわれた。門から出ると、駅の方向へと歩いていく。家以外の場所で見るお父さんの姿にわたしはごくりと唾を飲み込み、覚悟を決めて言った。
「……行くわよ」
緊迫した空気が伝わったのか、バシャリは神妙に頷いた。
お父さんは、人混みの中を歩き続けた。急いでいるせいかかなり早足なので、ついていくのがやっとだ。
なまぬるい風が体全体にまとわりつき、汗がふき出してくる。バシャリが耳元でささやいた。
「幸子、そんな速度では見失いますよ。足の短さが主要な原因だと推測されますが、回転率をあげれば、速度は上昇しますよ」
「大きなお世話だわ。わたしの足が短いんじゃなくて、あなたの足が長すぎるのよ」
わたしの二歩が、バシャリの一歩だ。何だかしゃくにさわる。
しばらく歩くと、あたりがにぎやかになる。赤ちょうちんが灯り、『酒の店』『大衆酒場』『小料理屋』と書かれた看板だらけになった。
すでにできあがったおじさんたちが、店前で座り込んでいる。ぷんと鶏が焼ける匂いがした。典型的な、飲み屋街だった。
やっぱり、お父さんは博打をやってるのかしら……
わたしの不安をよそに、お父さんはそのまま飲み屋街を通り過ぎた。だんだんと人通りも少なくなる。
右手に、各種研磨と書かれた建物が見えた。ずいぶんと町工場が多い地帯だ。こんな場所に賭場があるとは思えない。一体、どこまで行くんだろう。
何度か角を曲がると、お父さんはつきあたりにあったトタン屋根の工場へと入っていった。
板ガラス越しに、明かりが煌々と地面を照らしている。夜にもかかわらず、まだ作業中のようだ。
プレス機などの機械音が響き、油の臭いが空気に漂う。東京芝田電気という表札の下に、電球と冷蔵庫のイラストが描かれた看板が見えた。
「周一は、ここで何をしてるのでしょうか?」
わたしもさっぱりわからなかった。バシャリが帽子を深くかぶった。
「では、わたしが中の人々に訊いてきましょう」
「馬鹿なこと言わないで。お父さんに気づかれたらどうするのよ」
「じゃあ、どうするのですか?」
「……ここで待つしかないわ」
バシャリが露骨に嫌そうな顔をした。
「ええっ、こんなところでですか?」
「しかたないでしょ。我慢してちょうだい」
バシャリはぶつぶつと不満を述べたが、わたしは耳にふたをしてやり過ごす。
一時間が、経過した。だが、お父さんが出てくる気配はない。
「お腹がすきました……」と、バシャリはとうとうその場に座り込んだ。
「ちょっと、そんなところに座らないで」
注意したそのときだ。
「あんたらこんなところで何してるんだ?」
背後から野太い声で話しかけられたわたしたちは、びっくりして飛び上がった。
第50話に続く
作者から一言
昭和の飲み屋街の資料を見ていたんですが、いわゆる赤提灯の店が『大衆酒場』と暖簾に書いているのが面白かったです。大衆という言葉って、現代ではあんまりいい言葉じゃないじゃないですか。当時の人たちはさほど気にしていないってことなんでしょうか。
いいなと思ったら応援しよう!