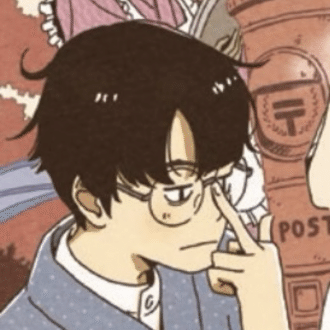note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第73話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。亡くなった母親の誕生日会をバシャリが開催する。
「私が教えたのですよ」
バシャリが代わりに答えた。
「近頃、幸子の感情色が暗いことに気づきました。幸子はフタが閉じているので、普段は感じませんが、仕事のことを尋ねたときだけ、暗い感情色が噴出したのです。
これは仕事上で重大な問題が発生したのだろうと思い、幸子の銀行に原因を探りに行きました」
「銀行に行ったの?」
「ええ、そこで西園が、幸子は銀行を辞めたと教えてくれました。
銀行の仕事が嫌いだとは知っていましたが、幸子の性格から辞めることはないと判断していたので意外でした。余程のことがあったんですね」
バシャリが一人頷いた。あなたのせいで辞めたのよ、という言葉が喉元まで出かかったが、それを何とかおさえてから訊いた。
「あなた、辞めた理由は訊かなかったの?」
「はい。西園は教えてくれませんでした」
おそらく西園さんが気を利かせてくれたんだろう。本当にありがたい先輩だ。
「そこで周一にすべてを伝えました。幸子が銀行を辞めたことや、杉本学園に興味を持っていることも。
すると周一がミシンを直すことを提案したのです」
お父さんが静かなまなざしでわたしを見つめ、おもむろに封筒を手渡した。百合子さんが返してくれたお金だ。
「この金はおまえが使いなさい」
「そんなの無理よ」
あわてて封筒をつき返した。これは、お父さんの人生のすべてだ。そんな大切なものを使えるわけがない。
でも、お父さんは封筒をわたしの手に押し戻した。手の甲にがさがさした感触が伝わる。お父さんの手だ。
「静子が死んでからはおまえがこの家を支えてくれた。これはおまえが稼いだ金と同じだ。
これからは俺の給料でおまえたちを養える。夜の工場も辞めて、これからはおまえと健吉と一緒にいられる時間を増やすつもりだ。
洋裁の世界に興味があるのなら、この金を学校の授業料に使いなさい」
「でも……」
希望から目をそむけ、ただひたすら耐え続けることが、わたしにとって生きるということだった。
いつの間にか、そうすることに何の抵抗も感じなくなっていた。だから突然それから解き放たれても、ただうろたえるばかりだ。
そのとき、バシャリがおだやかに語りはじめた。
「幸子、以前私が星野にもうすぐ答えは見つかりますよ、と言ったことを覚えていますか?」
わたしは頷いた。「ええ、覚えてるわ」
「あれは星野だけに言ったのではありません。幸子、あなたにも言ったのですよ」
「わたしに?」
「そうです。星野は導かれるままに小説の世界に出会いました。
そして、幸子。あなたは洋裁の世界に出会ったのです。ミシンを踏む幸子からは黄色の感情色がふき出していましたよ。
ぜひ、杉本学園で洋裁を学びなさい」
まだ、ふんぎりがつかなかった。お父さんがぽつんと言った。
「ーーお母さんもきっとそれを望んでる」
ふいに思い出した。お母さんが鼻歌を口ずさみながらミシンを踏んでいたとき、感極まったようにこう言った。
「お母さんも学生だったら洋裁の仕事がしたかったわ」
わたしに語りかけたのではなく、わたしと同じ歳だったころの、過去の自分に話しかけるような口調だった。
浮き立つようなお母さんの背中を眺めながら、わたしも同じ気持ちを抱いた。それは日々の生活の中でほこりをかぶり、なくしたことすら忘れていた感情だった。あの想いがゆっくりとよみがえってくる。
その気持ちが消えてしまわないように、そっと胸に手をあてて、わたしは目を伏せた。
「……わたし、やってみるわ」
バシャリが感激の声をあげる。
「そうですか。素晴らしい。星野に続き、今日は幸子の旅立ちの日ですよ。さあ、ビールです。
今日は周一の稼ぎで、朝までビールを痛飲することにしましょう」
と、ぐびぐびビールを飲んだ。健吉が珍しくきゃっきゃとはしゃぐ。その様子を見て、バシャリが何かを思い出したように、
「そうだ。健吉、あれがあるでしょう」
と、健吉に目配せした。途端に、健吉が気恥ずかしそうにうつむいた。
「ほらっ、健吉」
バシャリがうながすと、ようやく覚悟を決めたのか、一枚の紙をわたしにさし出した。
それは、わたしの似顔絵だった。緑のワンピースに身を包んだわたしが、にこにことわらっている。そして、幼い字でこう書きそえられていた。
『おねえちゃん、いつもありがとう』
そのたどたどしい文字が胸にしみ込み、目の奥がじんと熱くなった。ほら見たことかと言わんばかりに、バシャリが健吉に向きなおった。
「どうですか健吉、私の言った通りでしょう。あなたの似顔絵は贈答品に最適ですよ。
この幸子の表情が、いい証拠です。気難し屋の幸子が、感激のあまり声も出ませんーー」
「もうっ、黙っててよ」
涙がぽろりとこぼれた。絵がじわっとにじんだので、いそいで拭きとる。せっかく健吉がくれた絵が台無しだ。
でもーー涙が止まらない。
バシャリがおどけた口調で言った。
「幸子、泣いてますか。いいですか。涙が止まらないときは上を向くといいですよ。
涙がこぼれません。これはアナパシタリ星人のおばあちゃんの知恵ですよ」
「もう黙ってって言ってるでしょ。何よ、何よ……みんなしてわたしを泣かせて……もうっ、知らないわ」
ぷいと顔をそむけたけれど、涙は次から次へとあふれた。
最近、泣いてばかりだわ……
なかば呆れながら、わたしは泣き続けた。
16
ミシンを踏む足を止め、針をゆっくり上げる。バシャリが飛びつくように訊いた。
「幸子、できましたか?」
「ええ、できたわ」
わたしは、新品の腹まきをバシャリに手渡した。らくだ色の腹まきに『バシャリ』と大きく刺繍が入っている。
素早く身につけると、バシャリは大げさに身をふるわせた。
「なんと優雅で繊細な腹まきでしょうか。これならば、冬にかき氷を食べてもお腹への災難を阻止できるでしょう。
まさに鉄壁の防護です。幸子は、ますます腕をあげました」
「そう……良かったわね」
ミシンを直してから何枚目の腹まきかわからない。腹まきを作る腕だけが格段に上達した気がする。
ミシンの腕があがるのはいいが、腹まき専門のデザイナーになった覚えはない。
バシャリが縁側に座り込んだ。二月も末になったのに外はまだ肌寒く、庭の樹々もまだ冬めいていた。わたしは火鉢を置き、その隣に腰を下ろした。バシャリが何気なく尋ねた。
「幸子、もうお仕事は慣れましたか?」
「ええ、おかげさまでだいぶ慣れたわ」
わたしは、すでに新しい職を得ていた。
いいなと思ったら応援しよう!