
崇めるオオカミ by. 木森 林林
『狼と大神』
“狼” とは獣として
“大神” は神格化されるモノとして存在する
どちらも「オオカミ」に変わりはない
獣としての狼は
『ウルフパック』とも呼ばれる群れを形成し
その群れは特異な順位を元に維持される
この特性は後の人間界にも活かされたが
果たしてそれは有効に機能したのだろうか
崇拝されるべき “大神” に問いたい

- アルファとオメガの狼-
まず獣としての「オオカミ」(以下:狼) は過去記事でも少し触れたが、※以下参照
その昔に日本の野山では頂点捕食者として君臨し、
後に絶滅した。
他の動物とは異なり、雄雌別の “順位制” を持ち
最上位をアルファ、次にベータ、最下位がオメガとされる。
この名称は専門家である人間が決めたに過ぎないが、
実際の狼はこの順位制がとても厳格であり頂点捕食者である所以が随所に見られる。
「遠吠え」としても有名だが、
その鳴き声や仕草、表情や動きは群れの内外のコミュニケーションで遺憾無く発揮され、
それら全てこの群れの順位制が関係しているとされている。
主な特徴としては、
獲物を食す際に最上位のアルファとされる立場の狼が先に食べ群れの順位に従って食事をし、獲物の食べる部位すらも上位の狼が食した順に行うようだ。
さらにワタシが驚いたのは、
狼の群れは個々がその時の空腹が満たされればその場に残骸を放置し、
他動物に分け与えるかのように去っていく。
実際に人間が狼を見つける時は獲物の残骸が特徴的なため、
近くにいるかどうかの判断が容易だそうだ。
他動物では大きな獲物を捕らえた際に食べきれない場合
は巣や縄張りに持ち帰るが、
自然界で頂点捕食者である狼が、
そのような生き方をすることで狼が捕らえた獲物の後を食べにくる小動物も多くいる。
この小動物達も狼の標的になる事もありえるが、
必要最低限を食し分け与えるかのような様相は、
自然の摂理の象徴かのように本来の生きるための目的までも考えさせられる。
これは近代になり判明したことのようで、
実際には古来から身近に共存していた人間は、
これらの特性を思慮深く向き合い理解していたのではないか。
- 崇めるオオカミ -
そこで神格化される「オオカミ」(以下:大神)が、
音読する上で同名であることに疑問が残る。
“大神” とは神話や宗教的概念では馴染みがあるが、
ワタシは狼と大神が同一と述べたいわけではない。
だが過去記事や前述でも記したように、
“狼” の頂点捕食者としての役割や、その固有の特性は
まるで現在の人間社会のモデルとも言えるほどに自然の摂理を体現している存在である。
ニホンオオカミが絶滅した理由は諸説あるとされるが、
有力な説とされる「縄張り争い」という視点も
どこか『人間が争う根源的な理由』にも通づる部分がある。
野山では狼が頂点捕食者として個体数が減少したことで自然界の均衡が崩れたことは事実であり、
海外ではこうした理由から狼の生きる環境を整え個体数を増やす動きもあるようだ。
技術や知性が発達したことで人間が頂点捕食者として君臨する視点があるならば、
将来的にどのような考えや行動、視点が必要かは “狼” から学ぶことは多いように思う。
「大神」という表現も古くからの伝承とされているが、
その後日本で絶滅したニホンオオカミが「オオカミ」として同音で表現することは、
同一でなくとも何かの暗示のようにワタシは考える。
- さいごに -
ここまで見てくださりありがとうございます。
今回は以前の記事でも少し触れた『狼』と、
古くから崇める存在や地名としても馴染み深い『大神』が「なぜ同じ音なのか?」という視点で疑問に感じ、
過去に見たWilliam J. Longの『オオカミの生き方』を思い出し今のワタシの視点で記事にしました。
人間の特性は言葉や多くの知性と感受性がある以上、
新たな創造を具現化する能力には長けています。
ただそれらが時に予期せぬ行動に繋がり、
社会生活の中で衝突や争いが起きることも事実です。
一匹狼という表現があるように、
自然界の狼の特性全てに共感するわけではありませんが、
同種族の中に「順位制」を見出した実在の生き物が絶滅の道を歩んだことを考えると、
人間が生きる現代社会の仕組みを考える上で、
ナニカ活かせる視点があるかもしれません。
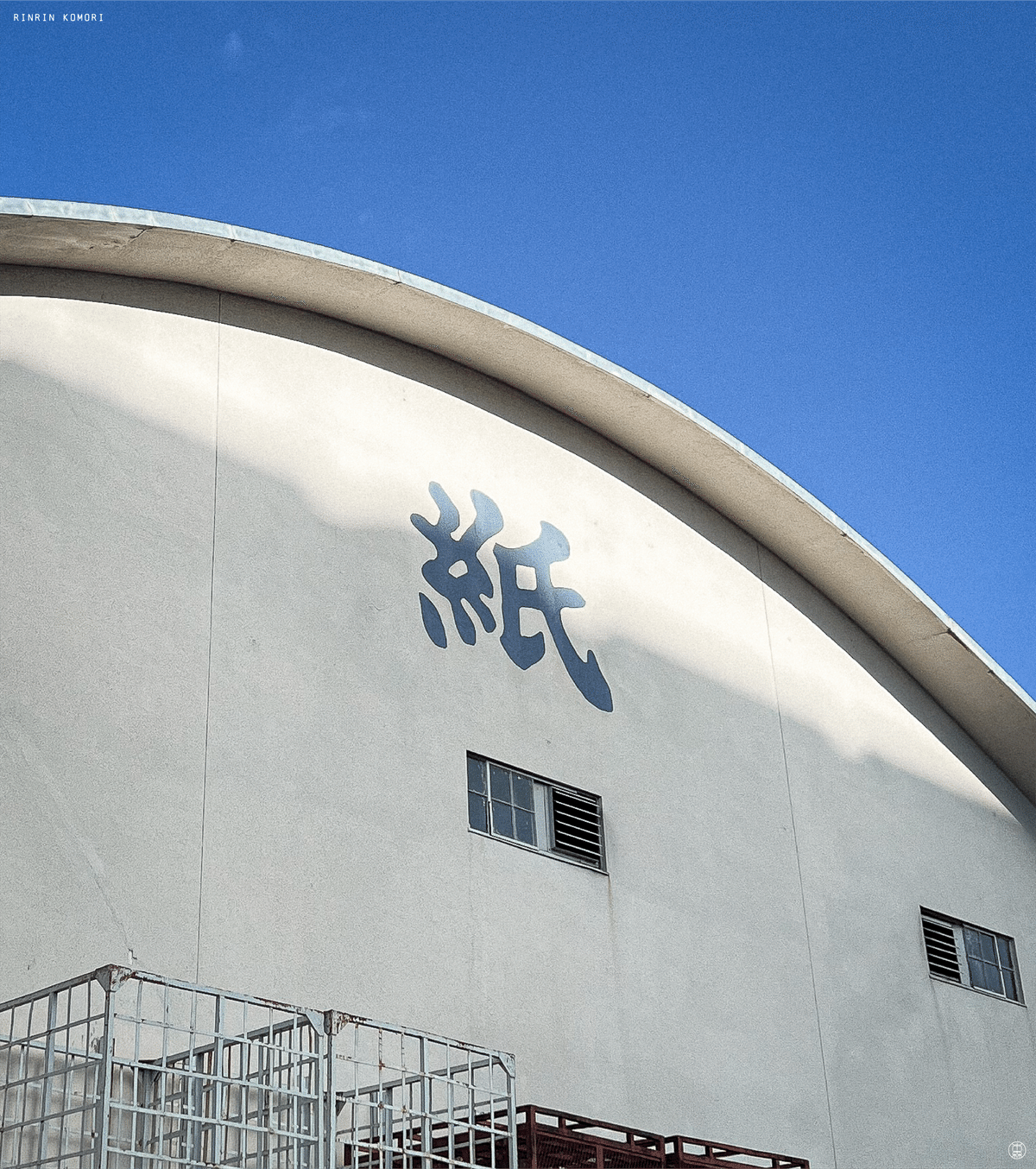
木森 林林(RINRIN KOMORI)
