
【たかしまサーカス企画 | BookTrunkCases vol.1】拡張人間のボーダーラインと手間のありか
いよいよ再来週2月22日に迫ったたかしまサーカス!
滋賀県は琵琶湖の西側、高島という地域にあるTAKASHIMA BASEという古い民家を改装した気持ちのよい場所で開催するイベントです。
*たかしまサーカスについて、詳細はぜひこちらの記事をご覧ください。
普段はそれぞれの地で、(瀬川くん曰く)「その人の表現のようなものとして」本屋や出版社などをされている方々がこの日ひとところに集い、非日常の愉快な場を繰り広げる予定です。
「たかしまサーカス」には、単に”ブックフェア”のようなことばでは表せないいろいろなものがたゆたっています。
それでも、やっぱり本を共通のものとした場所であることはたしかであるという中で、
本を通して、「結局よくわからない」かもしれないイベント「たかしまサーカス」のことをより深く掘り下げるような、そんな企画をはじめます!
「たかしまサーカスの本棚のようなものとして、それぞれが思い浮かべた本を集める」という枠組みがあるにはあるのですが、必ずしもそれにこだわるわけではなく、
本を真ん中に置きつつ私とたかしまサーカスのメンバーひとりひとりが1時間ほどじっくり話し、その内容をふまえて書いた文章をシリーズとして投稿します。
そんな私はたかしまサーカスにおいて、すこし前に書いた記事(とはいえこの記事はすごく内向きの文章なのですが)にもあるように、たかしまサーカスに対し居心地のよさを感じながらも、やっぱりものすごく自分の体重を乗っけられているような状況にはない存在です。
そんな存在に対し、「いるだけでうれしい」ということを伝えてくれた上で、私がやりたいこと、活き活きできることはなんだろうかというのをお互いにそれぞれの日々の表現や会話において伝える中でうまれたこの企画。
第1回目、たかしまサーカス発起人(?)である瀬川くんとのセッションの終了直後にメンバーでのミーティングがあることすら気付けていなかったくらいに現状をキャッチアップできていないという状態に対し、やはり後ろめたさが無くはないのですが、
私が対話し、それを書くということを、まっすぐに楽しみにしてくれる人たちのいるたかしまサーカスを、私なりの方法で愛でることを自分のひとまずの役割としてとつとつと話し、書くことができたらと思っています。
はじめに話したのは、私をたかしまサーカスにさそってくれ、この企画を提案してくれた人でもある瀬川くん。
「ふつうのことをふつうに話そう」という前提を共有し、おだやかに話がはじまりました。
瀬川くんがまず紹介したのはこの2冊。
1:東千茅『人類堆肥化計画』創元社(2020)

2:曽我大穂 (監修), 髙松夕佳 (著, 編集)『したてやのサーカス』夕書房(2020)

話をする中で、この2冊は「たかしまサーカス」のはじまりでもあるような本だということがわかりました。
1冊目の『人類堆肥化計画』は、今回出展してくださる「汽水空港」モリテツヤさんが紹介されていた本として出会ったそうです。
モリさんがたかしまサーカスの前日に開催される「未来のジャム」というイベントに登壇されることが先に決まり、モリさんが高島に来てくれるなら、という発想にたかしまサーカスの元始があります。
そんなヒストリーを思い起こすような本としての一冊。
その後そのアイデアを、神奈川の出版社:三輪舎の中岡さんに会いに行ったイベントで出会った夕書房の高松さんに話している中で紹介されたのが、2冊目の『したてやのサーカス』だったたと言います。
瀬川くんにとって「書かれていたことばひとつひとつが自分のつくりたいものだった」というこの本。
その精神性だったり、あらゆるものが居心地のよい場であることなど、本の中に書かれたときめく言葉たちを共有してくれましたがあいにく全てをメモすることはできませんでした。
もちろん聞けば抜粋もできるけれど、その「つくりたいもの」の詳細は、ぜひこれからの話やこれからの日々の中で自分たちなりの言葉が紡がれていくことを楽しみにしていようと思います。
ところでその、たかしまサーカスの発案段階、まずはどんどんアイデアを出していこうというような場においてはどのようなものが出てきたのか。
話を聞く中で私がとくに印象に残っているのは、
世代や地域や過去と未来、あらゆる分断のあいだにあるような、はっきりとはとらえられない、いろんなものが入り混じった場所としての「汽水域をつくりたい」というものと、
「ブックフェアでできないことをやりたい」というものでした。
いろんな人があつまり、出会う場として、「ただのブックフェアじゃない」イベントとしてのたかしまサーカス。

その上で、人と人が「どう出会うか」はとても大事だという発想をもって、たかしまサーカスではチラシに掲載する写真を自分達でその出店者の方々のもとへ出向いて撮りに行ったり、事務的なやりとりを非効率だけどあえてコミュニケーション機会が多くとれるような方法で行ったり、などをしていたりします。
たかしまサーカスのユニークさは今、こういうところに宿っているのではないかと思います。
現在そんなたかしまサーカスの関わり方について出店者の方からは「ていねいな運営」と言ってもらえることが多い、と瀬川くんはあっけらかんと言います。
でもこのことは、じつはとってもスリリングなことなんじゃないかなと私は感じるのです。
というのも、私や瀬川くん含め、たかしまサーカスの運営メンバーは出店者の方と比較すると”若い”とされる年齢です。
自ずと経験や知識もたくさんあるわけではないという状況。
そんな中で「”あえて”非効率なことをする」ということは、ともすればその行動のもどかしさや”無駄”とされるようなものが(経験の浅さによって)「わかってないがゆえに」生じるようなものとして認識される可能性があります。
経験も知識も十分に無いということはもう当然すぎるくらいのことで、それを気にしたってしょうがないし勿体ないのに、それでもどうしても舐められることが嫌で、わかっているということを示すために本質的ではない方法で速さや独自性のようなものをアピールしたり。
そんな、誤解されて悔しさや恥を感じることが怖く、認められたいという気持ちやプライドによる空回りをしてばかりをしているような私としては、同世代の瀬川くんが今そんな行動をとっているということが、すごく勇気や余裕のある行動のように感じられます。
だからこそ、出店者の方に手間をかけてもらうという局面においてはその相手を「信じる」必要があります。(ある程度伝わるはずだという信頼と、誤解されたとしても不都合はない、という信頼。)
そのことはたしかに難しいことではある、と瀬川くんは言いました。
でも、あらゆるところでとってもらう”手間”があったとしても、それがほんとうにムダな手間ではないのだろうということを感じてもらうために他の部分で必要な調整をしっかり行うことは必要である、
「効率的に執り行う」ということができる場は他にあるだろうから、それを求める人はここではなくそっちに行ってもらったらいい、
そんな言葉に、覚悟があるんだな~と思ったりしました。
そんなふうに瀬川くん(含めたかしまサーカスメンバー)が熱い気持ちを向ける出店者の方がた。
出店者のみなさんに共通するものはなんなのでしょうか。
そんなことを瀬川くんに聞いてみると、「本屋という場を介して人と物と自然が対話している感じなんじゃないか」という答えが返ってきました。
哲学がまっすぐにあるようなかんじ、でもそういうこだわりがあるのにひらかれていて、起こることに対して対話的で即興的に応答するという感じ、その人たちに関わった人たちもなにかを表現しちゃうような感じ。ポリフォニーというか、と。
…”ポリフォニー”という言葉をこのとき私ははじめて知りました。
複数のいろんな声が折り重なったイメージの音楽、というふうな意味があるようです。

日本全国の書店から条件にあう出店者候補を考えピックアップした、というよりは、すでに関係性があった人達の中で「人が活き活きすること」になにかしら関わっていると瀬川くんが直観した方に声をかけ、出店していただくことになったということです。
先ほど書いたように出店者の方々の大きさや本質的な感覚を信じ、且つこんなにも魅力を語れるなんて、出店者の方と瀬川くんはもう随分関わり合いの経験があるのかな、と思いました。
そこで、念のため確認するくらいの気持ちでそのことを尋ねてみたところ、「いや、ない。無くて、でもそういう対話や関わり合いの場を持ちたいからこそ今回呼んだ」と、
竹を割ったような、いや、あえて言うならばとうふを切ったかのようなあっさりとした返答があり、拍子抜けしました。
(今回のたかしまサーカスではとっておきのポイントとしてまちの豆腐屋さんの出店も予定しています)
一緒の作り手になる、ということ。
それは、わかりきった存在との信用の関係の中で、すばらしいものをつくろうとして時間や手間を費やしてこだわりのものを作品のようにつくり、それをお披露目するというようなものではなく、
わかっていないけれどなんだか直観的に惹かれるような人たちに誠心誠意をつくしながら声をかけ、オープンなやりとりを重ねながら、
当日の場自体も引き続きその人たちのことを知り、出会い、結ばれていくための過程の一部であるとするような、
そんなたかしまサーカス”観”のようなものを、より深く理解できたような気がしました。
日常につながる非日常として、その後の関係やくらしにも確実な影響を与えるものとして在りたいという「たかしまサーカス」。
「日常のいとなみの尊さ」みたいなものにこそ興味があるというような瀬川くんに対して、じゃあそもそもはじめから日常の場をつくるというのでもべつに良かったんじゃないのか?
…なんて、そのとき私はそんなことを思ったりもしたのですが、出店者の方のみでなく運営メンバーも、すでにお馴染みの人たちの集まりのようなものではない、ということを考えると、そんなきっかけのようなもの、向かっていく対象のようなものとして「非日常」が持つ力というのもたしかに納得したりします。文化祭前のたのしさみたいな。
日常をつくる場では集まらなかったかもしれない人たち、生じなかったエネルギーが、非日常の場をつくる場面だからこそ生じる、ということは実際たくさんあるのだと思います。
単なるスタッフとして、ではなく、その人の人生やその人がやってきたこと・やっていきたいことに重なっていると感じてもらえるような形で関わってほしい、と、瀬川くんは前から言っています。
それぞれにいろんなやりたいことやるべきことがある中で、たかしまサーカスに関わることを決めたメンバーへの責任のようなものとして「熱源をつくる」ということは意識しながら動いているという、
そんな瀬川くんが3冊目に紹介したのは、たかしまサーカス発起当時から一緒にアイデア出しなどをしていたというしほちゃんから紹介された本でした。
3:永井 宏『サンライト 永井宏 散文集』夏葉社(2019)
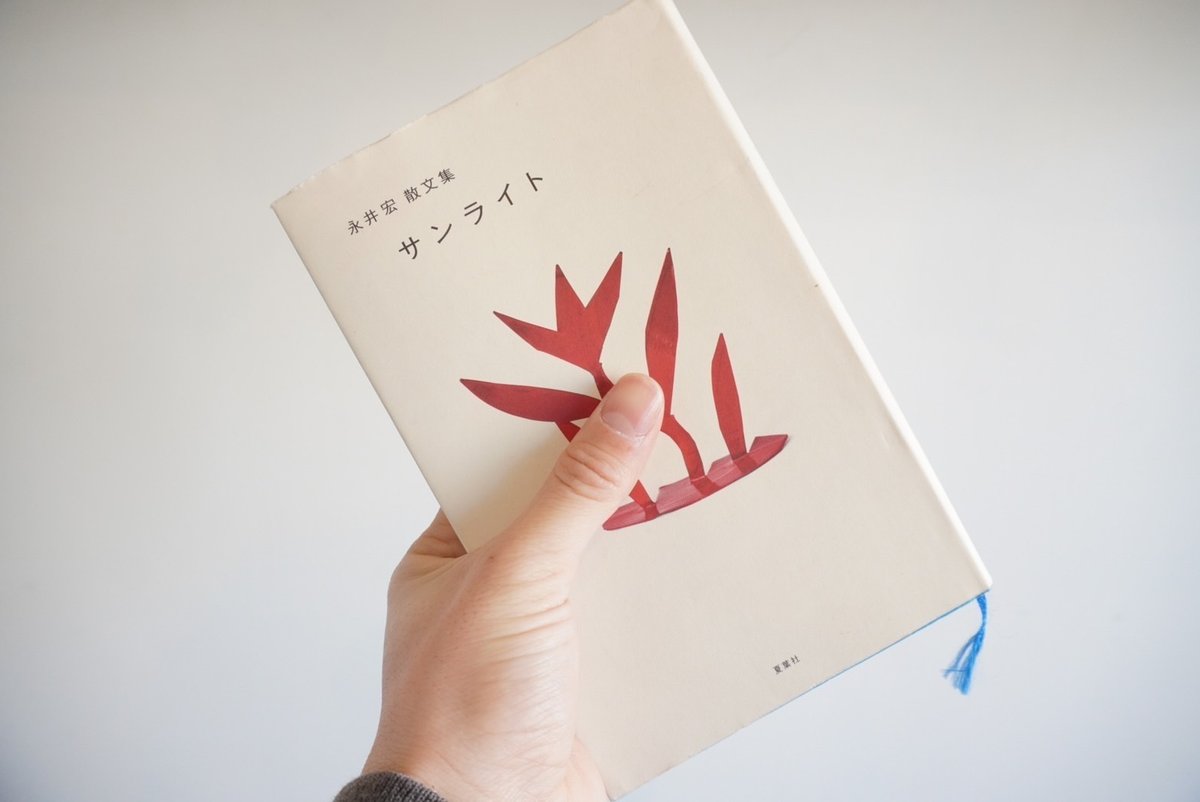
どう関わるかによっては縮まる距離も縮まらない、ということ。
そのことは、出店者の方がたとのやりときに限らず、運営メンバーとのやりとりにおいても同様です。
私のイメージでは、たかしまサーカスの準備の中で、それこそ熱源のようなものをずっと絶やさず維持してくれているような存在であるしほちゃん。
そんなしほちゃんも、元々瀬川くんと特別密な関わりがあってこそたかしまサーカスの運営になったというわけではなく、たかしまサーカスが始まるまでは、お互い会う度に軽くあいさつするくらいの仲だったといいます。
それでも、たかしまサーカスに関わることを決め、仕事を別でも持ちながら日々の取り組みを共にしていく中でお互いに新しい面をたくさん知り、今では「いなくてはならない相方」のようになっている、としほちゃんのことを話していました。
たかしまサーカスの過程の中で生じたメンバーと自分との出会いや関係性の変化は自分にとってかけがえない、スピリットのようなところでつながれる友だちができたことがうれしい、といいながら、しほちゃんから紹介されてうれしかった本として、まだ読んでいないけれど、とこの本をたかしまサーカスの本として挙げてくれました。
たんなるブックフェアではないにしても、本を介したイベントであることはたしかであるたかしまサーカス。
瀬川くんは、そんな”本”を通して人を知り、近づいていくということをたしかにしているように見えます。
今回挙げてくれた4冊のほかにも、メンバーすずちゃんが教えてくれて読んだという本『未知を放つ』(しいねはるか・2021)、
私と初対面する前にどんな人であるのかを知ろうという意図で、当時私が強く影響を受け、SNSなどでもかなりメンションしていたのを見て読んだという本『シングル単位の恋愛・家族論:ジェンダー・フリーな関係へ』(伊田 広行・1998)も、ほんとは紹介したい本としてこの話の初めに言及してくれました。
本はたしかに、背景を知る手がかりになります。
とはいえ本というのは、自分で出会ったり人から紹介してもらったりしていいと思ったすべてのものを読むにはあまりに時間がかかるものでもあるということを考えると、今回のようなブックリストの記事というのはどういうふに魅力的にありうるだろうか、ということを考えながら、この企画をすすめています。
(ちなみに言ってしまえば私はいわゆるブックフェアみたいなものについても、魅力的な本が溢れているのは確かだけどその場ですぐ読み切って体験や感想を共有できるわけではなく、その内容を知るのに最も適しているのは買ってじっくり一人で読むことだけど、それだって気になった本全部を読めるわけではないし、などを考えると、どういうふうに本を介してその場にいる人と関わったらいいのかがあんまりわからなくて、みんなどうしているんだろう、人は何をたのしみにブックフェアに行くんだろう、などと、前から結構疑問に思っています。その上でなぜたかしまサーカスが本を介した場として出発時点からあるのか、そのことについてはこれまで何度かメンバーに問い、話をしていますが、自分の中でしっくり来ていません。が、まだまだなにかがあるように思います。対話を重ねていきたいです。)
そんなことをやはりこのときも話す中で、最近瀬川くんとの話の中でしばしば出てくる「拡張人間」の話があります。
しほちゃんとのセッションの中でも改めて話すことになるかもしれませんが、今はたかしまサーカスの運営メンバーとして人の中で日々動いているように見えるしほちゃんは、「人といっしょになにかをやる」ということが苦手だったし今も苦手だ、ということを言っていました。
瀬川くんもそうだったと言います。
これまで、人とやることをあきらめていた、と。
自分のこだわりは自分自身でその面倒をひきうけてやっと発揮できるようなものなのであれば、自分ひとりでやっちゃったほうがはやい、と思っていたそうです。
でも最近、人にやってもらうほうがよくできるということを知った、と瀬川くんは言います。
あらゆる領域において、自分よりも上手にできる人が、確実に居ます。
そのことに直面するとき、前までは逐一くやしさを感じていたけれど、それを無理に自分がやろうとするのではなく、人の持ち味が発揮される環境をつくって任せてしまう方が、よりよいものができるということを知った、と。
その上で、その人がやったことというのがまるで自分がやったことであるように、まさに「拡張人間」のように、自分というものの領域がどんどん広がってきているような感覚がある、と。
自分自身がほんとうにこだわりたいところへのこだわりはそのままに、というかむしろより強くなったようでもありながら、ある意味で「(自分ができないことについて)いっぱいあきらめられるようになった」と瀬川氏。
この「拡張人間」の話を聞くたびに、「他のひとがやったことについても、自分やるやん、という気持ちになる」とにこにこしながら冗談まじりに言う瀬川くんの滑稽さをツッこむようなテンションで笑いながら、妙に納得するような、そのプラクティカルで愉快な姿勢に不思議と尊敬させられるような気持ちになります。
そしてそんなことを思っていると、本というのもまさに、1人1人が読める本には限りがあるという上で、
世の中にあるたくさんの本のうちごくわずかな一部の本をそれぞれ読んだ人が一同に会し、その場でその人を介して出会う本があったとしたら、
それがどれだけ些細でありふれてみえる出会いであったとしても、そこに至るまでにその多様な人たちが出会ってきた本の総体の中から相当のエネルギーをもって選んだくらいに純度や精度が高いものとしてありうるのかもしれない、などと思ったり。
そういうふうに考えると、本のあつまる場というのは智慧や情報や想いや思考や思想など、あらゆるパワーのつまったものすごい場であるかもしれません。
最後に紹介してくれた本の話の中では、そんな、目の前にふつうにあるものの中につまっている必然性、のようなものと重なると(私は)感じる、”路上”というキーワードが出てきました。
4:薄場圭『スーパースターを唄って。』(2023)

この漫画は、最近読んでハマった作品として紹介してくれました。
自分についてはいろいろあきらめたとしても、自分の人生を生きることについてはあきらめなくていいんだ、ということを思ったそうです。
たのしいことをしたり、人間っていいなあ、ということを言う上で
気持ちいいことをして、いいねーとなるだけではちがう、
社会のつめたさや人間のみにくさのようなものを見ないで言うのは違う、
ほんとうのことを言おうとすると、よくある言葉やいい話だけでは足りず、そこには痛みがあったり覚悟のようなものが必要だったりする。
そういうものには普遍性がある。
そういうようなことを考えるときに、”ストリート”というのを考える、
と言っていました。
このストリート感というのはみんなでやっているたかしまサーカスにおいて共有して出していきたいものというよりは、なんだかんだ大変なこともいろいろとある過程の日々の中で、瀬川くんにとっていつも自分をふるいたたせてくれるもの、としてあるらしいです。
と、こうしてその人のストーリーの中で大きな存在感を持つ本の話を聞いていると、なんだかんだ、どの本も読みたくなってしまいます。
読むべきかも、とかって思ってしまう。
それでもやっぱり、そういうふうに思うその全ての本を読むことはできません。
他に読みたい本もたくさんあるし。
そのこと、つまり、自分のキャパシティに限界があるからこそ自分の理想をいつも満たせないように感じるということについて、焦ろうと思えばいくらでも焦ることができますが、そんなときにいい意味で地に足をつけて等身大の自分として目の前に起こっていることをしっかり集中して味わうということに立ち返るようなニュアンスも、”ストリート”というものから広がる世界観の中にはあるかもしれません。
山の高いところに登っていこうとするような生き方ではなく、川を下るように生きていきたい、成長して成し遂げていこうとするのではなく、いろんな痛みを知ったりしながらより謙虚になっていきたい、失敗もいっぱいしながら、身体で示すように生きていきたい、という瀬川くんに、
「今回紹介してもらった4冊の中から1文だけ、これぞ!ということばを送ってくれないかな」と言うと、
『したてやのサーカス』内から「人生は偶然でできている」という一文が選ばれ、送られてきました。

明日以降もメンバーと話す予定がもりだくさんです。
たかしまサーカス 開催概要
日時:2025年2月22日(土)10:00-18:00
会場:TAKASHIMA BASE
※JR新旭駅徒歩1分(JR京都駅から新快速で約45分)
参加費:無料 / 申込:不要
トークイベントの参加のみ、チケットの購入が必要です
