
笑うバロック展(542) エマヌエルのハープ
エマヌエル・バッハのハープ・ソナタは、ペダル・ハープの最初のレパートリといえそうです。つまり、ペダル・ハープの訓練を受けた奏者の。ペダルなしのバロック・ハープのレパートリとは差異がありそう。ヘンデルの協奏曲とエマヌエルのソナタには、ペダルの壁があるみたい。
高田ハープのサイトにエマヌエルの記事。たしかに演奏者によって、特に 譜例の Adagio un poco と次の Allegro が入れ替わっている場合があるようです。 「(1)Adagio un poco (2)Allegro (3)Allegro 緩急急」が「(2)Allegro(1)Adagio un poco (3)Allegro 急緩急」という風に。エマヌエル・バッハの曲になれるほど、「緩急急」の方が「らしい」と思いますが。
C. Ph. E. Bach カール・フィリップ・エマニュエル・バッハ(1714-1789)
大バッハといわれたヨハン・セバスチャン・バッハの息子です。クラヴィアのためのソナタを数多く作り、古典派のソナタ形式の基礎を築きました。彼の「ハープ・ソナタ」(1762年)はオリジナルのハープ作品としては最も古いもののひとつですが、原本は「ハープのためのソロ」という題名でメロディーとバス・ラインの和音が添えられている小品集です。これを組み合わせてソナタとして1940年ころにニーマンが刊行し、その後ツィンゲルやグランジャニー、ヴァイデンザウルなどがそれぞれ編曲しています。小品を組み合わせてソナタにしているため、版によって楽章の順が違ったり、調が違ったりします。従って題名もツィンゲル版では「Sonata for Harp」でなく「Solo for Harp」となっています。
Sonata in g major Wq139/H.563

長澤真澄は楽譜の並び順で。シングルアクションのハープを使用しました。

催行されていればおそらく吉野さんも。

(2012年12月インタビュー)5年ほど前に同製作者・同モデルの古楽器「Beat Wolf製作“Louis XVI Harp(ルイ16世ハープ)”」を手に入れることができて以来、いつか現代のモダン・ハープと並べて2台を弾きわけるようなコンサートができたらなあと----弦の数はモダンハープが47 本、古楽器は39本で、楽器のサイズも古楽器の方がずっと小さくて、重さはモダンの半分弱の16kgほど----弦の間隔が狭く、張り自体も弱いです。モダンハープも同じガット弦(羊腸弦)ですが、古楽器の方が細い弦です----C.P.E.バッハ「ハープのためのソナタ」とシュポア「ハープのための幻想曲」と、ハープオリジナルのレパートリーをお聴きいただきます。シュポアはベートーヴェンより少し後の時代の作曲家なので、古楽器で弾くにはぎりぎりの作品ですが
古い録音は、1958年頃、グランジャニ。「(2)Allegro(1)Adagio un poco (3)Allegro 急緩急」の順。同じころのサバレタも同じ順。1966年録音とあるジャメ盤も「急緩急」。


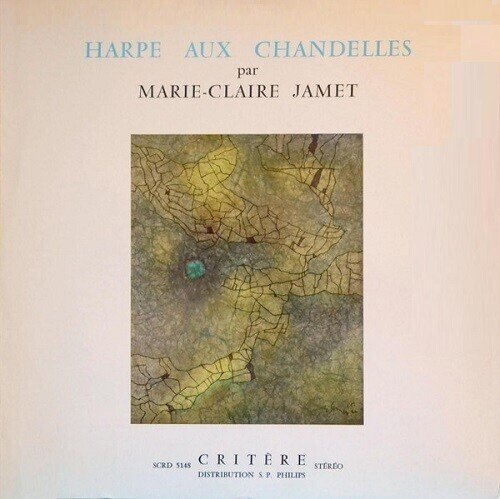
1969年のエリス盤は、「(1)Adagio un poco (2)Allegro (3)Allegro 緩急急」。「エリス・エディション」とあるので自ら実用譜を起こしたよう。

2016年「ハープ・コラム」より----ハープソナタのまとめ:1762年に書かれ、ペダルハープの最初のソロ作品と見なされています。(シングルアクションペダルハープは1749年にデビューしました。)ソナタに影響を与えた可能性のあるプロイセンの宮廷ハープ奏者フランツ・ブレネセルは、CPEバッハの見習いでした。その時代には、ハープは伴奏楽器として使われていました。----パッカード人文科学研究所に、Gのソナタの正しい動きの順序について尋ねました。正しい移動順序は、Adagio un poco – Allegro –Allegroである必要があります。----「1720年代までに、CPEバッハがライプツィヒで育ったとき、4つの楽章「遅-速-遅-速」の形式はイタリアのソロソナタ、3つの楽章「速-遅-速」の作品に取って代わっていました。その後、1730年代から1740年代にかけて、ドレスデンとベルリンで作曲されたソナタでは、「遅-速-速」の順序の作品が支配的になりました。----CPEバッハが書いたとおりである必要はありません。20世紀の主要なハープ奏者は、グランジャニーからローレンスまで、音楽的に「正しい」順序「速-遅-速」で演奏しました。それは、ロールモデルであったかもしれないJSバッハのイタリア協奏曲に準拠しています。CPEには、「遅-速-速」モードのソナタがありますが、特性はまったく異なり、「速-遅-速」ソナタに似ています。したがって、「遅-速-速」モードで再生することが「正しい」と言うのは誤りです。それに最初のAllegroより、2番目のAllegroをさらに速く演奏できることを前提としています。
「ハープコラム」というギルドマガジンがありました。

