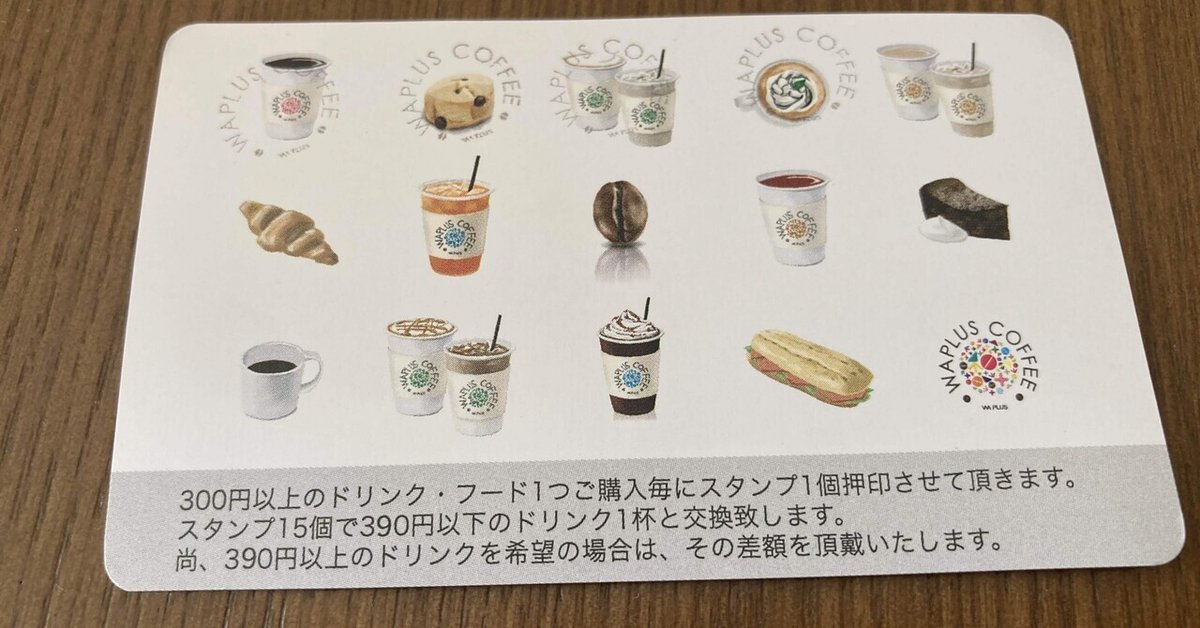
「二度と行けないあの店」の話
都築響一編集の「Neverland Diner 二度と行けないあの店で」というエッセイ集がある。
そこには、100人にとっての100軒の二度と行けないあの店についてのお話が収録されている。
私の人生においてもいくつかの二度と行けないあの店があるが、つい昨日リストに一軒が追加された。
店の名前や場所が分からないわけではない。
Googleマップにはぴしっと旗が立ててある。
手元には、ご丁寧にスタンプカードまである。
2人分のコーヒーとおやつ。
4つのスタンプが押されたスタンプカードだ。
15個たまるとコーヒーが一杯飲めるらしい。
しかしなぜか、あのお店に入ったとき、ポイントカードお作りしますかと尋ねられたとき、席に向かい合って座ったとき、閉店の10分前に最後の一口を飲み終えて席を立ったとき、カランカランと妙にけたたましく鐘を鳴らす扉を押したとき、どうしようもない切なさが(けたたましく)押し寄せた。
そして別に、これは特別ではない。(「別に」と「特別」の関係はよく考えると面白い)
いつだってどうしたって飲食店には切なさがつきまとう。
その要因は次の4つではないだろうか。
①人間関係の儚さ(各々の身上の儚さを含む)
②飲食物の儚さ
③建造物の儚さ
④経営の儚さ
切なさを生むのは単純に儚さだ。
何も特別なものではない。
「別に」「特別」ではないのだ。
それを特別なものにするのはやはり命名、ラベリングであろう。
ここにこうして「二度と行けない店」とラベリングした時点で、すでに特別な店になってしまっていることは、もはや書く必要のないことだ。
隣の友人に「さっきのカフェは『二度と行けない店』っぽかったね」と伝えると、彼は言った。
「そうはさせません。美味しかったからまた行きます。」
出た、儚いアWord金賞「また」!
