
創作舞台、大好きだ!(まちの不思議 おもしろ探究日記 #21)
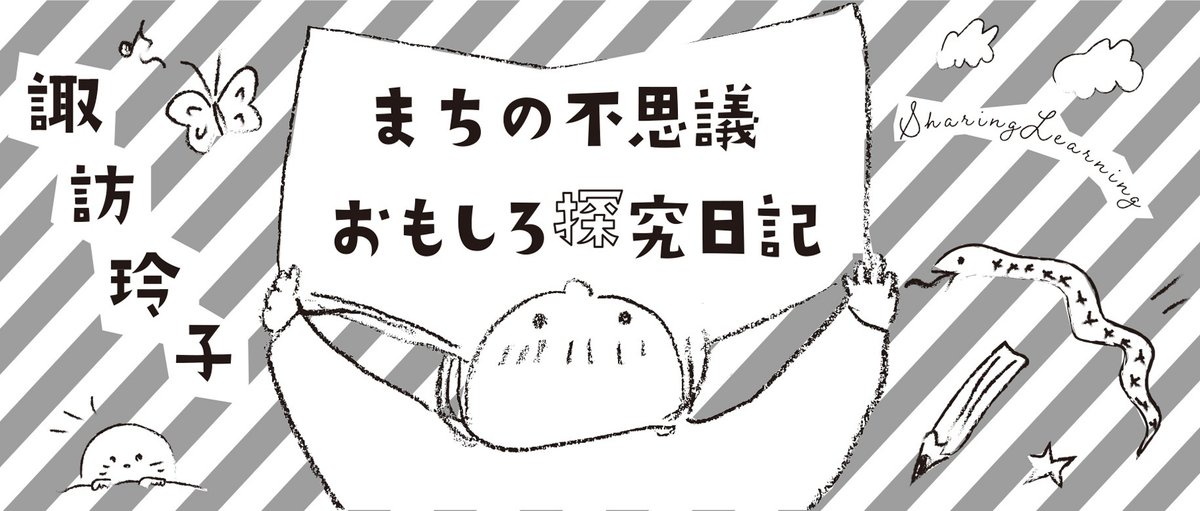
「みんなが何考えてるのかわからない。もう誰も信じられない。また誰かと仲良くなっても、裏切られて傷付くくらいなら、もう関わらなくていい。どうでもいい。」
そう言って下を向く長男に、私はかける言葉がなかった。
今年の春、それまでずっと仲良くしていた友人たちとの間にいざこざが起き、心を閉ざして学校も休みがちになった。
人生で初めての大きな挫折。そう言っても過言ではない。順調に過ごしてきていた中学1年生までの暮らしが一転、2年生になってからの日々は苦悩に満ちた日々であった。
長男と友人との間のトラブルは、学校でも問題となっており、先生やスクールカウンセラーの方と、何度も電話や面談を繰り返していたが、思春期の子どもたちの心が絡み合う人間関係のこじれは、そう簡単に解決する話でもなかった。
どうにもならない思いを抱えながら、始まった夏休み初日。
さぁここからどうやって過ごしていこうか、どうやって傷付いた心を癒していこうか、と計画を立てている中、ふと長男が「創作舞台、やろうかな」と言った。
毎年参加してきた創作舞台プロジェクトに、「もう中2だし、女子ばかりの中に入るのは、さすがに気まずい」と、3年目となる今年は参加を躊躇していた。しかし、「もういいや、やりたいことやろう」と、参加することを決め、この参加を決めた瞬間から、長男の表情は少しずつ変わり始めた。
自分を精一杯表現する機会
創作舞台プロジェクトとは、一般社団法人プレイキッズシアターが毎年行っているもので、やりたいと手を挙げた子どもたちが集まって、台本も何もないところから、10~15回のワークショップを重ねて、演劇の舞台を作って発表するというものである。
ワークショップの中では、即興劇をやってみたり、ジェスチャーで伝え合うゲームをやってみたり、身体を動かし、頭を動かし、心を動かして遊んでいく中で、自分が表現したいこと、好きなこと、やってみたいことなどを少しずつ出し合っていく。
今回のテーマは『とき』である。
そこから連想して、いろんな疑問を問いかけ合ってみたり、今自分が感じていることを言葉にしてみたりしていく中で、少しずつみんなでつくる物語が立ち上がり、舞台が出来上がっていく。
合言葉は、「いいね!」。
どんな表現も受け止めてもらえて、安心して自分でいられるこの場で、この夏、長男は精一杯自分を表現する機会を得た。

普段の学校生活では、友人たちに否定され、反応もなく、周りは全部敵のよう。怖くて不安で、居場所はないと感じていた。
それでも、プレイキッズのプロジェクトの中では、自分を認めてくれる人がいる。話を聞いて、反応してくれる仲間たちがいる。
そうやって過ごしていく中で、「自分はいてもいいんだ」「人と関わってもいいんだ」と思えるようになっていった。
舞台が終わった後のふりかえりで、長男は
「プロジェクトが始まる前までは、本当に自分を見失っていた。でも、この舞台で自分を取り戻すことができた。」と語った。
表情もすっかり明るくなり、言葉も前向きな言葉が多くなり、親としては一安心。もう大丈夫かな、と思わせてもらった。
学校だけが居場所じゃない、けど・・・
舞台が終わり秋になると、長男は完全に学校に行かなくなった。
それまでは週の半分くらいはなんとか行っていたのが、見事に完全に行かなくなった。「元気になったから、学校に行かなくなる」というのも不思議な話ではあるが、そばで見ている立場としては、まぁわからない話でもなかった。
学校だけが自分の居場所ではない。
自分らしくいられる場所はいくらでもあるし、自分らしくいられず、恐怖と不安の感情に包まれる場所に、わざわざ嫌な思いをしてまで、行く必要はない。そう吹っ切れたのである。
そうして完全に休み始めて、一週間がたち、二週間がたち、最初はのんびり楽しく過ごしていたのだが、そのうちに、長男には別の不安が立ち上がってくるようになった。
このままで勉強はどうするのだろう。
どこかに自分らしくいられる居場所はあるのだろうか。
将来、自分はどうなっていくのだろう。
しかし、そう思っても、なかなか身体は動かない。もともと今の学校の勉強スタイルにも嫌気がさしていたし、それを自分なりに進めていこうとも思えない。一方で、フリースクールなどを考えてみても、新しい居場所を作っていくということの大変さもわかっている。進学してみたい学校はあるけれど、今すぐに行けるわけでもない。学校のありがたさもわかるけど、やっぱり不安だし怖い。
自分はどうしたいのだろう。
どうやって、今を生きていきたいのだろう。
答えは出ないまま、時間は過ぎる。時間が過ぎると、どんどん勉強は置いていかれる。でも、でも、でも、、、
迷いと不安がどんどんと頭を支配していく。家にいても苦しいから散歩に行く。散歩に行っても答えは出ない。
夏とはまた違った形で、どうにもならない日々を過ごしていた。
そこで、どう生きていきたいのかという壮大なことではなく、学校に行くかどうかといった具体的なことでもなく、学校という仕組みに乗るのか、乗らないのか、という事だけでもとりあえず決めたら?と提案してみた。
乗るなら乗るなりの生活の組み立て方があるし、乗らないなら乗らないなりの組み立て方がある。行くか行かないかはまた別の問題だよ、と。
「それならまぁ、学校の仕組みには乗っかろうかな」と長男は言った。ちょうど期末テストも受けず、迷いや不安があふれて、あふれすぎてこぼれ落ち、「まぁもういいか」と吹っ切れた時でもあった。これを決め、また長男の表情は少しずつ変わり始めた。
今のぼくたちの声
ちょうどその頃、プレイキッズシアターの方から、隣のまちでやる創作舞台プロジェクトに参加しないかと声をかけてもらった。これまではそのまちに住む子だけが対象だったプログラムが、今年は対象が広がり、隣のまちからでも参加できるようになったのだ。せっかくの機会なので、長男も参加させてもらうことにして、また、舞台づくりの日々が始まった。
これまで参加してきたプレイキッズシアター主催のものとは異なり、まちの子どもたちを対象としたプログラムのため、本当にいろんなタイプの子が参加しているという印象を受けたと長男は言う。
創作の流れ自体は同じだが、人が違うと出来上がる作品もまた大きく変わる。今回は『声』をテーマに作品作りを進めていて、その中で、今自分たちが伝えたい声、言葉はどんなものだろうかと、みんなで話し合う時間が自然と生まれた。
「実は学校に行ってなくてさ…」
(あっ、俺と同じだ…)
「行かないって、実は結構しんどいんだよね」
(あー、めっちゃわかる!)
こういったやり取りから、物語の台詞が生まれてくる。この言葉も、物語の中で学校に行かない子の台詞として、実際に使われた。
―言葉で、声で、伝えることに傷付き、疲れ、いつしか気持ちを表現することをやめてしまった世界。それでも、やっぱり言葉を伝えたい。生の気持ちを伝えたい。言葉を、声を、思い出したい。そんな人々の思いが集まり、「声」を閉じ込めた「箱」を取り出すと・・・
「開け!」
―大きな声が響き、博士が「箱」を開くと、舞台は一気に暗転する。
暗がりの中から、子どもたちが一人、また一人と、立ち上がって浮かび上がる。
「あなたのおかげだよって言ってもらえて嬉しかった」
「なんで学校来ないのって聞かないでほしい」
「大丈夫だよって言われると励まされる」
「いつも一緒にいてくれてありがとう」
「ありがとう」
子どもたちがつくった舞台『今のぼくたちの声』の中の、終わりの一幕である。この「箱」を開く博士役を、長男は見事に演じきった。

そして、舞台が終わった後のふりかえりの場で、
「この創作舞台プロジェクトでは、自分が自分らしくいられる。本当の自分を取り戻せる。本当に何度も何度も人生を救われた。この場があって本当に良かった。大好きだ!」と叫んだ。
そう叫ぶ長男の横では、一緒の舞台に立っていた子が、ブンブンと何度も何度も首を縦に振っていた。
きっとその子にもその子の物語があって、この舞台につながり、長男の言葉につながる思いがあったのだろう。
思いを受け止め合う二人の様子に、私は胸がいっぱいになった。
わからなくても大丈夫
舞台が終わり、長男は少しずつ学校に行くようになった。
ちょうど1月末にある宿泊行事に向けたカリキュラムも始まり、まずはそのタイミングだけでも来てみたら?と先生に誘ってもらい、数時間だけ学校に行くことにした。
数ヶ月ぶりに学校に行ってみると、案外まわりの反応は普通で、思っていたような怖さを感じることはなかった。
「すわがすわった!」という誰かのギャグでクラスが笑い、明るい雰囲気だったというのも大きかった。週に1日、2日と、少しずつ学校に行ける日が増えていった。
学校という仕組みに乗るとしても、フリースクールでもよかったし、自分なりに学習するのでもよかった。でも、それなら結局学校に行った方が楽だなと思ったのだと言う。今でも行かない日はあるが、自分の中でいろいろと折り合いをつけながら、毎日を過ごしている。
いざこざがあった友人たちとは、気付けば今はまた、普通に仲良くしているらしい。
長男が言う。
「表現することって楽しいけど、難しい。
自分がうまく伝えてるつもりでも伝わらない。そういう場面もたくさんある。でも、それでもいいのかもと思ってきた。
相手が何を考えてるのかはわからないし、裏で何をしてるかもわからない。
だから「怖い」と思っていたけど、わからなくてもいいのかもしれない。
自分だって完璧な人間ではないし、関わりたくない人もいるし。本当にいろんな人がいる。
でも、そういうところも全部含めて、人と関わって生きていくという事なんだなと思った。それを創作舞台の中で学ぶ事が出来た。
だから、大丈夫とまではまだいかないけど、まぁどうにかやっていけるかな。」
居場所をつくりやすい演劇教育
長男の様子を見守る中、スクールカウンセラーの方に、「お母さんは不安になりませんか?大丈夫ですか?」と聞かれたことがあった。
「長男には、創作舞台という居場所があって、自分を表現する機会があるので、きっと大丈夫だろうと思っています。」そう答えた。すると、
「あぁそういう場こそ、今の子どもたちみんなに本当に必要な場ですね」と返ってきた。
1月20日、プレイキッズシアター主催で、「演劇教育フォーラム」が開催された。平田オリザさんが基調講演を行い、創作舞台プロジェクトの事例発表もあり、最後には教育現場にどう「演劇教育」を落とし込んでいくのかという対談も行われた。
日本では、演劇教育は公教育の中の科目とはなっていない。しかし、海外では美術や音楽のように「演劇」という科目があるのだと言う。子どもたちは「演劇」という授業の中で、コミュニケーションを学び、一人ひとりを認め合い、受け入れ合い、共に生きていくという事を学んでいく。自分を表現する機会を得て、他人との間に自分を見つけていく。
「美術や音楽と比べて、演劇が一番いろんな子の居場所をつくりやすいんです」と、平田さんは言う。
声が小さい子がいたら、声が小さい子の役をやってもらえばいい。しゃべらない子の役は、しゃべらない子がとても上手にやれる。
そのままの自分であるということも、一つの「表現」であり、みんなで物語をつくっていく中で、受け止め合っていくことができるのである。
演劇教育が教育現場の中で行われるようになったら、たしかに救われる子どもたちはたくさんいるだろう。
「創作舞台が学校の中でも行われたらいいよね。でも、みんな真面目にやるかなぁ、やらない子もいるよなぁ。ま、それでもいいか」
そう言って笑う長男の顔は、
もうすっかり、前を向いていた。
▼ 雑誌『社会教育』
