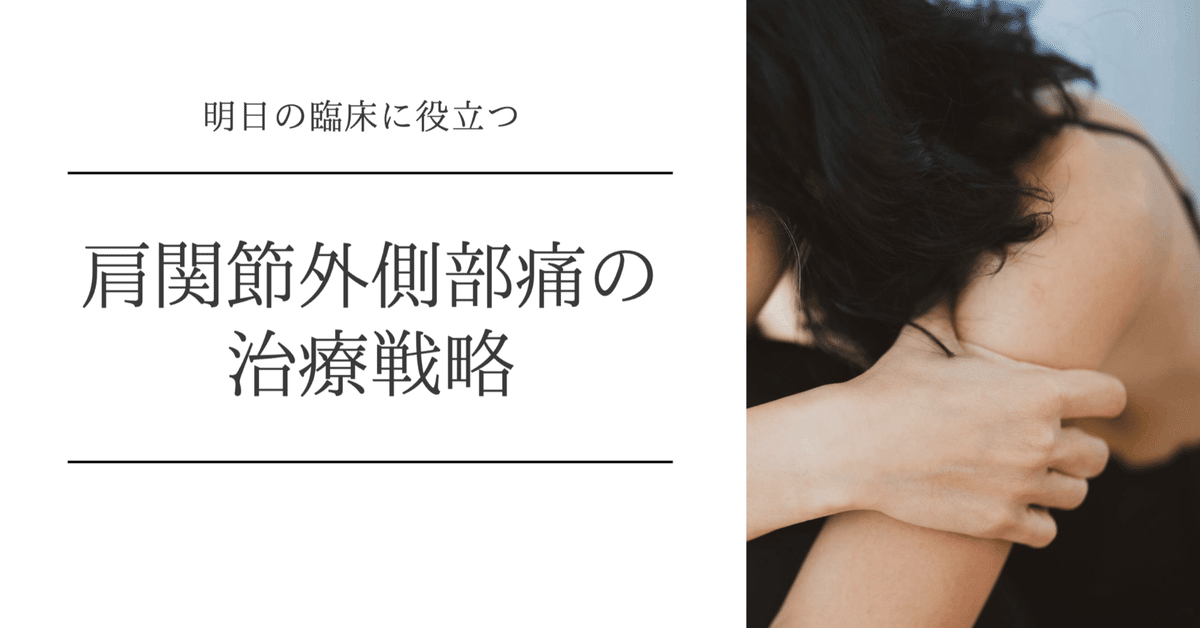
-明日の臨床に役立つ-肩関節外側部痛の治療戦略
皆さんおはようございます桑原です。
Instagram→@kei_6918
皆さん臨床で肩関節疾患を担当した際に肩関節外側部痛を主訴とする患者さんを経験した事はあるでしょうか?
恐らくよく経験するかと思います。
・挙上時
・結帯・結髪動作
・夜間時痛
場所を聞いた時に「外側が痛いんだよね」という主訴は多い印象です。
ではなぜ、肩関節外側部に痛みが出るのでしょうか?
今日はこの疑問を深掘りして治療戦略へとつなげていきたいと思います。
1)頸部疾患の除外
肩関節外側に疼痛があり、範囲をよく聴取すると頚部まで広範囲に及ぶ際は頚部の疾患を疑います。
広範囲に及ばない時もc4-6由来の場合もあるので忘れずに評価しましょう。
なので肩関節の戦略を立てる前に頚部の評価も最低限行い除外する事が大切です。
範囲の丁寧な聴取
頚部の動作時痛の有無
頚部の圧痛評価
spurling testやjackson testは行い頸部疾患を除外します。
2)QLSでの腋窩神経の絞扼性神経障害
頚部由来のケースを除外したらまず、QLSでの圧痛所見を確認します。
QLS(Quadrilateral Space:)とは、小円筋、大円筋、上腕三頭筋長頭、上腕骨内側縁で構成されるスペースです。

ここを腋窩神経と後上腕回旋動静脈が通過します。
腋窩神経はQLSを通過した後、上腕外側を感覚枝が走行するため
このポイントで腋窩神経が絞扼されると上腕外側に鈍痛や脱力感などの絞扼性神経障害の症状を呈することになります。
症状が進むと小円筋や三角筋(腋窩神経支配)に筋力低下が起こるので、小円筋であれば1st外旋より2nd.3rd外旋の方が左右差が顕著に現れます。
また、腋窩神経は前枝と後枝に分かれてそれぞれ支配する筋が違います。
前枝→三角筋前部・中部
後枝→三角筋後部・小円筋
QLSで絞扼されるのは後枝なので小円筋を用いて左右左を評価すると良いかと思います。
3)SAB(肩峰下滑液包)由来
もう一つの原因としてSAB(肩峰下滑液包)があります。
SABは棘上筋と肩峰下の間にある滑液包です。
えっ?なんでSAB?って思った方のために順を追って説明していきます。
まず、SABを支配する神経の確認です。
SABは肩甲上神経・腋窩神経・外側胸筋神経によって支配されます。
自由神経週末が多いことも報告されています。
なので関連のある神経の知覚領域に関連痛が起こる事が報告されています。
なので肩甲骨のマルアライメントの是正や
骨頭偏位の是正(特に後下方の関節包の拘縮による前上方への骨頭偏位)
SABの肩峰下での滑走訓練が必要になってきます。
戦略としては大体こんな感じです。
詳しい介入に関してはまた別の記事で投稿していこう思います。
今後こんな感じで評価や介入の記事も書いていこうと思いますでの、よかったらnoteのフォローお願い致します😄
いいなと思ったら応援しよう!

