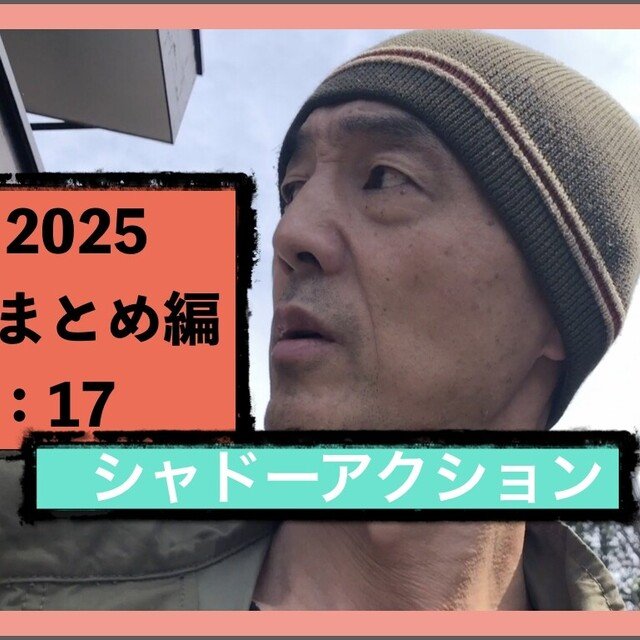
まとめ編17:シャドーアクション
石田憲一
00:00 | 00:00
今週も、まとめ編をお届けします。
<シャドー・アクション>
月:シャドー・ワーク
アクションには影の領域が多いということが、知られていないだけでなく、やっている当事者ですらわかっていない。
それを明るみに出し、名称を与えた。それがシャドー・アクション・シリーズといえるもの。
ルーツは、イリイチのシャドウ・ワークにある
シャドウ・ワークとは、産業社会が財とサービスの生産を必然的に補足するものとして要求する労働。=賃労働を補完する労働。家事や試験勉強、通勤・・・他。
火:シャドー・ムーブ
アクション進化論で発表済みである。
アクションの技とは、単独で成立しているのではなく、受ける(やられる)相手との協働運動とセットで成立している。その相手の協働運動をシャドームーブという。
「殴り」を例にとる。
「殴り」は、なぜ殴りなのか?という疑問。
「殴り」とは、「殴る」という運動と「殴られる」という運動、つまり「殴る側」と「殴られる側」双方の運動の協働によって成立している。そこに「殴り」という言い回しの微妙な意味性が含まれている。
しかし実際はそうでも、視覚的には見世物として主役側、つまり殴る側の動作が目立ってしまうだけでなく、意図的に目立たせようという表現上の力学が働くために、打撃技としてのパンチ=殴る行為だけが「殴り」だと思われがちになってしまい、殴られる側の運動は見過ごされてしまう。
この本来なら「殴る」+「殴られる」=「殴り」であるはずの、等価であり協働運動としての一つの表現の片側「殴られる」が「殴る」の影に隠されてしまうことをシャドー・ムーブと表現した。
水:シャドー・テクノロジー
アクションの本質、無空中枢の潜在下に構造化された独自技術体系。
ドーナッツの中央は、モビリティとアビリティ
その下に位置する筒状の空間が、無空テクノロジーなのだが、その最上部、アビリティに近い領域が、シャドー・テクノロジーである。
具体的にはモビリティとアビリティに直接的に関係のある技術が中心である。
例を挙げるなら、デリバリングが代表的。フォワード・デリバリングと、バック・デリバリングがある。
その他、構造的方向性を用いた打撃法、連関動作など。=手足のモビリティ
木:シャドー・ファンクション
アクションの技には、攻防以外の隠された機能が共存している。
だからそれを格闘技の技と比較したり、同一視してもあまり意味がない。
シャドー・ファンクションとは、秘められた、外部からは見えない、表現としての独自機能。見栄えのよさと、攻防のやりやすさを両立している。
相手を攻撃している打撃技であるにも関わらず、「殴り」を例にすると以下の特徴がある。
動きが大きく力強い(無段階で大きさが調整可能)
見栄えがするフォーム
何をやっているか分かりやすい
相手が受けやすい(ブロック)
相手が避けやすい
相手がやられやすい
シャドー・ファンクションを維持したまま、技のクオリティを向上させることが、アクションにおける技の上達であり、それ以外の(例えば格闘技的)上達は無意味で使えない。
金:シャドー・エリア+まとめ編
シャドー・エリアとは、シャドー・アクションの別名であり、アクションの持つ視覚的に見える領域以外の、影に隠れた技術領域のことである。
=シャドー・アクションは、領域というよりそこで行われる技術を指す意味が強い。
アクション表現における影の領域のこと。本来はプロしか存在しなかったアクションには、表からは見えない表現を成立させるための技法が、あたかも影で覆われているかのように、具体的形態とともに共存している。
その基盤があるからこそ、表現として成立するわけで、この点が武道・格闘技とは圧倒的に異なるところである。
逆に考えると、これまで武道家がアクション作品に参加しても、それなりに表現として成立していたのは、彼らのパフォーマンスが表現として成立するように、シャドー・アクションを駆使してやらせていたからであって、決して武道がそのまま映画表現に通用するというわけではないのだ。
要するに、やらせてもらっているだけだったのだが、そのことを当人が自覚していなかっただけで、そこを支えていたのはシャドー・アクションなのである。
シャドー・アクションには、このように「やらせてあげる」ことを可能にする機能があるのだ。
<シャドー・アクション>
月:シャドー・ワーク
アクションには影の領域が多いということが、知られていないだけでなく、やっている当事者ですらわかっていない。
それを明るみに出し、名称を与えた。それがシャドー・アクション・シリーズといえるもの。
ルーツは、イリイチのシャドウ・ワークにある
シャドウ・ワークとは、産業社会が財とサービスの生産を必然的に補足するものとして要求する労働。=賃労働を補完する労働。家事や試験勉強、通勤・・・他。
火:シャドー・ムーブ
アクション進化論で発表済みである。
アクションの技とは、単独で成立しているのではなく、受ける(やられる)相手との協働運動とセットで成立している。その相手の協働運動をシャドームーブという。
「殴り」を例にとる。
「殴り」は、なぜ殴りなのか?という疑問。
「殴り」とは、「殴る」という運動と「殴られる」という運動、つまり「殴る側」と「殴られる側」双方の運動の協働によって成立している。そこに「殴り」という言い回しの微妙な意味性が含まれている。
しかし実際はそうでも、視覚的には見世物として主役側、つまり殴る側の動作が目立ってしまうだけでなく、意図的に目立たせようという表現上の力学が働くために、打撃技としてのパンチ=殴る行為だけが「殴り」だと思われがちになってしまい、殴られる側の運動は見過ごされてしまう。
この本来なら「殴る」+「殴られる」=「殴り」であるはずの、等価であり協働運動としての一つの表現の片側「殴られる」が「殴る」の影に隠されてしまうことをシャドー・ムーブと表現した。
水:シャドー・テクノロジー
アクションの本質、無空中枢の潜在下に構造化された独自技術体系。
ドーナッツの中央は、モビリティとアビリティ
その下に位置する筒状の空間が、無空テクノロジーなのだが、その最上部、アビリティに近い領域が、シャドー・テクノロジーである。
具体的にはモビリティとアビリティに直接的に関係のある技術が中心である。
例を挙げるなら、デリバリングが代表的。フォワード・デリバリングと、バック・デリバリングがある。
その他、構造的方向性を用いた打撃法、連関動作など。=手足のモビリティ
木:シャドー・ファンクション
アクションの技には、攻防以外の隠された機能が共存している。
だからそれを格闘技の技と比較したり、同一視してもあまり意味がない。
シャドー・ファンクションとは、秘められた、外部からは見えない、表現としての独自機能。見栄えのよさと、攻防のやりやすさを両立している。
相手を攻撃している打撃技であるにも関わらず、「殴り」を例にすると以下の特徴がある。
動きが大きく力強い(無段階で大きさが調整可能)
見栄えがするフォーム
何をやっているか分かりやすい
相手が受けやすい(ブロック)
相手が避けやすい
相手がやられやすい
シャドー・ファンクションを維持したまま、技のクオリティを向上させることが、アクションにおける技の上達であり、それ以外の(例えば格闘技的)上達は無意味で使えない。
金:シャドー・エリア+まとめ編
シャドー・エリアとは、シャドー・アクションの別名であり、アクションの持つ視覚的に見える領域以外の、影に隠れた技術領域のことである。
=シャドー・アクションは、領域というよりそこで行われる技術を指す意味が強い。
アクション表現における影の領域のこと。本来はプロしか存在しなかったアクションには、表からは見えない表現を成立させるための技法が、あたかも影で覆われているかのように、具体的形態とともに共存している。
その基盤があるからこそ、表現として成立するわけで、この点が武道・格闘技とは圧倒的に異なるところである。
逆に考えると、これまで武道家がアクション作品に参加しても、それなりに表現として成立していたのは、彼らのパフォーマンスが表現として成立するように、シャドー・アクションを駆使してやらせていたからであって、決して武道がそのまま映画表現に通用するというわけではないのだ。
要するに、やらせてもらっているだけだったのだが、そのことを当人が自覚していなかっただけで、そこを支えていたのはシャドー・アクションなのである。
シャドー・アクションには、このように「やらせてあげる」ことを可能にする機能があるのだ。
