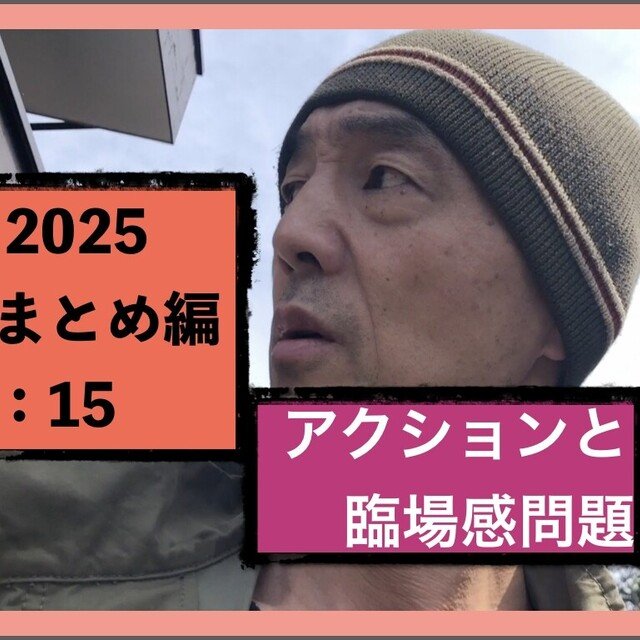
まとめ編15:アクションと臨場感問題
石田憲一
00:00 | 00:00
1月は、過去の配信を1週間分ごとにまとめて編集したものをお届けします。
<アクションと臨場感問題>
月:イントロ:振り付け問題について
段取りに見えるとか、見えないというのは臨場感の問題である。
アトミック・ブロンドについて
欧米型振り付けの問題
スコット・アドキンス、マイケルJホワイトの例
火:段取りに見えないとは
立回り概念がないから、スポーツ的発想になりがち。
知識がないものは見えない。
日本の立回り概念は、だから現代の初心者には難しい=容易に理解できない=実体験より
動画研究は、サンプリング思考になりやすい。
要するに実体験に乏しい者が、見よう見まねでやっているに過ぎない。
わかりやすいから、マネしやすい
権威盲信型劣化コピー=本質を理解していないから、よりメジャーなものの表現を盲信して、正しいことだという前提で自信を持ってマネする。
水:臨場感とバイオレンス
臨場感が高いということ
段取りを感じさせると、臨場感が下がる。
ということは、何に段取りを感じるか?がポイントとなる。
立回り鑑賞は、見る側に高度な認識的訓練を必要とする=高度な芸術性
だからその訓練がされていない場合、段取りと感じる可能性はある
立回り概念は高度なアート鑑賞眼が鍛えられてないと理解できない=楽しめない。
すなわち日本人は、そのものズバリの格闘表現は評価せず、高度に様式化された格闘を楽しむ知性を持っていた=浮世絵と同じ
芸術的理由でなく、商業的な理由による、わかりやすさの優先・追求によって、鑑賞眼どころか、理解力まで低下している。
時代劇映画の浮世絵的消費について
ありえないことを平気でやっているのだから、いくらリアルっぽく見せるためハードにやっても、段取りにしか見えない。
ハードさに誤魔化されてしまうのは、残念ながら鑑賞眼が未熟だから。
アクションは、その渦中にある
バイオレンス=死を感じさせる表現、それだけで自ずと臨場感が上がる。
格闘表現は、バイオレンスとの付き合い方、関係性の取り方に慎重になる必要がある。また踏み込みのレベルを熟考して全体を設計しなくてはならない。そこのバラツキがある作品は、未熟である。
木:臨場感とリアリティ
リアリティと写実性
臨場感は、リアリティと関係が深い。しかし映像作品については、リアリティを感じるポイントがちがう。
究極的には、作品を好きになってしまえば、作り手からすれば没入させてしまえば臨場感は高まる。
それがある意味、作品へのリアリティであり、一般的な写実性とはズレがある。
だから写実性を高めることがリアルという発想は、事実上の思考停止に相当する。
臨場感と写実性
例えば、殺し合いのアイデアとして写実性を高めるなら、武術の方法論導入が考えられる。しかし、究極的には地味な動きに終始するはずなので、見世物化としては失敗する可能性が高い。
かといって、それに見世物的アレンジを施してしまうと、単なる技やコンビネーションの羅列になるので、武術導入の意味は薄れる。
つまり写実性を高めると、観客側の臨場感は下がる傾向にある。ということは両者は反比例の関係にあるわけだから、相性は悪い。
現実の殺傷事件で残虐なものは、精神的に異常な状態で行われるケースがほとんど。だからアクション表現には、過剰な残虐性は適さない状況がほとんどのはず。
動きの写実性だけを取り出して、どうこうすることは無意味であることがわかる。
臨場感とカッコよさ
カッコよさを高めようとすると、臨場感が下がる可能性も高まる。
カッコよさを作るとは、作為性が高いからだ。
従って、自然にしていてもカッコいいという状態を先に作り出しておく必要がある。
いずれにしてもカッコよさとは、アクション表現の必須要素であり、それがあるならばアクションである。
金:臨場感と格闘法+まとめ編
段取りを感じさせる具体的な動き
板付きでの攻防
=捌かない防御
体格差やパワーの差を無視した攻防
自分に有利、相手に不利な状況を活かさないで無視した攻撃
板付きが要求されるカメラワークの場合
振付けに工夫が必要
演者にも工夫が要求される
横位置で前後の重心移動が可能なら行う。不可能なら左右の重心移動を取り入れる。
長引く戦いはリアリティを損なう
命の奪い合いは、長引かせると膠着するのがリアルな表現としては妥当。
つまり命の奪い合いと見世物化=長尺化は、表現として相性がよくない → リアリティを損なう。
長引かせるなら、逃げ回る状況を随時挿入するしかない。
いずれにしても、相性の悪い組み合わせは避けるのが無難。それがプロのセオリーというもの。その限界性があるのは当たり前で、その中での工夫がプロの技術。
その限界性を取っ払ってしまうのは、素人だから。メジャーであっても、素人表現は評価できない。それが受けているというなら、すでに崩壊の前触れである。
<アクションと臨場感問題>
月:イントロ:振り付け問題について
段取りに見えるとか、見えないというのは臨場感の問題である。
アトミック・ブロンドについて
欧米型振り付けの問題
スコット・アドキンス、マイケルJホワイトの例
火:段取りに見えないとは
立回り概念がないから、スポーツ的発想になりがち。
知識がないものは見えない。
日本の立回り概念は、だから現代の初心者には難しい=容易に理解できない=実体験より
動画研究は、サンプリング思考になりやすい。
要するに実体験に乏しい者が、見よう見まねでやっているに過ぎない。
わかりやすいから、マネしやすい
権威盲信型劣化コピー=本質を理解していないから、よりメジャーなものの表現を盲信して、正しいことだという前提で自信を持ってマネする。
水:臨場感とバイオレンス
臨場感が高いということ
段取りを感じさせると、臨場感が下がる。
ということは、何に段取りを感じるか?がポイントとなる。
立回り鑑賞は、見る側に高度な認識的訓練を必要とする=高度な芸術性
だからその訓練がされていない場合、段取りと感じる可能性はある
立回り概念は高度なアート鑑賞眼が鍛えられてないと理解できない=楽しめない。
すなわち日本人は、そのものズバリの格闘表現は評価せず、高度に様式化された格闘を楽しむ知性を持っていた=浮世絵と同じ
芸術的理由でなく、商業的な理由による、わかりやすさの優先・追求によって、鑑賞眼どころか、理解力まで低下している。
時代劇映画の浮世絵的消費について
ありえないことを平気でやっているのだから、いくらリアルっぽく見せるためハードにやっても、段取りにしか見えない。
ハードさに誤魔化されてしまうのは、残念ながら鑑賞眼が未熟だから。
アクションは、その渦中にある
バイオレンス=死を感じさせる表現、それだけで自ずと臨場感が上がる。
格闘表現は、バイオレンスとの付き合い方、関係性の取り方に慎重になる必要がある。また踏み込みのレベルを熟考して全体を設計しなくてはならない。そこのバラツキがある作品は、未熟である。
木:臨場感とリアリティ
リアリティと写実性
臨場感は、リアリティと関係が深い。しかし映像作品については、リアリティを感じるポイントがちがう。
究極的には、作品を好きになってしまえば、作り手からすれば没入させてしまえば臨場感は高まる。
それがある意味、作品へのリアリティであり、一般的な写実性とはズレがある。
だから写実性を高めることがリアルという発想は、事実上の思考停止に相当する。
臨場感と写実性
例えば、殺し合いのアイデアとして写実性を高めるなら、武術の方法論導入が考えられる。しかし、究極的には地味な動きに終始するはずなので、見世物化としては失敗する可能性が高い。
かといって、それに見世物的アレンジを施してしまうと、単なる技やコンビネーションの羅列になるので、武術導入の意味は薄れる。
つまり写実性を高めると、観客側の臨場感は下がる傾向にある。ということは両者は反比例の関係にあるわけだから、相性は悪い。
現実の殺傷事件で残虐なものは、精神的に異常な状態で行われるケースがほとんど。だからアクション表現には、過剰な残虐性は適さない状況がほとんどのはず。
動きの写実性だけを取り出して、どうこうすることは無意味であることがわかる。
臨場感とカッコよさ
カッコよさを高めようとすると、臨場感が下がる可能性も高まる。
カッコよさを作るとは、作為性が高いからだ。
従って、自然にしていてもカッコいいという状態を先に作り出しておく必要がある。
いずれにしてもカッコよさとは、アクション表現の必須要素であり、それがあるならばアクションである。
金:臨場感と格闘法+まとめ編
段取りを感じさせる具体的な動き
板付きでの攻防
=捌かない防御
体格差やパワーの差を無視した攻防
自分に有利、相手に不利な状況を活かさないで無視した攻撃
板付きが要求されるカメラワークの場合
振付けに工夫が必要
演者にも工夫が要求される
横位置で前後の重心移動が可能なら行う。不可能なら左右の重心移動を取り入れる。
長引く戦いはリアリティを損なう
命の奪い合いは、長引かせると膠着するのがリアルな表現としては妥当。
つまり命の奪い合いと見世物化=長尺化は、表現として相性がよくない → リアリティを損なう。
長引かせるなら、逃げ回る状況を随時挿入するしかない。
いずれにしても、相性の悪い組み合わせは避けるのが無難。それがプロのセオリーというもの。その限界性があるのは当たり前で、その中での工夫がプロの技術。
その限界性を取っ払ってしまうのは、素人だから。メジャーであっても、素人表現は評価できない。それが受けているというなら、すでに崩壊の前触れである。
