
【ディズニー】ラプンツェルとウォーリーとファンタジアとモンスターズインクとトイストーリーを見ました
こんにちは、たくやです。
明日ディズニーリゾートに行くということで、ディズニー映画5本を一気見しました。
今回は時間がないので簡単にですが、その感想をまとめていきたいと思います。
見た作品は、「塔の上のラプンツェル」「ウォーリー」「ファンタジア」「モンスターズ・インク(無印)」「トイ・ストーリー(無印)」です。
また、それぞれの映画について、どれもなんとなくキャラクターを知っている程度で詳細なストーリーなどは全く知りませんでした。対戦よろしくお願いします。
塔の上のラプンツェル

あらすじ
森の奥深くにある塔に住む「ラプンツェル」。その少女の髪は何十メートルもの長さを持ち、歌を歌うと触った者を若返らせる魔法の力を持っていた。
小さい頃から自分の誕生日になると美しい星が空を覆うのを何度も見て、いつかの誕生日には塔の外に出てその星を見に行きたいと願っていた。
感想
ストーリーライン自体は割と王道で、自分の出自を知らない王女がアウトローの男性と出会い、紆余曲折合って恋に落ちるといった感じで、言ってしまえばそこまで珍しいものではありませんでした。
しかし、話の随所に挟まれる楽曲の雰囲気づくりやギャグのテンポの良さ、終盤のランタンのシーンなどに代表される、視覚的な美しさには目を奪われました。
また、ストーリーラインが王道と言っても随所の展開は意外性が高いものが多く、自分も予想を裏切られるような思いを何度もしました。
特にラストのユージーンが髪を切るシーンは、今までの「髪を切ると魔法の効力が無くなる」「前にも同様の流れでキスをしようとするシーンがあった」などの伏線が見事に結実しており、同時にキャラクターのカッコよさも見える非常にいいシーンだったと思います。
印象的だったシーンとしては、もちろん上記で言及したシーンや、酒場で夢について語るシーンなどもそうですね。楽しげな宴というだけではなく、それぞれのキャラの目標を明確にしてストーリーの方向性やキャラの行動原理を明確にする役割も持っていました。
全体を通して、それぞれのキャラクターが立っていて行動原理も明瞭で破綻がありませんでしたし、それでいてそれぞれのキャラの見せ場などが明確に設定されているといった形で、ハイスタンダードなストーリーでした。
そのうえで視覚的・聴覚的な美麗さを通じた雰囲気作りなどのレベルが非常に高く、物語に引き込まれるような没入的な体験ができました。
ウォーリー

あらすじ
荒廃した世界でひたすらゴミを集めるロボット「ウォーリー」は、その過程で珍しいものを見つけると自室に持ち帰っていた。ある日宇宙からやってきた正体不明のロボットである「イヴ」と交流をしていると、イヴはウォーリーが持つ植物を見るとそれを格納して動かなくなってしまう。数日後、やってきた巨大な宇宙船へと回収されてイヴが宇宙へと旅立つと、ウォーリーはそれを追いかけようとする。
感想
基本的にメインキャラクターは「ウォーリー」と「イヴ」ですが、そのどちらもほとんど言葉をしゃべりません。また、人間のように顔のパーツが多くないのでそこまで表情のバリエーションが多くなかったように思えます。
そのうえでここまでストーリーや話の流れを作り切ったのは本当に演出とアニメーションの技量としか言えないですね。非常に興味深い体験でした。
個人的には二人が出会ってすぐにウォーリーが男性、イヴが女性に当たるキャラだということが直感的に分かったのは面白いなと思いました。
ウォーリーのジャンク感や古臭さが男性性のシンボルと結びついているのか、またイヴの曲線的なフォルムや感情的な行動が女性性のシンボルと結びついているのかは分かりませんが、ともかくとして表現力の一言に尽きます。
ストーリーも比較的凝っていて、メッセージ性としてはゴミ問題や「生きる」ことと「生き延びる」ことの違いのようなことを一貫して言及していました。目の前のモニターにばかり注目していて、自分のいる場所の景色や隣にいる人の顔を認識していなかった、というのは現代のスマホ問題にも通じるメッセージ性を持っていますね。
印象的だったシーンとしては、植物を見事回収したウォーリーとイヴが宇宙空間で踊るように漂うシーンでしょうか。
視覚的な美しさについては言うまでもないですが、ウォーリーが地球で夢見ていたダンスを行い、二人の「恋」も一応の決着を見るという象徴的なシーンになっており、それと同時に「ダンスとはなんだ?」と艦長が聞くシーンと並行させることで、そのシーンの意図が明確になっています。
宇宙空間・ロボット・消火器とジェットというように、とても我々の生活からかけ離れた要素の取り合わせでありながら、そこに「ダンス」という文脈と役割を持たせることで、このワンシーンと我々の現実世界を結び付け、人間の愛のようなロマンチックさを演出しているように思います。
ここでお互いの名前しか呼ぶことができないという制約が、逆にロマンチックさというか、愛の普遍性や強さを感じさせるようでとても良かったです。
総じて、地球の荒涼とした雰囲気や宇宙空間の美しさ、高いメッセージ性を持ちながら、あえて表情や言語に限界のあるロボットを主人公に据えながらその行動を表現しきった、意欲的かつそれが高い技量によって成功へと導かれた映画であったと思います。
ファンタジア

あらすじ
魔法使いの弟子として雑用をこなしていた一匹のネズミは、置いてあった師匠の帽子を使って魔法を使い、ホムンクルスに作業を代わってもらおうと画策する。
感想
正直なことを言うと…私にクラシックの素養が欠けているせいで、十二分に楽しむことができなかったように思います。
一応初めはすべてのパートを見ようと思っていたのですが、明確なストーリーが存在しないものも多く、また現代からしてみると音楽に合わせて作品を作る、楽曲に合わせて演出を行うというのは取り立てて珍しくもないので、あまり興味をひかれず、途中で視聴を中断しました…。
ですが改めて考えてみると、既存のクラシックにあわせて一本のアニメを作ることは非常に難易度が高いですし、フィルムなどが主流で、音よりも映像の進化が注目されていた時代において、オーケストラを使用することで音楽をメインにするといっても過言ではないような作品を作るというのは、確かに非常に挑戦的であったように思います。
そのような視点から、今日の映像作品全般や、音楽に関係する映像全般の源流になったものとしてはみる価値もあるかと思います。
モンスターズ・インク

あらすじ
モンスター界のエネルギー会社である「モンスターズ・インク」では、子供の部屋へと扉を繋げ、そこで得られる悲鳴を変換させることでエネルギーを生産していた一方で、社会全体にとって子供は恐怖の対象でもあった。その企業でナンバーワンの業績を持つサリバンは、ある日友人のマイクの日誌を提出しに行くと、業務時間を終了しても残っているドアから子供が出てきたのを見つける。
感想
子供が夜や暗闇への恐怖から、恐ろしいモンスターがいるのではないかと想像し怯えてしまうという共通体験に対し、その舞台裏を描こうとしたというのは非常に面白い着眼点で、いいテーマであるように思います。
その裏で、モンスターと人間という、お互いに偏見を持った存在同士の交流、そしてエネルギー問題に対する相互協調的な解決方法の提案というハイコンテクストなメッセージ性を持っていた作品であったと分析します。
キャラクター像としては、これまで自分が想像していたような、ディズニーにおいて典型的なキャラクターとは少しずれていたように思います。
昼行燈でありながら業績はピカ一であるサリーはその代表でしょうか。ことディズニーにおいてはあまり主人公に見られない性格だったようにも思います。
個人的に気になったのは、ブー周辺の行動や展開でしょうか…。
かなり個人的な感想になってしまうかもしれませんが、子どもが自分勝手に振舞って迷惑をかける…みたいなのはあんまり見ていても愉快ではなかったですね…。もちろんコミカルな描写が中心なので、そこまでハードにとらえることはないと思います。
ただまあ個人の浅慮や独断で問題が複雑化していくというのは結構見ている側もフラストレーションが溜まるように思います…。
そのうえで、サリーがブーに対して愛情を見せだすのもよく分からなかったですね…。
自分が見落としているだけかもしれませんが、サリーが本来強い偏見の対象であり、なおかつモンスター界で害を成しうる存在であるブーに対して愛情を見せるという展開は、あまり納得がいっていませんでした。
もう少し象徴的に愛が芽生えるシーンを時間使って描くだとか、せめて何らかの形でブーの行動によってサリーが救われた、というようなシーンがあれば、感情移入もしやすかったかと思います。ブーが描いたサリーの絵?そうかな…そうかも…。
それで言うと別にモンスター界の事情から考えれば子供を拘束してエネルギー源にしたところで、そもそも別世界の別生体の生き物なんだからそこまで非人道的だともいえないだろ…とも思ってました。まあそれじゃ悲鳴→笑い声みたいな形で相互協調的なエネルギー問題解決が描けなかったからかな…?そうかも…。
トイ・ストーリー
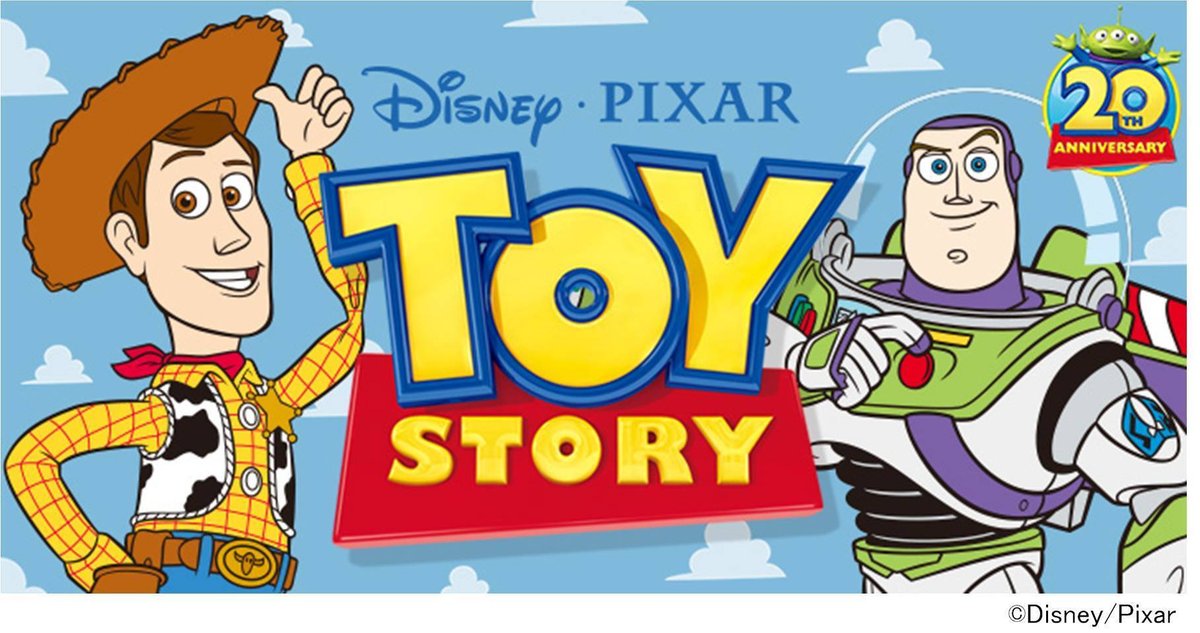
あらすじ
人間たちが見ていないとき、おもちゃたちは自由に動き回り、遊んでいた。保安官の人形であるウッディは、長い間持ち主の子供であるアンディのお気に入りだったが、ある日スペースパイロットのバズ・ライトイヤーがアンディにプレゼントされると、アンディはバズでばかり遊ぶようになる。
感想
こちらもモンスターズ・インク同様、面白い着眼点から生まれた、非常にいいテーマの作品だったと思います。
ジブリの「借りぐらしのアリエッティ」を彷彿とさせるような(もっともこちらの方がかなり後に作られた作品ですが…) 、小さい生物ならではのおもちゃの使い方やそれぞれのおもちゃの個性が焦点化された役割やストーリー展開は、独特な世界観を構築していました。
印象的なシーンとしては、バズが自分をおもちゃだと認めるシーンでしょうか。
それまでスペースマンとしてのアイデンティティを持っていた彼がそれを喪失し、そのうえでおもちゃとして誰か(アンディ)から愛されていることを自覚し、自己を再定義するという流れには普遍的なメッセージが包含されているように思います。そのうえで最後に「カッコつけて落ちているだけさ」とさらっと認めて言って見せるバズの姿は非常にかっこよかったですね。
その前の展開でいうと、嫉妬に駆られた悪徳保安官と世界五分間前仮設の被害者みたいなセットがどんどんと物語を悪い方向に転がしていくのは、モンスターズ・インクと同様にあまり気持ちよくなかったです…。
そういう意味でもこの二作品はかなり似通っているのかもしれないですね。
ともかく、そんな序盤からだんだんと成長して二人が「相棒」になっていく
という流れは痛快で、終わり方はかなり良かったように感じました。
総じて、子ども心をくすぐってを魅了するような世界観が展開される中でアイデンティティの拡散、再定義という流れがきれいに表現されていて、キャッチーでありながらよく考えられたストーリーであったと思います。
ディズニー全般についての感想
今までディズニーはアナと雪の女王くらいしか見たことがなかったので、今回が真面目に触れる最初のディズニーでした。
どの作品も子供が理解しやすく楽しめるようにキャッチーで、なおかつそこに込められた大切なメッセージのようなものを感じられる、まさに「子供向け」の作品群であったと思います。
特に、これは批判ではなくむしろ工夫として好感を持ったとことですが、展開のうえでそこまで中核ではないところは深く作りこまずキャッチーさに振り、重要な所はちゃんとつくる、というメリハリが印象的でした。
例えば「ラプンツェル」では、老婆の陰謀や髪の仕組みを利用した伏線など、破綻なく一貫した展開をしていたと思います。
その一方で「酒場の男たちはどうやってここまで侵入して助けに来てくれたの?」「馬なのになんでこんなに強靭で色々なことができるの?」といったようなところには全く触れず、展開の熱さやギャグに振っていたように思います。
まあそもそも現代のフィクションが設定偏重すぎるという話はありますが、子供向けということもあり、展開の辻褄合わせに終始することなく、なおかつ展開のキャッチーさのために少し「嘘」をつくといった作品作りからは工夫を感じ取れました。
また、その他に印象に残ったのはやはり「表情」でしょうか。
眉をひそめる、口角を上げる、鼻を鳴らすといった形で、豊かな表情変化を派手に分かりやすく演出していました。
ともすれば芝居がかって大仰で奇妙に見えなくもないのですが、まあ私も一応生活の中にディズニーがあった世代ということで、そこまで強い違和感を感じませんでした。ディズニーが子供の情操教育に一役買い、ディズニーがきっかけで感情の起伏を学ぶというケースも考えられるくらいの世代なので…。
それに加えてBGMだとか効果音だとかも感情表現を支えるエッセンスとしてうまく機能していて、そのリソースの割かれ具合からも「人間」を描こうとしている作品群だというような印象を受けました。
あと繰り返し使用されるシンボルで印象に残ったのは、「アウトローの仲間たち」でしょうか。
『ラプンツェル』の酒場のごろつきや『ウォーリー』の修理対象ロボット、『トイ・ストーリー』のシドの家のおもちゃたちなどです。
これらはなんで多用されているんでしょうね。
ウォルトディズニーの趣味なのか、海外の聖書的な、清貧的な世界観に起因するものなのでしょうか。なんにせよ、これらのアウトローはそれぞれの夢や異常性などの個性が非常に多様で、活躍が分かりやすく、派手でよかったです。
書いてから思いましたが、集団主義(画一化された兵士やロボット、おもちゃ)と個人主義の対立構造から生まれているのかもしれないですね。
5作品をかなりざっくりと視聴しましたが、どれも面白かったです。
ディズニーはほとんど知らないんですが、今回見た作品の続編や、他の面白い作品にも触れてみたいですね!
他にもおすすめのコンテンツがあればマシュマロに送ってください!
できるだけ摂取して感想を投稿します!
