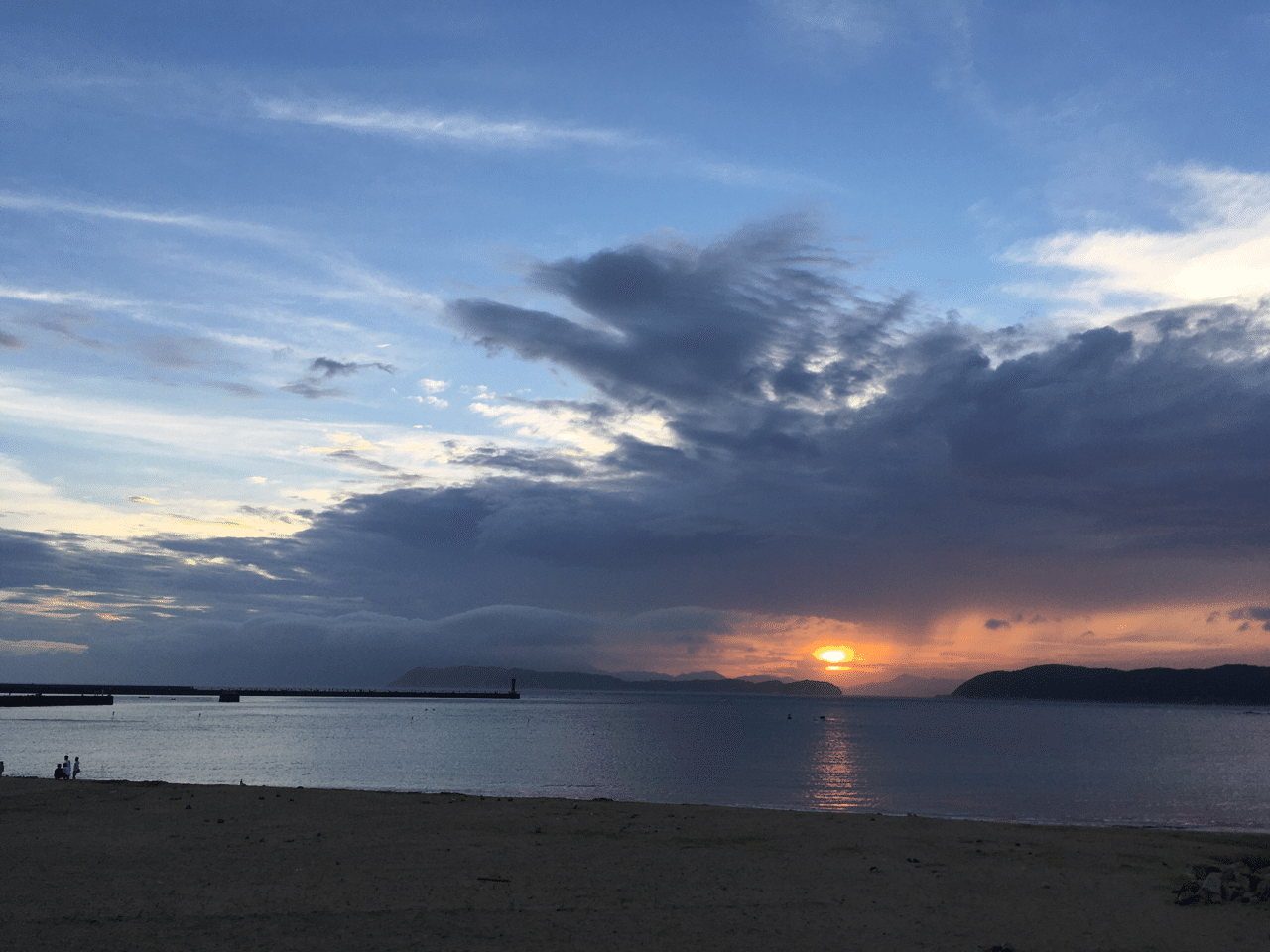「精神科医は何もしてくれない」は順調の証?
精神科医が、ちょっとテンション高い時、
体調が良くて、調子に乗って診療に当たっている時、
休み明けで身体も気分もリフレッシュされている時、
たいてい、精神療法としては、うまく行かない。
ということを、
経験上知っている。
余計なことを、してしまうんですね。
余計なこととは、親切、アドバイス、熱意、工夫、技法、、
一般的には、良いこととされていることが、回復を邪魔する。
助言や励ましなら、親切なおばちゃんのほうが絶対うまい(笑)、
精神療法や心理療法の時間なのに、もったいない使い方です。
逆に、寝不足や風邪っぽくて体調不良の時、
かえって、精神療法がうまく運んだりする。
力みが取れて、患者さんの持つ自然の回復力に、
任せられている感じですね。
神田橋先生は、「主体的受動性」と呼んで、
心身療法家の達人の姿勢だと、言っておられます。
まだまだ、そんな境地には程遠いですが、
自分の調子が診療に与える影響は、
若いときよりは、だいぶ減ったとは思う。
自己管理のコツは、気分や体調もよく、
何かしてやろうと熱を上げるのでなく、
自分のこころががニュートラルで、クリアな状態、
が、望ましいポジションという気がします。
そもそも、支えになる人物って、
なんかする、役に立つ、頼りになる、
から、存在価値があるのではなく、
打つ手なし、何もできん、役に立てない、
でも、話に向き合ってくれるところに、
存在価値があるように思う。
親や先生とかをイメージしたら、
そういう見守りの役割をしてくれたように思う。
不満や八つ当たりを言いながらも、
そんな支えになる存在がいてくれたから、
行き詰まってどうにもならない、と思った状況でも、
自分を生きてこられたように思います。
「精神科医は、何もしてくれない」と、
世間さまからお叱りの声をいただくことがあります。
これは、ある意味、その通り。
そこにふんばってこそ、治療的空間になり、
順調に進んでいる証、
今度から、
褒めてくれているんだと思おう(笑)