
『「ロウソクの科学」が教えてくれること』ほかレビュー

『「ロウソクの科学」が教えてくれること』~炎の輝きから科学の神髄に迫る、名講演と実験を図説で~
マイケル・ファラデー(原著), 白川英樹(監修), 尾嶋 好美(編集 | 翻訳), ウィリアム・クルックス(原著)
🕯 🕯 🕯
科学の本の世界に『ロウソクの科学』という歴史的名著があります。
これは、電磁誘導の法則や電気分解の法則などの発見、モーターやブンゼンバーナーの発明、そのほかさまざまな偉業を成し遂げて、科学史上最も影響を及ぼした科学者の一人とも言われている偉人、マイケル・ファラデーが、クリスマス・シーズンに子どもたちへむけて行った講演を元にした本です。
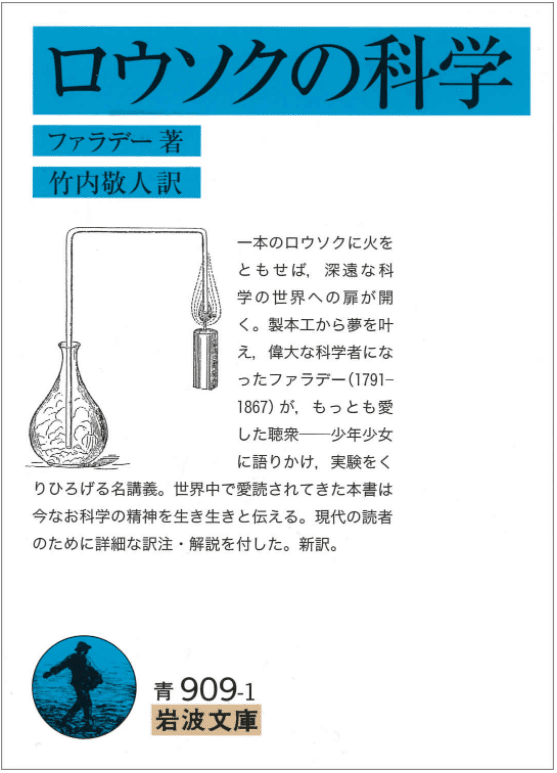
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784003390917
ロウソクはどうやって作られるのか、なぜ燃えるのか、炎はなぜあんな形をしているのか。といった素朴な疑問からはじまり、熱や光、燃焼とはなにか、空気とは? 水とは? 炎・空気・水から化合物や元素の話、大気圧に電気、雷のはなし、そして化学や生物、人体に至るまで非常に広範囲の科学の話題を、子供にもわかるよう丁寧に、興味深い実験を繰り返しながら説明してくれます。
そんなうるとら「名著」なんですが、何しろこの講演が行われたのは1860年、今から160年も前のこと。内容は今でも十分通用するとおもうのですけれど、実験方法や社会の常識などがちょっとばかり現代とそぐわなくなっていました。
なにしろ主題になっている、当時は照明の主役だった「ロウソク」が最近じゃあんまり身近じゃなくなってきてますもんね。
昔のことだよって最初に理解しながら読むと、歴史も味わえておもしろいんですけどね~。
で、そんな、イマドキに合わせて、『ロウソクの科学』を現代のご家庭や学校でできる実験にリファインし、図と写真で再構成したのが、この本
『「ロウソクの科学」が教えてくれること』
なわけです。
原書を読んでいてよくわからないなーとスルーしていたポイントがちゃんと図や写真で示されているのと、

原文のファラデーさんの言葉だけでなく、しっかり現代風に解説されているので、オビにあるとおりとってもわかりやすいのです。つまり、科学の解説の解説本ってわけ。
ちなみにこの本の監修者は2000年にノーベル化学賞を受賞された白川英樹先生!! めちゃ贅沢ですね!
そういえば、2019年にノーベル化学賞を受賞された吉野彰先生もこの(原本の)『ロウソクの科学』を愛読されていたとか。さすがは「名著」!
ちなみにちなみに、もしも19世紀にノーベル賞があったなら、ファラデー先生は幾度も受賞したにちがいないともいわれる大先生なのです。その講演録は、160年の時を超えて科学する心のときめきを私たちに伝えてくれるのです。ありがたやー☆
🕯 🕯 🕯
いっぱいのロウソク
さて、いくつかの余談ですw
なにしろ超古典的な名著なので、さまざま訳されておりまして

ぱっと探せるだけでもこのぐらい出てきました。
この中では左下にある
角川文庫版『ロウソクの科学』三石巌(訳)
がもっとも古い訳(1962年)ですが、2012年に改訂されているので、ふつうに読みやすい文になっています。また、けっこうルビも多いのでお子様でも安心♪(でもやっぱり古い内容なので小学校低学年だと理解はちょっと苦しいかも?)
つづいて、平凡社版の
世界教養全集〈30〉
に入っている『ろうそくの語る科学』岡邦雄訳(1963)が当時のままの文体でなかなか良い味w。とはいえ、ちゃんと現代文的に読めます。すこし古い言い回しがいとおかし。
さらに、なにしろ教養全集なので、他の教養を高めてくれそうな収録作品も名著ぞろいです。これ通読したら教養あふれちゃうことまちがいなし!?
わたしは幼少のころに挑戦しましたが当時の読解力では挫折したおぼえありですw
格調高い本を読みたい中二病世代におすすめかも?
岩波文庫版『ロウソクの科学』竹内敬人訳

こちらは新訳。旧訳版は1933年、ドイツ語版からの邦訳で矢島祐利訳とのことですがそちらは入手できず。図書館にあるかなー?
新訳は2010年の改訂版。ファラデーの講演からちょうど150年目に出された本で、昔の雰囲気をのこしつつ、現代人が読んでも理解できるように丁寧な訳注があり、「ファラデー 人と生涯」という人物伝記的なまとめも入っていてお得な本。先に書いたように原文訳ではこちらがいちばんおすすめです。
そして! ある意味ファラデーさんのオモシロ実験をつかった子どもたちへの科学啓蒙精神を継承している本がこちら!
角川つばさ文庫『ロウソクの科学』 世界一の先生が教える超おもしろい理科
平野累次/冒険企画局(著/文) / 上地 優歩(イラスト)
ファラデー先生ご本人ではなく、ファラデー先生のファンだという原出先生が登場。ふた子の子供たちの自由研究の題材にと、『ロウソクの科学』をつかって、興味をひくエピソードとともに実験を行っていくストーリー。ちゃんと『ロウソクの科学』していて、ちゃんと〈超おもしろい〉内容になっています。こういうのすきだわー☆
※(かるくネタバレ)岩波版の『ロウソクの科学』を読んでから読むと、二人がもらった本はレッド版とブルー版だったのかなーなんて想像してしまったりねw
🕯 🕯 🕯
と、ゆーわけで、『ロウソクの科学』は科学の初歩(といいつつけっこう高度なところまで)を解説してくれる名著中の名著。古今東西のノーベル化学賞受賞者が(たぶん)幼少のころに感銘をうけて人生を変えたであろう、ある意味ノーベル賞受賞者製造機とも言えそうなこの本。今回紹介した本たちは味付けがちょっとづつ違いますがどれも原書のファラデーさんの成分はしっかり伝えてくれています。
🕯
そうそう、英語版原書はファラデー著となっていますが、実はファラデーさんの講演をウイリアム・クルックスさん(この方も高名な科学者であり科学雑誌編集者)がテキスト化したものが原本なのです。で、その序文でクルックスさんはこう予言しています。
『この本を読まれた者の中で幾人かは、その生涯を科学の追求にささげるだろう』
と。
そしてまた、おそらくは、ファラデーさんの講演で語られていることにからめて科学を火にたとえつつ、青少年の心にともったその炎をさして、
『科学のともし火は燃えあがらねばならぬ。
炎よ行け。』
なんて檄文で序文を締めくくってくれています。かっこいい!!
くぅぅ、燃えるっ!!w
息子さん娘さん、親戚や縁のあるお子さんたち、または、あなたご自身でも。イマドキの高輝度LEDに過電流を印加したり、電球のフィラメントを燃やし切る実験でわかった気になっちゃう前に、まずはロウソクで科学する心に火を灯してみてはどうでしょう?
物理的に火事をおこしちゃダメですけど、心にともった炎は、いつしか燃え上がって、場合によってはノーベル賞が取れちゃったり、世界を変えたりできちゃうかもしれませんよ? 🕯
れっつふぁいやー! ("Alere flammam." (原文・ラテン語かな? 意味は訳してみて!))
#マイケル・ファラデー #科学の本 #児童書 #らせんの本棚 #ロウソクの科学 #白川英樹 #尾嶋好美 #ウィリアム・クルックス
いいなと思ったら応援しよう!

