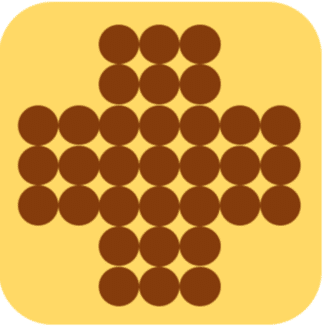The Genius GEMS の紹介
以前の記事「THE GENIUS STAR の考察」、まだ引っ張ります。
なぜなら同じパブリッシャーが、またしても次の作品を発表したからです。パズルゲームシリーズ第3弾です。すごい開発意欲のある会社さんです。
ところが、今回の表題は「The Genius GEMS の紹介」になってしまいました。実は、素人が「考察」できるようなゲームシステムではなかったのです。
今日は、悔しながらゲームの紹介のみとなります。
https://boardgamegeek.com/boardgame/364357/genius-gems
今回のもダイスを使うパズルゲームなのですが、今までとは異なり、お邪魔ピースはありません。
お邪魔ピースのかわりに、新規導入されたのは、ダイスで「形状パターン」を表示し、そのパターン完成をめざすという方式です。

例えば「赤」の宝石は「三角形状」に並ばなければだめで、青の宝石は「直線状にならんでないとダメ」・・・という、そんな指示が、ダイスでランダムに提示されます。ということなんです。
赤、青、緑、黄、橙、の5種の宝石について、それぞれの色ごとに個別の命令を、全部満たさねばならないっていうパズルゲームです。
ところが、宝石のピースの方は「赤宝石2個+黄色宝石1個=宝石合計数3個」がくっついてる状況で手渡されてくるせいで、「さあ、急いで5つの課題を全部満たす配置を発見しなさい」と言われても、なんだが自信がなくなります。
5個のダイスで示された「形状」全パターンを満たすような置き方が本当にあるのか??
ちょっと見した印象としては、完成できる気がしません。ちなみにマニュアルには、絶対に解があるのです!って自信満々に書いてあります。
私がなによりもガッカリしてしまう点は、以上の情報を見て、数学的に何か解析してみたい、という気持ちが沸き上がるけど、どこから着手すればいいか、途方に暮れてしまう。手がかりがない、というところなんです。
ダイスを振り、それによりランダムで表示される形状パターンを、5色すべてについて満たすような配置を考える。
それって本当に可能なのかどうか、数学的に調べてみたい!
でも、それを調べる術が思いつかないのです。
*まさか、コンピューターで総当たりする方法以外には、解析法がないのでしょうか?あの、数学的に有名な「四色問題」と同じように?
今日は、解析法が思いつかず、私、ラジくまるが解析断念。完敗。
というストーリーでした。
追伸:
「四色問題」で思い出すのは「ミヤザキ ユウ」さんの作品「サバンナテリトリー」ですよね。
後日、これの詳細記事を書きたくなるかもしれないので、ココでは簡単に書きますけど、おそらくボードゲームに「四色問題」を使ったのは、このゲームが世界初かと思います。
それって、ものすごいことですよね。
ちなみに、どうしてボドゲ業界にはノーベル賞的なものがないのでしょう?
世界初の試みなんだから、表彰されるべきだと思うんですが。
ところで、「四色問題」をずっと前から知ってるだけで、それを全然ボドゲに応用しようと試みなかった私は、すっごい悔しかったです。個人的に・・・・・
これをボドゲ販売店で発見した時に!
箱を見ただけですぐに「四色問題!」って気が付くようにデザインされている事もウマイと思いました。
いいなと思ったら応援しよう!