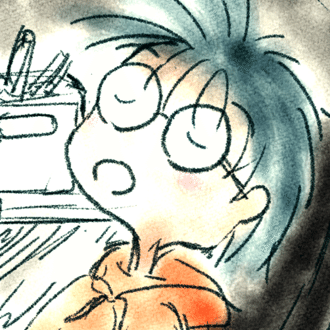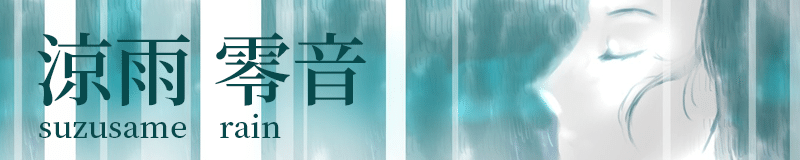世界と オレと シングルトン
仕事を終えて部屋に戻ると、オレは一人、ウィスキーを飲む。どこかでもらったジャック・ダニエルのマークの入ったグラスに、シングルトンを注ぐ。
一人暮らしの部屋でヘタったソファに埋まりながらシングルトンを舐めると、いつも不思議な爺さんのことを思い出す。
◇
その爺さんに会ったのは市立図書館だった。
高校のころオレは、毎日授業が終わると市立図書館へ行って閉館までずっとそこにいた。図書館が閉館すると建物の前にあるベンチに座って本を読む。すっかり暗くなってから家に帰った。オレにとって家はめしを食って寝るだけの場所だった。
その爺さんはいつも同じ席に座って、きまって分厚い本を開いていた。それがいつも同じ本なのか、ときどき変わっているのかはわからない。オレが行くと爺さんはいつも来ていて、閉館で追い出されるまでいた。
ある日、閉館まで居座っていたのが爺さんとオレの二人だけだった。オレが先に建物を出ると、後ろから爺さんが声をかけてきたんだ。
「おい若いの。いつもいるなおぬしは」
若いのって、本当に若いやつをそんな風に呼ぶ爺さんっているんだな。それにおぬしって、妙に感心した。
立ち止まって振り返ると、爺さんは思ったよりもでかかった。178cmあるオレと並んでも、ほとんど同じか爺さんのほうがでかいぐらいだった。体格は間違いなく爺さんのほうがいい。肩幅が広く、腰も曲がっていないし胸板も厚い。塩七割ぐらいのゴマ塩ひげをみっちりとたくわえ、そのひげにうずめるようにしてマスクをしていた。目はフクロウのように鋭くて、裏世界でなにか特殊な仕事をしている、とか言われたら信じてしまいそうだ。七十は過ぎているように見えるけれど、殴り合ったらかなわない気がした。あとにも先にも、そういう爺さんは他に見たことがない。
「若いの。名前は」
「答える必要、ありますか?」
オレが警戒してそう答えると、爺さんはそのフクロウみたいな目を細めて「はっ。はっ。はっ」と、ひとつひとつ区切りながら笑った。
「答えなくて構わんよ」
オレはこの爺さんのことを計りかねた。いつ来てもいるのだから、きっとこの爺さんは毎日朝から晩まで図書館にいるのだろう。それであの椅子に座って一日中分厚い本を読んでる。そういう爺さんに悪いやつはいないような気がしたけれど、まだ油断しちゃいけないと思った。
「おぬしはいつも夕方現れる。閉館になると外に出て、そのままは帰らずに、その屋根の下のベンチに座ってまた本を読んでいる」
「見てたのかよ」
「なにか、問題を抱えているな」
爺さんはオレの質問には答えずにそう言った。
「余計なお世話だろ。あんたになんか関係あんのかよ」
いらついて敬語がすっぽ抜けた。爺さんはまた「はっ。はっ。はっ」と笑った。
「今日もそこのベンチで時間をつぶすつもりなのなら、どうだね。かわりにわたしのうちへ来ないか」
「は?」
オレは面食らって爺さんの顔を見た。均等な密度で生えたひげはマスクの形に合わせて刈り込まれていて、そこにすっぽりとはめ込むようにしてマスクをかけていた。これを外したところはちょっと見てみたいと思った。
「不安かね。こんな死にぞこないの老いぼれがおぬしのような若者を力づくで誘拐したりできんし、まさか捕って食いやせんよ」
爺さんはどう見ても死にぞこないには見えないし、腕っぷしだってオレよりはるかに強そうだったけれど黙っておいた。
「別に無理にとは言わん。他にすることがないなら寄っていくかねと誘っているだけよ。ほっ。ほっ」
オレはどうするか考えながら空を見上げた。あたりは陽が落ちて、街灯のLEDが空になった駐車場を寒々と照らしていた。
「LEDはすぐに明るくなる。少し前まではあれは水銀灯でね。ぼんやりと青白く点灯してからしっかり白く明るくなるまでにえらく時間がかかったものだよ」
爺さんはオレの視線を追って言った。
「ま、好きにしたらいい。すぐ近くだから。興味があればついておいで」
そう言って爺さんはオレを置き去りにして歩き出した。オレは離れていく爺さんの背中を見た。曲がっていないその背中は背負ってきた過去のなににも負けていなかった。それは戦い続け、勝ち続けてきた背中だ。そう見えた。気づいたらその背中を追って駆け出していた。
◇
オレが高校に入学したのを見届けると、父さんは、いや、かつて父さんだった男は、家を出て行った。オレと母さんを捨てて、どっかの派手な女のところへ行ったんだ。母さんはやけになって、金の話しかしなくなった。ぜんぶあの男が悪いんだからふんだくってやるんだといきまいてた。だけどそんなもんはやぶれかぶれで、見ちゃいられなかった。あの男は、母さんと父さんが離婚しても父さんはいつまでもおまえの父親だからな、って言いやがった。父親ってのは金だけ出す男のことじゃねえだろ。おれは、てめえみたいなやつは地獄へ堕ちろって言ってやった。
母さんも母さんで、あんな男と結婚して失敗したって、ごめんねって。オレに謝るんじゃねえよ。あの男と結婚したのは失敗だったのかよ。じゃオレは失敗の結果なのかよ。勝手に人の命を失敗にしてんじゃねえ。どいつもこいつも、みんな地獄に堕ちればいい。
オレの高校生活は、こんなふうにして幕を開けたんだ。一言で言えばくそったれだ。高校受験の勉強をしながら、両親の間で起きていたことはなんとなく感じていたけれど見ないふりをしてた。オレが志望校に合格したら、そのニュースが家族になにか良いことをもたらすかななんて、思ったりもしたんだ。オレはどうしようもなくおめでたいやつだよ。両親はオレの合格を待って離婚しただけだった。大人なんてそんなもんだと、オレはその時知ったんだ。
家には帰りたくなかった。だからぎりぎりまで外にいて、帰ったらメシを食って寝るだけという生活をしていた。母さんは何も言わなかった。言えなかったんだろうと思う。
壁という壁をぜんぶ本棚で埋め尽くされた爺さんの部屋で、化石と一緒に発掘されたみたいなソファに座って、気づけばそんなプライベートな話を全部ぶちまけていた。薄暗い部屋で目を細めて聞いている爺さんは本当にフクロウに見えた。
図書館から住宅街と反対の方へ進んで細い路地を山の方へ少し入った、町の喧騒から離れた雑木林の中に爺さんの家はあった。白塗りの木で作られた古めかしい建物だった。壁はいまどきのサイディングみたいな仕上げじゃなくて、ただの板にペンキを塗っただけみたいなものだった。薄いガラスの窓が円柱状にはり出していたり、緑色の三角屋根がついていたりするような、昔の外国映画に出てきそうな家だった。それは、そうだな、ちょうどミス・マープルが住んでいそうな家だった。
マスクを外すと爺さんのひげはやっぱりマスク型にくりぬかれていた。それはちょっと異様な顔だった。マスクをしていると一見普通に見えるのに、外すと滑稽だ。
「そんなふうにするならいっそ全部剃ったらいいのに」
「これは表現だよ。マスクは今やパンツと同じぐらい身に着けるのが当たり前だろう。脱いだら恥ずかしいぐらいがちょうどいいんだ」
爺さんはそんなことを言いながらグラスを二つとアイスペイルをテーブルに置き、本棚に本と並んで置かれていたボトルを持ってきた。
「念のために言っときますけど、オレ高校生ですよ」
「ん。酒はダメか。酒じゃないものはレモネードしかないけどいいか?」
爺さんはそう言うと、オレの答えは聞かずにレモネードを出してきてグラスに注ぎ、自分のグラスにはウィスキーを注いだ。レモネードのグラスをオレによこして、自分のグラスを額のあたりに掲げた。オレが同じようにすると、「おぬしの未来に」と言ってオレのグラスに自分のをコツンと当てた。どこか頭の奥の方に波紋が広がっていくような音がした。
オレがレモネードを一口飲む間に、爺さんはグラスのウィスキーを飲み干しちまった。氷だけになったグラスをテーブルに置くと、すぐにまたボトルを出してきて二杯目を注いだ。
「未来に乾杯ですか。クサいですね」
爺さんの手元を見ながら言うと、爺さんはまた「はっ。はっ。はっ」と笑った。
「本当はこの酒をおぬしにも飲ませたいんだよ」
爺さんはそう言ってボトルを手に取ると、オレに見せた。
「シングルトン」
オレはラベルに書いてある名前を読んだ。
「シングルトンというのは単集合のことだ」
「単集合?」
「数学で集合論はまだやらないか?」
「数学の用語なんですか?」
「そう。シングルトンは単集合。単集合っていうのは元が、元ってのは集合の要素、まあ中身のことだが、その中身がひとつしかないもののことだ」
「それをなんでオレに飲ませたいんです?」
「シングルトンは世界に一つってことだからだ。おぬしは世界に一人だからな」
「それって独りぼっちってこと?」
「そうじゃあない。そこが集合の面白いところだ。集合の要素がまた集合であってもいいんだ。だからある集合一つだけを元に持つ集合は、シングルトンなんだ。おぬしは今は一人かもしれん。これからおぬしの集合に、おぬしの必要とする人だけを入れたらいい。それはこの世に一つだけの、おぬしだけの世界だ」
「単集合って都合のいいもんなんですね」
「はっ。はっ。なんであれおぬしの世界なんだから、おぬしに都合のいいようにやればいいんだ」
◇
あの夜のレモネードの味を、オレはずっと忘れないだろう。
帰り際、爺さんは本棚から一冊のでかい本を取り出して貸してくれた。『虚数の情緒』っていう本だった。高校の勉強を始める前にこれを読めと言って貸してくれたんだ。
オレはたしかに爺さんの家でレモネードを飲んだし、爺さんはシングルトンってウィスキーを飲んでた。そして本を借りたんだ。おれはそのときまで、シングルトンっていう酒も『虚数の情緒』っていう本も知らなかった。間違いないんだ。
翌朝目覚めたら、爺さんが貸してくれた『虚数の情緒』は市立図書館の蔵書で、自分で借りたことになっていた。
その日から図書館で爺さんに会うことはなくなり、記憶を頼りに爺さんの家を探したけれど、雑木林はただ雑木林で、あの風変りな白い建物は見つからなかった。
でも酒屋で調べたらシングルトンっていうウィスキーは実在していた。オレはたしかにそんな酒のことは知らなかったんだ。あの日、爺さんに教えてもらったんだ。
『虚数の情緒』は図書館のを返すとすぐに同じ本を自分で買った。それを読んだおかげで進みたい道が見つかった。読んでいなかったら、きっと高校生活はもっとずっと面白くないものになっていただろう。
二十歳になったとき、少しの迷いもなく酒屋でシングルトンを一本買った。爺さんがやっていたのを思い出しながら、氷を入れたグラスに少しだけ注ぎ、ちびちびと舐めるように飲んだ。最初の一舐めは強烈だった。香りから想像していたやさしい味ではなく、舌を焼き尽くすような刺激だった。すぐに喉が熱くなり、どこにも触れずに脈拍を数えられるぐらい、こめかみが脈打った。
これが単集合か、シングルトン。オレは単集合の味をしっかりと自分に刻み込んだ。
◇
爺さん、オレはとっくに酒が飲める年になってるよ。爺さんはいったいどこへ行っちまったんだ。これを一緒に飲むんじゃなかったのかよ。話したいことは山ほどあるよ。
今年、誕生日に送られてきた父さんの、あの出て行った父さんからのバースデーカードに初めて返事を出したよ。今年の父さんの誕生日に、二人で会って酒を飲むことにしたんだ。
父さんと乾杯するよ。爺さんの教えてくれたシングルトンで。もちろん単集合の話をさ、してやるのさ。父さんはクソ野郎だけど、オレの集合にはやっぱり父さんも入れなきゃならないんだ。父さんがどんなにクソ野郎でも、それでも父さんがいなきゃオレは生まれなかったんだって、伝えようと思うんだ。
ジャック・ダニエルのマークの入ったグラスを傾けてシングルトンを喉へ流し込む。
爺さん、オレもシングルトンがうまいと思うようになったよ。
オレはグラスを額のところに掲げて、爺さんがしていたみたいに目を細めた。
どこか頭の奥の方で、静かに波紋が広がった。
《了》
いいなと思ったら応援しよう!