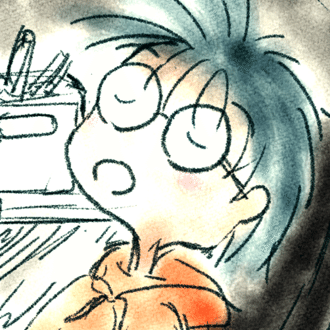あなたの作品を本当に好きな人は 好きと言わないかもしれない
もうだいぶ前のことになるけれど、わたしは音楽活動をしていた。
前に別のところで、文章を書くことは好きだったのにそれを仕事にするということはまったく考えもしなかったということを書いたのだけれど、実はわたしは楽器の演奏家になりたかったのだ。その夢が潰えたから、わたしはいまここにいる。
演奏家を目指して、自分のスタイルを追い求め、それなりに誰とも似ていない(と自分では思う)演奏をしているつもりだった。インディーズの、アンダーグラウンドなところで演奏活動をしながら、プロフェッショナルの道を目指していろいろなアプローチをした。
それがどうなったのかと言えば、どうにもならなかった。
つい先日習作として連載した「サイカイカフェ」をご覧いただいた方は「あれ?」と思うかもしれません。あの第三話に出てきた澄人というキャラクタ。まさにあれはわたし自身の経験に基づいて書いた人物でした。もちろん彼の通った道はフィクションですが、わたし自身の身に起きたこともあれにちかい感じではあった。
今でこそもう未練はなくて、当時愛用していた楽器は今も部屋に並んでいるけれど、もう手に取ろうとも思わないのですね。なつかしさは感じるけれど悔しさや寂しさはもうない。最初からなかったわけではなくて、時間をかけて癒えた。
どうにもならない状態で奮闘して、自分はそう悪くないものをやっているはずだという自負はありながら、でも客観的な評価はまったく得られない。そんなことが何年も続いていた。生活を維持しながら、まったく見えない将来のために日々頑張っていた。なにも実績ができないまま、時だけが無情に過ぎ、年齢がひとつ、またひとつと増えていった。
いよいよ進退窮まって、もうやめるしかないというところまで追い込まれた。でも簡単にやめられなかった。やめられるはずがなかった。
わたしは中学生のころから、なにもかもぜんぶなげうって音楽をやっていた。ぜったいに将来、演奏家として仕事をするんだ、と決めていた。いわゆる青春みたいな甘酸っぱいものは一切なく、限界まで自分を追い込んで鍛錬を重ねた。
これでちゃんと夢を勝ち取っていたら、これはとても美しい成功譚になっただろう。でもそうならなかったら、こんなになにもかも賭けてしまったもののやめるやめないの選択を迫られるというのは、端的に言えば地獄だ。
続けていてももはやどうにもならない。かといってやめるというのは、それまで生きてきた時間のほとんどすべてを否定するみたいなものだ。どうやって生きていけばいいんだとまで、思った。
悩みに悩んだけれど、よく考えてみたらやめるかやめないかという選択ではなくて、やめるか死ぬかみたいなことだった。死ぬわけにはいかないからはじめから選択肢などなかったということに気づいた。
そんな風に0か100かみたいに考えなくてもいいんでは? ということはよく言われたし、これを読んでそう思う人もおられるだろう。それが普通の感覚だし、きっと正しい。
でも生きていることの全部をぶち込んで頑張ったものを諦めるというのは、うまいバランスを見極めて折り合いをつける、みたいな器用なことができるような話ではまったくないのだ。これはわたし自身も、そこまで行って初めて体験した感覚で、おそらく同じことをした人以外にはこの感覚は伝えられないと思う。そこまで行ってしまうともうやめるか死ぬかみたいになるんですよ、としか言えないのだ。
◇
そんな想いで道をあきらめたあと、少ししてから一通のメールが届いた。
そのメールは、わたしの演奏を見るために何度もライブハウスへ足を運んだ、という人からのものだった。わたしの所属していたグループではなく、わたしの演奏が好きだったと、書いてあった。どんなプロとも違う演奏で好きだった、やめてしまったことは残念だと、書いてあった。
正直に書こう。わたしは、「なんで今さら言うんだ」と思った。こんなに嬉しい言葉はないはずなのに、嬉しいよりも先に「なんで、頑張ってやっているときに言ってくれなかったんだ」という恨み節が出てきた。そう言ってくれる人がいたら続けられたのにと、その時は思った。
自分を信じているのが自分だけだという孤独。そんな中で誰かの好きという言葉は強力な支えになる。たった一人でもそう言ってくれる人がいるとぜんぜん違う。それがまったくないまま自分だけが自分を信じて、真っ暗闇の中で見えない的に向かって弓を引き絞っている、みたいな状況は壮絶に苦しい。誰一人わたしのやっていることに価値を感じていないのであればまだしも、好きだと思っているのに言ってくれないなんてと、その時は本当に思ったのだ。逆恨みでしかない。
この時の経験があるから、わたしは自分のやっていることを好きでいてくれる人がいるかもしれないと、思うようにしている。たとえ誰からもひとつの評価ももらえなかったとしても、どこかでとても気に入ってくれている人がいるかもしれないと思うようにしている。
その見えない誰かにむかってわたしは作品を作る。
そして、わたしが他の人の作品を好きだと思ったら、それを作った人に伝える。
もしかしたら、その人に作品を好きだと伝える人が他に一人もいないかもしれないから。
いいなと思ったら応援しよう!