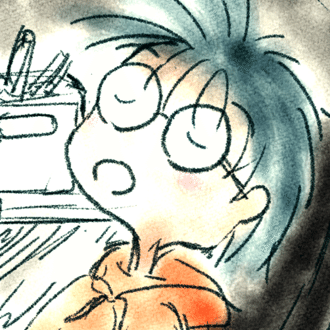[習作]サイカイカフェ #02 (#書き手のための変奏曲)
さすがに汗ばむ。こんな北の果てでも夏はけっこうな気温になる。冬はけっこうどころじゃなく寒いんだから夏はもう少し遠慮したらどうなんだ。避暑のつもりで戻ってきたのにこれじゃまったく涼めない。ここはひどく狭い町なのにこじゃれたカフェがいくつもある。スターバックスもマクドナルドもない町に自家焙煎のコーヒー屋ばかり何件もある。その全部がつぶれることもなく続いている。ここの住民はそんなにコーヒーを飲むのか。
今日は何年か前にできた店を紹介されて足を伸ばしてみたけれど、まず場所が不便すぎる。車に乗ってなきゃ行こうと思わない。それなのに駐車場には一台も入っていない。ほらみろこんなところまで客が来るものかと思いながらドアに手をかける。ビクともしない。少し体重をかけるとネズミを踏みつぶしたみたいな音がして開いた。なんでただのカフェにこんなレントゲン室みたいなドアが必要なんだ。
一歩足を踏み入れると、ドアのすぐわきに焙煎機が置いてあった。ステンレスの肌はオートバイのマフラーみたいにいくつかの色が混ざり合ったような状態に焼けていた。正しく使いこまれている証拠だ。正しく使われている機械を見るのは気持ちがいい。この焙煎機を見たら、バカみたいなドアのことは大目にみてやってもいいという気がした。
テーブルのところで接客をしていたらしい女がこちらを向いて「いらっしゃいませ」と言った。若い女と思ったけれどほとんど子どもだ。高校生か。
「カウンター席になさいますか?」と言いながら近づいてくる。
Tシャツにジーパンみたいななりでエプロンをしただけの姿だ。髪は一か所ゴムで縛っているだけだし化粧はまったくしていないようだ。いまどき高校生だってもう少し化粧ぐらいするんじゃないのか。奥を見やると店長っぽい男がカウンターの向こうで作業をしている。少し白髪も混じり始めたぐらいの年恰好で、ズボンはカウンターに隠れて見えないけれどTシャツにエプロンをしただけの姿だった。目の前のウェイトレスに目を戻すとそっくり同じ服装のように見えた。まさかこれがこの店のスタイルなのか。
「テーブルの席はある?」と聞くと「ございます。どうぞ」と言っておれを奥へと導いた。ぶっきらぼうな恰好をしているくせにふるまいは落ち着いている。高校生じゃないな。もう少し上か。
おれは店の一番奥のテーブル席へ案内された。一番奥と言ったって端から端まで7、8メートルといったところか。おれは一番奥の椅子に腰かけた。少し上体を傾ければ店の入り口が見える。あのバカみたいに重いドアが。
「お決まりになりましたら」とウェイトレスが言いかけたのをさえぎって「アイスコーヒー」と注文した。ウェイトレスは少しも表情を変えずに「アイスコーヒーですね、かしこまりました」と言ってカウンターの向こうへ入って行った。
長いカウンターテーブルは5、6人がけぐらいか。そのテーブルに使われている木材はおれの見立てによると大変なものだ。見たところ無垢材に見えるけれど厚みがゆうに10センチはある。それが4、5メートル。5メートル? さすがに無垢ってことはないか。しかし接いでいるにしても大変なものだ。この店で一番金がかかっているのはこのカウンターテーブルかもしれない。カウンターの奥はそのまま調理場のようになっていて、大きめのポットが三つ四つ湯気を立てている。そこに店長らしい男がいて、ほとんど無駄のない動きでコーヒーを淹れていた。店長は白髪まじりではあるものの顔のしわは少なく、それほど爺さんというわけでもない。決して若くはないだろうが。細いフレームの丸眼鏡をかけていてひげは無く、こざっぱりとした男だ。カウンターの奥の壁には音よりも見た目で選んだようなオーディオが埋まっていて、その周囲にはLPレコードやCDが詰まっている。一度も取り出されることのないものも少なくないだろう。レコードやCDだってかけるためじゃなく見せるために置いてあるだけだ。Tシャツにエプロンみたいな恰好で見かけは気にしませんみたいに見せておきながら、その実ほかのあらゆるものは見せることを強く意識して演出されている。何もかもポーズだし演出だ。
カウンターの一番入口に近い側の席にどう見てもこの店に似つかわしくない、よれよれの服を着たおっさんが座って店長に向かってべらべらとしゃべり続けていた。店長はろくに聞いていない風だけれどおっさんはまるで気にする様子がない。たぶん誰もいなかったとしてもしゃべり続るのだろう。よくもそんなにしゃべることがあるものだと思ったけれど、幸か不幸かおれの場所からは何をしゃべっているかまでは聞こえない。
「おまたせいたしました」と言ってさっきのウェイトレスがアイスコーヒーを置いた。おれが見上げて軽く頷くと、ウェイトレスは「ごゆっくりどうぞ」と言って会釈した。アイスコーヒーは入っている氷もコーヒーでできていた。こうすると氷が溶けてもコーヒーがうすまらない。たしかにそんな話は聞いたことがある。まさか本当にやる店があるとは。一口飲んでみると深煎りの香りが広がる。酸味のほとんどないタイプのコーヒーで、ブルー・マウンテンなんかを好む人にはウケが良くないかもしれないけれどおれは気に入った。
バカげたドアについた風鈴が仏壇のあれみたいな音をまき散らした。おれがドアの方を覗き込むと、すぐにあのウェイトレスが「いらっしゃいませ」と言って歩いて行った。細身のジーパンをはいた後ろ姿は少年みたいだった。ケツだ。ケツのボリュームが無さ過ぎるんだ。ぴったりしたジーパンなのに目を引かないようなケツがあるのか。あのケツが子どもっぽさの原因だろう。
戻ってくるウェイトレスが連れている客はまたもやしみたいにひょろ長い男だった。そいつはカウンターの一番奥、おれの目の前の席に座った。Tシャツの袖からほっそい腕が竹ひごみたいに突き出ていて、くしゃみでもしたらバラバラになりそうだった。おまえなにかの病気なのか。ミイラみたいだぞ。その男は身長分ほども離れていないおれにも聞こえないような声でウェイトレスになにやら注文をした。本当に生きているのか。おれにはウェイトレスの「かしこまりました」だけが聞こえた。
店の中に見るべきものがなくなってスマートフォンを取り出したらまたあの無神経な風鈴が鳴り散らかした。通路に乗り出すとおれの前にあの控えめなケツが割り込んできて「いらっしゃいませ」と言った。野暮ったいウェイトレスの後ろから入ってきたのは女だった。いるだけでそこだけ空気が変わるような女だ。照明灯の切れたトンネルの中を走ってくるヘッドライトみたいに周囲を照らすような、女だ。
「あれ? 優美じゃない? 優美」とおれは声を出していた。
「え、うそ。霧谷さん?」
優美はそう言っておれの向かいの席に座った。またドアの風鈴が鳴った。ウェイトレスはドアの方に目をやってから優美に水を出した。優美は座りながらおれの飲みかけのアイスコーヒーを指さして、「あれと同じのを」と頼んだ。ウェイトレスは優美に小さく「かしこまりました」と言うとドアの方に向いて「いらっしゃいませ」と言って次の客を出迎えに行った。
奥田 優美(おくだ ゆうみ)。またの名を坂城 夕(さかしろ ゆう)。なんだか都会の芸能事務所かなんかにスカウトされてアイドルみたいなことをやっている女だ。坂城のほうはそのアイドルをやるときの名前だ。この町からそういう女が出るのは珍しいから町じゃ誰も知らないものはないほどの有名人だ。それにしてはあのウェイトレス、優美を見ても顔色一つ変えなかったな。
「そっか。外の車、霧谷さんか。納得」
優美が両手で顔を扇ぎながら言った。
「なにが納得なんだよ」
「こんなところでポルシェなんか珍しいからね。霧谷さんなら納得」
「だからなにが納得なんだよ」
「霧谷さんって社長さんなんっしょ?」
「自分で会社を起こせばだれだって社長になれるよ」
「そうだけど、それがちゃんとうまくいってるんしょ」
「そうね。ポルシェ買えるぐらいには」
「そういう風に納得」
優美が口をあけて乾いた笑い声を立てたところにウェイトレスがアイスコーヒーを持ってきた。おれは残っていたアイスコーヒーを飲み干してウェイトレスにグラスを差し出し、「これもう一つ」と言った。ウェイトレスはグラスを受け取って「かしこまりました」とたいしてかしこまらない顔で言って下がった。
「優美はどうしてるのさ。うまく行ってるのか?」
「けっこうね。ぜんぜん有名にはならないけどそこそこ曲は売れてる」
「配信とか?」
「もちろん」
「へぇ、曲はどんなのやってるの?」
「そりゃ、アイドルっぽいやつだよ。ポップっていうの? だいたい片思いか背中押す系の歌詞」
「自分で書くの?」
「まさか、あたしが書けるわけないじゃん。音楽は1だし国語は2だよ。作詞も作曲もまったく無理。あたしは歌うだけ」
「じゃ曲は書いてくれるやつがいるわけか」
「いるいる。ふだんボカロっていうの? あのパソコンで歌ってくれるやつ。ミクとか。ああいうのでやってる人が書いてくれてる。ここの出身の人」
「ほんとに? ここの出身で作曲家なんているの?」
「いるんだよ。ロメオって人」
「なんだよそのふざけた名前は」
「ペンネームだけどさ。ロメオだよ。アルファベットでアールだけ大文字で、アールオー、ハイフン、エムイーオーって書くんだよ」
そんな話をしているところへ「おまたせいたしました」と言ってウェイトレスがおれの分のアイスコーヒーを持ってきた。
優美はウェイトレスを見上げて「ありがと」と言って笑った。おれはちょっと面食らって優美とウェイトレスを見比べた。ウェイトレスのほうはおれには構わずすぐ下がっていったけれど優美は見逃さなかった。
「あたしが店員さんにお礼言ったら意外?」
「え。いや、そんなことはないけど」
カウンターにいた男が立ち上がって出て行った。代金はカウンターに置いて行ったみたいだ。気取ったやつめ。ここは日本だぞ。日本のド田舎だ。金はレジで払え。ウェイトレスは出て行った男の背中に向けて「ありがとうございました」と言いながらカウンターの金を回収してレジを打った。
「同級生」
「は?」
「あの店員さん。あたしの高校んときの同級生」
「ああ、そういうことか」
「そういうことじゃなくてもありがとうぐらい言いますけどね、あたしは」
おれはカウンターの向こうで何か作業をしているウェイトレスを見やってから改めて優美を見た。この二人が同級生だとして、どういう会話をするのか想像もつかなかった。
変奏曲の主旨はこちら
いいなと思ったら応援しよう!