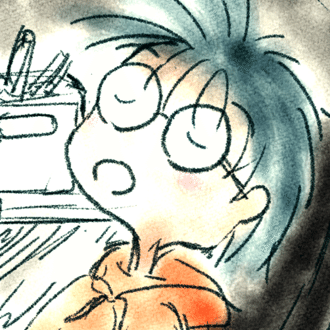[掌編]ヤバい
出発ロビーの窓から飛行機の翼を見るたび、脳裡に歌声が蘇る。ヤバいほど昔に流行ったアイドルの「時間旅行」という歌だ。そのヤバい歌声はまるで絹の手袋で陰嚢を撫でまわされているような感覚で脳に鳥肌が立つ。脳裡に響く歌がサビに差し掛かったとき、館内アナウンスが俺の乗る飛行機の遅延を伝えた。使用する機材の準備にヤバいほど時間がかかっているので出発が遅れるそうだ。ヤバい。俺は今日ヤバい会議に出るため、日本列島の半分ほどを移動しなければならない。そのために今空港の出発ロビーにいて、脳裡に「時間旅行」という歌を響かせながら飛行機を眺めているのだ。今日のはヤバいメンバーが揃うヤバい会議だから俺のような下っ端が遅刻するのはヤバい。かといって飛行機が遅れるんじゃこの事態をなんとかする方法は無いと言って差し支えない。端的に言うとヤバい事態だ。俺は窓から離れ、歩きながら現地で合流する予定の同僚に通話をかけた。
「飛行機が遅れるらしい」
「会議には間に合うのか」
「わからん。どの程度遅れるか次第だ」
「そいつはヤバいな」
「ああ」
「こっちは昨日ヤバいアイデアを思いついて資料を作り直してるところだ。ヤバいほど寝不足だがあと少しで終わる」
「そいつはヤバいな」
「マジヤバいから楽しみにしとけ」
「その前に俺は間に合うかどうかの方がヤバい」
「どのみち飛行機が飛ぶまではどうしようもない。到着したら走れ」
「ヤバいな」
待合の通路を無意味に何往復かしたところで通話を切って辺りを見回すと、ゲート付近に集まっている人々は各々どこかへ通話をかけていた。皆飛行機の遅れをどこかへ伝えているのだろう。
メイアイハブがアテンションされ、俺を含めたお待たせされている皆さんがご搭乗機へとご案内されるのは当初の予定よりもご一時間ほどご遅れになることが伝えられた。辺りにざわめきが波立つ。一時間はさすがにヤバい。到着空港からの移動も考えてヤバめに余裕を見てスケジュールを組んであるが、それにしたって一時間はヤバい。ヤバい力で走ったところで間に合うまい。開始時刻に間に合わないにしろ、せめて俺の発表には間に合ってほしいが、一時間も遅れるとなるとそれすらもヤバそうだ。俺は尻に汗がにじむほどヤバい焦りを覚えたがさしあたってできることは何もなかった。どうしようもないことを悟るととたんにヤバい空腹感が襲ってきた。近くに売店を見つけて行ってみると、空弁と称した弁当類やサンドウィッチなどが並んでいる。三千円近い値のついたヤバい海鮮ちらし寿司弁当を素通りし、六百四十円也のカツサンドを手に取る。カツサンドとのマッチングを考えてミルク入りのコーヒーを選んでレジに行く。貼り付けたような笑顔のヤバい店員がこちらを見ながら「次にお並びの方どうぞ」と俺を呼ぶ。俺の方に向けられた笑顔とはどうやっても目が合わなかった。アンドロイドかサイボーグか人造人間か何かそういったヤバいものなのかもしれない。店員は俺の差し出したカツサンドとミルクコーヒーを素早くスキャンし、「二点で七百七十七円です」と言った。俺は思わず「ヤバい」と声に出した。なぜ七が並ぶと幸運な気がするのかはわからないが、無駄なところで幸運を消費したような気がした。幸運というものが消費されるようなものなのかもよくわからない。俺は七百七十七円を電子マネーで支払うと伝え、手元の端末で支払いを試みた。が、残高が不足していた。ヤバい。慌てて二千円チャージしようと操作をしたら間違って二万円入れてしまった。ヤバい。
慌てながら支払いを済ませ、スーツケースを引っ張りつつカツサンドとミルクコーヒーを持って待合へ戻ると椅子は一つおきに埋まっていて座る場所は残っていなかった。ヤバいウィルスの蔓延によってソーシャルなディスタンスが維持されることを要請するため、椅子は一つおきにしか使えないのだ。迷惑な話だ。仕方なく俺は邪魔にならない場所を探してスーツケースを放し、その不安定な天面にミルクコーヒーのボトルを置いてからカツサンドに挑む。カツサンドは既にヤバいほどひしゃげていて、圧迫された部分のパンは踏み固めたはんぺんのような状態になっていた。カツサンドを包んでいるフィルムをはがすとそこら中押し出されたソースでヤバい状態になっている。俺は悪態をつきながらかぶりつき、指に付着したソースを舐めくりちらしてからミルクコーヒーのボトルに手を伸ばした。唾液で湿った指先がボトル表面の水滴と出会ってハイドロプレーンなことが起こり、ボトルは俺を嘲笑うようにスーツケースの天面から飛び降りて床に落ちた。ヤバい音を立てて着地したボトルは横倒しの状態で転がり、俺は慌ててかがんで手を伸ばした。はずみで傍らにあったスーツケースが走り出した。それぞれ反対方向に走り去ろうとするボトルとスーツケース。俺は自分がヤバいほどの運動能力を持ったスーパーヒーローであると錯覚して体をひねった。追い込まれた状況で脳の処理速度がヤバいほどブーストされ、俺は周囲の状況をスローモーションで認識した。片手を転がるボトルに伸ばし、反対の手をスーツケースに伸ばす。ボトルに手が届き、同時にスーツケースの方に伸ばした手にはカツサンドを持っていたことに気づく。ヤバい。とっさにカツサンドを中指と親指で挟み、薬指と小指をスーツケースの持ち手に伸ばす。スーツケースは無情にも傾きはじめ、俺の薬指と小指はそのままスーツケースの表面に突入した。ヤバい音と感触があった。ヤバい何かが脳に突き刺さり、少し間をおいてそれがヤバい痛みであることを知覚した。叫びそうになったが口が咀嚼中のカツサンドで埋め尽くされていることに気づいて踏みとどまった。残りのカツサンドは中指と親指の間でつぶれ、ヤバい方向に曲がった薬指と小指にソースを分け与えていた。
ひとしきり無言でのたうち回ったあと、俺は落ち着きを取り戻して床に座った。ミルクコーヒーのボトルはひしゃげ、カツサンドは見る影もなく、指はヤバい形になっていた。俺は股の間にミルクコーヒーのボトルを挟み、使えるほうの片手で蓋を開けようと試みた。片手ではなかなか難しく、開封と同時に飛び出したミルクコーヒーが俺の股間を濡らした。俺はヤバい状態で手の中に残っていたカツサンドの残りを口に入れ、ボトルからミルクコーヒーをあおった。口の中にあった何かがヤバいところに入り、俺はむせた。口の中のものを噴射しないようにがまんしたら鼻の方に押し寄せ、よりヤバいことになった。涙と鼻水を流しながらむせていると、ウィルスのせいで咳に敏感になっている人々が嫌悪感をあらわにして離れながら口々に言った。
「ヤバい」
「ヤバいね」
「マジヤバイ」
「ヤバすぎ」
「ヤバ」
それを聞きながら俺の脳裡にはまた「時間旅行」が流れた。
時計の針は戻せないのね。
《了》
いいなと思ったら応援しよう!