
11月20日(土) 緑肥作物
雑草の記事をアップした夜、
夫が『あるもの農園』のアイコンのイラストを描いてくれました。
ざっそうくん…草を愛でる気持ちが溢れ出ています♩笑

そして今回も、草に関する記事となります。
自然農で重宝される草。
畝を立てるために草を刈り、それを草マルチにして、その草マルチも畝の上で分解され、また草を敷き足し…さらに、雑草堆肥にも多くの草を投入して…
あれだけ草ボーボーだった『あるもの農園』が、気付けばサッパリ広くなりました。

「もしかして、このまま行けば草が足りなくなるのでは?」
そんな時、参考にしている竹内孝功さんの本で、緑肥作物というものを知りました。

緑肥作物とは、収穫を目的とせず、根の力で土を改善したり、茎葉をすき込んで堆肥や肥料代わりにする作物のことです。
収穫目的以外で育てる作物があるなんて!まだまだ勉強不足、奥が深いです。
緑肥と一括りに言っても種類は様々あり、主にイネ科やマメ科の作物が使われます。
自分で種を混ぜて用意される方もいますが、
今回はあらかじめ6種類の種が混ぜられている「緑肥mix」を、つる新種苗さんから購入しました。

●イネ科の緑肥作物
・えん麦
・イタリアンライグラス
・オーチャードグラス
・ペレ二アルライグラス
→細かな根が地中深くまで張って土を耕し、団粒構造を作る。
●マメ科の緑肥作物
・赤クローバー
・クリムソンクローバー
→根粒菌が根に共生し、土の中に窒素を固定して土を豊かにする。
イネ科とマメ科それぞれが異なる働きをします。また、クローバー類は生育が遅いので、自分で種を混ぜて用意する際も、イネ科と混ぜるようにとありました。
ここからは、緑肥を畑にまく工程の記録です↓
①通路に鍬でまき筋を付けます。


緑肥は踏むと消えてしまうので、通路の中央にまき筋を付けて、両サイドは踏まないように歩けるスペースを確保。通路幅はあらかじめ広く取っておく必要があります。

播種してから1ヶ月位はとても弱いので、踏まないよう特に注意が必要です。
(※踏んで消えてしまった部分は、まき足して覆土しておく。)
②まき筋に沿って種をおろします。

まき筋に、ムラにならないよう満遍なく種をおろします。
③覆土し、鎮圧します。
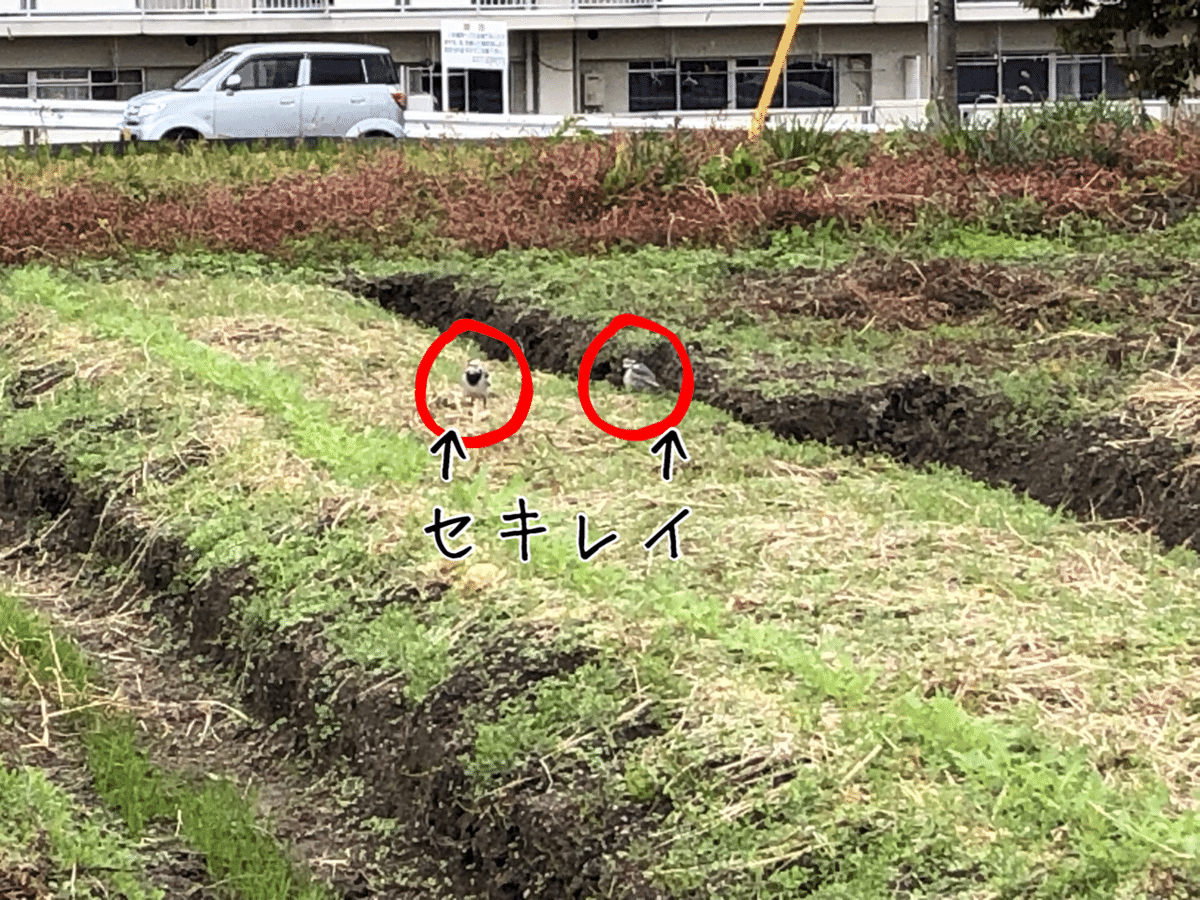
土を寄せて覆土し、足で踏んで鎮圧します。
消毒されていない種なので、鳥たちのご馳走になることも…『あるもの農園』にもよく鳥が遊びに来るので、種を隠すように覆土します。
以上で完了‼︎
1週間ほどで芽を出し、
1ヶ月を過ぎた頃には10cm程に成長しました。

緑肥作物の効果をまとめると↓
●草マルチ
通路の緑肥を草マルチにして、土の乾燥や、地温の上昇を防ぐ。
●堆肥効果
草マルチが微生物等により分解され養分となり、土の団粒化を促す。
●草を抑える
生育が旺盛でしっかりと根を張り、台頭する夏草を抑える。
●虫の住みか
通路の緑肥が益虫の住みかとなり、野菜につく虫を捕食し、虫害の減少につながる。
●通路を柔らかくする
しっかりと根が張ることで通路の土を柔らかくし、降雨後の水たまりを防ぎ、水はけがよくなる。
これらの効果に期待して、緑肥作物の成長を見守っていきたいと思います。
ちなみに、「緑肥作物は畝にまいてもいいのか?」
という疑問を解決しないまま、ひと畝だけまいてみました。

結果としては、
緑肥作物が野菜の背丈を越えると風通しや日照条件等が悪くなり、野菜の生育不良や病害虫を招く可能性があるため、畝にはまかないとありました。
(疑問を解決しないまま進めるのは危険‼︎)
まいてしまったものを取り除くわけにもいかないので、
この畝は野菜を植えずに緑肥専用畝として見守っていきたいと思いますヽ(;▽;)


通路に緑肥をまき終えたので、これからは畝以外の空きスペースにもまいていくことにします。
これで『あるもの農園』の草不足も一旦解決…かな♩

日々、学ぶことあり。
草や虫、自然の声に耳を傾けながら、色々と試していきたいと思います。
