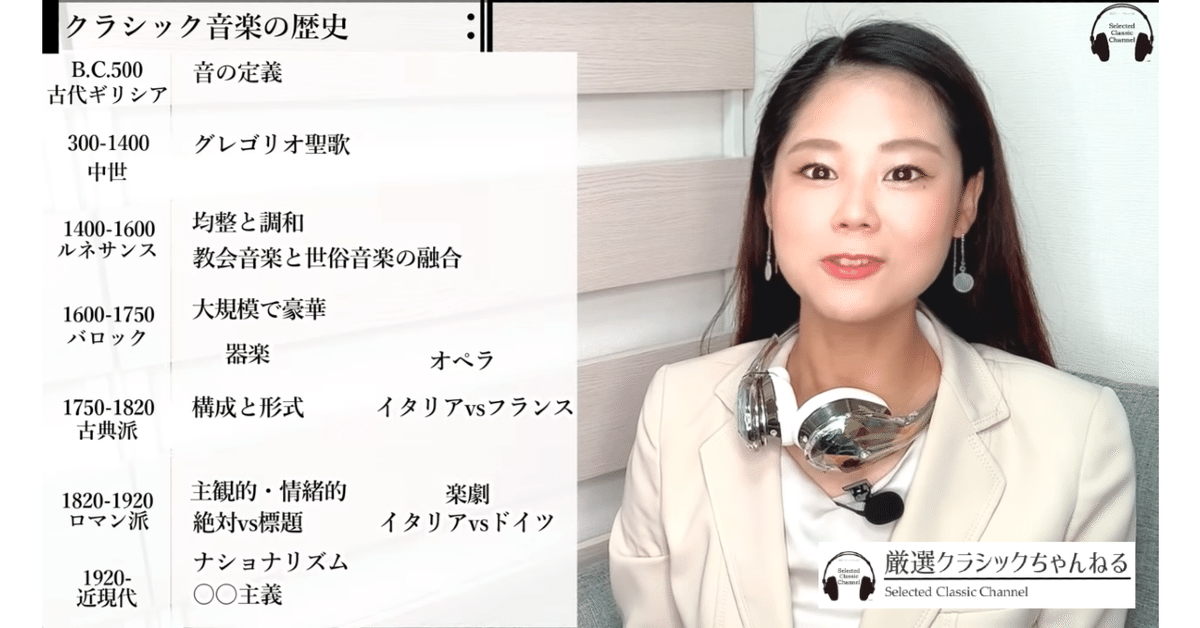
「音楽の勉強」by「厳選クラシックちゃんねる」
クラシックが好きなnacoさんが運営しているYouTubeチャンネル……
「厳選クラシックちゃんねる」で、
「西洋音楽の始まり」を勉強しました。
動画は、こちらです。
(動画では、実際の音楽も紹介されています)
特に知りたかったのは、「グレゴリオ聖歌」の話。
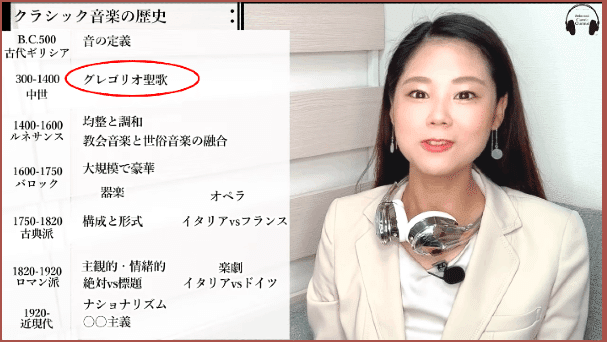
nacoさんの説明がわかりやすかったので、
個人的に忘れたくないポイントだけ、
noteにまとめようと思いました。
「グレゴリオ聖歌」は、
クラシック音楽のルーツとなった。
「グレゴリオ聖歌」には、
三位一体(キリスト教の神観)を表現するために、
「3回ずつ1つの旋律で歌う」という決まりがあった。
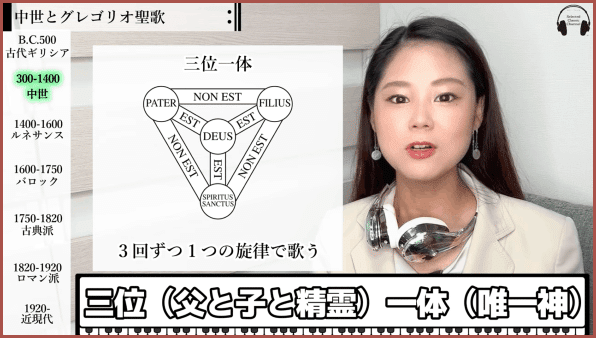
その単旋律のことを「モノフォニー」と呼ぶ。
中性音楽でもっとも美しいのは、
「(神の)モノフォニー」とされていた。
やがて、
オルガヌム(装飾の旋律)が施されるようになる。
(多声音楽、合唱音楽への発展)
課題として、
モノフォニーとオルガヌムがずれるという問題が残った。
このあたりから、
拍子と拍(楽譜)という概念が生まれた。
いいなと思ったら応援しよう!

