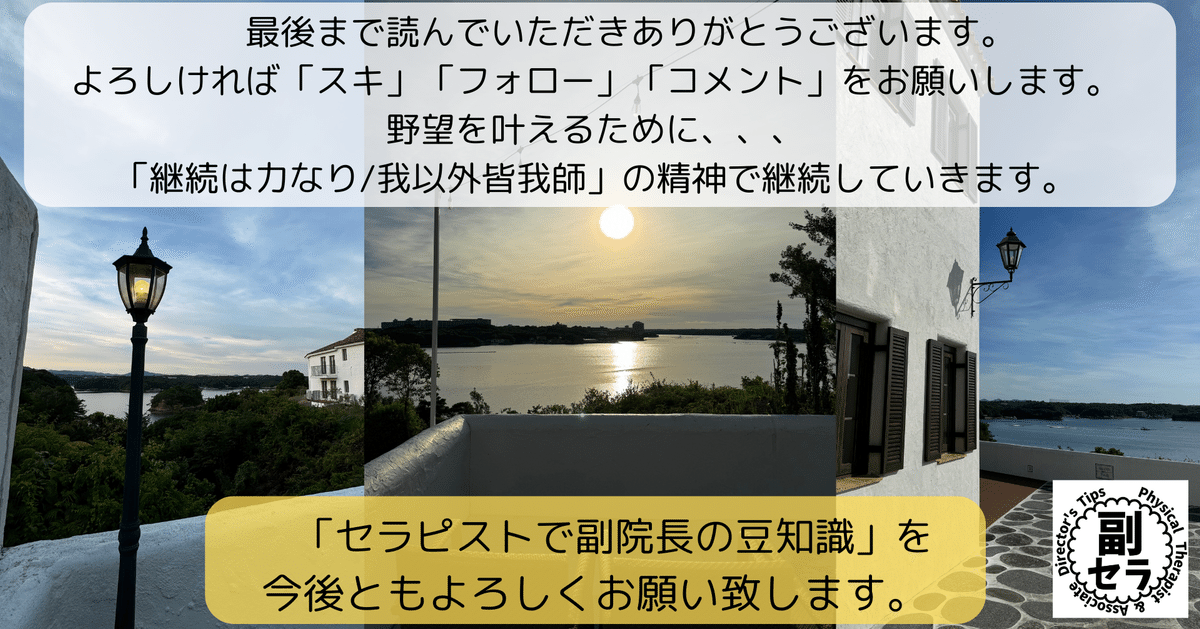寒い時期こそ気をつけたい!?四大骨折を知って怪我を回避しよう!!
おはようございます!こんにちは!こんばんは!「副院長でセラピストの豆知識」へ、ようこそ!
皆さんは「高齢者に多い四大骨折」というのは聞いたことはあるでしょうか?医療職の方は学校でも聞いたことがあると思います。この四大骨折の原因には転倒が関与していることが多いです。また、骨折の場所や状態により手術による固定や、人工骨頭に置換する手術が必要になる場合もあります。予防ができるのであればしておきたいですよね。しかし、どのようなところで発生することが多いのでしょうか?
今回は四大骨折のおさらいと、転倒予防のために気を付けておきたいポイントについて整理していきましょう!
1.四大骨折について
四大骨折とは①上腕骨近位端(頸部)骨折、②橈骨遠位端骨折、③脊椎圧迫骨折、④大腿骨近位端(頸部)骨折の4箇所になります。

①上腕骨近位端(頸部)骨折
部位:肩にある上腕骨の付け根の骨折
原因:転倒して肩をぶつける。手や肘をついた。
治療方針:
1.保存療法:転位(骨のずれ)が少ない場合、安定した骨折型の場合に選択されます。三角巾や装具で固定して骨が癒合するのを待ちます。骨の状態に合わせて、医師の指示でリハビリが開始されます。
2.観血的療法:転位が大きい場合や、不安定な骨折型の場合に選択されます。金属のプレートを用いた固定が多いですが、骨折によって骨の中に軸を入れて固定する髄内釘が選択されます。癒合が難しい状態であれば人工関節置換術が選択されます。手術の場合は入院が必要です。しっかり固定されるので早期にリハビリが開始される傾向があります。骨が癒合したのちにはプレートを抜く手術を行うこともあります。
処置後の生活への影響:肩の痛みや動きの制限があります。痛みは経過共に軽減していくことが多いです。着替え、洗濯物干し、歯磨き、洗体、食事など生活で肩を使っていることも多いため、それらの制限があります。少しずつリハビリを行い拡大していく必要があります。
②橈骨遠位端骨折
部位:手首にある橈骨の骨折
原因:転倒する時に手をついた。
治療方針:
1.保存療法:転位(骨のずれ)が少ない場合、安定した骨折型の場合に選択されます。ギプスやシャーレで固定し、三角巾で安静にして骨が癒合するのを待ちます。骨の状態に合わせて、医師の指示でリハビリが開始されます。
2.観血的療法:転位が大きい場合や、不安定な骨折型の場合に選択されます。金属のプレートを用いた固定が行われます。骨が癒合したのちにはプレートを抜く手術を行うこともあります。
処置後の生活への影響:ギプス固定されている間は、使えるとしてもギプスからでている指だけなので、利き手の場合は、食事の時の箸や、着替えのボタン、料理など身近な動作がしづらいことが多いです。非利き手の場合も、ビンの蓋を開けるときなど、両手で行う動作の時に物を抑えるために手を使っていることも多くあるので制限がでてきます。ギプス固定中からできる範囲で少しずつリハビリを行い、患部以外の動きの維持や拡大していく必要があります。
③脊椎圧迫骨折
部位:背骨の骨折
原因:尻もちをついた、くしゃみ、深く曲げた
治療方針:
1.保存療法:背骨の骨折になるので脇くらいから骨盤まである大きな装具(コルセット)やギプスを使って固定することが多いです。安静期間もありますが、医師の指示で、全身機能の低下予防のリハビリを行うこともあります。
2.観血的療法:骨の圧縮が強い場合や、骨折部が不安定な場合、神経症状が出ている場合に選択されます。つぶれてしまった椎骨の中にセメントを入れて固めたり、椎骨を支えるための金属のスクリューを入れたりします。保存と同じく、医師の指示で、全身機能の低下予防のリハビリを行います。
処置後の生活への影響:他の骨折と比較しても、装具が大きく、また固定していても装具がずれやすく、歩けば体重もかかるため生活も大変です。固定期間中は服の着替えも一苦労しますが、固定は必要なのでしばらくは仕方がないところもあります。できる範囲で歩行練習や患部外の運動を行い、廃用予防をしていきます。
④大腿骨近位端(頸部)骨折
部位:股関節にある大腿骨の付け根の骨折
原因:転倒してぶつけた、転倒時に捻った、尻もちをついた、躓いた。
治療方針:
1.保存療法:この部分の骨折はギプス固定ができないため、その期間中に体重がかけられなくなり寝たきりになるリスク高く、保存療法が選択されることは少ないです。他の疾患や体力の関係などで手術を行うことができない状態や、ベッド上生活が長引いても手術を選択しない場合のみ保存療法となります。
2.観血的療法:大腿骨近位端の中でも骨折した部位で選択可能な手術は変わりますが、金属製のプレート、スクリュー、髄内釘による固定を行います。骨頭と呼ばれる骨の先に栄養を送っている血管が損傷している場合には、骨壊死の可能性あるためその場合は人工骨頭置換術が選択されることもあります。これらの手術は、術後早期からリハビリが開始されることが多いです。
処置後の生活への影響:術後の経過でいくと、術後早期は傷口の痛みなどもあるため、靴下を履くような動きや、歩き方などはぎこちないですが、経過で比較的可動範囲や歩行などは改善していきます。杖の使用を勧められることもあります。人工骨頭置換術の場合は、脱臼リスクの回避のため無理に動かさない方向※)が設けられる場合があります。
※手術方法によって脱臼に注意すべき方向が異なるためネット情報ではなく、執刀医やセラピストなどその医療機関の方への確認がおすすめです。
2.高齢者と若年者の骨折の違い
骨粗鬆症という言葉を聞いたことがあるでしょうか?骨粗鬆症とは骨密度が減少している状態です。つまり骨が薄くなり、中はスカスカになってきて骨が折れやすくなってしまっている状態です。診断されていなくても、若い頃と比べたらどんな人でも骨は弱くなります。特に女性はホルモンバランスの関係で特に注意が必要です。これについて記載すると長くなるので割愛しますが、高齢者の場合は弱い外力で骨折が発生してしまう可能性があり、脊柱の圧迫骨折の場合はくしゃみや椅子に座った衝撃だけで発生してしまうこともあります。また骨が折れた時につぶれてしまうため、元の位置にもどしても隙間が空いてしまったり、戻しきれなかったりします。
3.転倒リスク
転倒が発生している場所で、意外な盲点は屋内になります。特に自宅内など身近なところでも発生します。これは明らかな段差などではなく、1cmも無いくらいのちょっとした出っ張りでも転倒することがあるからです。例えば、「じゅうたん」の縁や、家電のコード、床に落ちている物などです。またフローリングは足を擦ってでも移動できますが、「じゅうたん」との摩擦抵抗の違いで躓くこともあります。段差があると認識しているところや、滑りやすいと感じているところは、気をつけるので大丈夫なこともありますが、屋内屋外に関わらず「段差や障害物があるとは思わなかった。」「気づかなかった。」という声もよく聞きます。
💡豆知識〜なぜ冬に増える傾向があるのか〜💡
特に冬の時期に増える理由とては、寒くて体が動きにくく、厚着で動きにくい、季節家電の使用(こたつ、電気毛布、電気ストーブ、石油ストーブ)などがあります。普段は何も無いところに電気のコードがあって躓いたり、石油ストーブの灯油を運ぶ時に無理して、圧迫骨折やバランスを崩して転倒することもあるようです。
最後に
転倒リスクに関してはデータでもいろいろ出ており、バランス感覚や筋力などの素因もあるかもしれないですが、予想外のところで怪我をしてしまうこともよくあります。いずれも骨折も長い治療期間が必要であり生活に支障が出てしまいます。健康寿命を伸ばすためにも、身近に潜むリスクには注意していきましょう。
細かい病態や治療方針などについては医療機関に確認と指示に従ってくださいね。