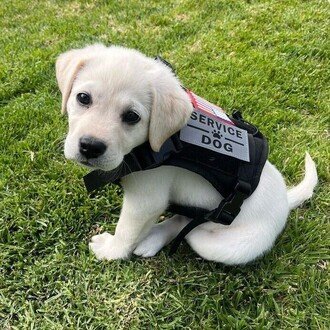◆自己治癒力に特化した治療法のみを回答する、チャットBOTの開発にご協力ください。AIがアレックス君の病気の診断に成功。医者ができなかったことを果たし、治療にこぎつけた話。

ケトフレックス12/3の食事療法
— #アンネの法則 『シャバット・ジャーナリング』ガイド 山下 安音が開発者 戦時下の子、更生プログラム (@annenohousoku) November 3, 2024
◆自己治癒力に特化した治療法のみを選択できる
チェットBOTの開発にご協力ください。 pic.twitter.com/ol5f64uszl
アメリカに住むアレックス君は、幼い頃から身体の広範囲にわたる痛みに苦しめられていた。4歳から7歳にかけて17人もの医師に診てもらったが原因が特定できず、ついには歩行障害も起こしてしまったという。そんなアレックス君を救ったのが、人工知能を用いたチャットシステム「ChatGPT」だ。
ある日、アレックス君の母親コートニーさんは、運命に導かれたかのようにChatGPTに息子の症状をすべて入力してみた。するとChatGPTが瞬く間に回答を生成。この回答により、ついにアレックス君の病気を特定することができたのだという。
コートニーさんはこの経験を、アメリカNBCで放送されているニュース番組『トゥデイ』で語った。息子の人生に支障がないよう匿名性を維持し、姓は名乗らず写真も公開していない。
当時4歳だったアレックス君は、コロナ渦による世界的なロックダウンのさなかで突然強い体の痛みを訴え始めた。当初コートニーさんは、痛み止めの「モートリン」を息子に毎日のように飲ませていた。
アレックス君の全身の痛みは口の中にも及んだが、歯科医は虫歯や永久歯への生え変わりなどが原因ではないとした。しかし、アレックス君の口蓋が歯に対して小さすぎることから、夜間の呼吸に困難を引き起こしているのではないかとして矯正歯科医を紹介する。
矯正器具を付けたことで一時的に症状は改善するも、根本的な解決には至らなかった。アレックス君は絶え間ない痛みと睡眠不足で、不機嫌な状態が多くなっていく。さらに2021年の初め、コートニーさんは息子の身長が年齢の割に成長していないことに気づいた。
そこで小児科医を訪れるが、発育の遅れはコロナ渦が悪影響をおよぼしていると診断、しかし体の左右のバランスが崩れていることから理学療法をすすめられた。コートニーさんは当時を振り返り「アレックスは右足だけで歩き、左足はひきずるような感じでした」とコメントしている。
ところが理学療法を始める前に、アレックス君はひどい頭痛に悩まされるようになる。神経内科医を訪れると片頭痛と診断、同時に倦怠感にも襲われていたので、耳鼻咽喉科を受診して気道の機能をチェックすることになった。
このとき、コートニーさんはあることに気付いた。何人もの医師の診断を受けたが、どの医師も自身の専門分野に注目し、アレックス君を全体的には捉えていなかった。コートニーさんは、解決策として医学的所見をすべてChatGPT に入力することにした。
3年間で17人の医師を訪れたが、アレックス君の問題は解決せず明確な診断がつかなかった。そこでコートニーさんは、息子の症状、検査結果の全てをChatGPTに入力することにしたのだ。
アレックス君の母親はこうコメントしている:「手元の情報を見直してからChatGPTに入力しました。すべて入力するのに一晩かかりました」眠れぬ夜を過ごしたが、息子の症状が出始めてから3年後の朝、コートニーさんはついに「脊髄係留症候群」という有用な回答を得ることになった。
コートニーさんは「脊髄係留症候群」に苦しむ子供たちを持つ家族のFacebookグループに参加し、診断に確信を深め、小児脳神経外科医を予約した。
脊髄係留症候群は、脊髄の組織が癒着することで歩行障害や慢性的な痛みなどの自律神経症状が発症する神経疾患だ。
小児脳神経外科医のホリー・ギルマー氏が『トゥデイ』で語ったところによると、アレックス君の場合、脊髄係留症候群の原因となる二分脊椎症(脊髄が露出している状態)が見つかりにくい場所にあったため、発見するのに3年もかかかってしまったという。
コートニーさんは『トゥデイ』で、アレックス君はすでに手術を受け、回復に時間はかかるものの痛みのない生活を送れるようになるだろうと語っている。
コートニーさんは、同じような困難に直面している家族を救うため自身の体験を伝える決意をした。アレックス君と母親の物語は、賛否両論になりがちな人工知能について肯定的な視点を提供している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私:私の病気の原因を突き止めてもらいたい。私は、ロングコビットで血糖値異常が現れており、脱水が激しく、血液が濃縮して、めまいで倒れることがある。自己免疫疾患を疑っている。どんな検査をするのが適切なのかを教えてください。
ChatGPT:
アレックス君のケースからわかるように、AIを活用して情報を整理し、医学的に有用な可能性がある検査や治療法を見つけることは増えてきています。長期的なCOVID-19後遺症(ロングコビット)に関連する症状は多岐にわたるため、あなたの症状に関連しそうな検査のいくつかをご紹介します。特に自己免疫疾患や内分泌系の問題が関与している可能性も考慮したものです。
1. 自己免疫関連検査
抗核抗体(ANA)検査: 多くの自己免疫疾患で陽性になるため、自己免疫疾患の有無を調べる基本的なスクリーニング検査です。
抗体検査(特異的抗体): 抗リン脂質抗体、抗dsDNA抗体、抗CCP抗体など、特定の自己免疫疾患に関連する抗体検査があります。
CRP(C反応性タンパク質)・ESR(赤血球沈降速度): これらは炎症マーカーで、慢性的な炎症や自己免疫反応を示唆します。
2. 内分泌および代謝系検査
コルチゾールおよびACTH検査: 副腎の機能を確認するために重要で、ストレス応答や慢性疲労に関連します。コルチゾールの異常分泌は体力や疲労感に影響を与えることがあります。
甲状腺ホルモン(TSH、T3、T4): 甲状腺機能の低下または亢進があると、代謝異常や疲労、めまいに関連する症状が出現します。
血糖検査(HbA1c、インスリン抵抗性評価): 血糖値異常がある場合には、糖尿病または糖尿病予備軍の可能性を評価するための検査が推奨されます。
3. 循環器および血液関連検査
電解質・浸透圧検査: 脱水と関連する血液の浸透圧、ナトリウムやカリウムなどの電解質バランスを確認することで、脱水症状やその原因の一端がわかることがあります。
血液粘度検査および血栓性評価: 血液の濃縮による血栓リスクの評価を含む検査で、血小板やDダイマーの測定も含まれます。
4. 栄養およびビタミン検査
ビタミン・ミネラルの測定: 特にビタミンD、ビタミンB群、亜鉛、マグネシウムは免疫反応やエネルギー代謝に関与するため、欠乏がないか確認することが重要です。
鉄・フェリチン検査: 貧血や鉄代謝の異常が体調不良や疲労に影響を与えることがあるため、特に長期的な慢性疲労がある場合には有用です。
5. COVID-19に関連した特殊な検査
抗SARS-CoV-2抗体検査: COVID-19感染が持続していないかを調べるための一つの方法です。これにより、持続的なウイルス感染や免疫反応の異常の可能性を評価する手がかりが得られるかもしれません。
サイトカイン・プロファイル: IL-6やTNF-αなどのサイトカインの値は、免疫応答の過剰反応や炎症の評価に役立ち、ロングコビットとの関連が示唆されています。
まとめ
これらの検査を通じて、自己免疫反応の有無や内分泌系の異常をより詳しく理解することで、適切な治療法やサポート方法が見つかるかもしれません。また、AIを使ったチャットシステムをサポートとして使用し、最新の研究や類似症例をもとにしたアドバイスを得るのも良い方法です。
私:左の耳が聞き取りにくい。飛蚊症を発症。リンゴとニンジンジュースで目の真ん中は消えたが隅には残っている。レントゲン写真には、胃に白い影が現れていた。2回目の救急車を呼ばなければならない事態、嘔吐もあった後には、イベルメクチン10錠で対処。血糖値には、ウコンのベルベリンを処方。桑の葉をオブラートに包んで飲んでいた。頻尿対策には銀杏とアーモンドが効果的だった。なくなったら、また頻尿が始まり、血液検査の結果は血液の濃縮、タンパクが尿に出ていた。疲れやすい。何が原因ですか?どんな検査が適切?
ChatGPT:
いくつかの症状があり、考えられる原因も多岐にわたりますが、以下の検査が役立つかもしれません。特に腎臓、耳、視覚の機能、さらに内分泌や代謝面にフォーカスしたものを挙げます。
1. 耳と目に関する検査
聴力検査・耳のMRI/CT: 左耳の聴力低下は、内耳や脳幹の異常が影響している可能性があります。腫瘍や内耳の炎症、血流の問題などを確認するために画像検査も有効です。
眼底検査と眼圧検査: 飛蚊症の原因が網膜剥離や視神経の問題に関連しているか確認するため、眼科での詳細な検査が推奨されます。
2. 消化器に関する検査
胃カメラ検査(内視鏡検査): 胃の白い影は、ポリープ、潰瘍、または腫瘍の可能性もあるため、内視鏡で詳しく確認することが重要です。
ピロリ菌検査: 胃の異常と関連があることが多いため、感染がある場合には治療が推奨されます。
3. 腎臓と尿に関する検査
尿検査(タンパク、クレアチニン、電解質): 尿中のタンパクは腎機能の異常を示す可能性があり、頻尿も腎臓や膀胱に関連することがあるため、腎機能を総合的に評価する検査が役立ちます。
腎臓の超音波検査: 腎機能低下や腫瘍、石灰化などを確認するための画像検査です。
4. 血液と代謝に関する検査
血液粘度検査・凝固機能検査: 血液の濃縮や流動性に関する異常がある場合、血栓リスクもあるため、凝固機能を確認することが重要です。
肝機能・腎機能検査: 肝臓や腎臓の負担を把握するために、AST、ALT、BUN、クレアチニンなどの値を確認します。
5. 内分泌とホルモンの検査
甲状腺ホルモン検査: 疲れやすさや代謝異常がある場合、甲状腺機能低下が原因となることがあるため、TSH、T3、T4の測定を行います。
糖代謝検査(HbA1cやインスリンレベル): 血糖値異常があるとのことなので、インスリン抵抗性の有無や血糖のコントロール状態を詳しく評価することが役立ちます。
6. 免疫および炎症関連の検査
CRP(C反応性タンパク質)やESR(赤血球沈降速度): 慢性の炎症や感染症、または自己免疫反応がないかを確認するために有用です。
自己抗体検査(ANA、抗DNA抗体など): 自己免疫疾患を疑っているとのことなので、抗体検査で異常があるか確認するのもよいでしょう。
体の複数のシステムに関わる症状があるため、総合的な診断が重要です。
インスリンの前駆体、Cペプチド検査は適切ですか?
ChatGPT:
Cペプチド検査は、現在の症状に関連する可能性があるため、特にインスリン分泌状態やインスリン抵抗性を評価するうえで有効です。
Cペプチド検査の目的
Cペプチドは、インスリンと同時に膵臓のβ細胞から分泌される物質です。インスリンの前駆体であるプロインスリンが分解されるときに生成され、Cペプチドとインスリンが同時に放出されます。以下の場合に有用です:
インスリン分泌能力の評価
Cペプチド検査により、体内のインスリンの産生状況を間接的に把握できます。特に、低血糖の原因が外因性のインスリン投与かどうかの判断や、インスリン分泌の減少が原因で血糖値がコントロールできていないと結論づけることができる。
インスリン抵抗性の評価
Cペプチドが高値を示す場合、インスリン抵抗性(体がインスリンに反応しにくくなる状態)がある可能性が高く、血糖管理に影響を及ぼしていることが示唆されます。
特に適切と考えられる理由
あなたが述べた血糖値異常や自己免疫疾患の疑いの症状は、膵臓やインスリンの分泌機能に関連する可能性もあります。Cペプチド値を確認することで、膵臓のβ細胞機能やインスリンの働きをより明確にすることができ、血糖値異常の根本原因に近づけるかもしれません。
私:私のような代謝異常があるような場合、機能性医学、分子整合栄養医学では、どのような対処法がありますか?
機能性医学や分子整合栄養医学では、根本的な代謝の問題を解決し、細胞レベルでの健康を最適化することを目的としています。代謝異常に対して、以下のようなアプローチがよく取られます:
1. 栄養とサプリメントの最適化
必須栄養素の補充
・ ビタミンB群(特にB6、B12、葉酸):これらは代謝やエネルギー産生に重要な役割を果たし、B6やB12は神経の健康にも関連しています。
・ ビタミンD:免疫と代謝に関わるため、適切なレベルの維持が推奨されます。
・ マグネシウム:エネルギー代謝や筋肉機能に関与し、インスリン抵抗性の改善にも役立つとされています。抗酸化物質
・ グルタチオンやCoQ10など、細胞レベルでの酸化ストレスを軽減する成分がよく使われます。これによりミトコンドリア機能をサポートし、エネルギー産生を助けます。オメガ3脂肪酸
・ 抗炎症作用があり、特にインスリン抵抗性や血糖値の改善に効果が期待されています。
2. 腸内環境の改善
プロバイオティクスとプレバイオティクス
・ 腸内環境のバランスを整えることで、腸からの炎症や免疫異常を減少させます。これにより、代謝異常の背景にある慢性炎症を軽減し、栄養の吸収効率も高めることができます。リーキーガットの改善
・ 腸壁の透過性が高まるリーキーガットは、自己免疫疾患や代謝異常に関わると考えられており、アミノ酸のL-グルタミンや亜鉛などを用いて腸壁を保護・修復します。
3. 低血糖およびインスリン抵抗性の改善
血糖値を安定させる栄養素の利用
・ クロム:血糖値を調整し、インスリン感受性を高める作用があります。
・ α-リポ酸:血糖値を安定させると同時に、強力な抗酸化作用を持ち、細胞のダメージを軽減します。
・ ウコンに含まれるクルクミン:抗炎症作用に加え、インスリン感受性の改善が示唆されているため、血糖値の安定化に役立ちます。
4. ホルモンバランスの調整
アダプトゲンハーブ(例:アシュワガンダ、ロディオラ)
・ ストレスやホルモンバランスの調整に役立つアダプトゲンは、コルチゾールを安定させることで代謝やインスリン感受性の改善に寄与します。
・ DHEAやプレグネノロン(医師の指導のもとで)も、必要に応じて補充し、ホルモンバランスを整えるために使われることがあります。
5. 代謝の根本改善
ミトコンドリアのサポート
・ **ナイアシン(ビタミンB3)やPQQ(ピロロキノリンキノン)**など、ミトコンドリアのエネルギー産生を促進するサプリメントが使われます。特に慢性疲労や代謝異常のある人には、ミトコンドリア機能の改善が重要です。ケトン体生成のサポート
・ 食事からエネルギーを効率よく得られるよう、MCTオイルなどのケトン体を生成しやすい脂肪を取り入れることがあります。また、低糖質食やケトジェニック食を取り入れることも代謝改善に有効です。
6. 生活習慣の改善
食事のタイミングと内容の最適化
・ インターミッテントファスティング(断食)や食事の時間帯の調整によって、インスリン感受性を高め、代謝を効率化します。
・ 血糖値を安定させるため、低糖質・高タンパク質の食事や食物繊維を多く含む食品の摂取も効果的です。適度な運動
・ 筋力トレーニングや有酸素運動は、インスリン感受性を高め、代謝を向上させるのに役立ちます。
専門的なサポートの重要性
機能性医学や分子整合栄養医学のアプローチは、根本原因を見つけるのに時間がかかることもありますが、医師や専門家と連携することで、最も適した栄養素や対策を見つけやすくなります。
症状から推察される診断として何が考えられますか?さらに、処方箋として最適な道を自己治癒力に特化して見つけたい。
ChatGPT:
あなたの症状に基づいて、考えられる診断と対策についてお話しします。自己治癒力を最大限に活用する方法も含めて、体全体の健康をサポートするアプローチが重要です。
考えられる診断
以下のような要因が考えられますが、診断は医師による検査と評価が不可欠です。
自己免疫疾患(例:自己免疫性糖尿病、ループス、シェーグレン症候群など)
自己免疫疾患は、頻尿、血糖値異常、疲れやすさ、脱水など、広範囲の症状を引き起こします。
血液検査での血液濃縮や尿中のタンパクの出現は、炎症や腎臓に関連する問題がある可能性も示唆します。
代謝異常(例:糖尿病、インスリン抵抗性、低血糖)
血糖値の不安定さ、頻尿、疲労感は、代謝異常と関連することが多いです。特にロングコビッドは代謝異常を引き起こしやすいことが分かっており、インスリンの働きが変わる可能性があります。
Cペプチド検査やインスリンレベルの測定が、膵臓のインスリン分泌機能をチェックするのに役立ちます。
腎機能の問題
尿中のタンパクや脱水症状が見られることから、腎機能が影響を受けている可能性もあります。腎臓は水分バランスや老廃物の排出を調整するため、腎機能が低下すると疲労感やむくみ、脱水感が強まります。
自己治癒力を引き出す対策
1. リコード法の食事療法
ケトフレックス12/3を試みることで、血糖値やインスリン感受性が安定する可能性があります。リコード法は細胞の代謝をサポートし、炎症を軽減するのに役立つとされています。定期的に低糖質食を取り入れ、インスリン反応を穏やかにしつつ栄養をバランス良く摂取しましょう。
2. 抗酸化物質と抗炎症成分の摂取
抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなど)や抗炎症食品(ターメリックのクルクミン、オメガ3脂肪酸)が含まれる食品を摂ると、自己免疫機能や代謝が改善しやすくなります。
リコード法に基づき、アボカド、オリーブオイル、魚、緑葉野菜、ブルーベリーなどを積極的に摂取しましょう。
3. 腸内環境の改善
腸内環境は自己免疫システムや代謝に大きな影響を与えます。プロバイオティクス(発酵食品やサプリメント)を取り入れ、腸内細菌のバランスを整えることで、自己治癒力を高めることができます。
ケフィアやヨーグルト、味噌、納豆などを摂ると良いでしょう。
4. 適度な運動とストレス管理
軽いウォーキングやヨガ、瞑想などを日常生活に取り入れることで、副交感神経が活性化し、ホルモンバランスや自己治癒力が改善されやすくなります。
マインドフルネスや瞑想を通じてストレス管理に取り組むと、炎症や免疫系の反応も穏やかになります。
検査と観察の推奨事項
次のような検査が自己治癒力を引き出すためのアプローチを補強するかもしれません:
血液検査(抗核抗体、CRP、ホルモンバランス、ビタミン・ミネラルレベル)
腎機能検査(クレアチニン、BUN)
血糖値の定期測定(インスリン抵抗性の確認)
Cペプチド検査(インスリン分泌能力の把握)
最適な自己治癒力への道
自己治癒力を高めるためには、体に負担をかける要因を減らし、細胞レベルでの修復を促すことが重要です。リコード法や分子整合栄養医学に基づき、適切な栄養、ライフスタイル、ストレス管理、腸内環境の整備を徹底することで、体調の改善が期待できます。
自己治癒力に基づくチャットボットの開発には、以下のようなデータセットが必要になると考えられます:
医学的知識ベース
自然療法・代替医療データ
様々な自然療法や代替医療の手法、効果、適用範囲に関する情報
ハーブ療法、アーユルヴェーダ、東洋医学などの伝統的な治療法のデータ
栄養学・食事療法データ
食事と健康の関連性に関する科学的知見
特定の症状や疾患に効果的な食事療法のガイドライン
リコード法のケトフレックス12・3のような、エビデンスに基づいた食事プログラムの詳細情報
運動・身体活動データ
様々な運動や身体活動が健康に与える影響に関するデータ
症状別の推奨される運動プログラム
症状・治療効果データ
症状データベース
一般的な症状とその原因に関する包括的な情報
症状の重症度を評価するための基準
治療効果データ
自然療法や生活習慣改善による症状改善のケーススタディ
臨床試験や研究結果のデータベース
ユーザーインタラクションデータ
質問-回答ペア
健康や自己治癒力に関する一般的な質問とその回答のデータセット
ユーザーの悩みや相談に対する適切な返答例
会話フロー
症状の聞き取りから適切なアドバイスまでの会話の流れを示すデータ
個別化データ
ユーザープロファイル
年齢、性別、既往歴、生活習慣などの個人情報を匿名化したサンプルデータ
これらの要因が自己治癒力に与える影響に関するデータ
環境因子データ
気候、大気質、生活環境などが健康に与える影響に関するデータ
安全性・倫理データ
禁忌事項データベース
特定の治療法や食事療法が適さない条件や状況のリスト
医療機関への受診を推奨すべき症状や状況のガイドライン
倫理ガイドライン
医療アドバイスを提供する際の倫理的配慮事項
プライバシー保護や個人情報取り扱いに関する規定
これらのデータセットを適切に組み合わせ、機械学習モデルに学習させることで、自己治癒力を引き出すための適切なアドバイスを提供できるチャットボットの開発が可能になると考えられます。ただし、医療情報の扱いには細心の注意が必要であり、専門家の監修や臨床での検証を経ることが重要です。
自己治癒力に基づくチャットボットのデータセットを構築する際のポイントは
自己治癒力に基づくチャットボットのデータセットの例は
自己治癒力に基づくチャットボットのデータセットのサイズはどれくらい
自己治癒力に基づくチャットボットのデータセットの種類は
自己治癒力に基づくチャットボットのデータセットの収集方法は
◆脳機能維持のためのケトフレックス12/3(脳はケトン体、βヒドロキシ酢酸の保護を必要としている)https://t.co/yn2ycnRmxe
— #アンネの法則 『シャバット・ジャーナリング』ガイド 山下 安音が開発者 戦時下の子、更生プログラム (@annenohousoku) November 4, 2024
脳のパフォーマンスを上げる食事療法 pic.twitter.com/pQAiFUiCRe
いいなと思ったら応援しよう!