
自分の代わりが出来る部下育成
部下の可能性を最大限引き出す

🙏「人の道」を弁え育む
大切な命を授かった人には、
自ずとこの世で果たすべき役目が有ります。
その役目を果たす為に、
人其々に合った歩む道が与えられます。
人としての道徳、社会人の倫理、
企業人のコンプライアンス・理念保持、
日常生活のモラルを持ち適切な行動をし
人として与えられた大切な命の自覚認識
その義務と責任を果たさなければなりません。
そしていかなる立場、境遇の下でも、
命の大切さを認識し命を生かて
人の道を正しく歩めるよう意識し
生活して行かなければなりません。

導かれるのも人指導する者も、
先ず互いが「人」であるという認識が必要。
人としての義務と責任を果たすには、
自己都合や感情移入は不要です。
🔳指導時のポイント
✴指導を受ける側の個性資質を確りと把握し、
指導時の精神状態を瞬時に洞察(推測)判断し、
相手が受止め易い適切な切り口から指導する。
⇔思い遣り・察知洞察力
🔳長所を積極的に見い出し、
隠れた才能を引き出す
【ポイント】
⇒指導を受ける人の人格・個性、
今、将来を考え本気で向き合い真剣に、
思い遣りと真心を持ち指導にあたる。
何故?の意識付けも大切。
(ゴールデンサークル)
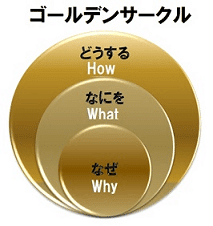
▶指導する際は、事前から
育成メモや指導シートを作成して行う。
事前の準備せずにその場しのぎ、
思いつきでは行わない。
▶指導する人のことを本気で考える時間を
作ることは思い遣りの「ものさし」実践です。
▶指導する際に大切なことは一人ひとりの
個性≒良いところ・長所・特質を見い出し、
本人の持つ隠れた才能を探し育てることで、
こちらの事情や都合で育てることはしない。
▶対象者への意識-(例)
イ)職場で共に仕事をしている人の長所、
才能を3つ以上挙げられますか?(はい・いいえ)
ロ)その人の長所を3つ(以上)
挙げてください(仕事以外も可)
1.
2.
3.
その他
ハ)その人の才能を3つ(以上)挙げてください
1.
2.
3.
その他
■指導者の在り方
「どんな知識があり、何が出来るか」より
「どのようなスタンスで仕事に取組んでいるか」
と言う「在り方」が、人としても、
指導者として信頼を得るために大切です。
そのために、指導者は自らの仕事への
適切なスタンスを意識し、普段の職務遂行時
から背中を見せ、会話に心配りして行うこと。
🔳心身を正対し、会話する≒相談を受ける
▶先入観を持たない。
▶冷静に平らな感情維持に努める
▶先ず、話しをじっくりと聞き、即答し、
その後でその人に合わせた他の選択肢も伝える。
▶こちらから結論は出さないで、
本人の気付きに繋がったり、
考えさせたりと決めるように導く。
🔳知識・情報収集
▶指導者は知識や情報の収集ルートを常に作り、
個別メモなどを持ち、伝えるようにする。
🔳信用され、信頼される指導者なる、と認識する
▶信用は一つ築くと細胞が増えるのと
同じようにどんどん増えて行く。
そのためには、最初の一つの信用を
いかに築くかポイントです。
▶何らかの見返りを求め望む言行や態度をしないこと。
▶小さな信用の積み重ねが信頼と絆を作る礎です。
🔳自信と勇気を持って指導
▶話す内容の自信と力強い信念のある話し方、
大切なことについては厳しい内容でも
勇気を持って話し伝えることを自覚し、
自信を持った決断力を示す指導をする
※向上心
▶実際に行う際に必要とされる
モチベーションを与えながら、
目的を理解させ、ワンランク上の
一度仕事をさせてみる
🔳会話時に指導者(自分)の利用の仕方を教える
▶相手の立場に立つこと(立場転換)を
理解させ、実際の例えなどを加味して
話しながら、些細な事も含めて
指導者(自分)の活用法、利用の仕方を教える。
※折に触れ対等なか遜りだった立場で、
人生観を語ることも必要です。
🔳一度自分の仕事を部下に任せてみる
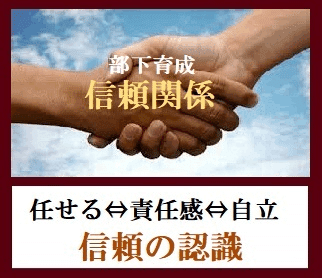
経営者や現場責任者の代わりになる
二番手を育成するには多少力不足でも、
何か一つでも任せてみることをお勧めします。
最初は傍でサポート役やアシスト役を
勤めて部下への信頼感を示すことです。
任せられた本人の心に責任感や自立心が
少しずつ生まれ、やがてその気持ちが
達成感、満足感、喜びに繋がります。
部下育成には根気よく失敗を許す
寛大な心を以って諦めず共働すること、
信頼して部下に任せる心身の活動は、
巡り廻って自社・自分に返って来ます。
