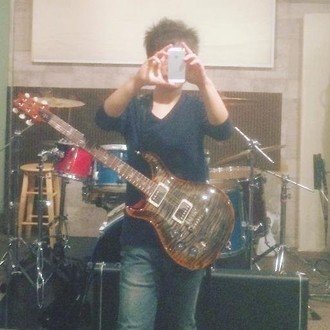初心者でも簡単!ダイナミックEQの基礎と即戦力の使い方
みなさん、ダイナミックEQを使っていますか?

ダイナミックEQとは、特定の周波数帯で音量が設定したスレッショルド(閾値)を超えたときに自動でEQ処理を行うエフェクトです。必要なときにだけEQが作用するため、ミックス内でのバランス調整が非常にスムーズになります。
現在、多くのメーカーがダイナミックEQを提供していますが、私が特に愛用しているのは「Waves F6 Floating-Band Dynamic EQ」です。
マルチバンドコンプレッサーとの違いは?
ダイナミックEQを理解する上で欠かせないのが、マルチバンドコンプレッサーとの違いです。
どちらも特定の周波数帯で音量がスレッショルドを超えた時に処理が発動する点では共通していますが、違うのはその処理内容です。
マルチバンドコンプレッサー
マルチバンドコンプレッサーは、あくまで「コンプレッサー」です。音を圧縮して抑える役割を持つため、必然的に圧縮感が生まれます。この圧縮感が、音に密度や存在感をもたらすのが魅力でもあります。
ダイナミックEQ
「EQ」であるため、ゲインコントロールで音を抑えます。特定の周波数帯のボリュームを操作するイメージです。そのため、マルチバンドコンプレッサーのような圧縮感がなく、より自然な形で音を抑えることができます。
また、マルチバンドコンプレッサーが広めの周波数帯に適しているのに対し、ダイナミックEQはQ幅(周波数帯の幅)を細かく設定できるため、特定の耳障りな周波数をピンポイントで削るのに向いています。
こうした点から、不要な帯域を自然に抑えたい場合にはダイナミックEQのほうが適しているでしょう。
私のダイナミックEQ活用方法
ギターは演奏方法やポジションによって音の出方が大きく変化するため、ギタートラックの処理においてダイナミックEQが非常に役立ちます。
例えば、ブリッジミュート演奏時に低域がモワッと出る場合、そのタイミングでだけダイナミックEQを使って低域を自動的に削るように設定することで、楽曲全体のバランスが整います。
ギターを弾いてるとブリッジミュート演奏時のみ低域がモワッと出てしまうことに悩んでたんだけど、アクティブEQで一発解決ではないか!!Waves F6めっちゃ良いなコレ!! pic.twitter.com/EG65bKqZ6Y
— Yuuki-T (@project0t) September 4, 2021
また、ギターソロでハイポジションを弾く際に耳に痛い帯域が出る場合も、その帯域だけを狙ってカットすることができます。こうしたピンポイントな調整ができるため、自然な仕上がりが期待できます。
私は特にギタートラックの処理でよくダイナミックEQを使用していますが、他の楽器やボーカルにも応用可能です。ぜひ、下記のSLEEP FREAKSさんの動画をチェックして、ダイナミックEQの使いやすさを体感してみてください。
いいなと思ったら応援しよう!