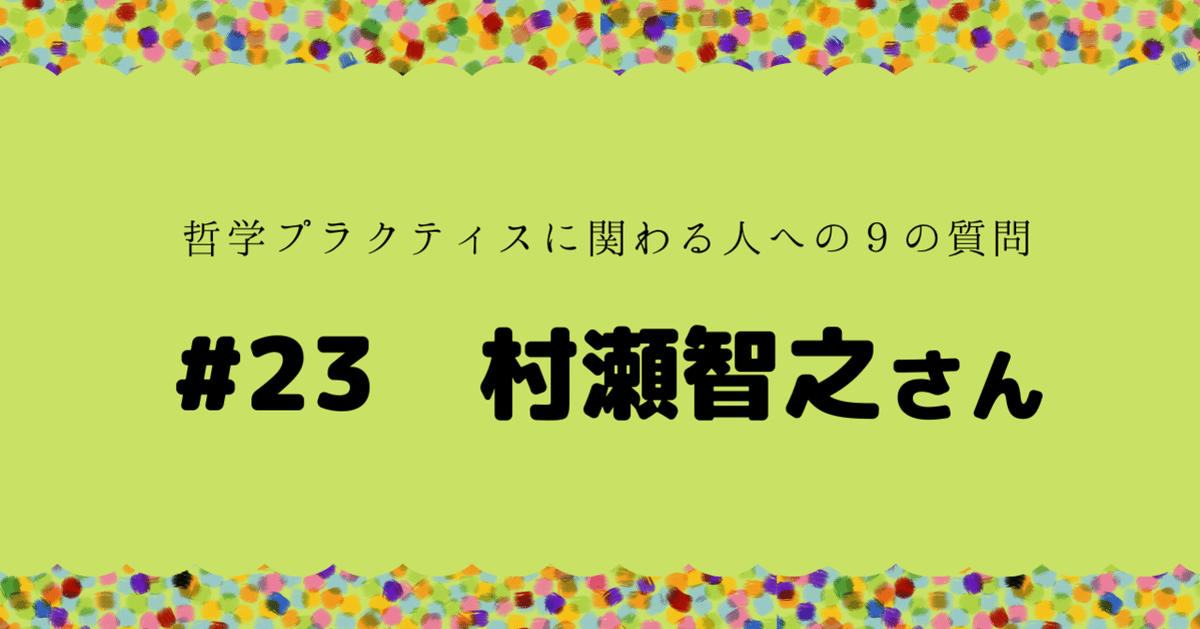
哲学プラクティスに関わる人への9の質問 #23 村瀬智之さん
1.肩書き・職業など
東京工業高等専門学校 一般教育科 准教授
2.現在の主な活動
学校での哲学対話
3.はじめて哲学プラクティスに出会った日はいつですか?
2008年。
公立の中学校の非常勤講師として「日本語・哲学」という授業を受け持つことになり、その授業を作っていく過程で「子どもの哲学」や臨床哲学の実践を知った。
4.はじめて哲学プラクティスを実施したのはいつですか?
2008年。手探りで実践を始め、土屋陽介さんや山田圭一さんと「子どもの哲学」を参考にした授業を行ったりした。
詳しくは、むかし「エッセイ」を書いたので、ご興味があれば。
「哲学教育を何ものとして行うのか?」
(P4E研究会編、『Philosophy for Everyone 2013-2015(UTCPブックレット)』、pp.39-42)
5.哲学プラクティスを、はじめてやろうと思ったのはなぜですか?
教員として授業をしなければならなかったから。
6.今まで哲学プラクティスを続けてきたのはなぜですか?
哲学の専門家養成ではない教育の中で哲学の教育を行うのであれば、対話型の哲学教育が(色んな意味で)良いと思っているから。
7.活動の中で、一番大事にしていることはなんですか?
無理をしないこと。哲学を嫌いにならないで、できれば好きになってほしいと思っていること。
8.あなたにとって、哲学プラクティスとは?
対話型哲学教育の教員としては、興味深い教育手法。
「哲学カフェ」等の参加者としては、色んな人と出会える楽しい場所。
9.影響を受けた活動、人物がいたら、教えてください。
中川雅道さん、得居千照さん、小川泰治さん、神戸和佳子さん、廣畑光希さん、木下真希さん、永井玲衣さん、私の授業を受けて対話に参加してもらった学生や生徒の皆さん。
(もちろん、臨床哲学やハワイp4c等の実践やそれに関わる皆さん、日本で「子ども哲学」や「哲学対話」を広めた研究者の皆さん。)
関連サイト
※「哲学プラクティスに関わる人の9の質問」については以下をご覧ください。
いいなと思ったら応援しよう!

