
さてもさてもの日本古典 🔮『平家物語』④ 和歌を残し消えゆく平経正
事実を伝えるを旨とする現代のルポルタージュでは、ある人の、人生の最期に立ち会ったとしたら、あるいはその場にいた信用できる人からの伝聞によるものであっても、多少は筆を抑えるかもしれないが、基本的には、「わめいた」とか「泣き悲しんで」とか「無言のまま」とか、見たまま、聞いたままを描写するだろう。それは、そこに人間の本態を見ようとするからだ。

『平家物語』を読んでいて気づくのは、滅びてゆく平家一門の人々の合戦場において、最期に発したことばが書かれている人と、いない人に分かれるということだ。しかし、ことばがない人は、それに代わるものとして和歌が記録されているのが大きな特色である。
ことばがはっきり出て来るのは、一の谷で果てる平敦盛の
「ただ何さまにも、とうとう首をとれ」
壇ノ浦で果てる平教経の
「いざうれ己等、さらば四手の山の供せよ」
さらには平知盛の
「見るべきほどのことをば見つ、今は何をか期すべき」
といったところであり、これらは『平家物語』中の白眉の場面であって、彼らこそ、物語の看板役者的存在と言っていい。

「経正都落」という段がある平経正 ( 平経盛の嫡子 清盛の甥 ) は、残した和歌によって語られている人物の代表例である。
経正は平家一門きっての文化人であった。一の谷の合戦で果てたのだが、どのように打ち取られたかは全く書かれていない。「経正都落」で語られる経正の姿はいかにも文化人、風流者の姿である。
都を落ちる際、もはや都に戻ること叶うまいとの覚悟の上で、鳥羽天皇の第五皇子である覚性法親王から賜っていた琵琶の名品を、我が物とせず返しにゆくのだが、語られているのは、親王からの別離のことばではなく、下された「うた」なのだ。また、経正は親王に和歌を返している。
くれ竹のかけひの水はかはれどもなほすみあかぬ宮のうちかな
大納言法印行慶もまた「うた」を下し、経正はそれにも返した。
旅衣よなよな袖をかたしきて思へば我はとほくゆきなん
この和歌を詠んだあと駒を早めて、落ちゆく安徳帝を奉ずる一門を追ったというのが、平経正の『平家物語』での最期の場面である。
『平家物語』は、それぞれの人物の最期の描き方を、場にいた者から聞けたか、知り得たかどうかで決めるのではなく、最もその人物を劇中人物として語るにはどういう場面がふさわしいかを主眼に置いているようだ。
経正は、一の谷の戦場では、上流生まれの悲しさ、非力なまま、やすやすと討ち取られてしまったのであろう。東国武士の手にかかるとき、一抹のゆかしさを漂わせるような最期のやりとりはなかったということか。20代前半であったろうとみなされている。
しかし若き芸術家であったと言っていい彼ならではのエピソード ( 都落ちの際の振る舞い ) が、都の上流貴族たちの記憶に残されていた。そこを『平家物語』は拾った。
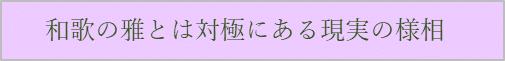
この時代の現実は、リアリズムそのものの世界であったのは、都に連れ帰られた敗残者たちの末路を述べた、鎌倉幕府の公式記述『吾妻鏡』からうかがい知れる。記述はこうある。
「皆八条河原に持ち向かひ、各長槍刀に付し、又木簡を付す。平家の由各それに差し付く。獄門に向ひ樹に懸く。観る者市をなす云々」
その様子を見るために集った庶民は、人の中に巣くう権力欲の恐ろしさをまざまざと見て、移り変わる時勢に理不尽の思いを募らせたことであろう。晒し首が平然と行われていたこの記述からは、合戦の実態は、大和絵に描くような情緒のある場面ではなく、腕や指が切り落とされて転がり、血が流れ落ちて地を黒く染め、戦にかり出された雑兵が、勝利の余禄として、高価な鎧、武具をはぎ取るために遺体に群がる様子を想像し得る。
勝敗を明らかにするのに、何事をも隠さない一目瞭然の見せしめ行為を必須とする掟は、武士社会には確実にあった。しかしまた、言霊を畏怖する精神があったのも確かで、その価値観の上では、「うた」を詠む人物においては、ことばより「うた」こそが魂の声であった。「うた」によって語られる人物は、創作上の意図で性格を作り変えてしまうことはできなかったであろう。「うた」をないがしろにすることは許されなった。
傍証として、リアリズムの記録書、『吾妻鏡』にあっても、たとえば静御前が義経を慕った、鎌倉幕府には好ましからざる和歌が記録されていることを挙げたい。
「よしの山みねのしらゆきふみ分て入りにしひとのあとぞ恋しき」
その思いに感じ入り、「上下皆興感を催す」と記述している。静御前という人物像を決定している記述である。

先に挙げた、平敦盛、平教経、平知盛ら、一条の光がくきやかにその横顔を照らし出している人物に比べれば、平経正は『平家物語』の中では、脇に沈む人物である。
しかし、文化の伝統の上に置くと、経正は、平家一門の中では、並みよろう平家の青年武人より一段高い処にいる人である。鳥羽天皇の皇子である覚性法親王が、訣別の意を持って琵琶を返しに来た経正に、手ずから和歌を下しているのは、格段の行いなのである。
覚性法親王は、名刹仁和寺の寺主であり、歌会や歌合を催していた文化の統率者と言える貴人である。経正が、この親王に気に入られていたのは、琵琶楽奏の巧みさが先ずあってのことだとは思うが、和歌を詠む才能を愛でられていたことも見逃せないことである。親王が経正に下した和歌を下に引く。
あかずして別るる君が名残をば後の形見につつみてぞおく
また、経正とはかかわりのない和歌ではあるが、親王は他にも下に引いたこういう和歌を詠んでもいる。( 下の和歌は『平家物語』には出てこない )
親王の性格がほの見える和歌で、経正との別離の際に、どのような惜別の思いを親王が抱いたかをしのぶよすがになるだろう。
はかなさを恨みも果てじ桜花うき世は誰も心ならねば (千載集 1053)
なき人を思ひ出でたる夕暮は恨みしことぞ悔しかりける(千載集 954)
令和6年6月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
