
詩の編み目ほどき⑰ 三好達治「菊」
菊
北川冬彦君に
花ばかりがこの世で私に美しい。
窓に腰かけてゐる私の、ふとある時の私の純潔。
私の膝。私の手足。( 飛行機が林を越える。)
―― それから私の秘密。
秘密の花弁につつまれたあるひと時の私の純潔。
私の上を雲が流れる。私は楽しい。私は悲しくない。
しかしまた、やがて悲しみが私に帰つてくるだらう。
私には私の悲しみを防ぐすべがない。
私の悩みには理由がない。―― それを私は知つてゐる。
花ばかりがこの世で私に美しい。
三好達治の第一詩集『測量船』所収の「菊」を今回取り上げる。
「北川冬彦君に」と副題にあるから、この詩は、詩友、北川冬彦に対して、告げたい思いを述べた詩であるが、北川冬彦には言わんとしていることが、具体的事情をもって浮かんで来るはずだから、友人相互の関係においてのみ理解できるように書いた性格の作品と考えるのは間違いだろう。
一説には北川冬彦の詩「絶望の歌」( 難解な詩なのでここでの解釈はしない ) への返しと見る意見もあるが、北川冬彦の詩作品の何かに触発された思索の一断片を、本人に伝えたいという思いを副題に据えたということだろう。

先ずこの詩の解釈の結論から言おう。
タイトルの「菊」とは、亡き人々を暗示していると思う。詩本編の中では、「菊」のことばは出て来ない。花と示されている。しかし、その花が「菊」を意味することを、タイトルが語っている。
そしてこの詩の裏に潜むテーマは、これもまたことばでは出てこないが、《死》と《追憶》であると思う。
「しかしまた、やがて悲しみが私に帰つてくるだらう」
「私には私の悲しみを防ぐすべがない」
「私の悩みには理由がない。―― それを私は知つてゐる」
と続く詩行は、予期せずに胸に去来する亡き人への追懐という事象を重ね合わせると、意味が取れるのではないか。
「花ばかりがこの世で私に美しい」という第一行と最終行に繰り返される詩句は、言い換えれば、「《 亡き人の思い出ばかりが 》この世で私に美しい」ということになる。
ではなぜそういうふうに率直に言わなかったか。
達治の全業を見ると、たとえば与謝野鉄幹、与謝野晶子ら「明星派」ふうの直情を明確に吐露する表現を好まなかったことが読み取れる。また、山村暮鳥、高村幸太郎、福士幸次郎らの人道主義的な表現も、深く心に留まらなかったことを「文学的青春伝」という随筆で述べている。
『花匡 ( はながたみ ) 』という全編花に思いを仮託した詩集があるのが象徴するように、達治にとって花というフレーズは、しみじみとした情の中へ入ってゆく心の乗り物とも、そこに憩うための椅子とも言える。
「椿花」「チューリップ」「藤浪」「薔薇」「桃の花咲く」「すみれぐさ」「日まわり」「さるすべり」など、達治は花をタイトルにした詩が多く、またタイトルにはしていなくても、花に託してたくさんの詩を書いた。
亡き友への追憶は、達治にとっては創作の動機をなすものである。その例証となる文章を引用する。
「菊」は、昭和5年2月初出、達治29歳の作品だが、それから9年後の昭和14年9月39歳のとき、雑誌「改造」に書いたのが「半宵記」である。
この「半宵記」は、三好達治が名随筆家でもある証をなす一文であり、壮年の半ばを迎えて、同じ道を歩みながら、若くして逝いた者にしみじみと思いを致した名文である。長いがぜひ、引用文を味わってほしい。
――我をして靜かにゆかしめ給へ。
これが私の希望であり私の祈りである。緩やかな坂路を下るやうに私は死の國へ下つてゆきたい。私は必ずしも長壽( ちょうじゅ )や老齡を希ふものではないが、それが死の國への緩徐な靜かな移行きである自然な通り路なら、私はそれをやはり自分の通り路としても撰( えら )びたいと思ふ者である。
私の親しい友人達の幾人かは、この緩徐な手間のかかる、しかしながら靜かな自然な通り路をよそにして、彼らの急坂を遽( あわただ )しげに驅け降りて、無慘な病魔󠄁にせきたてられて遠い地平に沒してしまつた。
K君は、とある初夏の日の夕暮、ある街角で私の飛び乘つたバスに向つて、片手を擧( あ )げて微笑と共に別れの合圖( あいず )を送つてゐたのが、そのままこの地上の最後の訣別となつてしまつた。
T君は、ある夜ふけの橋の上でいやといふほど私の足先をふんづけて、私を不機嫌にしたのを記念にして、その後間もなく永遠に消息を絶つてしまつた。
N君は、私の多年愛用したステッキの磨り減つて短くなつたのを、脊丈 ( せたけ )の低い彼には恰( あたか )も手頃だと稱( しょう )して所望してゐたが、そのうち私の宅まで受取りに來ると約束をしておいて、そのままたうとう來ずじまひになつてしまつた。ステッキは依然として拙宅の物置に殘つてゐる。
またもう一人のK君は、眞夏の暑い日に私が病氣を見舞つて訪問すると、恰もその人らしく私の制止するのも聽き容れず枕許に端坐して、浴衣一枚の寢卷姿のままではあつたが、甚( はなは )だ几帳面な應接ぶりで私を辟易( へきえき )させ、さうして彼といふ人物の印象を私のためにもはつきりと完成させて、その最後の終止符を打ちそへるやうに、玄關の閾際で極めて丁寧なお辭儀をした。
O君は、ある田舍へ突然私を訪ねて來て、そのまま私の忠吿も聽かず更にその山奧の溫泉場へ傭( やと )ひ馬に搖すられながら入つて行つたが、その彼の何ものかに追はれるやうなせかせかとした後姿は、今日も私の眼底に殘つてゐる。
このやうにして思ひ起してみると、これらの人々が私の記憶に殘していつた、それぞれのふとしたその最後の擧止や言動は、思ひなしか、みなそれぞれの深い運命の陰翳に隈どられた、何といつていいか、一種月光的なものとして思ひ起されるのである。死者らの姿の森嚴( しんげん )……それを森嚴と見る者は、多くの些事( さじ )から成立つてゐる私達の日常生活をも、やはり同じやうに森嚴と見なければならない筈( はず )だらう。さう思ふと、暫くの間の病院生活ででも、あれほど心をとり紊( みだ )した私のやうな凡愚の者の、日頃はどれ位迂闊( うかつ )に暮してゐるかといふことにも、小さからぬ且つは森嚴ならぬきを感ぜられるのである。
戦争の時代を生きた世代である達治には、軍の士官学校の仲間に、早逝した者もいて、そういう仲間の死を達治は随筆に書いてもいる。
達治が若いうちから、自分を世外の人のように意識し、老境を思わせるような詩や随筆を書いたのは、今では私たちには砂楼としか思えない皇国思想によって、青年の誰もが、ひとり永らえることが、行く末の幸福として視野には映っていなかったこの時代の、運命論的に傾かざるを得なかった人生観を抜きにしては考えられないだろう。
『測量船』出版は、天賦の詩才という術により、ずるずると足を取られそうな、自分では幸福感を持てない少年時代から続く日々の記憶の地盤を踏み固めて ( つまり作品として昇華して ) 過去へと送りやり、新体詩や読み古された文語定型の情緒に頼らない詩人としての飛翔を期した営みであったと思う。
巧みに実体験の場面を作り換えたり、象徴的な表現で遠回しにしているが、詩のことばに、幼い日から青春時代にかけての実体験が濃く反映されている点は、『測量船』を読み解くほどに見えて来る。
詩人にとって第一詩集とは概してそういうものだとはいえ、象徴的語法を駆使したと形容される『測量船』においても、達治の全詩集のうち、戦後の詩集を別格として、終戦までに出された詩集群では、どの詩集よりも、人生の軌跡が浮かび出ている特徴は顕著だ。
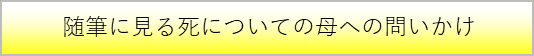
「菊」の表現を考察してみよう。
「ふとある時の私の純潔」「あるひと時の私の純潔」と、《 純潔 》が繰り返されていることに目が止まる。
「秘密の花弁につつまれたあるひと時の私の純潔
私の上を雲が流れる。私は楽しい。私は悲しくない」
と、《死》を題材にしているという私の見方からすれば、矛盾するような不思議なことばが出て来る。
この「 純潔 」「私は楽しい」「私は悲しくない」が、何を意味しているのか、ここにこの詩の核心がある、と言ってもいいほどだが、私にはこの詩の背景をなすように感じられる一文が浮かんで来る。
下に引用する一文、「放下箸」と題した随筆に目を止めた理由は、第一詩集『測量船』は、三好達治の作品を解釈した私の過去の記事で取り上げた「乳母車」「昼の月」「昼」「少年」など、多くの詩において、彼自身が随筆で後年語っているように、家庭の事情から来る少年時代の挫折と憂愁、死に対する恐れに捕らわれた経験が、影を落としていると読めるからだ。
死を題材にしながら、少年時代のある一日を懐古した、達治の随筆にしてはたいへん明るい印象を残す一文である。そこに書かれた情景を、「菊」の詩文に重ねてみると、私には「菊」という詩が愛しいものになってゆく感じを覚える。
「放下箸」より、その一文を下に示す。
ある日洗濯をしているお袋さんにかう言つて尋ねてみた。
ー どうして人間は死ぬのだらうかね?
ー さあお母さんにも分からないね、そんなむつかしいこと
さすがにお袋さんもつと仕事の手を止めて、突然な私の質問にけげんな顔をしたが、意外にもその顔はすぐと晴れ晴れしい笑顔になつて、
― そんなことを考へたら何も彼もつまらなくなつてしまうよ、誰だつて。
と平凡な返辞であった。
さうしてそのまま仕事の手をしばらく休めているのが、私にはたいそう無邪気にさへも見えた。
(中略)
私にはさふいう無邪気な考へ方もあるものかといふ感じがした。何か少しをかしさがこみ上げてくるやうで、一瞬私は気持ちが軽くなるのを覚えた。
(中略)
私にはふだんにはただ鬱(ふさ)ぎの蟲のお袋さんが、その暫くは不思議と晴れ々とした笑顔であつた。その眉根のあたりの記憶しかない。貧しいながらもそれは一つの啓示であつたといつていい。
私の二度目の苦しい発作的な時期は、それでどうやら打ち切りとなつた。さすがにそれも不思議だつたから忘れがたい。
明治41年、8歳の達治は神経衰弱となり長く休学した事実があって、上に引いた「放下箸」の一文も、その事情を背景にしている。この出来事は、少なくとも「菊」を書いた時点 (「菊」初出は昭和5年2月 ) では、私事を誰かに語ることは考えていなかったはずで、 「―― それから私の秘密。」と言ってもおかしくはなかっただろう。
『測量船』の詩篇は、母恋いの思いが核になっているという有力な見方がある。母によって、死の観念の呪縛を解かれたことが、「菊」の創作に響いているとすれば、母恋いの解釈の対象作品には取り上げられることのない「菊」が、実は母への追憶がもたらしたものであると言える。

また、菊が追憶の導きとなっているのを、「花の香」という詩に見ることもできる。
花の香 ※一部のみ抽出
三好達治
霜の後(のち)なほ殘る軒端の菊 ほろ苦(にが)い香を
冬の薔薇(ばら) 甘い薰りを 私は思ふ
とりどりの思出の姿のやうに 聲のやうに
目方のやうに 私はそれを爐邊に受とる
すなはちそれが私を呼ぶ この
心一つを さてまた風にさらさうと
旅の仕度にとりかかる
「達治にとって花というフレーズは、しみじみとした情の中へ入ってゆく心の乗り物とも、そこに憩うための椅子とも言える」と、先に述べたが、この感覚の背景に、達治が読みこんでいた陶淵明の漢詩への共感があると思う。菊が重要な詩の核をなしている詩だ。
『飲酒』第五
(『飲酒』連作の中の一編 ) 陶淵明
廬(いおり)を結んで人境(じんきょう)に在り
而も車馬の喧(かまびす)しき無し
君に問う何ぞ能(よ)く爾(しか)るやと
心遠ければ地自ら偏(へん)なり
菊を東籬(とうり)の下に采り
悠然として南山を見る
山気(さんき)日夕(にっせき)に佳(よ)く
飛鳥(ひちょう)相与(とも)に還る
此の中(うち)に真意有り
弁ぜんと欲すれば已に言を忘る
■ 大まかに意をとれば、次のようになろう。
人里には住んでいるのだが、心を、静かな処に置いていれば、田舎にいる
のと同じようなものなのだ。菊の花を東のまがきの下から採って来て置
き、南山をゆったりと眺める。そういう暮らしの中に、山に靄のかすむ夕
べの景色はすばらしく、その山へと鳥たちは帰ってゆく。
自然の教えてくれる真理が、この眺めの内にある。それを悟れば、発すべ
き言葉もなく、もう何を言葉にすることもなかろう。
令和6年8月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
