
『とうもろこしぬぐぞう』で衝撃のデビューから2年…2作目のため、描いたピーナッツは200パターン!難産な絵本づくりを語る
8月末、製本所から届いたばかりのほやほやの新刊『ピーちゃんとナッツくん』を受け取りにポプラ社にかけつけてくださったのは、絵本作家のはらしままみさん。2年前のデビュー作『とうもろこしぬぐぞう』はあっという間に日本中の親子や園で人気の絵本となりました。この日は、デビュー前からずっとそばで見守り続けたフリー編集者の松田素子さんにもオンラインで参加していただき、おふたりに新作に込めた思いを聞きました。 (聞き手・ポプラ社編集部 小堺加奈子)

『ピーちゃんとナッツくん』(はらしままみ 作・絵 ポプラ社・刊)
ピーナッツの男の子と女の子がリズミカルな言葉とともに、手やおしり、からだをくっつけあっていく楽しいスキンシップ絵本。

【はらしままみ】(以下 は)
1983年東京都生まれ。明治大学商学部商学科卒。
電機メーカー勤務。「パレットクラブスクール」絵本コース、「キルタースペース絵本勉強会」、絵本ワークショップの「チャブックス」に参加し、絵本創作に取り組む。デビュー作は『とうもろこしぬぐぞう』(ポプラ社)。
【松田素子】(以下 松)
編集者、作家。児童図書出版の偕成社に入社。雑誌「月刊MOE」の創刊メンバーとなり、編集長を務めた後1989年に退社。フリーランスとして多くの作家や絵本の誕生に関わっている。絵本のワークショップ「チャブックス」を主催。
難産で生まれたかわいい新作絵本!
ーーついにできました! 2作目の新刊、おめでとうございます!
は:(フラップをめくりながら)両面に印刷されているのを見るのははじめてなので、ちゃんとできていてよかったです! ぴったりきれいに合わさっていますね!
松:「おかあさんおめでとう」って感じですね。私や小堺さんは言ってみれば助産師だからね。いい子が生まれましたね!! おめでとうございます。

努力家ゆえの難産!? 製作開始から5年を経て……
ーー見本を手にした今のお気持ちをお聞かせください。
は:無事に本になってよかったなあ、と。キャラクターが決まる前に、何種類のピーナッツを描きましたかね。あれは第一の迷走でしたね。「200個描いて」って松田さんに言われて、スケッチブックにびっしり描いて送ったらすべて却下されて、またひたすら描いて。そのなかでやっと一つだけ、松田さんと小堺さんが「いい!」という絵があって方向性が決まったんですよね。描けばかくほど、かわいく描けなくて、でもこうやって形になって、ホッとしています。

松:この絵も今見たら全然違うね。他の絵はリボンがまだついてなかったり。これで方向性、向かうべき場所が見えたのよね。はらしまさんは頑張り屋さんだからね。そこはすごい尊敬しているんです。でもたくさん描けばいいわけじゃないのよ。(笑)あっちこっち行くときがあるから、まず向かうべき場所が見えることが大事だからね。
は:松田さんから「これでいい」ではなくて「これがいい」ということを意識して、と言われましたね。自分が話す言葉もそうで。「私はこれがいいです」というのを心がけましたね。
松:「コーヒーと紅茶どっちがいい?」「コーヒーでいい」じゃなくてね。自分が出す作品に対する責任と覚悟が必要でしょ。作家としての心構えや姿勢につながってくるから、そんなことも言ったかもね。難産だったから、ある意味今、すごく嬉しいんじゃない?
は:本当にうれしいです。取り掛かりはじめてからなんだかんだ5年かかっていたので。『とうもろこしぬぐぞう』と同時に進めていましたからね。

「めくる喜び、くっつく喜び」新作に込めた思い
ーー新作はどんな絵本ですか?
は:この本で、めくってぴたっとくっつく喜びをたくさん感じてほしいですね。小さい子がお母さんやお父さんとこれを読んで「わたしもぎゅっとしてほしい」「ぎゅっとしたい」という気持ちになってくれたらと思って、一生懸命作りました。めくる喜び、くっつく喜びを楽しめる絵本になったかなと思っています。
松:その通りですね。『ぬぐぞう』を作るときから、耳にタコができるほど言い続けてきたのは、この絵本を通して、そこに幸せな時間、場所が生まれるかということ。絵本というのはだれかに届くものでしょ。そこには必ず幼い子どもたちに読んでもらう現場がある。そういうところでこの絵本がどんな風に読まれるか、そこを徹底的に考えて、そこに幸せな時間が生まれるか、そこだけはしっかり見ながら作ろうね、と言ってましたよね。それがようやく形になったなと思っています。今から読者の声が楽しみです。
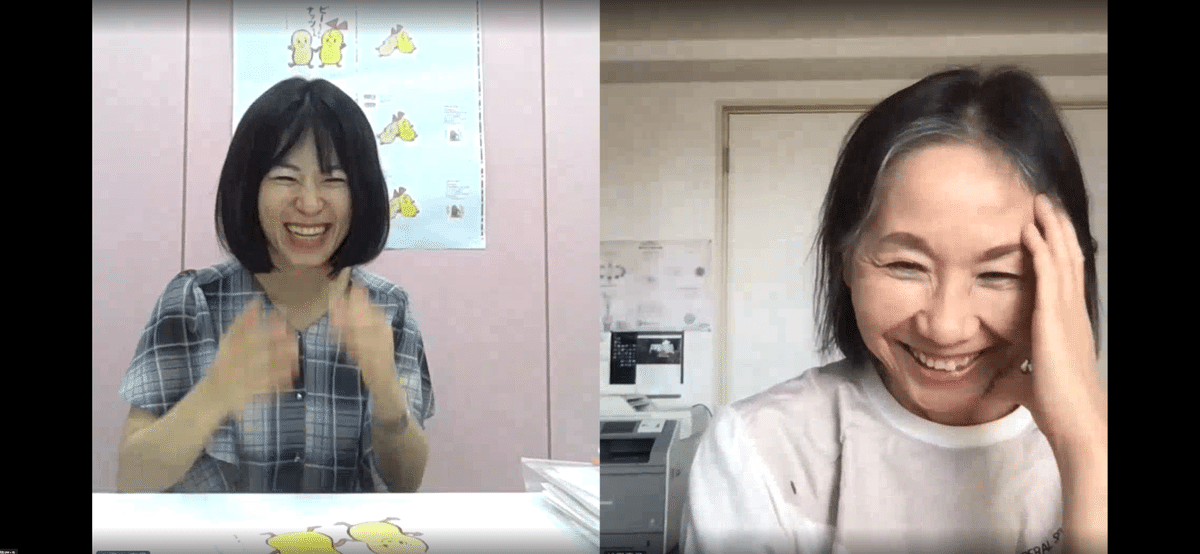
ーー新作を見た社内の別の編集者から「シンプルって、一番難しいけど一番大事だよね」と声をかけられました。このシンプルな絵本に、5年も費やしているんですよね。キャラクター設定や展開でも、いろんな選択肢がありましたよね。
は:豆が登場するパターンも実際に作ってみて、子どもたちの前で読んでみたんですよね。ところが、せっかくピーちゃんとナッツくんを自分だと思ってみているのに、豆が出てくると「ピーちゃんはおかあさんだったの?」って思ってしまうことがわかって。ちがうんだなとわかりましたね。
運動会で保育士さんを見て感じたこと
ーーこのお話が生まれたきっかけはありましたか?
は:「ぎゅうする」って大人も幸せな気持ちになりますよね。子どもが通っていた保育園の先生が、運動会でゴールテープの代わりに手を広げてゴール地点で待っていたんです。子どもたちが全力で先生に向かって飛び込むのを見て、こんなにも自分の子のようにかわいがってくれるのかと、嬉しくって。保育園には息子がゼロ歳児の時から預けていて、先生が家族のように愛情を注いでくださったのでほんとうに感謝していました。「ぎゅう」って、しても、されても、見ていても幸せな気持ちになるんだなって思いました。


ーーよくわかります。特に疲れたときには、ですね。
は:そうなんです。忙しすぎると、触れあうこと自体遠ざかってしまいますよね。そんな人たちにも、思い出して「ぎゅう」ができる時間になればいいなと思いながら、この本を作りました。
ーー『とうもろこしぬぐぞう』を初めて見せていただいたときに、この『ピーちゃんとナッツくん』のラフも同時に拝見しましたね。
は:そうなんです。出版社に作品を売り込むときに松田さんから「1冊だけではなく、いくつかもっていったほうがいい」と言われたのも、実はきっかけなんです。いろんな種類の絵本を見せたほうが、出版社の方に自分の作風を見てもらえますからね。
「ピーピーナッツ ピーナッツ おなかをぶつけて ピーナッツ」という詩が浮かんできたんですよね。それでラフを描いて保育士の友達に見せたら「おもしろいよ!」と言ってくれて。それで「とうもろこしぬぐぞう」の他に「ピーちゃんとナッツくん」のラフも作り、出版社に持って行きました。

ーー最初のラフは今とは違うものですか?
は:半分くらい今と同じですが、さかだちしていたり、転んだりしている場面もありましたね。キャラクターもふたごのような見た目でした。アーモンドやカシューナッツが出てくるパターンもありました。
鮮烈なデビュー作を経てーーー
ーー『とうもろこしぬぐぞう』が出たのが今から2年前。話題のデビューとなり、いろんな賞にも選ばれました。ぬぐぞうさんの反響は届いていますか?
は:そうですね。「お風呂に入る前にぬぐぞうごっこしました」などといった声を聞くと、自分が作った本でこんなにも人が喜んでくれるんだ、と本当にありがたいと思いました。

ーー1年目、2年目と夏を迎えるたびに、広まっているのがわかり嬉しくなりますね。
は:保育園でもとうもころしの皮むき体験前に読んでくださっている園もあって。この前は、私の幼稚園時代の先生が園の子どもたちに読んでいる写真をいただいて、感動しました。小学校、中学校の時の先生もお孫さんに読んでくださっていて、嬉しかったですね。
作家としての可能性を広げる2作目に
ーー2作目のプレッシャーはありましたか?
は:『とうもろこしぬぐぞう』と『ピーちゃんとナッツくん』は全然毛色が違うので、少し不安はありましたが、待っていてくれる人がいると信じて作りました!
松:編集者的には『ぬぐぞう』シリーズの続刊だと同じパターンになって、よくないと思ったんですよね。同じものへの期待もあるでしょうけど、「いつもの感じ」になってしまうのは、はらしまさんの扉の多さ、可能性を狭めてしまうし。私は全然不安はなかったですよ。むしろ「これがいい!」と思っていました。人は一つ成功すると、それを踏襲しようとする傾向があるけれど、私はむしろそれは危険だと思っていて。自己模倣になってしまうからね。
は:友達からは「この作品は私っぽい」と言われるんですよ。むしろ、『ぬぐぞう』が私っぽくないのかも?(笑)
ーー『ぬぐぞう』の作者ってどんな人なんだろうと思いながら、はらしまさんにお会いした方、みなさんそのギャップに驚かれますよね。たしかに、デビュー作とはまた違った新作で、はらしまさんの可能性の大きさを感じます。
松:はらしまさんはまだこれからだから、自分の中の新しい可能性をさぐってほしいですよね。
読まれる現場を意識した本づくり
ーー製作中に、松田さんから他にもアドバイスはありましたか?
は:「この本の先に小さい子がいることを忘れないで」ということをよく言われましたね。自分だけが作品を分かっていてもいけないし、理屈っぽくなってもいけないし、リズムが悪くならないように、ということを意識をしていました。
ーー意識することで、具体的に変わったところはありますか?
松:最後のシーンが変わったよね。
は:抱きつくシーンですよね。最初はピーちゃんに対してナッツくんが完全に両足をあげて飛びついていたんですよね。

松:この絵本は読者の子どもたちが絶対に真似したくなるはずで、そうなると、両足あげて飛びついていると、危ないですよね。例えばおじいちゃんと真似っこをしたら転んでしまう可能性もあるし、片足は地面につけよう、という話し合いをしましたよね。それは読まれる現場を考えたからよね。
作品を出すということは、ある意味責任を伴うことだから、こうしたいという作家の希望だけではダメで、ここは冷静に考えましょうと言いましたね。
は:そうですね。抱きつくシーンも何枚描いただろう。
松:最後はもうかなり細かい調整でしたね。ちょっとした表情の違いや手脚の角度とかね。

は:裏表紙の寝ているふたりの絵も、実際に寝ている子どもの写真を友達に送ってもらったりしてたくさん描きました。

●きいろいおうちfarm(神奈川県・伊勢原)でも、ラフを読ませていただきましたね。
は:はだしで土の上を走り回っている子どもたちが、ちゃんと聞いてくれるかなとドキドキしていたんですが、絵本の真似をして手を合わせたり、「もっと読みたい」と言ってくれる子もいて、すごく嬉しくて、頑張って作るぞ! という気持ちになりました。
ーーこの本をどんな人に届けたいですか。
は:あらゆる人にですね。小さい子だけではなく、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、みんなに読んでほしいですね。
読まれてはじめて命が吹き込まれる絵本
松:『とうもろこしぬぐぞう』とこの本の違いは「スキンシップ」があることですよね。『ぬぐぞう』はスキンシップはなくて、自分で脱ぐ! だもんね。この本は、相手がいて成り立つスキンシップを描いている。こういうのって、今足りないじゃない。そこで育つもの、安心できるものがいっぱいあるはずで。いろんな機器が発達して、肌でふれあうこと以外のコミュニケーションもある意味できるようになってしまって。ふれあうことで育つ何か大事なものが忘れられているようにも思うんですよね。
小さいころから何かを覚えさせよう、わからせようという教育も否定はしないけれど、理屈ではない生き物としての肌と肌のふれあいが、どれほど大事なものを育てるのか。私はすごく価値のあるものだと思いますね。

は:現場で読まれてはじめて命がふきこまれる絵本ですね。
松:そう、本だけで完結している作品ではなくて、読まれる現場と一緒になって完結する作品なのよね、これは。そういう本はものすごい大事だと思います。ただかわいい、というだけでなくてね。
ーー会社で校正をしていたときも、とくに男性がよく声をかけてくれたんですよね。「ピーちゃんとナッツくん、いいですねえ」と。
松:子どもたけでなくて、大人のほうも、そういうふれあいを求めているかもね。大人にとってもほっとする本かもしれませんね!
ーーこの絵本は言葉をつくさなくても、見ていただければわかる絵本かもしれず、まずは手にとってめくっていただきたいですね。さて、最後に、今後はどんな絵本を作っていきたいですか?
は:お母さん、お父さんとの思い出の一冊なんだよね、と言ってもらえるような本を作りたいですね。
松:大学生への講義で「あなたにとって忘れられない絵本は?」と聞いたことがあったんですけど、男性も女性も、「お話の内容がおもしろくて」ではなくて「お母さんの膝の上で読んでもらったことが忘れられないから」といった、読まれた空気、思い出が一緒になって忘れられない絵本、というのが多かったです。
は:読者の方の手に渡って、読者が育ててくれる絵本になったらいいですよね。そんな絵本をこれからも描いていきたいです。
ーー『とうもろこしぬぐぞう』もまさしくそうですね。いろんな家庭で、それぞれの「ぬぐぞうさん」が活躍していますよね。
は:書店さんがグッズが欲しいと言ってくださったので、ぬぐぞうグッズもできましたしね。あ、これは小堺さんからいただいたピーちゃんとナッツくんのアクリルスタンドです。


松:かわいいじゃない。私、子どものころ、タオルが好きだったんだけど、ピーちゃんとナッツくんも、タオル地のぬいぐるみとかあったら、いいなあ……。ぎゅーってしたい!
ーー商品化のお話、お待ちしております!!(笑) 今日は本当に、ありがとうございました!
松:本当におめでとうございます。この子は元気に絵本の世界をわたっていきますよ。3作目、がんばりましょうね!!
は:はい! 次の絵本もがんばります。


デビュー作『とうもろこしぬぐぞう』の誕生秘話はこちら!
★ご紹介した本
『とうもろこしぬぐぞう』グッズもできました!
