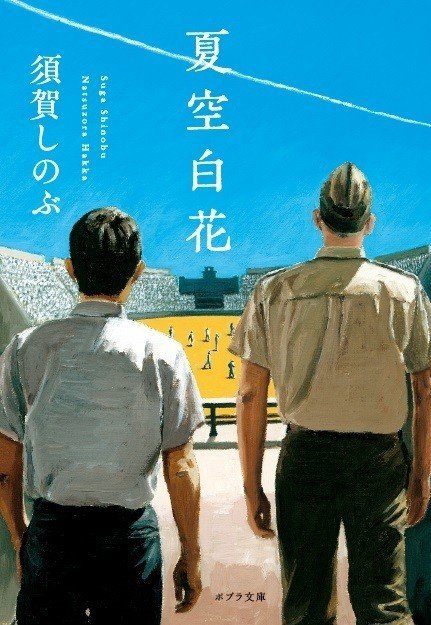キャラクターの名前は「あ」で開く?――実力派作家・須賀しのぶが自作を解説! 作家の頭の中を全公開
まずはこの二つの文章を読みくらべて欲しい。
風のない日だった。
朝日新聞大阪本社の屋上に掲げられた国旗は、力なく垂れている。そよとも動かぬ旗の前には上野社長が立ち、その背後には百五十を超える社員がただじっと頭を下げている。
整理部の真田武彦は、後ろのほうでぼんやりと立ち尽くしていた。
暑い。うなじに突き刺さる陽光は、凶器である。帽子を脱いでいるせいで、刈り上げた後頭部から首にかけて今にも燃えあがりそうだった。
こらあかんなぁ。
ラジオから流れる声を聞いた神住匡は、真っ先にそう思った。
「シカルニ、コウセンスデニシサイヲケミシ、チンガリクカイショウヘイノユウセン、チンガヒャクリョウユウシノレイセイ……」
あかん。
内容があかんのではない。何を言っているか、聞き取れないのだ。
昭和二十年八月十五日。東の空には入道雲が湧いてはいるが、いまいましいほどの晴天である。
この二つの文章は、どちらも同じ作品の冒頭である。
一つ目は雑誌掲載時の冒頭部分で、二つ目は書籍化されたときの冒頭部分。
それぞれ描かれているシーンは同じだが、アプローチがまったく異なっていて、文章から喚起される映像が違って見えてとても面白い……と思うのは僕だけだろうか。
この二つの書き出しが存在する作品は、須賀しのぶさんの『夏空白花』。
須賀しのぶさんは言わずと知れた実力派作家で、『革命前夜』で第18回大藪春彦賞受賞、『また、桜の国で』で第156回直木賞候補、『夏の祈りは』で「本の雑誌が選ぶ2017年度文庫ベストテン」1位……などなど、幅広いジャンルの小説を手掛けられ、そのどれもが文芸界で高く評価されている。
2018年に刊行された『夏空白花』は、須賀さんが取り組んできた「歴史」と「高校野球」という二つのテーマが融合した一冊。
終戦直後の日本を舞台にし、戦争で失われた高校野球を復活させるべく奔走した男たちのドラマを熱く描いた骨太な歴史大作で、第9回山田風太郎賞にノミネートされるなど話題を呼んだ。
『夏空白花』はもともとPR誌「アスタ」にて連載された作品だった。
連載を終え、書籍化に向けて須賀さんが手を入れてくれた原稿が届いて僕は目を丸くした。
なにせ冒頭から全部書き換えられていたのだ。
ついでに言うと、主人公の名前も変わっている。
神住って誰やねん!
そう突っ込みながら読み始めたが、たちまち唸らされた。
連載時から読み応え抜群の素晴らしい作品だったが、それが更にドラマとしてパワーアップしている。なにより文章の美しさ。
川の流れのように淀みなく、ただそこに浸っているだけで心地よく感じる文。
文章というものはとても難しい。
ただの言葉の連なりなのに、それだけで何かを伝え、人の心を感動させることができる。
同じ事柄を伝えるにも、文章次第で無限の方法がある。
最初に引用した冒頭のシーンもそうだ。あるシーンを言葉で描く方法は幾通りもあって、その中で作家さんはベストの描き方を掴み取っている。
きっと須賀さんは、この作品のベストな文章を探りながら連載の冒頭を書き、書籍化の際にまた違うベストを見つけたから冒頭の文章を変えたのだろうと思った。
はたしてそれはどういう思考と選択を経て、選び抜かれたのか。
「文章の書き手」として『夏空白花』にどのようにアプローチし、完成させていったのか。
そういえば、主人公の名前もなんで変わったんですか、須賀さん!
そんなことを聞いてみたいと思ったので、須賀さんと一緒に『夏空白花』の原稿をふり返りながら、どのようにこの作品を「書いて」いったのかを語ってもらうことにした。
いわばオーディオコメンタリーならぬ、テキストコメンタリー(?)である。
作家の頭の中をのぞき見できる珍しい機会だと思うので、本と合わせてお楽しみ頂ければ幸いである。
(聞き手:担当編集者 森潤也)
※『夏空白花』を未読の方には一部ネタバレになる可能性がある箇所もございます。ご注意ください。
<須賀しのぶプロフィール>
1972年、埼玉県生まれ。上智大学文学部史学科卒業。94年「惑星童話」でコバルト・ノベル大賞の読者大賞を受賞しデビュー。2010年、『神の棘』が各種ミステリーランキングで上位にランクインし、話題となる。13年「芙蓉千里」三部作で第12回センス・オブ・ジェンダー賞大賞、16年『革命前夜』で第18回大藪春彦賞、17年『また、桜の国で』で第4回高校生直木賞を受賞。
著作に『紺碧の果てを見よ』『くれなゐの紐』『雲は湧き、光あふれて』『夏の祈りは』『荒城に白百合ありて』などがある。
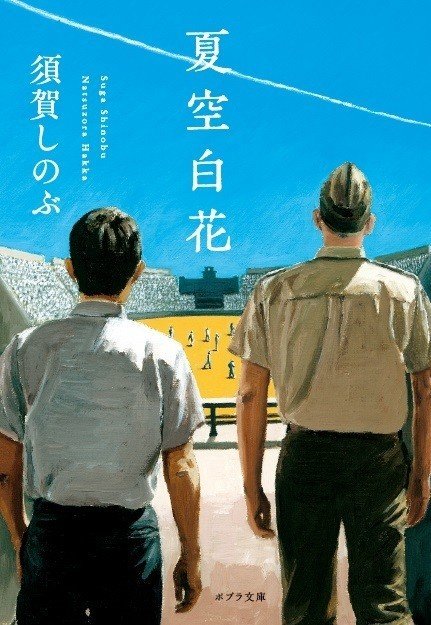
<『夏空白花』内容紹介>
1945年夏、敗戦翌日。昨日までの正義が否定され、誰もが呆然とする中、朝日新聞社に乗り込んできた男がいた。全てを失った今こそ、この国に希望を作るため、戦争で失われた「高校野球大会」を復活させなければいけない、と言う。
不良記者の神住は、人々の熱い想いに触れ全国を奔走するが、そこに立ちふさがったのは、思惑を抱えた文部省の横やり、そしてGHQの強固な拒絶だった……。
シーンにカメラをどう当てていくか
森 小説の「書き出し」はやはり難しいですか?
須賀 難しいですね。最初の数行で読者を惹き込まないといけないとよく言われますけど、ぱっと出てくるときとそうでないときがあります。
森 書籍化したときに連載時から冒頭を書きかえられていますが(記事冒頭の引用参照)、なぜ変更されたんですか? 僕も書籍版の書き出しのほうが好きですが、連載版も決して悪くないと思いましたが。
須賀 連載版の書き出しも悪くないんですけど、なんか物足りないなと思ったんです。それで色々と考えて、こう書きかえました。連載を書籍化するときに冒頭は変えてしまうことが多いですね。
森 でも、冒頭のシーンのイメージは須賀さんの頭の中にあるんですよね。
須賀 シーンのイメージは頭の中で固まっていて、それにどうカメラを当てていくかという違いなんですけど、読者さんが入りやすいのはどういう描き方だろうとすごく考えますね。連載から変えたのはそういう点が大きいです。
森 連載版はカメラが外から徐々にズームしていく感じですけど、書籍版ではすでに内に配置されている印象です。
須賀 そうですね。連載を通して主人公の神住のキャラが掴めたことで、書籍版ではその配置が可能になったんだと思います。
(※書籍化に際して主人公の神住の人物像も変更されている。アスタ版:過去のトラウマから厭世的で抜け殻のように生きている人物→書籍版:過去のトラウマから人生がばからしくなり、ちゃらんぽらんに生きている人物)
森 最後まで書ききることでキャラクターが自分の中で整理され、文章も再構成できた……ということですか?
須賀 作家としてどうかと思いますけど、私は最後まで主人公のキャラが掴めないことが多くて(笑)。主人公はいわばカメラなので、主人公自身の役割に加えて物語を俯瞰して見るところもあります。特に私は一人称に近い書き方をするので、主人公の眼を通して物語を書いている途中で「あなたそういう人だったのね」と理解できることが多いですね。
キャラクターから人間に変わる瞬間
森 書いている途中でキャラクターを理解するという話ですが、執筆に入る前に須賀さんの中でイメージしていたキャラクター像があるわけですよね。でも、書いていく中でそれが別の形に息づいていくわけですか?
須賀 キャラを立てるときは「次こそは変えないぞ」と思って毎回臨むんですが、途中で絶対に考えていたのと違う動きをします。キャラクターが「自分はこんなことしないんだけど」と言ってきて、「たしかにね」と作者が納得させられるんですよ。
森 書きだす前にキャラクターの設定はどこまで詰めておくものなんですか?
須賀 決めているのは基本的な性格と背景ですかね。昔は年表を作ったりしたこともありましたけど、今は家族構成とか簡単な経歴や性格くらいで、それを自分の中に飲み込んで動かしていきます。最初はキャラクターとして動かしていきますが、ある時点で人間に変わる気がしますね。
森 その垣根というか、ラインはどこなんでしょうか。
須賀 それが私も分からないんですよ。説明するのはとても難しいですね。
森 登場人物の名前はどう決めてるんですか? ちなみに連載時の主人公名は真田で、書籍では神住に変わりましたが。
須賀 名前にそこまでこだわりはないです。連載から名前が変わったのは、作中に真田という別の実在の人物が出てきてややこしかったからです。
でも、実は名字か名前が「あ」で開く言葉で始まることが多いんですよ。(真田=さあ、神住=かあ)。『革命前夜』の主人公は眞山柊史(まあ)で、『また、桜の国で』の主人公が棚倉慎(たあ)、と他の作品もそうです。昔は無意識でつけてたんですけど、途中からは意識的にそうしています。だから真田から名前を変える時もア行で行こうと思って神住とつけました。あと神住の人物的に、こいつ霞食ってるみたいなやつだな、と思って(笑)。
歌うように書く
森 それらキャラクターを魅力的に伝える「文章」ですが、本当に須賀さんは文章が美しいなあと思います。
第一章で好きな一文があるんですが、
頽れそうになるほどの悲憤を、少し羨ましく思う。
こんな文章、絶対に書ける気がしないなあ……と。
須賀さんが文章をどう紡いでいるのかすごく知りたいんですが、こうした一文はすっと降りてくるんですか?
須賀 もちろん降りてこないことも多いんですが、この辺りは悩まず書いてたと思います。
私も他の人の文章を読んでいて、よくこんな文が出てきたなと思うときはあります。でも、たぶんそういう文章って、あまり気負わず出てくることが多いように感じます。作り込んだ文章ってバレますし、そういう文章は読者にあまり響かない気がしますね。
森 ということは、意識して「うまく書こう」と作り込んだ文章はあまりないんですか?
須賀 ないですね。むしろ読み返して、そういう文章だと感じたところはゲラで全部削っています。
森 なるほど……。どちらかというと「頭で書く」というより「吐き出す」ような感じなんでしょうか。
須賀 そうですね。一番大事にしているのがリズム感なので、あまり頭でこねくりまわした文章だと話が流れていかない感じがしますね。だから歌ってるというか、しゃべっているように書いています。
歴史資料を物語に落とし込む難しさ
森 本作を書いていて大変だった箇所はありましたか?
須賀 新聞社のシーンですね。途中で写真資料が見つかって助かりましたけど、終戦当時の様子が全然イメージできなくて。どのくらい人がいるのか、どんなやりとりをしているのか分からなくて辛かったですね。
森 たしかに歴史小説だと、現代では分かりようがない「当時」を想像で描く難しさがありますね。
須賀 頭の中で映像を思い浮かべて書くわけで、光景がわからないのは致命的なんです。わからないところをぼかして書くこともあるんですが、やはり全景が見えないと何も書けないので。
自分の物語の作り方として、建物や小物に主人公の心情をリンクさせて物語を作っていくことが多いので、具体的なイメージがないと困るんですよ。
神住は、しみじみと会館を眺めた。黒い壁に黄金の窓枠。建築当時は革新的だったのであろう洒落た外観は、焼け野原の中ではずいぶんと浮いている。ニューヨークのラジエータービルを参考にしたと聞いているから、米軍がやって来た時にはお気に召すのだろうか。あるいは猿まねだと馬鹿にされるか。昨日まではなんとも思っていなかった外観が、妙に気に障る。
(建物の描写が心情とリンクしているシーン例 第一章より)
森 なるほど! 細部をいったん保留にして物語を進めるのではなく、その細部があることによって話が広がっていくんですね。
須賀 そうなんですよ。そうじゃないと白い壁の前でしゃべってるだけになってしまい、自分の中でリアリティが沸かないですね。
森 そのためには膨大な歴史資料を整理して咀嚼しないといけないわけですが、どう資料の山を整理されてるんですか?
須賀 メモをすごくとります。人物、事件、建物とかの小物でメモを分けていて、特に重要なのが小物メモですね。そこから主人公にふさわしいものを繋げていって……みたいに作り上げています。事件だけでは話は作れないので、写真も載っている「新聞」は資料として助かりますね。
自分の好きな一文
森 作中で須賀さんの好きな一文はありますか?
須賀 冒頭の一文が好きですね。神住という人物がよく現れてるなあと思います。
こらあかんなぁ。
ラジオから流れる声を聞いた神住匡は、真っ先にそう思った。
あと、1章で平古場と話すところは好きですね。神住は架空の人物ですが平古場は実在の人物なので(平古場昭二:戦後初の高校野球優勝投手となった実在の人物)、そこを合わせる時は気を遣うんですが、これはうまく次元の壁が合わさったように感じられて嬉しかったですね。
「今日も練習に来てみたら、神住さんの姿が見えたんで。こらもしかしたら大会復活か? って盛り上がって、俺が偵察に来たんですけど。そういうことや思てええんですか?」
平古場は目を輝かせて神住を見た。そう言われてみれば、部員たちもキャッチボールをしながらやたらちらちらとこちらを見ている。
「まあ、そうしたいのはやまやまやけどな。現実問題としてな、平古場君、投げられるか?」
(平古場と神住の会話シーン 第一章より)
森 歴史をセリフに落とし込むのは地の文より難しいのではないかなと思います。血の通ったセリフではなく、説明的になりかねないところがあるのではないかなと。
須賀 そこは私もまだまだ課題ですね。つい会話で説明させてしまおうというところが出てきてしてしまって、本当に難しいです。説明のための会話だと分かってしまうと読者が白けてしまいますからね。
「書かない」ということ
森 この『夏空白花』は2年前に刊行された作品ですが、2年ぶりに自分の文章を見直すと、いかがでしたか?
須賀 めちゃくちゃ辛かったです(笑)。文庫のゲラを読むと、無駄が多いなあと毎回思いますね。だから、書きすぎだと思う所をゲラでがんがん削っています。もしもう一回ゲラをチェックする機会があれば、また削るんでしょうね。

(文庫の初校ゲラ赤字例)
森 やはり最初は書きすぎてしまうものですか?
須賀 読者にちゃんと伝えられるか自信がなくて、最初は書きすぎてしまうんだと思います。でも最後まで書いてみるとわかることがいっぱいあるし、書かなくても伝わる部分も見えてきますね。
森 書くことよりも「書かないこと」のほうが難しいことだろうなあと思います。どう意識されてるんですか?
須賀 私は昔からクライマックスになればなるほど文章量が減るんです。でも、そうした書かないシーンを作るためには、そこまでの準備が必要ですね。情報量が少ない方が人間は想像がしやすいと思うんですが、それまでにちゃんと情報が提示されていないと、単に分からないシーンになってしまうので。
森 例えばラストの神宮の試合のシーン。安斎がふっと笑いますが、その説明や、その後のセリフなどはありません。作家さんによってはそこを描く人もいるかもしれないし、僕自身も安斎の会話などを読みたい気持ちもあるんですけど、描かれなかったからこそ、あそこのシーンは素晴らしいんだと思いました。
結局、ロングリリーフを務めた安斎を、米軍が捉えた。最後に起死回生のタイムリーを放ったのは、エヴァンスだった。四回の代打の場面ではフルカウントまで粘ったものの三振に倒れ、次は四球を選んだものの点に繋がらなかったが、最後の最後で〝ジョー〟を捉えた。
四回に登板してから一人で投げ続けた安斎は、打球がライト線に抜けた瞬間、ふっと笑った。
(余韻の詰まったシーン 第七章より)
須賀 あそこは文庫化の時に悩みました。実は少し追加しようかな、と悩んだんですよ。でも、何回も読んでやっぱりこのままがいいなと思い直しました。森さんのおっしゃるように、この後に安斎の会話を読みたい読者はいるだろうし、私も読みたいと思ったんです。でも、あそこの肝は最後のマーカットのセリフなので、そこまでの流れを邪魔してはいけないんです。もし会話などを追加してしまうとその流れが乱れてしまうので、加筆をやめました。
「今」この本を届けるということ
森 こうやって須賀さんが悩み抜いて書きあげてくださった『夏空白花』ですが、まさか文庫になるタイミングで、再び甲子園が途絶えてしまうとは思ってもみませんでしたね……。
須賀 今回ゲラを読み返して、単行本を書いたときと見え方がまったく違いました。あらためて甲子園というものの大きさや、それがどれだけの意義を果たしてきたか、また高野連創設の理念がどれだけ熱い物かというのを噛みしめましたね。
森 僕も編集者として文庫のゲラを読むと、単行本と違う印象を受けることはよくありますが、この本に関してはそうした次元ではない受け取り方の変化があったなあと思います。敗戦で希望がなくなった世界をどこか他人事として見ていましたが、それが一気に自分事になってしまったなあと。この本の持つ希望がすごく胸に沁みたので、ぜひ今こそ多くの人に読んで欲しいです。
須賀 人々の希望の象徴というのは、甲子園のみならず色んな所に存在すると思いますが、それらを守っていこうという気概はなくしちゃいけないな、ということをあらためてすごく感じました。そういう意味でも、ぜひ今、読んで欲しいですし、読むタイミングで受け取り方が違うのも本が持つ魅力だなあとしみじみ思いました。
森 本当にそうですね。本日はありがとうございました。
▼『夏空白花』詳細はこちら