
待合室にて
咳がとまらないので、とある内科のクリニックへ行った。
平日の午前中だが待合室はそれなりに混んでいる。空席を見つけて座り、ぼんやり順番を待っていると、外から白髪の老夫婦が入ってきた。
おふたりで何やら言葉を交わしながら、受付を済ませ、待合ベンチのほうへとやってくる。そのままでは揃って座れるところがなさそうだったので、わたしは一度立ち、「こちらにどうぞ」とお通しして別の席へ移動した。
自然と、わたしはその老夫婦の真後ろに座るかたちになった。
あまりじろじろと観察するのも失礼かしらとは思いつつ、それでも目の前におられるもので、どうしてもようすをぼんやりと目に入れてしまう。
ぱっと見た印象では、おふたりともかなりのご高齢のようだった。
80代、もしかしたら90歳前後くらいかもしれない。どちらも痩せていらして、ここがクリニックということもあるけれど、少なくとも元気はつらつといった印象ではなかった。ただ奥さまがご主人に対しても「〜らして」などの語尾を使われていたことや、ご主人の身なりもシャンとされていたことから、弱々しい中にもどこか気品のようなものが醸されていた。
ご主人は背が高くて背中が広く、一方で奥さまのほうはとても小柄だ。そのツーショットを後ろから眺めていると、わたしはつい勝手にタイムスリップして、若かりし頃のおふたりの姿を妄想してしまう。
バレーボールかバスケットボールか、はたまた陸上か体操か。スポーツマンでがっしりとした背の高い男性と、そんな彼に憧れる小柄な女学生。少女漫画の読みすぎかもしれないが、青空の校庭、さわさわと葉が揺れる木陰のベンチではにかみあう姿がぱぁっと脳裏に浮かび、目の前のおふたりの後ろ姿に重ね合わせてしまう。
ああ、こうしてずっと連れ添ってこられたのだろうか。色恋や倦怠期や小競り合いや、もしかしたら修羅場なんかもとうにくぐり抜けて、何十年という時をこうして連れ添ってこられたのだろうか。
白髪のおふたりを後ろからそっと見つめながら、わたしはなんだかしみじみとしてきてしまう。
*
ふとご主人が立ち上がり、慣れたようすで待合室においてあるウォーターサーバーの水を紙コップに入れ、奥さまに手渡した。何のことばもなく成立するその手渡しを見て、ふたりの間に積み重ねられてきた時間に思いを馳せ、ふたたび脳内で妄想旅行をはじめてしまうわたし。
ところがご主人が席へ戻ってほどなくして、奥さまのほうが突然「ああ今日は気分がわるい……」と言い出した。大丈夫だろうか、ほんとうにご気分がわるそうな声で、聞いているこちらが心配になってしまう。そのときスッ、とご主人の手がのびて、横に座る奥さまの肩をもみはじめた。ああ、素敵だなぁ。わたしは目の前で繰り広げられる光景から目が離せずにいる。
ここから先は
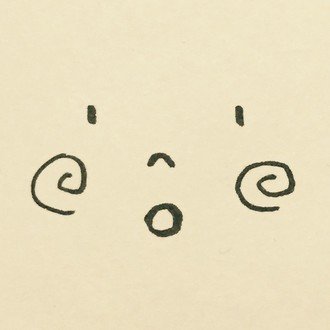
とるにたらない話をしよう
<※2020年7月末で廃刊予定です。月末までは更新継続中!>熱くも冷たくもない常温の日常エッセイを書いています。気持ちが疲れているときにも…
自作の本づくりなど、これからの創作活動の資金にさせていただきます。ありがとうございます。
