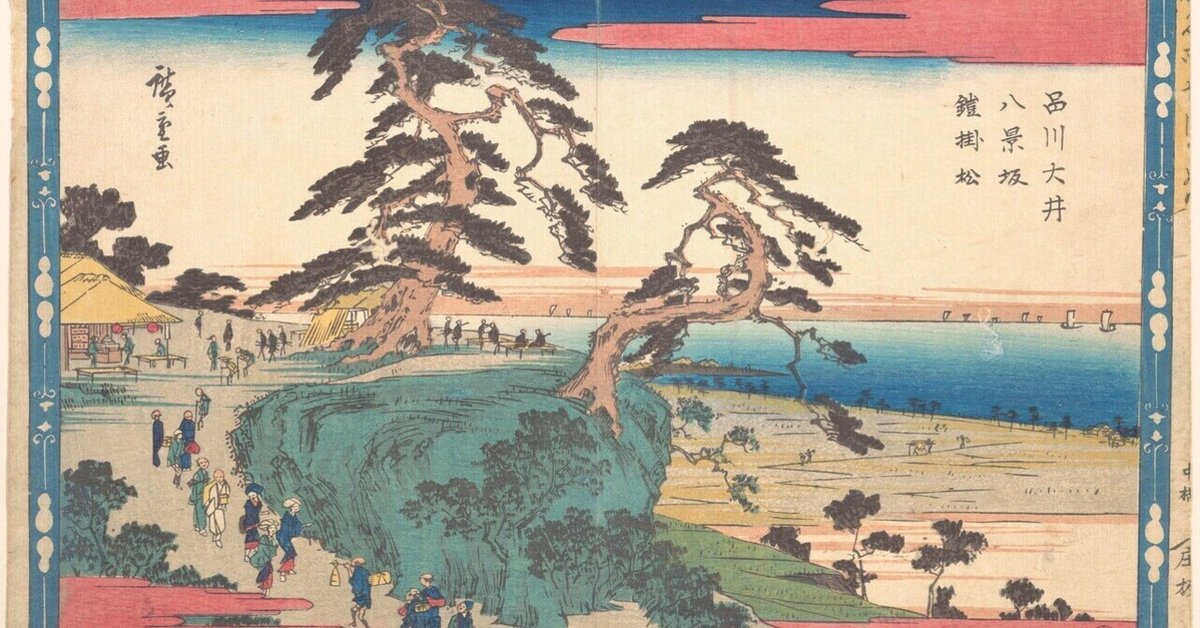
続・日本史の謎は「地形」で解ける!?
昨日に引き続き、
元建設官僚・竹村公太郎氏の著書から
興味深いネタを紹介したい。
全部で18章からなるこの本は、
どの章を見ても、非常に興味深い
内容が記されている。
昨日紹介した話は、第7章の
「なぜ江戸は世界最大の都市になれたか③」
というところに書かれていたものである。
実は日本列島にも森林荒廃が迫っていた
江戸時代、意外にもペリー来航によって
その森林の荒廃を免れたという事情に
ついて解き明かした内容であった。
次に紹介したいのが、第12章の
「「小型化」が日本人の得意技になった
のはなぜか」という内容である。
この章では、1982年に出された
『「縮み」思考の日本人』という
名著のエッセンスを紹介しつつ、
そこで解き明かされていなかった疑問に
取り組んだ結果たどり着いた著者の
「解答」を紹介してくれている。
この本は、『菊と刀』と並ぶ、
外国人の手になる日本文化論の傑作との
評価もあるようで、別途読んでみたい
ところだが、取り急ぎ竹村氏の簡潔な
要約に沿ってエッセンスを示そう。
団扇を扇子に、
洋傘を折り畳み傘に、
室内のステレオをウォークマンに、
大型コンピュータを電卓に、
大自然を日本庭園に、
大きな木を盆栽に、
テーブルの食事を幕の内弁当に、
ご飯をおにぎりに、
詩を短歌や俳句に、
という具合に、挙げ出したらキリがない。
この、何でも「縮める」(小型化、コンパクト化と言い換えても良い)ことこそが、日本人と中国・韓国人とを分ける特徴である。
著者の李御寧氏は、この特徴をあぶり出すことに成功したものの、なぜそのような特徴を持つに至ったかは「分からない」と正直に述べている。
竹村氏は、李氏が分からなかった
その原因を、長距離を自分で歩いて
移動しなければならないという
日本人の地理的・文化的な背景・宿命に
求めた。
中国にせよ、ヨーロッパにせよ、
大陸では人や荷物の移動に、
馬や車を使うのがあくまでも主流。
しかし、川が多く、海峡や湿地帯を
越えねばならないことも多くて、
更には急峻な山越えも多いという
日本列島の特徴から、荷物は人が
担ぐのが基本となった旨を指摘。
歩く上で、モノは出来るだけ小さく、
軽くしたいのが当然。
それ故に、モノを縮める、小さくする
ことがこの上ない価値となり、
それらの工夫は優れたものであれば
ある程、瞬く間に列島全体へと広まった
であろうと結論付けるのである。
細工して、細かくする。凝縮して小さく詰め込む。細工していないものは「不細工」と非難した。詰め込まないものは「詰まらない奴」と侮蔑した。
「不細工」
「詰まらない」
といった言葉の起源にまで及ぶ文明論は、
誠にお見事だと思う。
つい覚えた興奮を共有するべく紹介させて
もらった。
いいなと思ったら応援しよう!

