
研究者の登竜門、学振に関する知見を共有 採用編
今思えばよく通ったなぁ。借金地獄に落ちるところだった。
まぁ側から見れば、借金地獄の方が面白かったのかもしれないけど。
はじめに
こんにちわ。ぴくむんです。
私は、
小さい頃から実生活で役に立たない学問ばかり教えられる。
「現代社会でダイレクトに役に立つ学問がない」
研究は、勉強の醍醐味であるのに大多数の人がやっていない。
「大多数の人は研究をする機会がない」
ことに対して疑問を覚えていました。そこで、
国なんてあてにせずに
自分の力で「実生活に直接役に立つ学問の確立」することや、
大学に行かなくても「誰でも研究できる環境の整備」する活動を始めようと思いました。
この記事では、研究者を目指す方に情報発信しています。
研究者の登竜門である学振についてのお話です。
誰かのお役に立てたら幸いです。
本文
特別研究員(DC2)の任期が終わったので、忘れないうちに色々知見を共有したいと思う。採用編と採用後編に分けて知見を共有したいと思う。
学振って何?
M2, D1, D2が応募できるやつ。当たると2 or 3年間、毎月20万の生活費と毎年研究費80万がもらえる。
つまり、合わせると
DC1は 720万+240万= 960万
DC2は 480万+160万= 640万
がかかった採用枠。
採用率は30%程度。
奨学金という借金地獄の大学院生にとっては、
当たれば借金地獄からの解放と自己肯定感、落ちれば借金地獄と敗北感。
ある意味、研究者人生として最初の関門。

こんなポスター作るぐらいなら、少しでも採用枠広げてくれや。
っと暴言が吐きたくなるぐらい当事者は追い詰められます。
https://www.jsps.go.jp/j-pd/
採用編
自分の話
まずは、自分の話からさせて欲しい。
私は、D1のときに数物系科学の区分でDC2に採用された。
学振で切っても切れないのが業績の話だと思うので、
まず業績の話から
業績
不採用だったM2のDC1の業績は、
査読なしのアブストラクト1本
国際会議ポスター2回
国内会議ポスター2回
で、もちろんスカスカの業績だった。
結果は、不採用の区分Cだった。

今思えば、よくこんな成績で、自信満々に博士課程突っ込めたのかと思う。
多分、馬鹿だったのでしょう。いや今もその馬鹿さ加減は変わってないから、今こうやってnote書いているんでしょうね。
採用の時の業績は
論文は、主著の国際雑誌2本、共著1本、査読なしのアブストラクト1本
国際会議ポスター5回、国内会議口頭2回、ポスター2回
大学の専攻賞
であった。まぁボチボチ埋まってたと思う。
論文の査読が間に合ったのはデカかった。
in pressで書いた。
かかった日数
採用された原稿の叩き台ができたのが、4月17日であった。
そこから例の如く、担当教員との攻防戦が始まり、約11回のアップデートを経て、原稿が完成したのが、5月13日あたり。
内容
修士で論文化した内容を現在までの研究状況に書いて、
D論でやる内容をこれからの研究計画として書いた。
採用通知書
なんの証拠にもならないが、一応上げておく。

自分の話としては、ざっとこんなもんだろう。
採用について
基本的に、採用は
・採用は実績ゲー
・採用は先輩の遺産ゲー
・採用は教授ゲー
であると私は思っている。
では、一つ一つ語っていきたい。
・採用は実績ゲー
まぁお察しの通りだと思う。
どっかの小耳で聞いた話だと、「審査するときはまず、業績から読む」と聞いたことがある。業績を読んでバイアスかけて、書面読んで決めるらしい。
これは、憶測だが、
論文2本だと内容に不備がなければOK
論文1本だと内容が理解できればOK、内容が理解できなければNG
論文0本だと、基本NG、内容が超素晴らしければOK
というのが審査員の考えていることだと思う。
あくまでも憶測。
ちなみに、自分の業界では毎年DC2は1人出れば、御の字だったが、自分の代からは2人でた。そして、2人とも論文は2本あった。
そんなこともあって、自分は後輩には
2本あれば多分大丈夫だよ
1本はちょっと内容次第かなぁ、全力で申請書頑張れ!
0本はあまりリソース割くのはおすすめしないかも知らん。とは言ってもお金絡むからそれは無理だよなぁ。まぁ、無理しない程度に頑張り。
という話をよくしていた気がする。
・採用は先輩の遺産ゲー
よほどの天才ではない限り、研究室に入って完全に0からDCまでに論文を2本出すのは無理ゲーもいいところである。
先輩の遺産という豊かな土壌にしか論文という花は咲かない。
これを読んでいる人は既に遅い人が大多数だろうが、基本的にはテーマが面白くなさそうでも、先輩の遺産が多いテーマを選ぼう。
ちょっと大事なことを言うと、一部の人たちを除き、大多数の研究者の未来は業績で決まる。
もっと平たく言うと、インパクトファクターの大きい論文に投稿した数で決まる。
どんなに人柄が悪くても、どんなに研究のスキルがひどくても、全て論文で決まる。
そして、その論文は、学士修士時代も含んでいる。
そして、大多数の研究者は博士号取得後、ポストの先では全く別のことをやることがほとんどである。よほどの大天才ではない限り、研究者として生き残りたければ、大学院は面白いとか面白くないとかはどうでもよく、論文の数が最大化するムーブをするべきで、その最大化のために、いかに先輩の遺産を食い潰すかを考えるべきである。
私は、所属した研究室に、論文のタネは5本程度置いてきた。
もう原稿そのものができているモノもある。英文すこし訂正するだけで、余裕で通ると思う。と言うように、遺産はあるところにはある。
それが有効活用されるかは、担当教員の研究統制力と学生のセンスにかかっている。なので、まずは研究室でのテーマ選びは最も遺産が残っているテーマを選択しよう。
・採用は教授ゲー
とは言うものも、やはりボスの言うことは絶対である。
基本的にボスの雰囲気に全てが左右され、修士博士号は教授の一存で全てが決まる。
どんなにひどい博士でも、教授が出すといったら出すし、逆に言えばどんなにスキルのある博士でも出さない言えば、博士号が出ないのがアカデミックの世界である。(学生の経済状況と未来なんて知っちゃこっちゃない)
それは、学振かて例外ではない。
もし教授が非協力的であれば研究も進まないし、論文も出るわけない。
一学生に教授を共著から外し単著で書くなんて真似はまずできるわけない。
面白くもなんともない話だが、学振は運ゲーである。
どんなにイキっている採用者であっても、所詮運ゲーを制しただけの人間である。
採用された私が言うので、間違いない。
まぁそこら辺は、
サンデル教授が指摘している通りだと私も思う。
成果がでるような努力できるのは、そのような環境に与えられた幸運の持ち主だけである。
あとがき
学振なんて、運ゲーだから採用されてもされなくても気にすることはありません。
別に採用されなくても研究者になった人はいっぱいいるし、私みたいに採用されたけど研究者になれなかった人も山ほどいるからそこら辺は安心していいと思います。
しかしながら、お金の面で天国と地獄の差は否定できません。
自分はそこら辺をちゃんと支援したいと思っていて、自分のHAKUSHIの口コミサイトを完成させて、口コミサイト兼就活サイトにして、最終的には借金まみれの精神状況ズタボロの博士課程のセーフティーネットになるような環境を作れたらいいなぁっと考えています。
何か学振で困っていたら、Twitterで声かけてください。
地獄を見た者として話を聞いて、共感することぐらいはできるはずです(笑)
なんか、序盤の学振の説明書いてると、
学振ってカイジみたいな地獄のギャンブルみたいに見えてきました。
勤勉に勉強した行き着く先がこんな地獄のギャンブルとは、
なんか感慨深い気持ちになってくる。
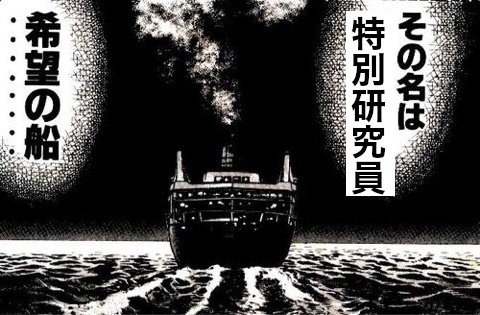

採用されれば平均所得、不採用であれば圧倒的時間の無駄。正気の沙汰とは思えない。
しかし、圧倒的自己責任……!!これが、アカデミックの世界……!!!
すいません、楽しくなってクソコラ作ってしまいました。
特に深い意味はないので気にしないでください。
これから学振を出す人は頑張ってください。心の底から応援してます。
では、次回の学振採用後編で会いましょう!
協力者募集中! 一緒に何かしてみませんか
絵が書ける人(グラレコ)
自分は本当に絵が書けないので、自分の書いた記事の内容をグラレコ(一枚の画像に絵付きまとめたもの)にしたいのですが、諦めているという状況であります。
見ての通り全く収益化とは、遠い活動をしているので、自分の記事でお名前を紹介することぐらいしかできませんが、もし絵が書くのが好きな人で、自分の記事に共感してくれて、1回ぐらいならお絵かきしてもいいよっと言ってくれる神みたいな人がいるのであれば、下記のTwitterで連絡してくれると嬉しいです。
グラレコは
を見てわかるとおり、仕事になるので是非自分を踏み台にして仕事につなげてほしいと思っております。
このような感じでコラボが進むので参考していただけたら、嬉しいです。
プログラミングに興味ある人
自分が研究者を目指していたときに、もっと先輩の情報が欲しいという思いをきっかけに、「博士の口コミ」サイトを開発しています。
現在アルファバージョンを公開中です。
hakushi.bizは
フロントエンド言語は、HTML, CSS, javascript
バックエンド は、django(python)
サーバーサイドは、docker-compose, gunicorn, Nginx,AWS EC2
リモートレポジトリは、 git-hub
で開発されています。
プログラミング初心者でも、開発に参加できるように環境を整えたので、ちょっとでも上記の技術を使ったwebサービスに興味ある人は下記のTwitterに連絡してください。
git-hubのプライベートレポジトリに招待します。
その後、DMで話し合ってどういうことをするか考えましょう!
技術のある方は、是非手伝ってください。
初めはボランティアベースになりますが、収益化ができたら報酬はお支払いします。
ここまで読んでくださった方へ
自己紹介
自分に興味があれば自己紹介noteがあるので読んでくれると嬉しいです。
おすすめ記事
日本人なら誰でも適用できるような大切なことに気がついた記事です。
実学 ビジネス編
になります!
もし興味があれば読んでみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
