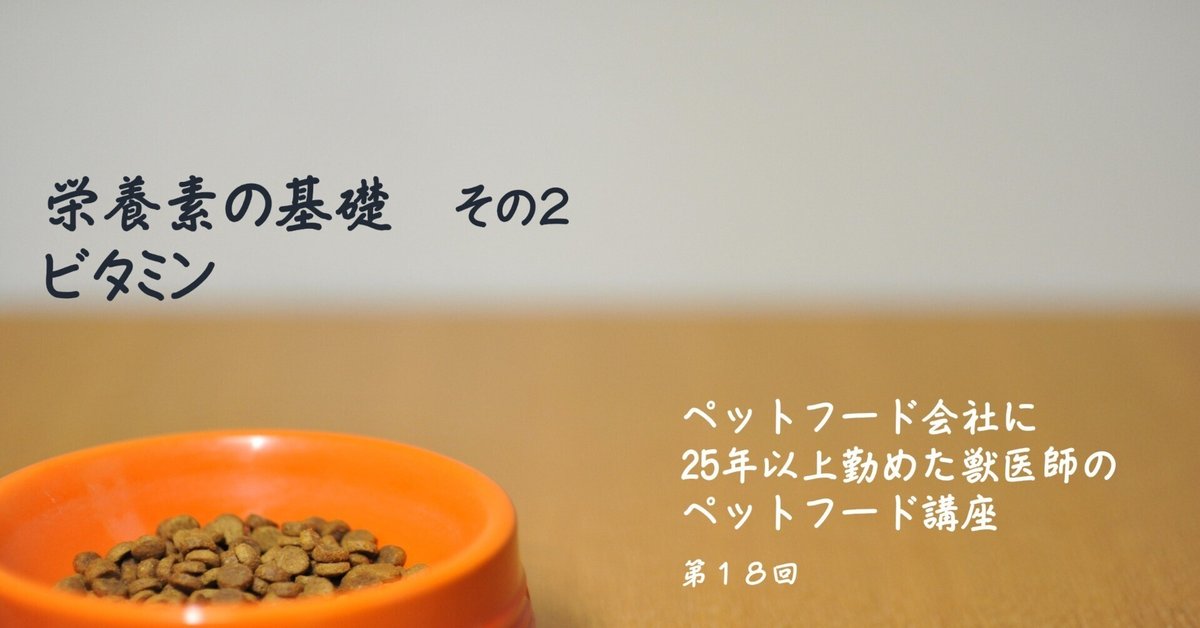
栄養素の基礎 その2 ビタミン
はじめに
前回に引き続き栄養素についての基礎的なところを解説していきます。
前回のまとめは・・・
栄養素とは「生きるために食べたり飲んだりしなければいけない物質」
栄養素は
タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの5大栄養素+水栄養素の働きは
① エネルギー源になる
② からだのパーツをつくる材料になる
③ いろいろな機能を調節して、からだの中を一定の状態にたもつタンパク質、脂肪、炭水化物の働き
(前回の記事はこちら)
さて、今回はビタミンについて解説します。
ビタミンがフードに含まれる量は3大栄養素と比べると微量です。
ですが、どれもネコやイヌが生きるために必要不可欠な栄養素です。ですからビタミンが不足すると当然ですが欠乏症がおきます。
では、ビタミンをとにかくたくさん取ればいいかというと、いくつかのビタミンは取り過ぎると過剰症がおきてしまいます。
つまりビタミンは微量ながら必要不可欠であり、同時に適切な量を取らなければいけないため、摂取量の調節が難しい栄養素です。
ねこさん・わんちゃんにおやつやサプリメントをあげるときには、ビタミンの取り過ぎにならないように注意してあげてください。
とくに手作りフードに興味のある飼い主さんは、ビタミンの働きや多く含む食品、欠乏症・過剰症などをきちんと理解する必要があります。
おもなビタミンの働き・多く含む食品・欠乏症・過剰症を下の表にまとめておきましたので、ひとまず、この表をご覧ください。
(文字が小さくて申し訳ありません。)
なお、多く含む食品はビタミンの特徴をイメージしやすいように一般的な食品をあげたもので、これらをねこさん・わんちゃんに食べさせてあげましょう、ということではありません。
手作りフードを作る場合、ビタミンやミネラルはサプリメントを使って量を調節します。
そのあとにビタミンについてもう少し詳しく解説していますので、いささか文字数が多いのですが、できれば最後までお読みください。

ビタミン
「ビタミン」もなじみのある言葉ですよね。
栄養と聞くと、ビタミンを真っ先に思い浮かべる人もいるかもしれません。
ところで、ビタミンとは何でしょう?
まず、その定義を見てみましょう。
ビタミンとは、「微量ではあるものの、体の機能を正常に保つため必要な有機化合物」と定義されています。
つまり、ビタミンは「栄養素の働き③」のための栄養素です。
「有機化合物」というのは、「炭素を含む物質」だと思ってください。
ただし、一酸化炭素(CO)や二酸化炭素(CO2)などの単純な構造のものは、一般的には有機化合物には分類されません。
「有機化合物」の反対語は「無機化合物」といいます。
ほとんどのビタミンは必要な量を体の中では合成することができないため、食べ物から取らなければなりません。
ビタミンは全部で13種類ありますが、水に溶けるかどうかで「水溶性ビタミン」と「脂溶性ビタミン」に分類されます。
水溶性ビタミンにはビタミンB群、ビタミンCがあり、脂溶性ビタミンにはビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKがあります。

またビタミンは「ある働きをもつ物質」に対する名前で、「ビタミンなんとか」とは別に物質名がつけられています。
たとえば「ビタミンC」の物質名は「アスコルビン酸」です。
さらに脂溶性ビタミンは、同じ働きをもつ、よく似た構造の物質をまとめて「ビタミンなんとか」と呼んでいます。
ビタミンのほとんどは、物質が発見されてからその物質の働きがわかったわけではなく、「こういう働きをする物質があるはずで、それを『ビタミンなんとか』と名付けよう!」というのが先にあったんです。
ところがよく調べてみたら『ビタミンなんとか』がじつはビタミンではなかったとか、ビタミンだと思ってなかったものがビタミンだったとかいうことが結構おきました。
名前の並び順がきれいでなかったり(水溶性ビタミンがB→Cで、脂溶性ビタミンがA→D→E→K)、途中が抜けていたりするのはそのせいです。
ここから先は

ペットフード会社に25年以上勤めた獣医師のペットフード講座
2頭のねこさんと暮らす、ペットフード会社に25年以上勤めた獣医師が、ねこさん、わんちゃんの健康と栄養学、ペットフードの本当の中身について、…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
