
【投資ノウハウ】会社分割のメリット・デメリットと株価への影響
最近、大企業の会社分割のニュースを目にすることが多いのではないでしょうか。特に11月は、米国では、ゼネラル・エレクトリック(GE)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、日本でも東芝(6502)が、会社分割の計画を発表しました。今回は、会社分割についてみていきましょう。
会社分割とは

まず、簡単に会社分割とは何か見ていきましょう。会社分割とは、複数の事業を持つ会社が、その中の事業の一部、もしくは全部を他の会社に承継させることです。
会社分割には、大きく分けて2つの種類があります。
一つ目が「吸収分割」と呼ばれるもので、設立されている会社に事業を承継させるものです。これは、持ち株会社制に移行する際などに使われる方法です。そして、もう一つが新しい会社を設立し会社分割を行う「新設分割」です。ゼネラル・エレクトリック、ジョンソン・エンド・ジョンソン、そして、東芝でもこの手法が用いられています。
社内の事業を分離独立させるスピンオフ

ゼネラル・エレクトリックを例にすると、現在、同社は航空機エンジン事業、医療機器事業、デジタル事業、発電・送電設備、再生可能エネルギーなどの事業を行っています。まず、2023年初頭に医療機器事業を分離独立させ、次いでデジタル事業、発電・送電設備事業、再生可能エネルギー事業を一つにし、電力事業会社として分離独立、そして航空機エンジン事業が本体のゼネラル・エレクトリックとして残ります。
このように、会社の中の各部門を分離独立させる方法を「スピンオフ」といい、海外では一般的なM&Aの手法です。過去にも、製薬会社のアボット・ラボラトリーズから新薬の研究・開発・販売を行うバイオ製薬会社としてスピンオフしたアッヴィ(ABBV)や、イーベイからスピンオフしたぺイパル(PYPL)など数多くの例があります。
会社分割のメリット・デメリット

メリット1 中心となる事業が明確になる
会社分割を行うメリットは、事業ごとに、その実情にあった経営に専念できることです。また、関連性の薄い複数の事業を持つが故に投資に二の足を踏んでいた投資家を引き付けることも可能になります。
たとえば、東芝は、原子力を含む発電事業、公共インフラ事業、ITソリューション事業などの「インフラサービス事業」と、ハードディスクや半導体などの「デバイス事業」を展開する会社を新たに設立します。この二つの事業ですが、一般的にインフラサービス関連事業は、公共事業や大型案件が多いので、景気減速期や景気後退期に強いと言われる事業です。その一方、半導体などのデバイス事業は、景気動向の影響を受けやすい事業です。もし投資家が、今後、景気が拡大し、半導体需要が大幅に増加するとの思惑から、東芝株を購入しようとしても、社内に原子力を含む発電事業があると、そのために株式購入を踏み止まってしまうかもしれません。しかし、会社分割することにより、その事業に関心がある投資家を呼び込むことが可能になることが予想されます。
メリット2 コングロマリット・ディスカウントを取り除ける
また、性格の異なる複数の事業を持つ企業では、その企業が何を主とした事業を行っているのか、見えにくくなりがちです。さらに、各事業に適切な経営判断ができていないケースも散見され、企業価値が事業ごとの価値合計に比べ、過小評価されることがあります。これを、コングロマリット・ディスカウントと言います。会社分割は、このような大きいが故の弊害を取り除く効果があります。
会社分割のデメリット
一方、会社分割のデメリットですが、会社を分割するので、当然、会社は小さくなり、経営基盤の安定性は低くなります。また、先ほどの東芝の例で言えば、景気減速・後退期に強い事業を持っていることで、企業としての安定性が担保されていたと考えることもできます。会社分割は、専業性を高めることにつながるので、リターンが大きくなる一方、リスクも大きくなります。
今後の会社分割の行方

株価の上昇が経営の命題と捉える向きも多く、株価上昇につながりやすい会社分割は、今後も増えていくでしょう。また、脱炭素化やDX化といった流れが加速する中、これらの関連事業に経営と資本の集中、そして上場を見据えて、会社分割を行う企業も多くなるでしょう。
なお、会社分割を行う企業の特徴としては、高い優位性がある事業を持つ企業、経営不振に陥っている企業、物言う株主(アクティビスト)を取締役に迎えている企業、そして、大型の訴訟を抱えている企業などが挙げられます。いま、いずれかの理由で株価が低空飛行をしている企業の中に、分割により光があたる企業があるかもしれません。年始年末の大型連休にそういった企業を調べてみるのも面白そうです。
記事作成:2021年12月15日
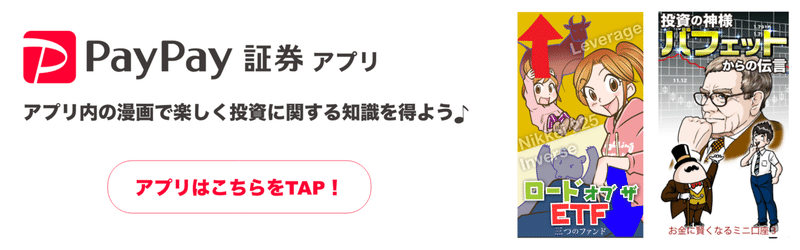


佐藤隆司(ライタープロフィール)

佐藤 隆司(さとう りゅうじ)
米大卒業後、金融・投資全般の情報ベンダー、株式会社ゼネックス(のちの株式会社オーバルネクスト)入社。原油、貴金属、天然ゴムなど工業品を中心としたアナリスト活動を経て、金融市場全般の分析を担当。
2010年、エイチスクエア株式会社を設立し、セミナー講師、アナリストリポートを執筆する。また、「FOREX NOTE 為替手帳」、「チャートの鬼・改」などの企画・出版も行う傍ら、ラジオ日経「ザ・マネー」の月曜キャスターも務める。
資格
「国際テクニカルアナリスト連盟 認定テクニカルアナリスト」
メディア情報
・ザ・マネー 月曜日キャスター
・「夜トレ」(ラジオ日経)、「昼エキスプレス」(日経CNBC)など出演
本資料のご利用にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を、本資料の最終ページに記載いたしました。ご確認のほど、お願い致します。
《ライターによる宣言》
私、佐藤隆司は本調査資料に表明された見解が、対象企業と証券に対する私個人の見解を正確に反映していることをここに表明します。
また、私は本調査資料で特定の見解を表明することに対する直接的または間接的な報酬は、過去、現在共に得ておらず、将来においても得ないことを証明します。
《利益相反に関する開示事項》
●エイチスクエア株式会社は、PayPay証券株式会社との契約に基づき、PayPay証券株式会社への資料提供を一定期間、継続的に行うことに対し包括的な対価をPayPay証券株式会社から得ておりますが、本資料に対して個別に対価を得ているものではありません。
また、銘柄選定もエイチスクエア株式会社独自の判断で行っており、PayPay証券株式会社を含む第三者からの銘柄の指定は一切受けておりません。
●執筆担当者、エイチスクエア株式会社と本資料の対象企業との間には、重大な利益相反の関係はありません。
金融商品取引法に基づく表示事項
●本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等
商号等:PayPay証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2883号
加入協会:日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
●リスク・手数料相当額等について
証券取引は、株価(価格)の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがあります。
お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、「リスク・手数料相当額等(https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html)」について内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。
免責事項等
●本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。
●本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。
●本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、PayPay証券株式会社及びエイチスクエア株式会社は一切の責任を負いません。
●電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複製、転載、転送等は行わないでください。
PayPay証券株式会社
https://www.paypay-sec.co.jp/
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2883号
