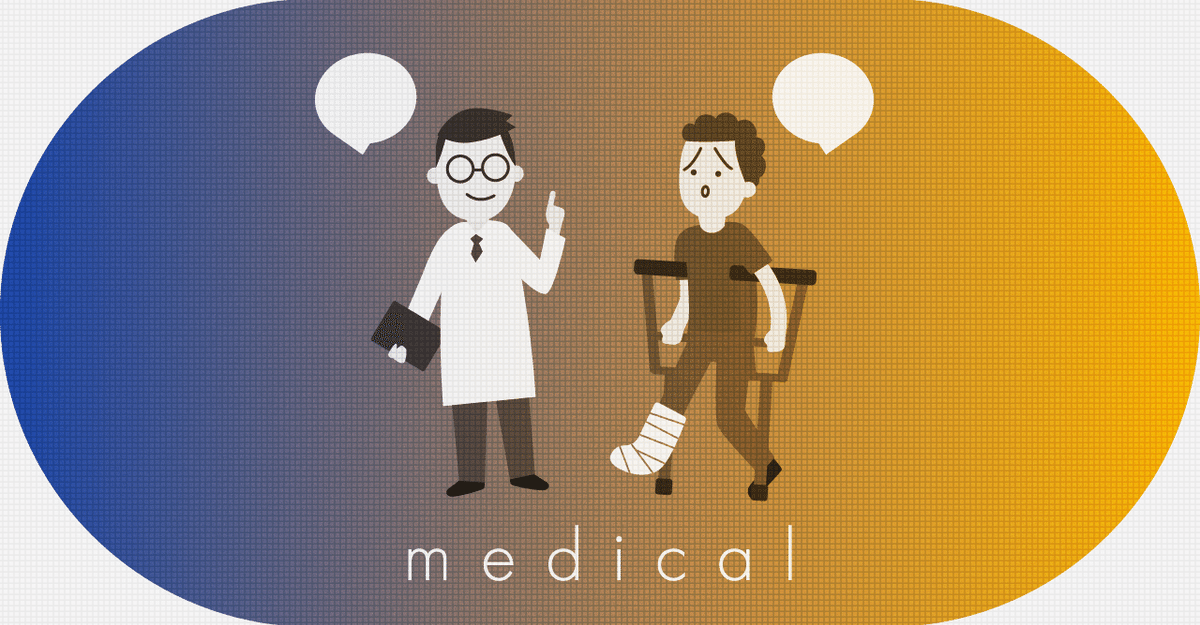
ケガ予防のトレーニングについて
こんにちは。
久喜市鷲宮のスモールジム&整体「身体改善サロン ペインフリー」店長の高橋です。
気温を下がり乾燥してきたこともあり、例の感染症が少しずつ再流行し始めていますね。。
世の中の流れには注視しながら、やるべきことに集中していきたいところです。
さて、そんな今日のテーマは「ケガ予防のトレーニングについて」です。
昨日は「関節と軟骨」について記しました。
その中で「ひざ関節の軟骨に関する痛み」の主な原因として以下の2つを挙げました。
①約4mmあると言われているひざの硝子軟骨が摩耗して、骨との距離が近くなることで起こるパターン
②ひざ関節の靱帯が正しく機能せずに関節に隙間ができることで硝子軟骨が割れたりかけたりすることで起こるパターン
①と②はセットで起こり、②になってしまう原因はひざの靱帯損傷後に適切なケアをしなかったため、靱帯として正しく機能しなくなってしまうことが多い、そして、すでに痛みが出てしまっている場合でも「これ以上悪くしない」「再発を予防する」ことは可能というところまで記したかと思います。
今日はその続きです。
靱帯はイメージ的には「ガムテープ」と同じだと言われています。
骨と骨をガムテープで止めているイメージですので、それが切れてしまうと骨と骨はぐらぐらになってしまいます。
靱帯損傷後に適切なケアをしていない状態はいわゆる靱帯が緩くなってしまっている(破れたままでかたまってしまい本来の長さより長くなっている)状態ということです。
この状態を「これ以上悪くしない」ためには以下の方法が有効と言われています。
①筋力でカバーする
②神経系のトレーニングでカバーする
①に関しては、靱帯の機能低下によってズレやすい方向が決まってくるため、それとは反対の方向に引っ張る筋肉を鍛えるというやり方です。
②はいわゆる脊髄反射を起こすトレーニングを①の筋肉に行うことでズレそうになった時にすぐに反応できるようにしておくということですね。
この二つを行うことで「これ以上悪くしない」+「再発予防」ができるということです。
これを行うためには「解剖学」ではなく「機能解剖学」を理解しておく必要があります。
「ここの筋肉は○○筋です」ではなく「この動きをするの使われる筋肉は○○筋と○○筋と○○筋でこれくらいの割合で使われる」という理解です。
当然、起始と停止の理解も必要ですが、どう動くのか、どれくらいの割合でその動きに関与するのか、そこを理解することで初めて「この動きのカバーをするために○○筋を鍛えよう」につながるということですね。
「基本の”き”は機能解剖学」
頭に入れておきたいですね。
