
ことばは生命体。
村上春樹はかつて作品『街と、その不確かな壁』でことばに命をあてた。
「語るべきものはあまりに多く、語りえるものはあまりに少ない。おまけにことばは死ぬ。」
「お客さん、電車が来ましたよ」。氏は、電車が入線した直後に言葉が死んでいくのをその目で見ていた。
ことばに、生きたことばがあるんじゃない。私たちはもともと生きていることばでつながりあっている。つながっていかないのは、終わってしまったことばに甘んじているからだ。
死んでしまったことばは、引用しやすい。足元のそこここに身動きせず、息もせず、横たわっているだけなのだから。
死んでしまったことばは、一見、拾いやすいように見える。だが、意図的にそいつをとらえ、行動力学が腰を屈ませ、指先で拾い上げる意思が働いて初めてそいつを手にできる。使いこなすのにも難儀を強いる。
死んでしまったことばでさえかくも操るのに手強いものなのに、どうやって生きたことばを捕まえ、操ればいいというのだろう。
氏は文芸誌に該当作品を寄稿後、インタビューで、アレは失敗作と語ったという。
生きたことばを操る者でさえ、ことばを生かしきることはできない。生きたことばを操るというのは、至難の業なのだろうか?
多くの人がいいという本を読むと、、、。
閉じ込められてしまった時間や人やモノやできごとか、ある瞬間から息をし始める。
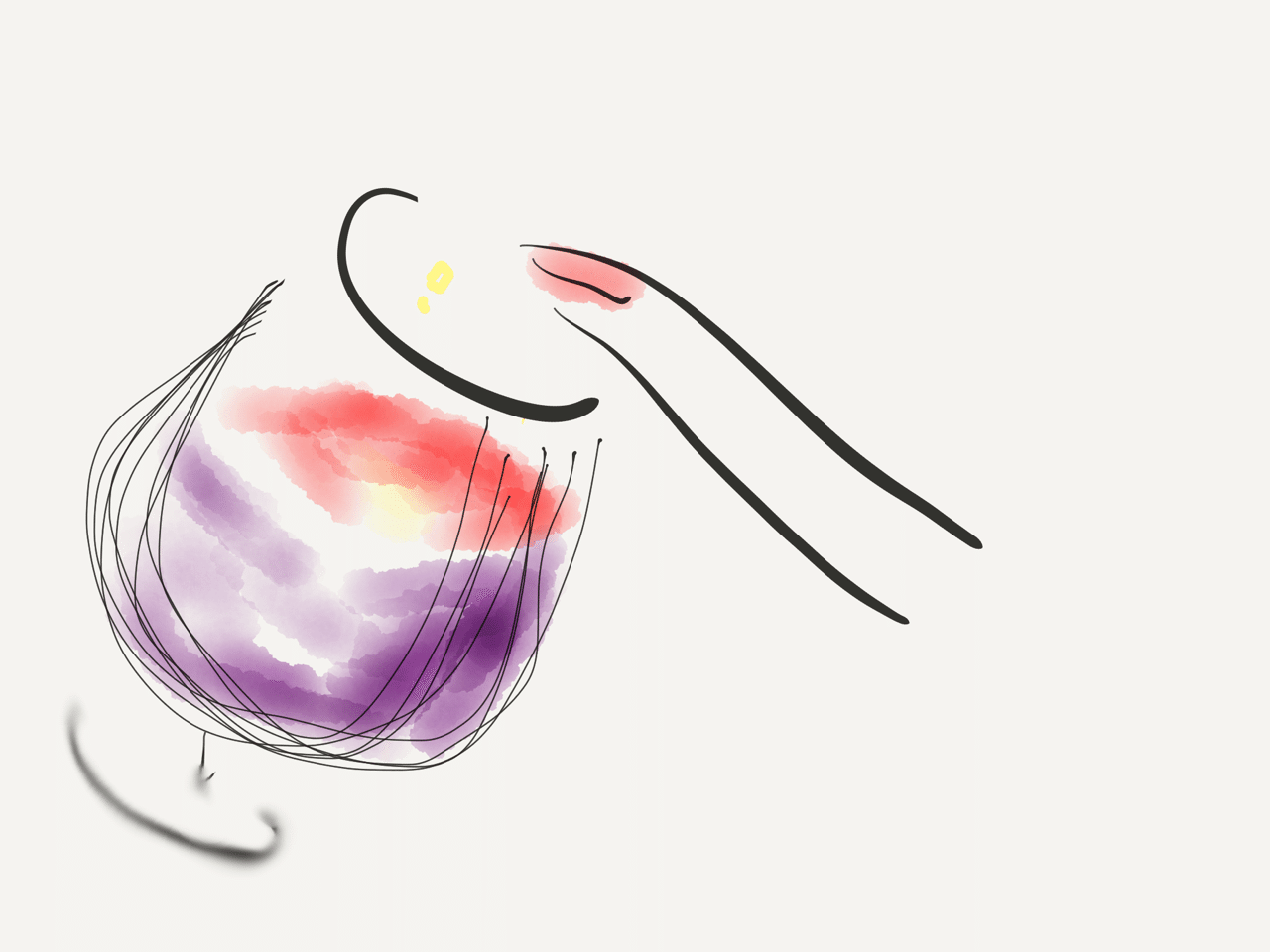
過去に書いた自分の作品を読み返すと、、、。そこには死体が無造作に色もなく淡々と並べられているだけだ。
残ることばは死なない。
では、命のあることばとはなんなのか?
探求の旅は続く。
