
刑務所しか居場所のない障害者たち Part Ⅱ (司法は守ってくれない)
(2020.11.25 投稿)
どうも、おっさーです。
前回、「刑務所しか居場所のない障害者たち」というテーマで、身寄りのない知的障害者が、社会のセーフティーネットから漏れ、刑務所にしか居場所がなくなってしまう問題について記事にしました。
今回は、そのような身寄りのない知的障害者たちを「司法は守ってくれないのか」ということをテーマとしてお伝えしたいと思います。
この記事はこちらの本を参考としています。
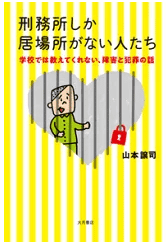
この本の著者はこのような方です。
山本譲二(やまもと じょうじ)
1962年生まれ、元衆議院議員。2000年に秘書給与詐取事件を起こし、一審での実刑判決を受け服役。獄中体験を描いた『獄窓記』が新潮ドキュメント賞を受賞。障害者福祉施設で働くかたわら、『続・獄窓記』、『累犯障害者』などを著し、罪に問われた障害者の問題を社会に提起。NPO法人ライフサポートネットワークや更生保護法人同歩会を設立し、現在も高齢受刑者や障害のある受刑者の社会復帰支援に取り組む。PFI刑務所での運営アドバイザーも務める。
その調書ありえないでしょ!
「被告人は前へ。本名と生年月日は?」
これは、裁判で罪に問われた被告人が最初に聞かれる「人定質問」です。
重い知的障害のある被告人は、この認定質問に答えられないことがあります。
ワーワーと騒いだり、関係のないことを延々としゃべったり、裁判官に向かって「その黒いマント、かっこいいね!」とうれしそうに言う人もいます。
残念なことに、裁判官の知的障害に関する理解は決してじゅうぶんとはいえません。
真顔で、
「その障害って、薬で治らないの?」
「いつから知的障害者になったの?」
などと、とんでもない質問をしてくる裁判官もいるほどです。
仮に供述調書の内容が事実と違っていても、気づいてくれる裁判官は少ないです。
供述書には、もっともらしいストーリーが書かれています。
たとえば、「私は店員に怒りを覚え、強固な犯意を持って、コンビニエンスストアで弁当1点を盗む計画を企てた」などです。
しかし、被告人に知的障害があることをふまえると、「ほんとうにこの人が自分で言った言葉なのだろうか?」と不自然に感じるほど、話の筋道が通りすぎた供述調書がよくあります。
知的障害のある人は、自分の気持ちを言葉で表現するのが苦手で、他人の意見に同調しやすい特性があります。
実際には、おなかをすかせて弁当を万引きし、店員を振り切ったときにからだが当たってケガをさせたのだとしても、警察官や検察に「最初から暴力をふるって盗む計画だったんだろう!」と凄まれると、おびえて「はい、そうです」と答えてしまうこともあるでしょう。
それが供述調書に書かれると、強盗傷害罪に問われるかもしれません。
単に物を盗んだ窃盗罪よりも、はるかに重い刑罰となってしまうのです。
知的障害者の犯罪は、罪名と実際にしたことのギャップが大きい傾向があります。
車にあった30円を盗んだ「窃盗罪」や、知り合いとケンカして、つい手に持った刃物が相手の首にちょっとふれて「殺人未遂」など、罪名を聞いて想像するより被害が小さいことが多いのです。
これは、日本の司法精度が被告人の知的障害に配慮するしくみがないことが関係していると考えられます。
アメリカでは、IQ50以下の被告人には「アンフィット」といって、ふつうの裁判が受けられる状態ではない人と判断されます。
知的障害についてよく理解した裁判官、検察官、弁護士のもと、裁判を受けることになります。
イギリスやオーストラリアでも、同じような制度があります。
日本には、国としてのこのような制度はありません。
他の先進国と比べて、日本の司法制度は遅れているといわざるおえないのが現状なのです。
「責任能力」ってなんですか
著者はかつて、重い知的障害のある人は、刑務所で服役することはないだろうと思っていました。
「責任能力なし」ということで、罪に問われないだろうと。
ところが実際には、刑務所の中には、自分がどこにいるかもわからないほど重い知的障害の人がおおぜいしました。
刑務官すらも「いったい、どんな裁判を経てここへ来たのか?」と首をひねるほどです。
2016年には、裁判にかけられてから心神喪失が認められ、無罪になった被告人は5人でした。
逮捕されたが、心神喪失や心神耗弱のために不起訴になった人は507人。
同じ年に、不起訴になった人は全部で16万人いますが、そのうちの0.3%でしかありません。
ちょっと信じられないですよね。。。
では、どうしてこんなことが起こるのでしょうか?
その理由のひとつは、心神喪失や、心神耗弱かどうかを判定する「精神鑑定」に問題がひそんでいるからです。
精神鑑定には、お手軽な「簡易鑑定」と、何か月もかけて、しっかり鑑定する「本鑑定」がありあす。
どちらも検察官に依頼された医師がおこなうことがほとんどです。
軽い罪でも、犯罪をくりかえす累犯者だったり、明らかに知的障害や精神障害のある被告人だったりすれば、起訴される前に簡易鑑定を受けることがあります。
しかしこれは、検察庁のおかかえ鑑定医が1~2時間くらいの問診をして、ざっと資料を読むだけ。
往々にして、「責任能力あり」を前提として鑑定をされます。
知的障害者によくある、カップ酒を1本盗んだような軽い罪は、弁護士も「本鑑定をすべき」などと主張することまでしません。
こうして、重い知的障害者でも「責任能力がある人」として裁判を受けることとなるのです。
今の司法制度で、知的障害のある人を裁くのは、仕組的に無理があるのです。
弁護士も仕事を選ぶ
検察官や裁判官が知的障害に理解がなくても、弁護士が味方をしてくれたら、状況は変わるかもしれません。
しかしながら、そうした弁護士はきわめてまれです。
なぜなら、知的障害者を一生懸命に弁護しても、弁護士が得られる報酬はあまりにも安く、手間ばかりかかるからです。
刑務所の寮内工場に来るような被告人は、ほとんどが国選弁護士に弁護をしてもらっています。
私選弁護士の報酬額額が、だいたい依頼時にかかる着手金が30万前後、執行猶予つきの判決を勝ち取ったときの成功報酬が30万から50万くらいというのに対して、国選弁護士に支払う報酬は1時間前後の裁判で8万円くらい。
困ったことに、国選弁護士は必要最低限の弁護しかしないとよく言われています。
ただ、まれに熱心な国選弁護士もいます。
たとえばこんな話。
被告人は50才の男性。
スーパーで何時間も女子トイレにこもっているから、チカンと思われて逮捕された。
過去にも同じことをしていて、その時点で3度目の逮捕でした。
たまたま国選弁護士として派遣された弁護士が「このまま裁判を進めてはいけない」と思って、自分で費用を負担して精神鑑定を受けさせました。
その結果、被告人には重度の知的障害があることがわかりました。
なんでも、母子家庭に育って、中学生くらいのときにお母さんを亡くし、以来、トイレのサニタリーボックスがお母さんだと感じるようになったらしいのです。
そばにいると安心すると。
さらにその弁護士は、身元引受人にはなってくれる福祉施設を見つけて、重度知的障害であることを証明してくれる人も連れてきました。
判決は、3度目の犯行だったので執行猶予こそつきませんでしたが、短期の懲役刑で済みました。
じつは、その弁護士には、知的障害のある弟さんがいました。
損得勘定を度外視して弁護をしたのは、このケースを通じて「知的障害のある被告人には配慮が必要だ」ということを世の中に伝えたかったためでした。
弁護士も、経営のことを考えると、報酬の安い仕事はできないのかもしれません。
しかし、社会全体として「刑務所の中に障害のある人がおおぜいいる」ということを認識するようになれば、弁護士の活動も変わってくるかもしれません。
まとめ
今回は、「刑務所しか居場所のない障害たち」の問題について、司法の側面からお伝えしました。
この話を知って「日本の司法制度は欧米に比べて遅れていて、知的障害に配慮されない裁判がおこなわれている、今の日本の司法制度で知的障害者を裁くのは無理がある」ということがわかりました。
現実、多くの身寄りのない知的障害者たちは、裁判で知的障害を配慮されず、犯罪者として刑務所の中で生きていくしかない状態となっています。
このような人たちが、刑務所ではなく、福祉とつながっていける世の中になることを願います。
我が家では、脳に障害のある4才になる娘を育てていますが、親なきあと、娘の生きる社会は、どんな社会になっているんだろうかと考えさせられます。
次回は「刑務所しか居場所のない障害者たち」の partⅢ として、「福祉は知的障害者たちを守ってくれないのか」ということをテーマとしてお伝えしたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
