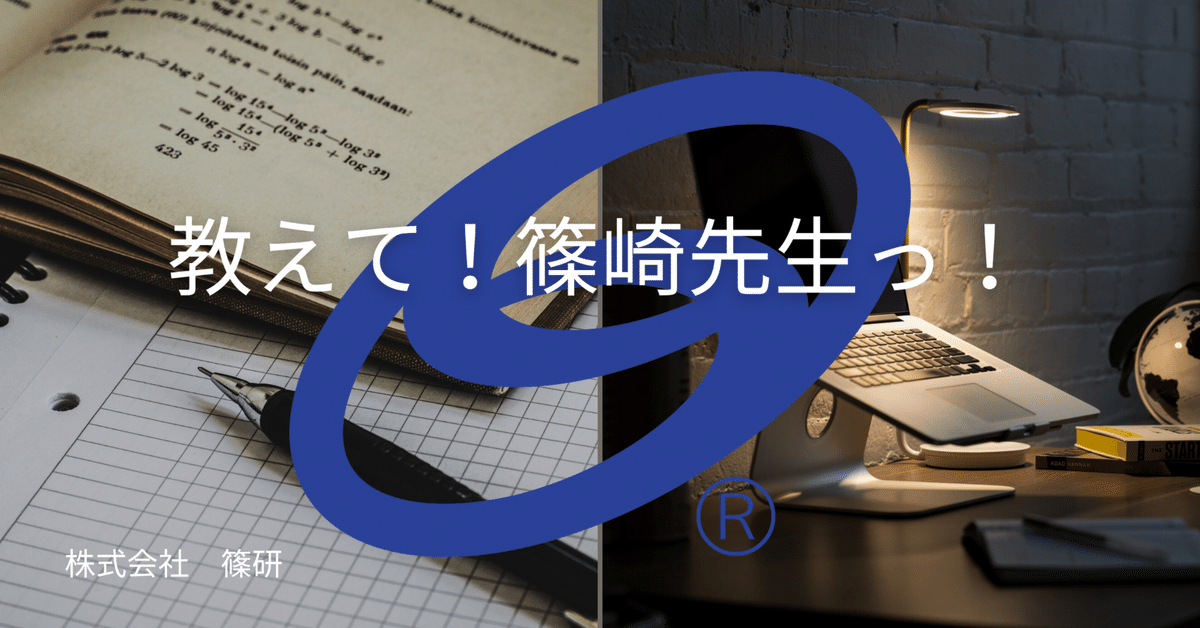
オーディオリンガルメソッド(教授法)では日本語が身につかない?
ご質問
質問は外国語教授法のオーディオ・リンガル・メソッド(ALM)とコミュニカティブ・アプローチ(CA)についてです。
各種参考書・用語集などの説明を読むと、戦後、一世を風靡したALMはその機械的(非人間的)な教え方によって、教授法の主流は創造味溢れる人間的なCAにとって換わった、とあります。
もちろん、今も教室ではALMを取り入れたパターンプラクティスを併用しながらも、日本語教育が目指すのは基本的にCAであるとの解説が目立ちます。
もちろん、極度に意味・流暢さを重視したCAへの反省から、フォーカス・オン・フォームという考え方も登場して、ALMとCAのバランスのとれた教授法が今の主流となっているというのは理解できるのですが、こうした考え方に個人的に疑問も感じています。
今回の質問が「軟派なもの」となるのはここからです。
こうした教授法の変遷について、私は昨今の教育界全体に漂う、なんだかうさん臭さを感じるのです。
日本語をはじめとする外国語教育を振り返ると、私の場合、英語と中国語を勉強しました。
英語は世間一般の標準的な「使えない英語」となる一方、大学で第一外国語で学んだ中国語は先生が厳しかったこともあり、英語よりも100倍以上話せるようになりました。
なぜそうなったか。答えは簡単です。
とことん、基本文型を覚え、単語をアホのように記憶したからです。
中途半端に考えて話すことをあきらめ、暗記に徹したのが「使える中国語」につながったと思うのです(飽くまで英語と比べるとのレベルですが…)。
大学時代に中国語を学んだ際に、意味・コミュニケーション重視で教わっていたら今の中国語レベルはなかったと思うのです。
中国人よりも中国語が上手いといわれた日本人の先生から教わったのは、「型から入って型から出よ」ということ。
単純な文型練習だけでなく、一般的に難しいといわれる中国語の発音も、母音・子音を徹底的に仕込まれ、半泣き状態で教室で繰り返し「学ばされました」。
こうした経緯から、日本語教育の現場では、ALMは飽くまで添え物的な教授法として隅に置かれ、日本語教師が目標とするのは、CAとの折衷案ともいうべきタスク中心の教授法というわかりにくいものとなっているという感じがするのですが、いかがでしょうか。
私の感覚としては、今でもALMが授業の8割くらい占めて、1~2割程度がCAの要素があっても良いと思うのですが…。
恐らく先生の答えは、日本語教育の生徒は国も職業も年齢もいろいろだから、その場その場で教授法は判断すべきというものになるだろうと思います。
さらにこうした私の考えは飽くまで教師のビリーフ(信条)の問題なので、そのまま持ち続ければ良いというものになるのでしょう。
ただ、篠崎先生に聞きたいのは、参考書が指摘するように、そんなにALMは恥ずべき(責められる)教授法なんでしょうか、ということです。
外国語を学ぶ者の目標はいろいろありますが、やはり自由自在に話せるようになることが優先順位としては上位にくると思います。
ご返事
そんなにALMは恥ずべき(責められる)教授法なんでしょうか
ここから先は
¥ 300
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
