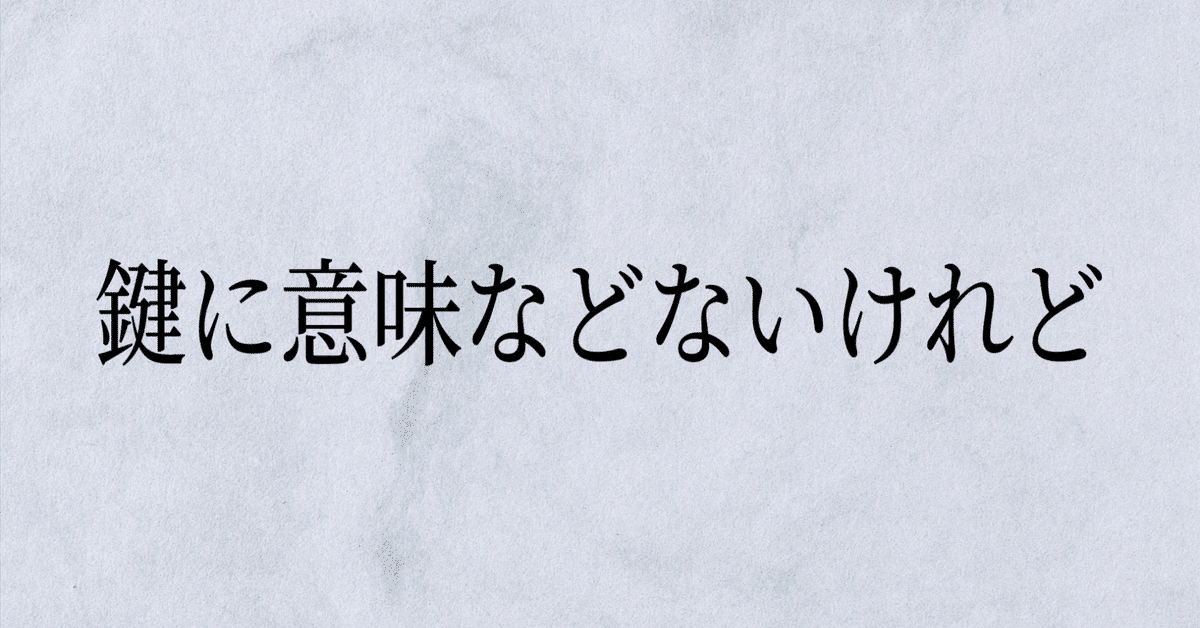
鍵に意味などないけれど
「食べ盛りの56歳。不安な糖を洗い落としてくれるのは古事のお茶」
四人用ブースのテーブルに広げた新聞広告を見下ろして、向かいに座る女はゆるやかな口調でそう読み上げた。薄化粧に黒々とした髪を首元で結ぶ丸い頭は、禁欲的な生活を守る修道女を思わせた。東京都庁薬務課に従事する者は厚労省からの出向だと聞いたことがある。難関大学を卒業し、上級公務員として人並以上の給料と地位を手にしているはずだろう。五年前に立ち上げた健康食品の通販会社を経営する牧原に対して、女は疑り深そうな表情を向けた。必要最小限にしか開かない瞼の奥のドットのような瞳には一切の揺らぎがなかった。
今年の四月二十六日、大和新聞に掲載されたこちらの全面広告は、御社が出されたもので間違いありませんね、そう女の乾いた唇が確認してきたので、牧原は机の上で両手を組んだまま黙って頷いた。実は通報が寄せられまして、と女の手に包まれたペンがこつんと机を打った。この広告の文言に法令違反の疑いがあり、本日はご足労願いました。具体的に言いますと、まず「古事のお茶」というのは御社商品である糖桑茶を指すのでしょうが、こちらが「糖を洗い落としてくれる」つまり血糖値を下げると暗示されています。この効能を裏付ける臨床試験などのエビデンスはお持ちでしょうか? 桑の葉が原料とありますが、エビデンスをお持ちであれば後日ご提示をお願い致します。もしお持ちでなければ消費者に誤認させる表現として、健康増進法に抵触する可能性があります。あるいはお持ちだとしても、血糖値を降下させる効能は医薬品の部類に入ります。もし御社の糖桑茶が医薬品として登録されていなければ、無許可で医薬品を販売したということで薬機法に抵触する恐れがあります。次に文中に出てくる体験談についてですが、糖桑茶を飲んだ大阪府在住の坂田とし子さん六十三歳は「女手一つで子ども三人を育ててきて、昔はずっと働きっぱなしやったわ。体力を付けるためにとにかく食べました。特に甘い物が好きでね(笑)。今じゃ子どもたちは独立しましたけど、食べることはやっぱ止められへん。つい手が伸びて、どうしても食べ過ぎてしまう。するとな、逆に体力が落ちてすぐにしんどくなったり、ぜえぜえしたり、いつも飲み物を欲しくなってまう。調べてみると血なんやら値っていうのが高くて、びっくりしてもうたわ。これはなんとかせなと焦ったときに、この桑の茶と出合いました。飲み始めてしばらくしたら、まず朝すっきり起きることができて、軽やかに家事をこなせて、飲み物を欲しがることがなくなりました。そして気がかりやった数値がなんと安心域に! おまけに洋服のサイズが一つ小さくなってな、外出が楽しいてしゃあないわ。でも食べる量は全然減らしてへんのよ。まだまだ食べ盛りやもん。このお茶は私にとって人生のパートナー。これから元気に毎日を過ごすためにも、ずっと飲み続けていきます!」と一件落着で締め括られています。この、スカートをひらひらさせて、満面の笑みを浮かべている写真の女性が坂田さんですよね。糖桑茶の飲用前後で、坂田さんの体調がどう具体的に変化したのかは書かれていませんが、医薬的効果が暗示されているのは明らかです。高血糖状態による疲労や喉の渇きが改善されて、血糖値が標準域まで下がり、さらにダイエットにも効果があったこと。この広告全体から伝わるイメージによって、坂田さんが御社の糖桑茶を飲んで血糖値が下がったことは消費者に容易に暗示されます。やはり健康増進法または薬機法に抵触する可能性があります。あと、下の方に掲載されている糖桑茶のキャンペーンについてですが「今なら半額」と書かれています。しかしキャンペーンの期間がどこにも明記されていません。本来は常時半額なのに「今なら」と消費者の購買欲をむやみに煽っているのであれば、景品表示法にも抵触する可能性がありますね。
そこまで続けると、薬務課の女はすっと顎を引いて、牧原の顔を見据えた。話を始める前と同じく、微小な瞳がまっすぐ向けられている。きっと大阪弁を棒読みしているときも、女の瞳は打たれた釘のように動じていなかったのだろう。
何か釈明されることがあれば、と女はかちりとペン先を出し、こちらの言葉を待った。牧原は大きく息を吸った。そして神妙に眉根を寄せ、両手を脚の付け根に添えて、本当に申し訳ございませんでした、と平身低頭に謝った。まだ会社設立から間もなくて社員も少ないのですが、なんとか給料を出してやりたい一心で、社内社外かかわらず毎日ばたばたと奔走しておりました。そのぶん関連法規についての知識が完全に抜け落ちていたことを認めます。確かに鎌倉時代の僧侶である栄西は『喫茶養生記』で桑の葉が飲水病──今でいう糖尿病に効果があると書いていますし、坂田さんの体験談は牧原が実際に取材したとおりの言葉であります。ですが弊社としましては勉強不足の点をしっかりと自覚し、今回ご指摘の内容を充分に反省して、代表である牧原はもちろん社員一同、今後は法令遵守のために社内チェックを徹底してまいります。
あらかじめ準備された台詞には興味を示さず、女の視線は手元に置いた名刺に注がれていた。えっと、牧原さんというのが代表取締役で、つまりあなたですよね、と訊ねた。そのとおりですと頭を下げた。女は訝しそうに少し首を捻ねったが、できるだけ早く話を終わらせたいようにノートにメモを取り始めた。筆圧が高いのか、ペンの走る音が二人の沈黙を際立たせた。書き終わると、思い出したように女の顔がこちらを向いた。仰るように昔の文献には様々な民間療法が書かれていますし、桑の葉が糖尿病に効くということも実際に記述されているのでしょう。この坂田さんも、本当に糖桑茶を飲んで血糖値が下がったと話されたかもしれません。ですが『喫茶養生記』というのは特定の商品についての広告ではありません。坂田さんも牧原さん個人に対して話しただけで、決して不特定多数にアピールしたわけではありませんよね。嘘を書けということではありません。広告に書いて良いことと悪いことが法律で定められているということです。
女を見つめてみた。細い目に白くつるりとした額。もしかしたらこの女は法律と付き合っているのかもしれない。法律と結婚でもしようとしているのかもしれない。それでも牧原は女に同意するように深く頷いた。本当のことを書いてはいけないことはわかっています、と自戒するように述べた。たとえ本当のことでも法律に反する場合がありますから。
微妙に違います、牧原さん、女は抑揚のない調子で返した。法律の外側に本当のことはありません。本当のことは法律の内側にだけ認められるものなのです。
大江戸線から銀座線に乗り換え、蛍光灯が明滅する地下道から地上に出ると、同じぐらい仄暗い空が広がっていた上に、細かい糸のような雨が降っていた。折りたたみ傘を取り出すのも億劫なほど多くの人が路上に行き交っていた。赤信号に変わりそうな横断歩道を小走りで駆けていくと、コンビニのレジ袋を手にした加治木がビルの前でビニール傘の釦を留めているのが見えた。近づいて声を掛けると、あ、早いっすね、と加治木は笑みを浮かべて、ちょこんと頭を下げた。どっちも慣れたもんだからな、と牧原はジャケットに付いた雨粒を払ってから、ビルの重いガラスドアを押し開けた。なあ加治木、さすがに血なんやら値はないだろと注意し、すみませんと加治木が苦笑したところで、いつもの黴臭いエレベーターの扉がぎこちなく開いた。互いに窮屈そうに身を押しこめて、事務所の階へと上っていった。
錆びついたドアを開けるなり、新人の小川が自席で立ち上がって、おはようございますと元ラグビー同好会らしい声を張り上げた。うっせえよと加治木が苛ついたように呟いたので、おまえが言うことじゃないよ、代表への挨拶なんだからと牧原は背後に向かって突っこんだ。というかさ、小川を一人にして、おまえはなんでコンビニなんか行ってんだよ、そう言いながらいちばん奥の窓際の席に腰を下ろした。加治木も自席につき、デザイン制作用のiMacで顔を半分隠して、寝不足のような赤い片目をこちらに向けた。すみません、朝飯食ってなかったもんですから。反省している様子ではなかった。ペーパーレス化された社内とは決して呼べず、積み上げられた新聞や雑誌の向こうからレジ袋の軽々しい音が聞こえてくる。牧原は机の引き出しから煙草とライターを取り出した。火をつけて、煙を深く吸いこみ、数本の吸い殻が転がっている灰皿に微かな灰を落とした。そっか、給料が振り込まれたばっかりだし、どうせ今朝は牧原が都庁に直行するから、昨夜はソープに行って、家に帰って深夜アニメを見て、またオナニーをして、いつもより睡眠を貪って、結局事務所に来たのが遅かったんだろ、加治木の赤い目に向かってそう投げてみた。なあ小川、加治木が出社したのは何時だと訊ねると、十時半は過ぎていなかったですと小川は滑舌よく即答した。ついさっきじゃん、と牧原は思わず漏らした。加治木さ、小川は入社してまだ一ヵ月も経ってないんだから、もし何か起こったら、先輩のおまえがすべて責任を持って対応しなきゃいけないんだぞ。ソープで楽しんでいる間もそのことだけは頭の隅に置いといてくれよな、とパソコンのログインパスを入力しながら口調をきつくすると、加治木の片手はおにぎりを掴んだまま、ソープはもうやめました、最近はブラッキングですよと小声で答えた。
煙草を灰皿に押しつけた後、広告予定表のファイルをクリックして、媒体ごとの進行状況を加治木に確認した。加治木はペットボトルのお茶で口内を整理してから報告しにきた。週刊誌と宗教誌はまだ締め切りが先だったので、問題なく出稿をキャンセルすることができました。スポーツ新聞も報知、ニッカン、スポニチ、すべてキャンセル済みです。地方新聞については秋田、新潟、長野、徳島、南日本が間に合いましたが、大阪日日だけが明後日の掲載なので、なんとかならないかと代理店に泣きつかれています。牧原は紙面を見せるよう加治木に指示した。加治木は席に戻ってiMacのキーボードを素早く叩き、複合機からプリントされた糖桑茶の五段広告ゲラを手に取って、こちらに差し出した。
健康食品を取り巻く関連法規は年を追うごとに厳しくなり、牧原たち販売会社としても効能効果を示す直接的な表現は抑えてきた。しかしたとえ直接的表現が明記されていなくても、広告全体としてのイメージが効能効果を暗示させてはならないというのが健康増進法の奇妙な点だった。暗示とは何か。たとえば映画や小説から受ける印象は人それぞれであり、全員が同じただ一つの感想を持つわけはない。だがたった一人でも法が規制する印象を受ける者がいれば、その創作物は違法とされるのか。あるいはマインドコントロールとかサブリミナル効果とか催眠術のような、もっと作為的な仕掛けのことを指しているのだろうか。ならばむしろ情報を操作できる政府やマスコミが得意とするやり方だろう。本当のことは法律の内側にだけ認められるのです──薬務課修道女の薄い唇が浮かんだ。法律という枠組み自体があやふやなら、その内側にある本当のこともきっとあやふやなのだ。いずれにせよ今日、都知事名義で行政指導を受け、報告書を提出するように指示された。指導内容は大したものではないが、しばらくは自主的に広告を控えなければならない。もし近いうちに再び都庁薬務課に呼び出されたなら、次は措置命令が下される可能性だって少なくない。売上が徐々に軌道に乗り始め、増えてきた業務量を分散させるために小川を採用した矢先のこと。タイミングの悪さが邪魔をするように、牧原は修正すべき文字を何度か書き損じた。
ほら加治木これ、と赤ペンの先をおさめて、広告ゲラを加治木に戻した。ここの「糖対策」は「数値対策」に修正して「疲れ」は「くたくた」に修正して「数値が下がった」は「明らかに変わった」に修正してから、大阪日日新聞に入稿しといてくれ。たぶん注文ゼロの死に金になるけど、今回の罰金と考えるより仕方ないから。あと、広告代理店の連中は何か言ってたか、そう訊ねると、加治木は牧原の前に立ったまま、顎下の緩んだ肉をつまんで斜め上を見た。結構みなさんぶうぶうとぼやいていましたけど、最終的には承諾してくれました。ただキャンセルが何度も続くと、版元がもう受け付けてくれなくなるよと釘を刺されましたけど。牧原は首を横に振った。スペースブローカーとしてのたんなる意地だよ。横流し商売として意を張れるのは流れが滞るときだけで、また発注すれば何もなかったように駆け寄ってくるさ。
会員向けのDMは変更なく郵送するんですよね、と席に戻った加治木が確認してきたので、変更なく郵送するよと答えた。DMまで止めて売上が落ちると、さすがに資金繰りが厳しくなるからな。ただし文章表現は今渡したゲラと同じぐらいに弱めといてくれるか。少ない部数でも薬務課が目にしないとは限らないし。印刷所に入稿する前にいったん見せてくれ。加治木は頷くとiMacの向こう側に完全に隠れて、ドミノが倒れていくような音でキーボードを連打し始めた。
時間ができたなと頬杖を突きながら何通かのメールを確認していると、机の上でスマートフォンが震えた。コールセンターで牧原たちの会社を受け持っている営業担当者からだった。通話をタップして挨拶を交わすと、さっそく野次馬のような口調で話し始めた。都庁からの呼び出しはどうでしたかと訊ねてきたので、いつものことだよとこめかみを揉みながら答えた。お上もノルマがあるから一件ずつ丁寧に対応してられないし、こっちも無知なふりして頭下げて、ほとぼりが冷めるまで大人しくしときゃ問題はないよ。そっかそっかと営業担当者は小さく唸った。牧原さんもこの業界は長いから、呼び出しを受けたことは何回もあるベテランですよね。逮捕はまだ免れていますけど、ははっ。だけど最近は僕らコールセンターも気をつけてますよ。いくら跡に残らない電話口での説明といっても、癌が治るとか糖尿病が治るとかはさすがに言えません。口頭表現でも規制対象になりますからね。オペレーターには違法な発言をしないよう徹底させていますし、クライアントさんは安心してもらって構いませんよ。安心できないよと牧原は自嘲気味に返した。法律を守れば守るほど、売上がどんどん落ちていく。こっちは単価の安い商売でシニア層の病気を治して、厚労省の保険料負担を減らそうとしてるのに、既得権益を奪われる医師会の方が反発してるんだよ。今回もどうせ医療関係者か同業他社のチクリだろうね。
まあ、とりあえず大事にならなくてよかった、近々一杯いきましょうと営業担当者は通話を切った。牧原はスマートフォンを机の上に放り投げ、頭の後ろで両手を組んだ。確かに牧原にとっては何回も経験してきたことで、大した出来事ではないはずだった。だが実際そのとおりを口にしてみると、なんなく通り過ぎようとしたものを引き止めてしまったみたいに、終話した後も硬いざわめきが腹のあたりに残った。絡んだものを吐き出すように牧原は顎を上げて、小川に声を掛けた。先週言っておいたお客さんへの取材アポは取れたか? はい、少々お待ちください、と小川は頑丈そうな首を左右に回転させ、手元の資料をいくつかまとめて、こちらの席まで近づいた。
飲用歴が一年以上のお客様をピックアップしました、と小川は太い声で報告した。さらにそこから直近で血糖値が下がったという声のあったお客様を絞りこんでいます。小川が差し出した取材先リストには顧客三十名ほどの氏名と住所が並んでいた。試しに一人、電話を掛けてみましたと小川は続けた。仙台に住む三十八歳の女性で、定期的に送っていただく葉書には「毎日糖桑茶を飲み続けています。おかげさまで生活が変わってきました。ぜひ一度、糖桑茶の詳しいお話を聞かせてほしいです」と毎回ほぼ同じ文章が書かれています。取材の話を向けてみると、構いませんよ、日程はそちらのご都合に任せます、と物静かな感じで承諾してくれました。
どの人だ、と目でリストを追いながら訊ねた。叶井真言さんですと小川が指差した名前は、いちばん下の行に印字されていた。
三十八歳で高血糖ってめずらしいな、1型かもしれない、とただ呟いたつもりだったが、申し訳ありません、そこまでは確認しませんでしたと小川はやはり軍隊のような声で頭を下げた。じゃあとりあえずこの叶井さんに会いにいくか、と牧原は席から立ち上がった。牧原と小川の二人で行くから、スケジュール表で二人の予定が空いている日に取材を入れといてくれ。椅子の背もたれに掛けていたジャケットに袖を通し、牧原は事務所を出る準備をした。おい加治木、今度都庁から呼び出しがあったら、次はおまえ一人で行ってもらうからな。経験値アップだよ。はあいと間伸びした加治木の返事を断ち切るように、牧原は事務所のドアをがたんと閉めた。朝から何も食べておらず、行きつけの蕎麦屋で早めの昼食を済ませようと思っていた。
十三時に叶井真言の自宅に到着するためには、東京駅から十時過ぎの東北新幹線に乗って仙台駅まで行き、タクシーで国道を十分ほど走ると見えてくるマンションを四階まで上がっていく。昼食を車内の駅弁で済ませることにして新幹線の時間をちょっと遅らせるかと提案してみたが、せっかくなんで仙台駅で牛タン的なものでもと小川は遠慮深そうに自らの案に固辞した。小川の手配したチケットは二人並びの指定席だった。修学旅行じゃないんだからと突っこむと、せっかく同じ会社の者同士なんでと小川はなぜか照れ臭そうに太い首をすくめた。
えらく空いてますね、と隣の小川は腰を浮かせて車内を見回した。こんなに空いてるのに男同士が並んでるって車掌に怪しがられるよ、そう牧原が窓の外に目をやると、すみません、次からは気をつけますと声量を落とした。
窓の外ではどこまでも乾いた十月の空が通り過ぎていった。誰かがこぼした涙もあっという間に吸いこまれてしまいそうなほどだった。加治木さんとも一緒に取材に行くんですか、大宮駅を過ぎたあたりで小川がそう訊ねてきた。加治木はコミュ障だから取材には行かせてないよ、と牧原は首を横に振った。昔、まだ前の会社で一緒に働いてたときさ、こっちから話を聞きに行ったくせに一言も質問しないで、出されたお茶とお菓子を口にしながら、一時間ほど生い立ちをお客さんから訊かれ続けたことがある。結局自分が取材されて帰ってきたんだよ。へえ、なかなか想像できない姿ですね、と小川は腕を組んだ。代理店や印刷会社と電話でやりとりしているのを横で聞いてますけど、てきぱき無駄なく話を進めているように見えますよ。あいつの対人姿勢は関係性によって極端に変動するからな、そう牧原は冗談と皮肉をこめた。代理店とか印刷会社にとっては自分が発注側だし、小川にとっては自分が先輩だから、舌滑らかに厳しいことや冷たいこと、非人間的なことを平気で言うし、事務的なやりとりだけで無駄な話はしない。でも自分より立場が上の相手や関係性が掴めない相手には言葉がまるで出てこないんだ。表情一つ変えずに、ただ虚空を凝視しているだけ。だから基本的には外に出さずに、広告とかDMの制作をやらせてるんだよ。
そういった意味では、加治木さんにとって牧原社長は特別な存在なんでしょうね。二人のやりとりを見ていると僕はそう感じますよ、小川は微笑んだ。特別かどうかは知らないけど、と牧原は素っ気なく答えて、線虫が脈打つようなむず痒さを背中に感じた。とにかく十五年の付き合いだから、互いに腹の内を見透かしてて、今さら隠すものなんて何もないっていう感覚はあるかな。小川はこちらに身を寄せて、目を大きく見開いた。前の会社から独立されるとき、加治木さんを連れていこうと思ったポイントは何だったんですか、そう訊ねる口調には加治木への揶揄が塩胡椒ほど含まれていたが、コミュ障で楽だったから、と牧原は前を向きながら答えた。前の会社の代表オーナーがかなりの爺さんでさ、五年前に会社を商品ごとに分割して、数人の幹部社員それぞれに経営を任せようとしたとき──牧原もその一人だったんだけど──一緒に連れていく後輩がもう加治木しか残ってなかったんだよ。有能な後輩は他の幹部社員といつの間にか話が出来ていてな。仕方ないけど、まあ気が合わないわけではないから、おい加治木、一緒にやるかって声を掛けたら、あぁ、別にいいですけど、だって。なんでこっちが許可される立場なのか、ちょっとかちんときたけどね。小川は車内に響くほどの声で笑った。加治木さんも嬉しかったと思いますよ。コミュ障で良かった、これからもコミュ障を貫こうって決心したんじゃないですかね。やはり小川の表情には嘲笑が混じっていた。おまえの性格をわかってくれる貴重な人材が社内にいるぞって加治木に言っておくよと釘を刺すと、あ、それはやめてくださいと小川は早口で言った。仲良くなって風俗に誘われたりするのはちょっと困るんで。彼女もいますし、小川はそう言って背もたれにどすんと体を預けた。座席の振動に若々しさが伝わり、牧原はペットボトルの緑茶に手を伸ばして、いつまでも続く田園風景へと視線を外した。
一時間ほど目を閉じて、車体の揺れに身を任せていた。しだいに途切れ途切れの揺れになり、その合間に短い夢を見ているような状態になった。揺れの間に浮かぶ短い夢をいくつか飛び渡っていったが、とうとう夢は途切れてどこにも行けず、ぼんやりと目を開けた。新幹線はまだスピードを落としていなかった。隣の小川はスマホを鼻先まで近づけて、画面を素早くタップしている。仕事だとは思えない真剣な目つきだった。そういえばさ、と声を掛けると、小川はびくっと体を震わせて、驚いた表情をこちらに向けた。牧原は咳払いをしてから、ブラッキングって何と訊ねてみた。えっと……ブラッキングですか、と小川はそれまで集中していたことを一旦整理するように言い淀み、スマホを上着の内ポケットにしまった。僕も詳しくは知らなくて、加治木さんから説明されただけなんですけど、要するに闇鍋みたいなもんだと思います。自分の手も見えないぐらい真っ暗な部屋で女の子と楽しむ風俗ですね。女の子の顔も体も見えない状態で、こっちは声とか匂いとか体の感触だけで相手を想像する。オプションで明かりを調節できるみたいですが、加治木さんは視覚に強く依存していたそれまでの自分を見つめ直したいっていうことで完全な闇を選んでいるようです。風俗界はついに新しいプラトニックなフェーズに突入したって力説してましたよ。たぶん、と牧原は溜め息をついた。リスクが少ないぶん料金が安いからだけだろ。確かにと小川は太い腕を組んで頷いた。店側は客の視覚的欲望を満たす必要がありませんからね。あと電気代も節約できる。失礼ですが、牧原社長もそういう店に行かれたりするんですか。寝起きのぼやけた頭に少し嫌気が差した。若い頃に何度か誘われたことがあるぐらいだな。いくら新しいプラトニックなフェーズだとしても、相手の顔が見えない設定で集客するためには料金を下げなきゃ仕方ないだろ、そう言い捨てると、小川は再びこちらに体を近づかせてきた。
重ね重ね申し訳ないですけど、牧原社長って仕事以外の時間はどんなふうに過ごしているんですか、小川が訊ねてきた。仙台まで一時間を切っていた。できることならもう一度目を閉じて、飛び石の上を朦朧とさまよっていたかった。エロ記事のスクラップ作業と答えても、小川はくすりともせず、それも仕事の一端ですよね、と牧原が薬務課修道女に見せたのと同じような神妙な表情を浮かべた。やっぱり社長になると生活は変わるものですかと続けてきたので、別に変わらないよと首を傾けた。今でもカウンターで牛丼食ってるし、好きなものは変わらないだろ。強いていうなら自分の机で煙草が吸えることぐらいかな。それもただのタイミング。五年前の分社化のときにたまたま居合わせただけのことだよ。でもそれって、と小川は上目遣いになった。めちゃめちゃ運が良いってことですよね。さあ、運が良いのか悪いのか、そんなのはわからない。わかるのは、ただのタイミングで今おまえの隣に座ってるってことだけだよ。そう言うと、小川はしばらく通路を挟んだ向こう側の窓に顔を向けた。さっきまでスマホで集中していたことを気にかけているようにも見えた。だが小川はふとこちらを向いた。なんだろ、変な言い方ですが、牧原社長ってもう一人の牧原社長がどこかにいるみたいですよね。二人いるっていうか。いつも自分のことを牧原って仰るのも、そういうふうに感じちゃうのかな、と呟いた。独り言のような物言いに答えようがなかったので、牧原は目を閉じて、再び飛び石を探すことにした。
仙台駅前のショッピングビルにある和食屋までエレベーターで上がった。秋空が広がる見晴らしの良いテーブル席で牛タン定食を口にしていると、小川の上着の中でスマホが鳴った。小川は画面を確かめ、あ、叶井さんからです、とお茶を一口飲むと、少し離れた窓際のあたりへ小走りで移動した。その間に牧原は料理を平らげ、水を飲み干して、窓の外を眺めていると、小川が戻ってきた。
叶井さん、取材の場所は自宅じゃなくてもいいだろうかということです、と小川は言った。直前の連絡になって申し訳ないんですけど、急に電車に乗って行く用事ができたので、できるならその前に仙台駅周辺で話ができたら助かる、取材が終わりしだい電車に乗って行けるから、ということでした。話を聞かせてもらえるなら場所はどこでもいいよ、と牧原は紙ナプキンで口元を拭った。はい、僕もそのように返事をしたら、じゃあ駅前に大きなショッピングビルがあるから、その正面入り口で待ち合わせましょうと指定されました。ショッピングビル? と訊き返すと、つまりこのビルですね、と小川は冷めた牛タンに箸を伸ばした。
叶井真言が姿をあらわしたのは十三時を数分過ぎたときだった。紺色のカーディガンを羽織り、ライトブルーのタイトなジーンズを穿いて、深めに被ったつばの長いキャップからはまっすぐな黒髪が背中の真ん中まで伸びていた。手には小ぶりなバッグを持っている。ひとたび雑踏に紛れると二度と見つけられそうにないほど地味な格好だった。一目見た瞬間、あえて自らを街並みに潜ませようとする意図が石鹸の香りみたいに漂っているのを、彼女の自然すぎる佇まいに感じた。はじめまして、叶井真言です、ネクタイを締めた二人の男性だからすぐにわかりましたよ、そう近づいてきた声は白湯のようになめらかで、つばを上げた大きな目元は柔らかく緩んでいた。牧原と小川から受け取った名刺をしげしげ眺めると、ここから五分ほど歩いたところに会館があるので、そこでお話しましょうと叶井は歩き出した。
歩道を進みながら、牧原たちは天気のことや仙台の街について言葉を交わした。赤信号で叶井はぴたりと両脚を揃え、信号が変わると早くも遅くもないスピードで、ほとんど足音を出さず、アスファルトの上を滑るように歩いた。大通りから外れた道へ曲がり、中小のビルが並ぶあたりをしばらく進むと、やがてベージュ色の建物が見えた。三階建ての小学校ほどの大きさで、切り出された四角い木材を積み上げただけのようなシンプルな造りだった。建物の前には十台ほど駐車できるスペースがある。叶井は敷地に足を踏み入れると、迷いなく建物の入り口まで進んだ。牧原と小川も後に続いた。古そうな木で出来た扉の上には、見憶えのある宗教団体の看板が控えめに掲げられていた。飴色の木目に隷書体で刻まれている。普段車を走らせていると、景色の中でたまに目にする団体名だ。小川の不安そうな視線がこちらに向けられているのを感じたが、叶井が扉を引いて、どうぞお入りくださいと建物の中へ手を差し出すと、牧原は失礼しますと緩んでいたネクタイを締め直した。
質素な外観とは対照的に、館内には来訪者を包みこむような装飾が施されていた。奥まで見渡せる広々としたホールには、大理石と思われる光沢のある柱が何本もそびえ立っている。天井ではゴシック様式もしくは涅槃図を思わせる巨大な彫刻紋様がこちらを見下ろしていた。壁に彩色されている茶色や黄色の微妙な濃淡のラインは古い地層の断面を思わせた。絵画のようなものも各所に飾られていたが、虹色のラインが互いに交わりながら描かれていて、壁の模様の延長として一体化しているようにも見えた。
牧原たち以外に人の姿はなかった。来館者を受け付けるカウンターらしき台もない。叶井は数歩先を進みながら、牧原たちを奥に続く廊下へと案内した。床にはブロッコリーのような濃緑色の絨毯が敷きつめられ、やはり叶井の足音は響かなかった。館内は暖色の明かりに照らされていたが、電灯は天井のどこにも設置されておらず、どこに光源が隠されているのか見当がつかなかった。牧原はあらためて宗教団体の名を思い浮かべた。その団体が仏教系なのか神道系なのかキリスト教系なのかを思い出すことができなかった。装飾に近づいて細かい箇所を確かめても、自分の知識では判別することができない。ただ建物の雰囲気には、自らの活動をしっかり示そうとする意志が床の隅々にまで充満しており、だからといって眩しく煌びやかな輝きを放っているというわけでもない。それが一体何に向けての装飾なのだろうかと、ついあたりを見回していた。教団の存在感で信者を圧倒させるためか、寄付によって建てられた会館で信者に少しでも還元するためか、それともただ教団の理念に基づかれているだけなのか。外界からの雑音は一切遮断されていて、ほんのり漂う柑橘系の香りを深く吸いこんだところで、前を進む叶井が小部屋の前で立ち止まった。
部屋にはドアがなかった。それまで目にした装飾は室内のどこにもなく、壁や天井には建売住宅に使われるようなクリーム色のクロスが貼られ、六畳ほどのスペースに簡単な応接セットが置かれているだけだった。シンプルな細いコーナーラックには白い花が一輪挿しに生けられている。廊下の奥に目をやって、同じようなドアのない入り口がいくつか並んでいるのを確かめてから、牧原は部屋の中に入り、奥のソファに小川と並んで座った。叶井も向かいのソファに腰を下ろした。背筋を伸ばし、揃えた両脚を少し斜めに傾け、信頼できる相棒とでもいうように脱いだキャップをバッグの上に丁寧に置いた。ひとまず取材の時間を割いてもらったことに牧原は礼を述べた。叶井も膝の上で両手を重ねたまま頭を下げた後、羽のように軽そうな長髪をかきあげた。
まず確認させていただきたいのですが、と叶井は牧原を見つめて言った。牧原さんと小川さんのお二人は入会されている方々という認識でよろしいのでしょうか、そう訊ねる叶井の澄んだ目に強引さのようなものはなかった。まずはその前提を明らかにしないと話が前に進まないという事務的なものだった。いえ、そういうわけではありませんと牧原はできるだけ柔らかく答えた。確かにこちらで発行されている『やくそくの環』に弊社の広告を出したことはあります。ただこの月刊誌への広告は、こちらの出版部の承諾さえ受ければ、いわゆる一般企業でも広告を出すことができます。『やくそくの環』に載っている企業が必ずしもこちらの関連団体というわけではありませんね。
そうですか、やっぱり、と叶井はテーブルの上に視線を落とした。そして持て余していたパズルのピースを嵌めるように一人で何度か頷いてから、再び姿勢をまっすぐ戻した。わざわざ遠い仙台まで来ていただいた方々に対して率直な言い方になってしまいますが、と叶井は前置きをした。つまり『やくそくの環』を利用したというおつもりなんでしょうか? 会の人たちはこういった刊行物に目を必ず目を通しています。そして文章を読んで環心を感じ得ようとします。たとえ会に関連のない糖桑茶の広告が載っていたとしても、きっとこれは糖尿病に困っている信者に向けて会が勧めているお茶なんだ、会のお墨つきのお茶なんだと信じこんで、注文の電話を掛けてしまいます。牧原さんたちはそういった読者の信心につけこんで、商品を売りつけているように見受けられるのですが。
叶井の目は刺々しくはなかった。言葉一つ一つはこちらを糾弾するように聞こえたが、強い義憤がこめられているわけではなく、やはりあくまで牧原の経営姿勢を確かめたいという中立的な目だった。叶井様への答えになっていないかもしれませんが、と牧原は大きく息を吸いこんだ。そもそも広告とはそういうものです。テレビゲームを宣伝したいなら子ども向けの雑誌やアニメ番組に広告を出し、化粧品を宣伝したいならファッション雑誌や通販カタログに広告を出します。その商品を求めていそうなターゲットが集まるメディアに広告を出すのが宣伝方法の定石となっています。お客様が商品を選ぶのと同じように、商品もお客様を選んでいます。牧原が聞いた話によると、こちらの会の方々の平均年齢は六十代で、ちょうど糖尿病の兆しがあらわれる頃でしょう。どのような信心を持たれているとしても、病気や死は平等に訪れるものだと思います。ただ確かに叶井様が仰るように個別的な要素もあります。『やくそくの環』のような会員誌であれば公に目にされにくいぶん広告表現を強めることができますし、読者にはきっと真面目な方々が多いので商品を購入してくれる確率は高いといえます。ちなみに、と横から小川がおずおずと言葉を挟んだ。今のネット広告では、性別や年齢や職業や趣味嗜好なんかでターゲットをピンポイントに分類して、広告効果の精度をさらに高めようとしてますよ、秘密の取引でもするような小さな声で小川はこちらに目を向けた。
広告活動もビジネスの重要な一端だということは理解しております、と叶井は返してきた。私も若い頃にしばらく百貨店に勤めていたことがありますから、と肩に掛かっていた髪を後ろに小さく払ったところで、叶井様、と小川が遮った。定期的に叶井様から届くお葉書には、糖桑茶で体調が良くなってきたと書かれていました。本日はぜひそのお話を聞かせていただきたいのですがと小川が促すと、体調が良くなったとは書いていないはずですよ、と叶井は子どもに話すように首を傾げた。生活が変わってきた、とだけ書いたはずです。そう、お二人ともすでにご理解されていると思いますが、今日私は糖桑茶に感謝をする話をしにきたわけじゃありません。この何の効果もないただのお茶に、糖尿病が治るという不明瞭な価値と一万円もの価格を付けて、平然と販売しているあなた方がどういう考えをお持ちなのか、直接話を伺いたかったのです。
叶井はやはり冷静だった。感情に引っ張られ、この場に想いの丈を吐き出しにきたという響きではなかった。弁護士かもしれないとよぎった。たとえば信者の中で糖桑茶に不満を持つ人たちが増えてきて、教団の顧問弁護士として訴える準備をしているのかもしれない。もうそうなら薬務課修道女に報告書を提出するより何倍も厄介な事態になる。ここはとにかく頭を下げて、早く引き払った方がいい。
裁判とか、そういう大きな話をしているわけじゃありませんよ、叶井は牧原の目を覗きこみながらそう口元を緩めた。今日のお話について会は関係ありません。あくまで私が個人的にあなた方と話をしたいだけです、とカーディガンの袖を片方ずつ引っぱり上げた。細い手首が蛍光灯の光に白く反射したが、叶井の生活ぶりが垣間見えるものはなかった。隣に目をやると、小川はテーブルの上にただ視線を固定させている。実際は何も見ていないのだろう。牧原はネクタイの結び目に手をやり、肩の力を抜いた。そして、叶井様が個人的にということであれば、と切り出した。やはり叶井様ご自身が血糖値にお困りで、ご自身のために糖桑茶をご購入されたということですよね。
もちろん、と叶井の長い睫毛が上下にゆっくりと動いた。微かに風が舞った気がした。私は生まれつき膵臓からインスリンがほとんど分泌されない1型糖尿病です。子どもの頃から三度の食事前に打つインスリン注射を欠かしたことがありませんし、外出時はスマホよりも注射器とブドウ糖の携帯を絶対に忘れないようにしています。注射のタイミングを間違えれば低血糖状態に陥って、命を落とすかもしれない危険と常に隣り合わせで暮らしてきました。私にとって糖尿病は切実な現実というより自己の一部となっています。だから糖桑茶についても正直期待は寄せていませんでした。そして一年ほど飲み続けて、やはり状態が改善される兆しは今のところありません。別に腹を立てているわけではありませんよ。こういった紛い物は世の中にいくらでもありますものね。ただ、私が『やくそくの環』に載っていた広告を読んで、糖桑茶を買ってみようと気持ちになったのは確かに本当のことです。こんなもの効くわけがないと頭では理解しながら、この文章を書いている人が紹介しているお茶を自分は飲むべきだというふうに心が結合した感覚がありました。最初は環心の手繰り寄せかと気持ちが輝きましたが、結局は未熟な私の錯覚によるものでした。たぶん私が入信していることとは別の、もっと個人的なことに由来したんだと思います。
叶井は話している間、姿勢を一切崩さなかった。話に集中しているときは他のことに気を取られまいとする意志のあらわれにも見えた。あるいは普段の仕事に取り組む癖のようなものが無意識に出ているのかもしれなかった。風を舞わせる大きなまばたきと鼻孔からの呼吸音によって、自分の言葉の跡をすぐさま掻き消している、そんな感じで注意深く自らについて語っていた。
言い訳を二つさせてください、と牧原は言った。まず弊社が糖桑茶をお勧めしているのは、主に糖尿病予備軍あるいは2型糖尿病の方々になります。後天的に血糖値をコントロールできなくなること。その原因は食生活の乱れによるものが多く──もちろん医師が処方する薬によって数値を抑える方法もありますが、食事が根本的な原因であれば、食事を変えることによって、たとえ時間が掛かろうと健康な体に戻れるというのが牧原の考えです。そして腸内で糖分の吸収を抑制させる糖桑茶にはそのサポートができると考えています。一方で、先天的にインスリンの分泌が困難なお客様には糖桑茶を積極的に勧めておりません。過剰な糖分摂取が原因ではないからです。もちろんどんなお客様であれ、ご購入の意志があれば販売いたしますが、叶井様が1型糖尿病であることをきちんとヒアリングできていなかったことは、弊社の落ち度として判断されても致し方ないことです。もう一点、確かに一万円という価格は決して安くありません。ただし一ヵ月ぶんの内容量に対して一日三回の食事時に飲用するという設定ですので、一杯あたり百円強ほどの計算になります。これはコンビニに並ぶ特保のお茶より安い価格です。弊社がお客様の病につけこみ、紛い物を売りつけて暴利を貪ってやろうという考えなど、塵ほども持っていないことだけはご理解いただきたく存じます。
そう話しながら、この小さな部屋で小さなテーブルを囲んでいる三人以外、館内には誰もいないのではないかと牧原はときどき耳を澄ませていた。駅から歩ける距離で、扉を引けば簡単に入ることができる決して小さくはない施設に、関係者が誰も詰めていないことは考えにくい。宗教施設といえども保守管理しなければいけない物品はあるだろう。しかしいくら神経を尖らせても、足音一つ、囁き声一つ聞こえてこない。ただ叶井の目だけが館の主のようにまばたきを繰り返しているだけだった。
わかりました、と叶井は膝の上に両手を重ねたまま、あえて頭頂部を見せつけるぐらいに深々と頷いた。頭を上げると、ほどけた髪をするりと耳にかけ、淀みなく黒光りする瞳をこちらにまっすぐ向けた。申し訳ないですが、今後私が糖桑茶を購入することはないでしょう。しかしそれは決して後ろ向きの決裂ではなく、私の話を牧原さんが聞き、牧原さんの話を私が聞いて、相互理解が得られた上での選択だと考えていただければ幸いです。今回は残念ながら環心による手繰り寄せはなかったということでしょうね。ただ最後に一つだけ、確かめたいことがあります。今回の件とは関係のない個人的な興味です。会社の代表として牧原さんはきっと様々な経験を重ねてこられたと想像しますが、ビジネスにとっての成功と失敗を分けるポイントは何だと考えておられますか。端的に言えば商品を買うか買わないかのポイントです。
ふと、片側の頬に小川の視線を感じた。それまで大人しく目を伏せていたくせに、何事もなく話が無事に済みそうになると、顔の前で手を組んで、こちらに好奇の目を向けていた。ただ確かに、それまで超然とした雰囲気で話していた叶井が、なぜ突然経済誌のインタビューのようなあらたまった質問を向けてきたのか、牧原も違和感を覚えた。作為があるのは明らかだったが、この場を早く切り上げられるならば頭を掻いて濁すわけにはいかなかった。先ほど叶井様が言われた話に答えは含まれています、とひとまず牧原は話し始めた。叶井様が広告を読み、こんなもの効くわけがないと拒否されながら、それでも糖桑茶の購入に至った。つまり手前味噌になりますが、人の心を表面的に覆う理屈や常識を突破する何かが広告の中にあったんだと思います。もちろん糖桑茶自体が良い商品であることに弊社は自信を持っていますが、良い商品が必ずしも多くの方に購入されるわけではありません。広告による刷りこみとイメージで購買欲が喚起されることが多いでしょうが、では同じ広告マーケティング理論を実践すれば、すべての商品が同じように売れるのかといったら、答えはノーです。牧原が思うのは、理論化あるいは言語化できるぎりぎりの寸前まで進み、その力の余波が一歩先にある言葉の届かない壁を突破できたとすれば、その広告はお客様の心に触れたことになり、商品の購入に繋がるかもしれないということです。うまく言えず、叶井様の質問にきちんと答えられているのか恐縮です。
ほとんどその場で思いついたことを並べただけだったが、嘘を言っている白々しさは不思議と覚えなかった。叶井に質問され、叶井を前に話しだすと、詰まっていた栓がぽんと外れたように自分の中からするすると言葉が出てくるようだった。それはちょうど叶井とショッピングビルの前で待ち合わせて、何本かの道路を迷いなく曲がり、会館の小さな部屋までの道のりを流水のように誘われてきた感覚に似ていた。
叶井は唇を薄く開いて、口角を微かに上げている。きっと牧原さんは鍵を探しているんですね、と叶井は告げた。すべてのものは自分のまわりに鍵の掛かった扉を設けており、分断された状態が定常しているとされています。そして、ときに自ら分断を好む場合もあれば、ときに鍵を開けてまわりの扉を開放したいと欲する場合もあります。しかし本当は、扉などいつでも開けられるのです。なぜなら鍵は一つしかないからです。たった一つの鍵でこの世のあらゆる扉は開かれ、あらゆるものは一つの大きな環で繋がることができます。たとえば牧原さんが御自身のことを牧原と呼ぶという分断も、その一つの鍵で開け放つことができるのです。
大きな環、と牧原は無意識に声に出した。それがつまり環心というものでしょうか、訊ねるつもりはなかった質問に、叶井は声を出さず、ゆっくりとまばたきをした。壁を軽く叩く音がした。入り口に目を向けると、スーツを着た男がいつの間にか立っていた。灰色のスーツに黒いネクタイを締め、食の細そうな骨張った顔をしている。ご歓談中に失礼します。真言さん、そろそろ時間が迫っております、と男は廊下に立ったまま控えめな声を出した。叶井は振り返り、男に向かって頷くと、こちらに体勢を戻した。そして、牧原さん小川さん、本日はお手間を取らせて申し訳ありませんでしたと頭を下げた。またいつか、ということは言えませんが、もし再びお会いすることがあれば、それはきっと環心による手繰り寄せかもしれませんね、叶井はそう微笑み、カーディガンの袖を元に戻した。ふと顔を上げると、男の姿はすでに入り口になかった。あらわれたときと同じように、男は物音一つ立てずにいつの間にかいなくなっていた。そこに立っていた気配すら残されていなかった。
薬務課への報告書は、いくつかの細かい修正を何度か重ねた後にあっけなく受理された。先方が必要とするのはとにかく形式であり、牧原たちの会社が行政指導を受けた事実は揺るぎない記録としてファイリングされることになった。ブース席に座っていた女の顔はすでに思い出すことができなかったが、あと二、三ヵ月は広告を控えた方がいいだろうと牧原は重い肩をゆっくりと回した。
その朝、パソコンの前で売上集計など一時間ほどのルーティンワークを終えてから、広告掲載誌を並べているキャビネットの棚を開けた。叶井が初めて糖桑茶を購入したのは昨年の九月と彼女の顧客情報に入力されている。その直前に糖桑茶の広告を掲載したのは昨年の八月号だった。『やくそくの環』には年四回ほどしか出稿しておらず、牧原は該当の号を抜き取った。B5判の小冊子ほどの月刊誌で、発行部数は十八万部。表紙には会館の看板と同じ隷書体による誌名と、紺や赤や緑のラインが重なって波打つ抽象的なイラストが印刷されている。ぱらぱらとページをめくり、文字が多く並ぶモノクロページに糖桑茶の広告を見つけた。確かに牧原が制作したものだった。フォントや級数や段組みなどを本誌のレイアウトに似せて、あたかも『やくそくの環』の記事だと読者に思わせるように作ったのだ。叶井が指摘したように、いわゆるステルスマーケティングと呼ばれても仕方ない。だが逆にいえば誌面の形さえ整っていれば、信者たちはただの広告を『やくそくの環』からの有難い記事として見誤り、たやすく自然に読み入ってしまうものなのだ。
自席に腰を下ろし、他のページをめくってみた。環心という言葉が頻繁に使用されているのが目につく。会の幹部らしき男へのインタビューを載せた記事では「……日々を過ごしていると、うまくいかないことが当然あるでしょう。うまくいかないこと、言い換えれば自分の思いどおりにならないことですね。自分の思いどおりにならなかったこと、それは他の誰かにとっては思いどおりになったことだとも言えます。ある事象が自分にとっては不満なのに、逆側にいる誰かにとっては満足だという分断は、二者間が扉によって隔てられていることで起こることです。個と個、社会と社会、国家と国家、人間と環境、そして精神と肉体、世に生きる様々な存在は分断によって対立し、干渉し合い、攻撃し合っています。私たちが本当に成るべき状態を一言で要約すると、世を分断するあらゆる扉を開放し、一つの大きな環心があらゆる存在の中をスムーズに流れ渡っていくことに尽きます。環心の流れには対立も干渉も攻撃もありません。もちろん満足も不満もなく、ある一つの存在に起こったことは、世のあらゆる存在に同時に起こったこととして受け止められるのです。では扉を開放させるためにどうすればいいか? 当然ですが私たちは暴力を使いません。どんな種類にせよ、結局のところ暴力が最も扉を固く閉ざしてしまうことを歴史的に学んでいるからです。私たちは非暴力の中にこそ環心に導かれる鍵が隠されているのだとして日々の活動に励んでいます……」と行間をたっぷりとった教科書体で書かれていた。インタビューに答えている男のモノクロ写真も掲載されていた。髪は短く刈りこみ、頬は痩けて、太い眉毛に覆われた目は力強く反射していた。細めのネクタイを締めたスーツ姿は、廊下から叶井に声を掛けてきた男をなんとなく連想させた。
牧原はページを閉じ、雑誌をデスクの端に積み上げた。そして数ヵ月先の広告スケジュールを組み立てるためにExcelファイルを開いた。灰色のラインに区切られた掲載日、媒体名、料金、紙面仕様のセルを一つずつ目で追いながら、いつしか別のことを考えていた。牧原が書いた広告の文章を読んで、叶井は糖桑茶を買おうという気持ちになった。心が結合した感覚があったと言った。環心と結合したという意味だろうか。だが糖桑茶は効果を果たすことなく叶井は落胆し、牧原は糖桑茶を売ることができた。やはり互いの間の扉は閉じられており、環心とは関係のない個人的なことに由来しただけだったと叶井は微笑んだ。だが『やくそくの環』の記事を読む限り、環心とはあらゆる存在を流れていくもので、それに包括されない個人的なものなど存在し得ないというのが理屈のはずだ。彼女の話しぶりや落ち着いた態度から、入会してずいぶんな年月が経っているのは明らかだ。それでも、特にこれといった特徴のない広告文によって感応した叶井の個人的なこととは何なのか。広告制作の参考にできるかもしれない、と牧原の頭にふと浮かんだのは注射針の先端だった。誰の目も届かない場所で、ひっそりと洋服の裾を上げ、腰からやや上の腹部に向かって、冷たいインスリン注射を自ら突き刺す叶井の姿が思い浮かんだ。体内に流れこむインスリンをじっと見つめる彼女の姿も、いずれは環心によって一つに結合されるものなのだろうか。
牧原さん、DMの色校、確認してくれました? 加治木が立ち上がって、こちらに目を向けている。昨日すぐに確かめるからって言って、そのまま帰っちゃうし、と加治木は口を尖らせた。仙台での取材が空振りでショックなのはわかりますけど、人間が相手のことだし、そういうこともたまにはありますよ。新人くんが挽回しようと今日も取材に走り回ってますし、とりあえずあいつに任せておけばいいんじゃないっすか。牧原は『やくそくの環』に下に敷いていた色校正紙を引っぱり出し、昨日すでに赤字を入れていた箇所を確かめた。加治木、このままじゃまだ強すぎるよと立ち上がり、目前を漂うぼんやりとした塊を振り払うように加治木の席まで近づいた。「喉が渇いて」は「いつも飲み物がほしくて」に修正して「体重が落ちた」は「服のサイズが変わった」に修正してくれ。あと体験者の言葉以外は客観的に書くように。地の文で商品を勧めるようなことは書かないようにな。商品を押しつけるんじゃなく、商品が必要かどうかを考えさせるんだ。自分で決めさせた方が購買欲は高まるし、継続するんだからな。
加治木は受け取った色校正紙をサイドデスクに置き、キーボードを叩き始めた。加治木の後ろからモニターを見ていると、牧原に指示された箇所はあっという間に修正され、画像の細かい補正へと作業が移った。ミスタッチが一切ない素早い指の動きと、呼応して次々と切り替わるウィンドウに目を奪われていると、やはり世の中は合理性とスピードによって支えられている気がしてくる。小川とはうまくやってるか、と訊ねてみた。まあまあっすかね、加治木はモニターに顔を近づけてそう答えた。お互い正反対のタイプなんで根本的には合わないんですけど、小川の方が結構気を遣って話を合わせてくれるんで、まあ当たり障りなくやってますよ。この仕事は続きそうかな、と牧原が独り言のように呟くと、あいつはネット広告を積極的にやりたいみたいですねと加治木はこちらを見上げた。今、ネット広告を出していないB to Cの会社なんてどこにもないでしょ。なんでうちの会社は出さないんですかって息巻いてましたよ。単純に必要ないからだよって答えておきました。牧原さんの指針は人がやっていることを追うな、身の丈に合ったことをやれ、なんだぜって。今のやり方ならこの少人数の規模で充分食っていける、馬鹿の一つ覚えみたいに会社を大きくすることだけが優先事項じゃないぞって言ったら、小川の奴、納得いかなさそうに腕組みしてましたよ、そう加治木は小さく笑った。
加治木の笑い声は、まわりを一瞬白くした。書類が山積みにされたデスクが消え去った。灰色のキャビネット棚も、昼寝から目覚めたようにときどき震える複合機も、わずかな隙間に設えられたミーティングテーブルもすべて消え去り、真っ白な空間に立ち尽くしていた。立ち尽くす牧原は確かめるようにこちらを振り返った。そして音を立てないように鼻孔から息を吸いこんだ。加治木は変わらずキーボードをぱたぱたと叩いている。牧原はゆっくりと息を吐き出し、今日久しぶりに飲みに行くか、そう加治木の指先に向かって声を掛けてみた。あ、すみません、牧原さん、せっかくですけど今日は用事あるんすよ、と加治木はモニターに向かって抑揚なく答えた。なんだよと牧原は苦笑して立ち去ろうとした。もし良かったら、と加治木は振り返った。牧原さんも一緒にブラッキング行きます? 牧原は苦笑を張りつかせたまま、行かないよ、そう事務所の重いドアを開けて外へ出た。
日ごとに秋が深まり、吊り革を握って山手線の車両から窓の外を見ていると、夜の闇が街の光を煌々と際立たせていた。コート姿の人波に押されながら、最寄り駅で降りた。ロータリーから伸びる細い通りの商店街の手前で、中華と洋食と丼物のどれを夕飯にするか、数歩進むうちに決めるのがいつものパターンだった。その夜はすぐに決められなかった。あまり腹は減っておらず、老夫婦が営む中華食堂の暖簾をくぐって、餃子と野菜炒めと瓶ビールを注文することにした。テレビでは民放のクイズ番組が映し出されていた。何人もの芸能人が首を捻っていたが、答えが発表されると出演者は満足そうに頷いた。染みだらけの白衣をまとう妻はテレビを見上げてぶつぶつと呟いている。運ばれた料理を掻きこむように平らげ、店を出て、商店街を抜ける。二十代で初めて就職したときから住んでいる単身者向けマンションが見えてくる。エレベーターに乗りこみ、部屋のドアを開け、薄暗い明かりを点けて、黒いナイロン製の鞄を床に置くまで、牧原は誰かにしつこく引き止められているような重い手触りを胸の中にずっと感じていた。
牧原さんの指針、と加治木は口にした。人がやっていることを追うな、身の丈に合ったことをやれ──そんな台詞を加治木に対して言ったことがこれまであっただろうか。確かに通販の仕事を二十年ほど続けてきた中で、大きく変わったことはせず、商品を一つでも多く売るために目の前の仕事をただ粛々とこなすことが、事業を長く継続させるこつかもしれないと個人的に感じることはあった。だがその考えを誰かに対して、あるいは加治木以外の誰に対しても言葉で表明したことはなかった。加治木とは長い付き合いだし、一緒に酒を飲み、いろんな話をして、牧原のそんな姿勢がいつも漂う匂いとして彼にも染み移っているのかもしれない。ただ、あらためて誰かの口から牧原さんの指針などと名づけられると、いつの間にか面識のない他人がどこかで勝手に口にしている言葉のような居心地の悪さを覚えた。
熱めのシャワーを浴び、バスタオルで髪を拭きながら、指針などという大それたものと自分がいかに無縁に生きてきたかを牧原は思い返していた。自転車通学が可能な範囲で高校を選び、必死に受験勉強をせずとも入れる大学を選び、競争倍率が低い名のない健康食品の零細企業に入った。小さい頃から貧乏でも金持ちでもなく、他人の上に立つより他人のいない場所を好んだ。高級車に乗りたいわけでもなく、複数の女と遊びたいわけでもなく、都心のタワーマンションに住みたいわけでもない。人から与えられた仕事をこなし、制作した広告の一つがたまたま好調な売上を生んだ。そしてたまたま創業オーナーの引退時に名前を呼ばれて、たまたま会社の一つを任せられることになった。もちろん喉が枯れるほど腹が立ったことや、睡眠を惜しんだ努力が一切実を結ばなかったことや、まわりの誰からも背を向けられた経験はそれなりにある。だが感情が震えるほど切実なことが起こっても、牧原自身がどこかに傾き、ある一つの指針を頼りにすることはなかった。翌朝には何事もなかったような顔を鏡に写して、懸命に歯を磨いた。ただ、自分のことを牧原と三人称のように書き換えることで、いつもと変わらないバランスを保とうとしていた。
枕元のあるオレンジ色の常夜灯を点け、ベッドに横たわって眠りに入ろうとするとき、果たして自分のような人間が会社の代表に就いていて良いのかと疑わしくなるときがあった。たとえたった二人の社員でも、自分は彼らを先導していけるような人間なのかと。そもそもは先導される側のはずだった。多くの人たちと同じように先導されながら生きてきた。何が自分を先導してきたのか、と思いつき、体の向きを反対に変えると、仙台の会館で向かい合わせのソファに腰を下ろした叶井の姿がふと浮かんだ。長くまっすぐな黒髪を耳にかけている。紺色のカーディガンに通した両手を膝の上で重ね、揃えた二本の脚を少し斜めに傾けている。そして、分断、と唇が動いている。自分を牧原と呼ぶ牧原のことを、あなたは分断されていると告げている。たった一つの鍵で牧原さんの分断は開放されるのよ、叶井はそう言ってソファから立ち上がった。そしてカーディガンの釦を一つずつ外し、床に脱ぎ捨てると、中に着ていた白い長袖のシャツも脱いだ。それからジーンズのホックを外し、二本の脚を勢いよく抜き出した。叶井は下着をつけていなかった。そんなものは最初から必要ないとでもいうように、白い乳房と白い太腿と生えたばかりのような陰毛を堂々と差し出していた。注射の跡を探してみたが、叶井の腹は整地されたように真っ平だった。そういえば繰り返された注射痕など目にしたことがないことを牧原は思い出した。叶井は微笑を浮かべていたが、やがてベッドに横たわる牧原のそばまでゆっくり近づき、するりとベッドの中に滑りこんできた。冷ややかな風も一緒に入ってきた。シーツの中で温度の違う空気を攪拌しながら居心地の良い体勢を探り当てると、叶井は冷たい両腕を牧原の頭の後ろへ回した。そして顔を近づけ、きっと環心の手繰り寄せかもしれませんね、と唇を動かした。
それが夢だと気づいた翌朝、牧原はすぐに異変を感じた。呼吸がスムーズにできなかった。口元に手をやると、薄く乾いたものが鼻のあたりに張りついている。指を少し動かすだけで、ぱりぱりとたやすく剥がれる。目前のシーツは野球のボールほどに赤黒く汚れていた。上半身を慎重に起こし、再び手をやると、鼻孔の奥に小さな塊が留まっていた。おそらく鼻血だろうと牧原は口から息を吐き出した。自然に流れ出たものなのか、あるいは寝相で鼻の中を傷つけてしまったのか。とりあえず洗面所の鏡で確かめるため、ベッドから立ち上がった。少なくとも夢の中で叶井の指が鼻孔に入ってきた記憶は残っていなかった。
満員電車に閉じこめられている間も、牧原は昨夜の夢に引きずられていた。ベッドの中で叶井は裸だった。そして寝巻きのままの牧原を性的に導こうとしていた。叶井の手は牧原の体に触れようとせず、ただこちらの胸元に身を寄せて、じっと固まっているだけだった。だがそれでも性的な脈動がどくどくと搾り出されていく感覚が腰のあたりを巡った。だからといって鼻から流血するほど強烈な快感があったわけではなかった。むしろこれはごく自然なことなのだと静かに受け止めている自分がベッドの外からこちらを眺めていた。急ブレーキで車体が大きく傾いた。隣に立つ男がこらえる素振りもなくこちらに体重を預けてきた。体を後ろにずらすと、たがが外れたように男はバランスを崩して片膝を車両の床についた。
事務所のドアを開けると、加治木が自分の席のまわりで動き回っていた。おはようございますという小川の挨拶に反応し、加治木もこちらを振り返って頭を下げたが、すぐに資料の山をめくったり、机の下を覗きこんだりした。めずらしく朝から軽快なフットワークだなと声を掛けると、加治木は重そうな体を立ち上らせて首を捻った。いやあ、いくら探しても見つからないんですよ、代理店からの請求書。先月分をまとめてクリップで挟んで、確かに昨日帰る前に机の上に置いといたはずなんですけど、今朝来たらどこにも見当たらないんですよ。もちろん捨てたりなんかしてませんよ。ごみ箱は全部漁りましたけど、どこにも……加治木はそう首の後ろに浮き出ている汗を拭った。牧原は自席で上着を脱ぎ、腰を下ろして、パソコンを立ち上げた。加治木、支払い日はまだ先だけどさ、金額は前もって把握しとかなきゃいけないから、代理店に電話して再送してもらうよう謝っといてくれ、そう低い声で指示すると、わっかりましたと加治木は呟き、あっさりと席に着いた。
ぼそぼそとしか聞こえないくぐもった声で、加治木は次々と代理店に電話を掛けた。請求書の再送を頼むぐらい大したことではなかったが、向かいの席に座る小川は意味もなさそうに書類をめくりながら、背中を丸めている加治木の様子をひそかに窺っていた。散漫な態度の小川に昨日の取材はどうだったと訊ねようとしたとき、電話が鳴った。小川は我に返ったように背筋を伸ばし、受話器を取って応対し始めた。
請求書が机の上から消えたのは加治木の責任なのだろうか、と前日の出荷明細表をCSVに出力しながら頭をかすめた。新人の小川の前で加治木を叱責することなどは気にしない。ただもし引き出しの奥にでも厳重に押しこんでいたら、請求書は紛失されなかったのだろうか。たとえば牧原がたまたま経営者という立場にいるのと同じように、請求書はたまたま加治木の机の上で紛失されただけではないのか。幸福とはただの幸運で、不幸とはただの不運で、それらは誰の責任でもない──そんなどこにも当てがないような気分で牧原は頬杖を突いていた。他人の弱みを逃さないような小川の粘ついた視線にうんざりしたせいかもしれないし、昨夜見た夢に引きずられているせいかもしれなかった。ただその日、牧原の責任を持って為されるべき仕事はモニターの中に映し出されていた。糖尿病予備軍の増加は過剰な栄養摂取が日常的に増えていることを意味する。美味い食事とは糖分と脂肪分にまみれており、糖尿病予備軍の嗜好はこれに向けられている。糖桑茶の広告を出しづらくなるなら、高カロリーの美味い食品を会員に向けて販売し、糖桑茶の必要性をより切実に感じさせる。つまり血糖値を上げる商品と下げる商品を同時に販売して、顧客の購入単価を上昇させるのだ。そのためには希少性や高級性のある食品を提示して購買欲を刺激しなければならず、黒毛和牛の霜降り肉やドイツ産バウムクーヘンなどの候補商品の画像を画面に並べていた。
牧原社長、保健所からお電話ですとの小川の呼びかけに、クリックをしようとした牧原の指先が止まった。小川は通話を保留にしたまま、こちらの席まで小走りで近づいてきた。糖桑茶を飲んで体調を崩したというお客様から保健所に連絡が入っているみたいです、と小川は声のトーンを落とした。合わせて十件ほどらしく、衛生管理者の方から現状について聞き、いくつか質問をさせていただきたいとのことです。牧原は保留を解除して電話に出た。相手は落ち着いた声の女で、電話を掛けてきた理由を事務的に説明した。この三ヵ月ほどで糖桑茶による健康被害の通報が全国の保健所に複数入り、牧原の会社が登記する住所の保健所に情報が集約されたとのことだった。症状としては下痢、湿疹、頻尿、めまいが報告されている。ちなみに御社にはこういった話が消費者から直接届いておりますでしょうか? 届いていないと牧原は答えた。そうですか。いずれにせよ一度保健所に来ていただき、販売数量、製造方法、衛生管理、原料などについてお話を聞かせいただければと思います、女はそう言い、来所の日時を提案してきた。
牧原は電話を切った後、ネット上の社内カレンダーを開いて、一週間後の午後に保健所に出向く旨を入力した。小川が心配そうにこちらを窺っている。来週保健所に行ってくるよと牧原はわざと面倒くさそうに口にした。前にも一度あったんだ。うちが製造委託している工場は衛生管理を徹底してるし、原料についての検査資料を見せれば問題ない。ただ消費者個人との相性が良くなかったっていうだけさ、そう言うと、小川は何も言わずに頭を下げて、パソコンに向かい直した。加治木はすでに受話器を置いていたが、iMacの向こう側からは何の音も聞こえてこなかった。
その日、加治木も小川も定時を少し過ぎたあたりで退社した。都庁と保健所との二役所からの呼び出しで、それぞれ進めるべき業務を一旦停止させなければいけない状況だった。牧原も二人の銀行口座への給与振込を終えた後、パソコンの電源を落とし、電気を消して、事務所を後にした。駅までの道のりには小さな店舗がひしめいている。居酒屋やうどん屋や回転寿司屋や交番や風俗案内所の前を雑踏がうごめいている。人の固まりを避けながら、健康被害という言葉を思い出していた。小川に言ったことは嘘だった。過去に顧客から糖桑茶を飲んで頻尿になったとのクレームを直接受けたことはあったが、保健所から呼び出されたのは初めてだ。もし今回の件で健康被害が発生したと認定されれば、糖桑茶は販売停止にされ、さらに顧客からの回収作業を命じられて、顧客に返金する必要がある。最悪の想定だが、そうなる前に何か手を打っておかなければならない。
唐突に肘を引っぱられたみたいに、牧原は足を止めた。数秒前、あるいは十数秒前に、何かとすれ違った気がした。振り返っても、大学生ぐらいの若い男女が横断歩道の前で笑い合っているだけだ。何か、あるいは誰からしき姿は見当たらない。足元に視線を落としてばかりで通り過ぎてしまったが、どこか見覚えのある誰かと肩が触れるほど交錯した感覚が残り香のようにまとわりついていた。引き出しのことが気になった。そういえば振込作業の後、現金をしまっている引き出しの鍵をきちんと掛けただろうか──確信が持てなかった。牧原は踵を返して、事務所に戻ることにした。何かが起こったわけではないが、何も起こっていないまま帰宅することはもはやできないかのように背中が強引に押されていた。
ビルを見上げて、事務所の階に明かりが点いていないことを確かめる。ガラスドアを開けて、一階に止まっていたエレベーターに乗りこんだ。扉が開くまでに鞄の中から事務所の鍵を取り出そうとすると、上昇スピードが減速して、いつもよりもふわりと体が浮ついた。扉が開くと同時に、ホールに足を踏み出した。十分ほど前に立ち去ったときと変わらず消灯されたままだ。だが空気が違った。冷たい空気と温かい空気が混じり合い、微かな対流が舞っている。壁のスイッチに手をやり、明かりを点ける。手にした鍵をノブの鍵穴に差しこみ、解錠の音を確かめる。ドアを開けると、長い影が仕事場に横たわっていた。どのモニターも真っ暗で、複合プリンターのスリープランプだけが虫のように点滅している。蛍光灯を点けて、いつもの昼光色に照らされた窓際の自席に目を向けた。そこに誰かが座っている。24インチのiMacの向こうに隠れ、肩のラインだけを見せた誰かが座っている。牧原は物音を立てないようにゆっくりと奥へ進んだ。視界の角度が次第に広がり、まっすぐ伸びた背筋とぴんとした鼻尖があらわれても、その者は姿勢を変えたり、逃げようとしたりしなかった。牧原の席に座っていたのは叶井真言だった。
牧原との対峙を正面から受け止めるかのように、叶井は椅子のキャスターを使って、体ごとこちらに向けた。長い髪は黒いニット帽に収められ、まずは牧原の反応を待っているみたいに口角を微かに上げている。上下のジャージは目立たない紺色で、ファスナーは首元まできっちり閉められ、膝の上で重ねた手には薄い生地の手袋が嵌められている。仙台で会ったときと同じように両脚は品良く揃えられていたが、紐のないゴム靴はそぐわなかった。
ドアの鍵は掛かっていました、そう牧原は口にした。エレベーターも一階に下りたままだった、と独り言みたいに呟いた瞬間、鍵は内側から閉めたのだろうし、エレベーターを降りる直前に一階のボタンを押したのだろうと思い直した。誰も事務所の中にいないと思わせ、誰もエレベーターを使っていないと思わせるために。
牧原さん、と叶井は椅子に座ったまま、こちらを見上げて呼びかけた。鍵なんて本当に何の意味もないんですよ、少なくとも私にとっては、叶井はそう言って事務所を見回した。だけどまさか牧原さんが戻ってくるとは予想していませんでした。さっき道ですれ違ったときに気づかれたのかもしれませんね。どうでしょう、もう警察を呼ばれますか、と叶井は頬を緩ませて首を傾けた。牧原は胸に手をやり、ジャケットの内ポケットにスマホがあることを確かめた。だが取り出すことはせず、息を大きく吐いてから訊ねた。ここで一体何をしているんですか、叶井さん。馬鹿な質問だったが、訊ねないわけにはいかなかった。叶井はまだ糖桑茶を買っている客なのだと思っていた。叶井はすぐに答えなかった。再びあたりを見渡しながら、ずいぶんと物が多い職場、と言った。私が昔働いていた職場もこんな感じでした。いろんな物が乱雑に積み重なってて、なんだか懐かしいです、そう叶井は息を吐いて、肩を落とした。そして、私がここで何をしているか、と牧原の質問を繰り返した。それは今ここではお答えしかねる内容です。牧原さんが私の格好を見て、私が誰もいなくなった暗い事務所に一人でいる姿を見て、私が一体何をしようとしているのか、もちろん牧原さんにはすでに想像がついているはずです。ただ申し訳ないですが、今ここでそれを明確に言葉で表すことはできません。なぜなら私はまだ現実的に警察に連行され、事情聴取を受けているわけではないから。
牧原は叶井に視線を合わせたまま、後ろにあったシュレッダーの上に腰を下ろした。叶井の姿勢は話している間にやや崩れていた。牧原の椅子に浅く腰を掛け、前屈みになって、少し開いた脚の間に両手をだらりと垂らしている。足元にはエコバッグのようなものが置かれていた。黒くて小さく、押し潰されたようにくしゃくしゃに丸められている。仙台のショッピングビルの出入口で渡した名刺の住所を使って、ここまでやってきたのだろうと牧原は思った。もしかしたら初めからそのつもりで取材を受けたのだろうか。あるいはそもそも一年前、そのつもりで糖桑茶を注文する電話をかけてきたのだろうか。叶井はこちらの足元あたりに視線を落としていた。自分の一部だと話していたインスリンの注射器とブドウ糖は、ちゃんとエコバッグの中に入れられているのだろうか。
ご覧のとおり、うちはしがない会社です、と牧原は切り出した。メンテナンスが滞った古い雑居ビルの小さなスペースで、私を含めた三人だけで業務を回しています。紙の資料が散乱している中で、今どき煙草を吸いながら仕事をしています。昨日は担当者の机から請求書がなぜか丸ごと失くなりました。飲み会は毎回居酒屋チェーン店の飲み放題コース。そんな取るに足りない零細企業に、人から羨ましがられる物が保管されているとは誰も思わないでしょうし、叶井さん自身も実際にここに入ってみて、落胆されたかもしれません。自分で言うのもなんですが、金目のものは多少の小口現金ぐらいです。しかも法を犯すリスクに見合うほど高額ではありません。もちろん叶井さんは何にも触れていないし、何も手にしていないかもしれない。だけど他人が借りている事務所に勝手に侵入したというだけで警察を呼ぶには充分な理由だと牧原は思っています。
牧原、と叶井は反応したが、すぐに視線を下げた。窓の外から強いブレーキ音が聞こえた。男の怒鳴り声が響き、低いエンジン音が唸りながら遠ざかっていった。その間叶井は視線を上げなかったが、やがてニット帽を脱いだ。そして念入りにまとめられた頭からピンを一本ずつ取り外し、水のように流れ落ちる長髪を何度か指で梳かした。
なぜ私が逃げようとしないのか、そういった疑問を牧原さんは今お持ちでしょう、と叶井は姿勢を正し、こちらを見据えた。平静さを示そうとする叶井のあらたまった表情を牧原はただ見つめた。仙台で言ったはずです、と叶井は続けた。もし再びお会いすることがあれば、環心の手繰り寄せかもしれないと。もし本当にそうであるなら、私と牧原さんを分断する扉は開放されて、二人とも同じ流れを流れていくことになる。そんな相手からもはや逃げることはできないでしょう。
便宜的な説明をするなら、私は仕事のために今この場所にいます。かといって牧原さんの事務所に入ってこいと誰かに依頼されたわけではありません。ビジネスとは売り買いであり、私は私の売るものを手に入れる必要があります。それを売って、生活を成り立たせる必要があります。叶井はそこまで言うと、椅子から立ち上がった。両腕をぴたりと体に沿わせ、片足をわずかに後ろに引いて、踵を揃えた。その立ち姿は一瞬、夢の情景を思い起こさせた。服をすべて脱ぎ捨て、ベッドの前で一糸纏わぬ肉体をあらわにしている叶井の姿──牧原も無意識にシュレッダーから立ち上がった。
先ほども言ったように、私にとって鍵というものは意味を成しません、と叶井は言った。そのことが私に役割を与えています。こんなふうに鍵の掛かった場所に入る仕事を与えているのです。そして牧原さんも私に依頼することができます。鍵の掛かった扉の向こうに牧原さんの手に入れたい何かがあるとき、私は牧原さんの代わりにそれを手に入れることができます。たとえばセキュリティが厳重に掛かった部屋から巨大な黄金の像を持ってこいと頼まれたら、かなりのプランを練る必要はありますが、おそらく大体は実行可能なケースでしょう。
叶井の背後には牧原の机があった。机の上には二人の話に無関心な態度を示しているマウスがあり、電話機があった。ふと保健所からの電話を思い出した。
叶井さん、と牧原は言った。はい、と叶井は答えた。あなたはさっき、環心と言った。つまりこういったあなたの行為はあの会が関係していると考えていいんでしょうか。会から組織的に指示されているということなんでしょうか。
叶井は遠くを眺めるように目を細めた。牧原の体を通り抜けて、もっと先にあるものを見定めようとする澄んだ瞳だった。牧原さん、それは間違った推測です、と叶井は落ち着いた声を出した。私のこの仕事に会は一切関知しておりません。私の仕事は、私の個人的なものに由来するものです、叶井はそう長い髪をかきあげた。
牧原は少しだけこちらを振り返り、何かを確かめるように目を細めた。
一週間後の午後、牧原は地下鉄に乗って、保健所へ出向いた。通された部屋には四人掛けの机があり、電話を掛けてきた女と、話の内容を筆記する若い男が、牧原の前に並んで座った。女は最初から眉をひそめ、居心地の悪そうな表情を浮かべていた。具体的にどういった体調の変化がお客様から届いたのでしょうか、と牧原は訊ねた。女は芝居掛かった手つきでファイルのページを何度も前後にめくったが、目当ての書類はやはりどこにも見つからないみたいだった。十日ほど前に各保健所から報告書が届いていたんですが、申し訳ありません、ちょっと今手元になくて……と女は隣の男を横目で睨んだ。どうやら男がファイルの管理担当者のようで、決して視線をペン先から上げようとしなかった。結局工場の衛生管理証明書を女に提出しただけで何事も起こらず、牧原は十五分ほどで保健所から立ち去ることになった。
再び地下鉄のホームから、会社と反対方向の電車に乗った。大手町で降り、複雑な地下の通路を上がったり下がったりしていくと、巨大なオフィスビルの真下に出てきた。地上から一階ぶん下がった広々としたスペースに常緑樹の植えこみが均等に配置され、弁当を食べたり休憩したりするためのベンチが備えつけられていた。叶井真言を見つけることはすぐにできた。髪を後ろで簡単にまとめ、ベージュ色のコートを着て、膝の上に載せたバッグを両手で抱えてベンチに座っている。牧原の姿を認めると、ほんの少し頷いた。バッグの持ち手にぶら下がっている何かが小さく反射した。
牧原は隣に腰を下ろし、ひとまず保健所でのことを叶井に伝えた。結局話は何も進みませんでした。証拠となるべき書類が見つからなくて、先方としては梯子を外されたみたいにどこにも行き場がない感じでした。健康被害とか販売停止といった言葉は出てこず、こっちの話もほとんど耳に入っていないようだったし、最後にはわざわざご足労いただきと深々と頭を下げられました。叶井は遠くのベンチに座る制服の女性社員たちに視線を向けながら、ときおり黙って頷いた。そして思い出したように、久しぶりにFAXの粗い印字を見ました、と鼻尖に指を当てた。昔から役所って横割りの連携に弱くて、保健所同士のやりとりって今でもFAXを使っているんですね。びっくりしました。ただ送信元には原本の書類が残っているはずだから、これで今回の件が無事に終わったとはまだ判断できませんよ。きっともう一度送信してもらうでしょうね、叶井はそう牧原の顔を覗きこんだ。そうなったときはまた考えます、と牧原は答えた。ただ何百件もの苦情が寄せられているわけじゃなく、こっちは規模の小さい会社だし、保健所の方は今感染症の増加でパンクしそうでしょう。今回の件は急いで対応しなきゃいけないことなのか──もし呼び出しの電話がまた掛かってくるとしても、ずいぶん先のことだと想定しています。いずれにせよ最初の段階で相手の動きを止めることができたのは助かりました。
顔を上げると、何棟ものビルに包囲されている空が見えた。ふと、自分たちが巨大な円状の塀に囲まれているような錯覚に包まれた。もし、と牧原は叶井の横顔を見た。今回のようなことがまた必要になれば、そのときはあらためて依頼することは可能ですか、そう訊ねると、叶井は言葉を選ぶように視線の先をずらした。そうですね、牧原さん。今回は例外的に金銭を発生させない条件でお互いが合意しました。私が保健所から書類を手に入れる代わりに、牧原さんは警察に通報しない。牧原さんが警察に通報しない代わりに、私は書類を手に入れる。ただ本来は金銭によって依頼を受けるものだし、今後牧原さんとも金銭による仕事のやりとりをすることは理屈としては可能です。ただ参考情報として言うなら、私に仕事を依頼するリピーターはまずいない。お客様は皆様、いわゆるまともな人たちです。牧原さんも言いましたよね。お客様は相手を選ぶけど、私もお客様を選びます。仕事や生活や色恋で行き詰まった方たちが、最後にどうしようもなく出す切り札のカードとして、私に仕事を依頼するんです。そういう方たちは一回きりの依頼なんです。牧原さんのお客様にはリピーターが多いでしょうけど、私のお客様はその場限り。私と関わったことを忘れたいように連絡してこないし、同時に私自身、足がつかないためにあえてそうしている意図もあるの。牧原さん、わかってくれますよね。
そう叶井がこちらを振り向いたとき、軽い金属音が小さく響いた。叶井のバッグに付いているアクセサリーだった。ちょうど指輪ほどの大きさのリングが二つ、絡み合いながら金色に光っている。わかりました、とたやすく答えようとする牧原を何かが引き止めた。牧原はただ頷いた。確かに今、扉の向こうに叶井はいる。叶井の姿は向こう側に見えている。だがそれが開かれようとしている扉なのか、それとも閉じられようとしている扉なのか、いずれかわからないまま牧原は何度か頷くだけだった。
血糖値の状態はどうですか、と牧原は話を変えた。叶井は不思議そうに目を見開いたが、最近はそれほど変わらずに過ごせてます、と微笑んだ。でも実は血糖値のせいだと思うのと呟いた。何がですかと牧原は訊ねた。叶井はコートの袖を手元に引っぱった。普段ならあんなミスはしなかった。路上で相手の関係者とすれ違ったり、現場で見つかったりするなんて初めてのこと。今回は依頼じゃなくて、自主的な仕入れだったから、緊張感が少し低かったかもしれない。シニアの個人情報を欲しがる人は多いから、あらかじめ手に入れておこうと思ったの。でもそれだけじゃない。きっと食事と注射のタイミングがどこかでずれて、あの日の血糖のバランスが狂ってしまって、集中力が落ちたんだと思う。だってちょっと目の前がふらついていたから。それともたんなる歳かな、と叶井はバッグを抱え直した。たまにふらついたり? と牧原が訊ねると、叶井は首を横に振った。何か言おうとしているのか、しばらく間を空けていたが、まあずっと付き合ってますからね、と叶井は一言だけ口にした。そして鞄のチャックを開けて、白い封筒を取り出した。はい、これ。受け取って中身を取り出すと、三つ折りにされた書類が十枚ほど重ねられていた。それぞれのヘッダーには静岡、岐阜、大阪の保健所名が書かれ、具体的な苦情内容が記されている。牧原はざっと目を通し、ありがとうございますと礼を言った。
叶井は立ち上がり、コートの皺を伸ばした。鞄を手にして、背筋をまっすぐ整えると、そうだ、糖桑茶に使っている桑の葉ってどこで栽培されてるんですか、と訊ねてきた。島根ですと牧原は答えた。江津市にある畑で、電車でも飛行機でもかなり行きにくいところですよ。へえ、と叶井は何度か頷いた。一度行ってみたいな。糖桑茶は効かなかったけど、江津の桑畑は一度見てみたい、もちろんプライベートですよ、今のところは、と叶井は駅の方に続く階段の方を振り返った。
もう仙台に帰るんですか、と牧原も立ち上がって訊ねた。叶井はすぐに答えず、そうね、と目線を外して濁した。もうそろそろ引っ越そうかなって思ってたところだし、仕事柄いろんな土地を転々としなきゃいけないし。牧原は手にしていた封筒をジャケットの内ポケットに入れた。正直なところ、と切り出した。牧原の会社がやっていることもグレーゾーンの商売です。いつ法令違反で取り締まれてもおかしくない仕事です。もし何か必要な事態になれば、そのときはちゃんと金銭を発生させて依頼させてもらいたいと思っています。だからこないだ教えてもらったアカウントは変えないでくださいね。
叶井は何も答えず、深々と頭を下げた。牧原さん、とこちらの目をじっと見つめた。次にまたお会いすることができれば、今度こそ本当に環心の手繰り寄せだと思います。そのときには牧原さん自身も同時に開放されている、そうであることを祈っております。あ、そうか、と叶井は一瞬空を見上げた。私が見つかったのは、たぶん牧原さんの気配のせいだ。だって牧原さんってびっくりするぐらい気配のない人だから。私みたいな仕事に向いてるかもしれませんね、そう言うと、叶井は背を向けて、地下鉄への階段を下っていった。叶井の姿が消えるとき、リングの金属音が一度だけ小さく鳴った。
会社のパソコンで顧客管理システムを開き、叶井真言の履歴情報を確かめてみた。電話番号は090から始まるもので、住所は仙台市から変更されていない。半年ほど前にコールセンターとの応答を記録した内容には、住所変更を受け付けたという旨が残っていた。仙台市から前の住所はすでに消去されている。おそらくこの携帯電話の番号も間もなく不通になるのだろうとウィンドウを閉じた。
カレンダーは十二月に変わっていた。大手町のベンチで別れてから、叶井にメッセージを送信することはなかった。返信がなかったり、メッセージ自体を送信できなかったときのことを想像すると、スマホを操作する指はためらわれた。叶井は今どこにいるのだろうとマウスを適当に動かした。新しい町の新しい部屋に移り住み、どこかの扉をたやすく解錠しているのだろうか。誰もいない部屋でインスリン注射を打ち、何かに対して祈りを捧げているのだろうか。叶井が所属している宗教団体のホームページを見ると、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の都市には大人数を収容できる会館が建てられているようだったが、それ以外にも点在している小さな集会所の場所については何も記載されていなかった。もしかしたら、と一瞬よぎった。この宗教団体に所属していることさえ、叶井の仕事にとってのフェイクなのかもしれないとマウスを回す手が止まった。
賞与を振り込んだ翌日だった。遅めの昼食を済ませて、事務所のドアを開けると、小川が加治木に対して突っかかっていた。何で勝手にキャンセルしたんですか、と小川はパソコン越しに加治木に声を荒げていた。当たり前だろ、誰にも許可されていないんだから、と加治木はモニターに向かってキーボードを打ちながら、冷ややかな声で答えた。牧原は事の経緯を見計らおうと黙って自席に腰を下ろした。
どうやらDMの入稿窓口である小川が色校正紙を印刷会社に戻す際に、糖桑茶のランディングページのQRコードを勝手に紙面に追加したようだった。気づいた加治木はネット広告に糖桑茶が掲載されていることを発見し、小川に問い質した。小川は社内の承諾なくネット広告の代理店に発注し、自力で糖桑茶のランディングページを作り、少しでも売上成果を出すためにDMからも顧客がアクセスできるようにしたとのことだった。
別に会社に不利益を被らせることをしたわけじゃないですよね、と小川は食い下がった。むしろ売上を上げるため、会社のためにしたことですよ。リスクはないに等しい。QRコードを載せることで顧客の購入経路を増やせるし、ネット広告の掲載料は成果報酬型なんで、クリックされなければ広告料はゼロです。会社にとってどこにもマイナスはありませんよ、そう小川は加治木を睨みつけた。そんなに前向きな話ならちゃんと説明すればいいじゃん、と加治木は頬杖を突きながら答えた。俺にも牧原さんにもちゃんと話してさ、こういうことをやりたいって言えば良かったじゃん。なんで言わなかったのか、そこを問題にしてんだよ。なんか疚しいことでもあるんじゃないかと当然こっちは勘繰るよね、加治木の抑揚のない話し方に、小川はますます表情を固くして反論した。なんで言わなかったか。そりゃあもちろん言いたくなかったからですよ。言ってもどうせ、駄目だ、やらない、の一言ですぱっと断ち切られるだけですからね。保健所からの呼び出しがお咎めなしだったし、僕としてはできるだけ早く売上を回復させなきゃいけないって必死だったんですよ。それなのに加治木さんは何もしないし、何も変えようとしない。一日中パソコンの画面を睨んでるだけのぶら下がり社員。小屋に閉じこめられて死ぬまで餌を食わされてる豚と同じだよ。
椅子が倒れそうなほど、加治木は勢いよく立ち上がった。手にはテープ台が掴まれていた。やめろと牧原は止めにかかった。だが遅かった。加治木は小川の席まで迷いなく近づき、小川の脳天めがけてテープ台を振り下ろした。牧原はぶつかるように後ろから腕を回して、加治木を押さえつけた。加治木の荒立った息が牧原の手を湿らせた。首筋からは何日も風呂に入っていないような汗の匂いが漂った。小川は動かなかった。椅子の上で上半身を折り曲げ、頭を両手で抱えたまま、次の行動をどう取るべきか思案しているみたいだった。よく見ると、手の甲が赤みを帯びている。頭には直接打撃を受けなかったのかもしれない。大丈夫かと声を掛けようとした瞬間、小川は立ち上がった。何も言わず、こちらに一切目を向けることなく出口まで進み、ドアのノブを掴んだ。おい小川、と牧原が呼び止めると、小川は立ち止まり、五分後に戻ってきますよと静かに言って、事務所を出ていった。
加治木を着席させて落ち着かせていると、小川がレジ袋を手にして戻ってきた。無表情のまま、まっすぐ自分の席に向かって腰を下ろすと、レジ袋から便箋を取り出し、素早くペンを走らせた。わずか一分ほどで書き終え、便箋を三つ折りにたたみ、一緒に購入してきた白封筒に収めると、雑な字で「退職届」と表に書いた。そして立ち上がり、今この瞬間辞めさせてもらいます、と牧原に封筒を差し出した。小川の顔からは興奮が抜け落ちていた。しがみついていたものが吹き飛んだ後の水平線が引かれていただけだった。
初めからこういうつもりだったのか、と牧原は退職届を手にして訊ねた。小川は視線をずらして、少し首を回した。牧原社長には気づかれるかもと思いましたが、やっぱりその通りでしたね。ちょうど昨日がボーナスの日でしたし。牧原は小川の目を見据えた。辞めたければ、大人しく辞表を出して辞めればいい。わざわざこんなことを引き起こさなくてもいいだろう。小川は床を見つめたまま、体を傾けて、片方の口角を上げた。いやあ、それじゃあつまんないなと思いまして。僕としてはなんとか一撃を喰らわせたかったんです。このままじゃこの会社は潰れますよって示してあげたかったんです。だけどまさか加治木さんから一撃を食らわせられるとは正直予想していませんでした。大丈夫です、ネットに拡散したりはしませんよ。それじゃあほんとに短い間でしたけど、お世話になりました、小川はそう頭を下げると、手にした鞄を肩の後ろで背負うように持ち、事務所のドアをがたんと閉めて出ていった。
その夜、牧原は加治木と二人で居酒屋に入った。忘年会シーズンということで四、五人の店員が忙しそうに動き回っていた。グラスを傾ける客たちは大声で笑い合ったり、納得できないように眉を吊り上げて熱弁を振るったりしていた。牧原たちはタイミング良く空いた奥のテーブルに通された。近いうちにこんなときが来るのをわかっていたみたいに、加治木は突き出しの枝豆を一つずつ吸い上げていた。変に欲かいて人を増やしたりしない方が良かったですね、と加治木は枝豆を手にして呟いた。別に欲をかいたわけじゃないよ、必要に迫られただけだよ、そう牧原は答えた。それから小川の話は出なかった。その代わり小川がアポを取っていた客への取材にどう対応するかという事務的な話を交わした。僕、行きますよ、加治木がそう言ってハイボールのジョッキに口をつけた。口に含んだ液体が喉元を通り過ぎていくのを見てから、たぶん五件ほどあるぞと牧原は返した。全然オッケーっす。五件とも僕が行きますよと加治木は即答した。なんで牧原さんは僕に取材を任せないんだろうと思ってましたよ。僕もね、変わったんです。ブラッキングで成長できました。見映えとか表面的な肩書きに惑わされず、その人の本質に向けて話をするってことの大切さを知りましたよ。牧原は煙草に火をつけた。人間的に成長した奴が事務用品で人の頭を殴るかよと笑った。
注文した料理がテーブルに出揃ったとき、そういえばと加治木が切り出した。ちょっと前にブラッキングの店に行ったときなんですけど、そのときの女の子のことを僕まだ憶えてるんですよ。話し方が機械みたいで、ずっと敬語で、しっかりとした過不足ない文法っていう感じで喋ってくるんです。そういう固い優等生タイプは嫌いじゃないので、オプション代追加するから部屋ちょっと明るくしていいって訊いたら、それだけは申し訳ございません、ご遠慮願いますって。何度か交渉したんですけど、どうしてもうんと言わない。じゃあわかった、その代わり普段は何の仕事をしてるのかだけ教えてって頼みました。牧原は三杯めのハイボールを飲み干そうとしていた。やっぱり真っ暗で何も見えないと少しの情報でも想像力が刺激されるものなのかと適当に言葉を挟んだ。確かにそうなんですよねと加治木は大きく頷いた。それで相手はためらってたんですけど、結局都庁の薬務課で働いてるって教えてくれました。今でも現役? って訊いたら、もう一年以上は経ちますって。それ聞いて、仕事柄こっちもぐんぐん勃ってきちゃって。いやあ、あの夜は盛り上がりましたね。
女はテーブルを前にして座っていた。首元で髪をきつく結んで、丸い頭をこちらに向けている。ノートを広げ、ペンを細かく動かしている。覗いてみると、首から下は本当に修道女が着るモノトーンの衣装をまとっていた。法律の外側に本当のことはなかったんじゃないのか、お前は法律と結婚しているんじゃなかったのか、そう問い詰めた。ええ、そうですよ、と女はノートから顔を上げずに答えた。副業は公務員法に抵触するだろうと覆い被せた。ええ、だからブラッキングで働いている私は本当の私ではないということです。法律の外側にいる私は本当の私ではないということです。女はノートにも同じように書いていた──法律の外側にいるのは本当の私ではない、と。牧原さん、と女はペンを止めた。だって牧原さんがしていることも、本当の牧原さんがしていることではないんでしょう。書類を盗み出してもらったことだってそうです。本当でないものは取り締まられなければなりません。
加治木は女の横に座っていた。体を寄せて、女の書いているものを一緒に目で追っていた。女の肩に手を回し、ときおり耳元で何かを囁いている。そのたびに女と加治木はこそこそと小さく笑い合った。加治木の息も女の息も臭かった。真夏のエレベーターに閉じこめられたような酸っぱい匂いを漂わせていた。加治木は女から修道女の衣装を一枚ずつ剥ぎ取っていった。女は下着をつけていなかった。裸のままテーブルに向かい、やはりメモを取り続けている。加治木は太い指で女の顎を掴んだ。そして強引に唇を重ねた。豚の鼻先同士が体液を垂らしながら絡み合っている姿だった。女の痩せた乳房を撫で回し、女の乳首を刺激する加治木の指先はキーボードを打つように駆けずり回っている。
本当でないものは取り締まられなければならない、と女は言っていた。ベアリングボールのような硬いざわめきがどこかで回転している。いや、ざわめきは自分自身だと思い直した。テーブルの上にはテープ台がある。蛍光灯に反射している金属製だ。持ち上げてみると、ずしりと指の肉に食いこんだ。だが片手で振り被れないほどでない。女の乳房に顔を埋めている加治木の後頭部をめがけ、勢いよく振り下ろすには充分な役割を果たしてくれた。鈍い音と共に、加治木の脳天は縦にぱくりと割れた。なかでは大量の赤黒い虫たちが慌てふためいている。動きを失くした加治木の体を蹴飛ばし、次は股を開いたままの女の顔をめがけて、テープ台を何度も振り下ろした。女の顔は低反発性クッションのように内部にめりこみ、中心からは鮮血が水のように吹き上がった。もはや女が本当の女自身なのかどうかは、どっちでもよくなった。
その様子を牧原がじっと眺めていた。新幹線のリクライニングシートに身をあずけ、眠そうな目をして、手に持った歯ブラシで歯を磨きながら、こちらのざわめきを黙って観察している。そうだ、この男こそが殺すべき相手だった。テープ台を振り下ろすべき相手だった。乗客は他にいない。大股で通路を進み、牧原の座席まで近づいていく。そのとき、明かりが落とされた。視神経が切断されたように突然何も見えなくなった。こちらの動きを停止させ、束縛する完全な闇だ。おい! と声を張り上げる。牧原が近くにいるのかどうか見当がつかない。その代わり白湯のような柔らかい声が耳を打った。ここではそんなに大きな声を出さなくても大丈夫ですよ、と声は囁いた。聞き覚えのある声だったが、薬務課の女ではなかった。あなたが話したい相手はそこにいます。いつもすぐそばにいるのです。あなたが話しかけさえすれば、相手も話してくるはずです。
掴んでいるテープ台は汗でじっとりと濡れていた。どういった言葉を掛けるべきなのか。それはおそらく簡単な言葉のはずだ。闇の中で鋭く光る金属の固まりのように。
「本当は俺のはずだろ。その席に座っているべきなのは」
返事はない。唾を飲みこむ音が闇の中で拡大する。息を深く吸いこみ、もう一度口にする。「おまえじゃなく、俺がそこにいるべきなんだ」
「……そうだったかもしれない」
牧原はそう答えた。扉の奥から聞こえてくるような、くぐもった声だった。「でもずっとこうして生きてきた。別に意図したわけじゃない。指針なんてない。たまたまこうなっただけなんだ。どちらのせいでもない」
「本当にそうなのかな。いつからか俺を扉の奥に閉じこめようとしてきただろ」
「それは叶井真言が言ってたことの受け売りだな」長い息を吐く音が聞こえた。「たぶん同じことなんだよ、いずれにしても。お互いの場所が入れ替わろうが、場所そのものがまたお互いを作り替えていく。結局どっちもどっちなんだよ。修道女が言ってたこともそういうことさ」
牧原の声は疲労が溜まっているみたいに萎びていた。朝起きて、空を横切る鳥を見上げ、沈む夕日に目を細め、暖かいベッドに入って深い眠りにつく。そんな毎日を繰り返すうちに、自らの意識が平穏に閉じていくのを願うような話し方だった。そうなったのはこちらの責任でもあった。牧原をいつまでも殺そうとしなかったこちらの責任だった。ふと、頬を微かに打った。生ぬるく、ささやかなものが頬を伝った。流れていたのは涙だった。哀しいわけではなかった。体の中の熱く硬いものが涙を流させ、手を前方に差し出させていた。手の先は冷ややかなドアノブに触れた。強く掴み、開けようとした。しかし鍵が掛かっている。いくら回しても、ドアは開かない。鍵は一つしかありません──叶井はそう告げた。世のあらゆる扉はたった一つの鍵で開かれます。だからそもそも鍵に意味などないんです──闇は次第に薄まろうとしていた。遠くに揺らめく微小な点。それは赤い光を放ち始めた。周囲の闇を飲みこんでいき、蝕むように拡大した。闇は無力なほど追いやられ、やがて巨大な光源が毎朝頭上に姿をあらわすように、赤い光はそこにあるすべてを包みこんでいった。
はっきりと意識を取り戻したのはベッドの上だった。枕から頭を浮かした瞬間、脳の中心が焼けただれているかのようなひりひりとした頭痛が走った。浴びるようにハイボールを何杯も飲んだ後のことは憶えていない。どのように自宅まで帰ってきたのかという記憶もきれいに抜け落ちている。確か加治木がいろんな種類の風俗店について話し続けていたと横になりながら思い出した。それほどの酒量ではなかったのに、酔っ払ってしまったのか。記憶を失くすほど酒を飲むなんて信じられなかった。しかし思いきって上半身を起こしたときに再び激しい頭痛を覚えた。ベッドから立ち上がったときにめまいに襲われ、胃は伸び切ったように重く、左脚の脛に青い痣ができているのを発見すると、やはり二日酔いによる体調不良だと認めざるを得なかった。
洗面所の鏡の前に立った。髪はぼさぼさで、瞼はむくみ、頬にはうっすらと影が落ちている。まるで誰かと喧嘩でもしたようなひどい顔をしていた。だがいくら我を忘れるまで酒を飲んでいようと、鏡に映っている男は紛れもなく牧原だった。そのことを一応確かめてから、牧原は歯を磨き始めた。
年の瀬が迫った厳しい寒風は牧原の崩れ落ちそうな頭と体を引き締めてくれた。満員電車の吊り革を握っていると、肩を寄せ合う無関心な人々の距離感がどこか居心地良く感じられた。事務所のビルに着いたとき、すでに十時を過ぎていた。エレベーターから降りると、ホールの電気は点いておらず、ドアの鍵は閉まっていた。予想はしていた。おそらく加治木も同じぐらい酒を飲んだはずだ。決してアルコールに強くない体質のことを考えると、あいつは今ごろ便器に向かって嘔吐しているのかもしれない。牧原はドアを開け、事務所の蛍光灯を点けて、しんと静まっている空気に身を馴染ませるよう音を立てずに席に着いた。
ルーティンワークの前に、牧原は社会労務士に電話を掛けた。小川が退職したことを伝え、社会保険の喪失手続きや離職票を発行するまでの手順を確認しなければならなかった。小川は保険証と会社の鍵を机の上に律儀に並べて、事務所を出ていった。わずか三ヵ月ほどの在籍だったが、小川が会社を辞めた気持ちが牧原にはわかる気がした。自分が求めるものはこの会社にはない、そんな場所で貴重な時間を無駄に使うわけにはいかないと早々に判断して、行動に移した。きっと小川は自分が求めているものを明確に知っていて、そのために次々と扉を開けていくタイプなのだろう。先導されるより、先導していく者。そして先導するべきでない者によって自分が先導されることに我慢ができない男だ。きっとそのうち自分で事業でも立ち上げるのかもしれない。
年末に高まる世間の購買欲は牧原の会社にも多少の好影響を及ぼしてくれたようで、売上の集計作業が終わったのは昼前だった。事務所には牧原がパソコンを操作する音しか響いていなかった。牧原は加治木に電話を掛けてみた。しばらくスマーフォンを耳に当てたまま壁の時計を見上げていたが、コール音は鳴り続けた。一旦終話ボタンを押し、もう一度呼び出したが、コール音は空しく吸いこまれていくばかりだった。念のために状況を確認するメッセージを送信した。加治木が何かの事故に遭ったとは考えにくかった。昨夜別れた後に事故に巻きこまれたとしても、加治木の鞄には名刺も保険証も運転免許証も入っているだろう。もし救急車で運ばれて警察沙汰になっていれば、会社に電話が掛かってくるはずだ。それとも家に到着した後に体調を崩して倒れたのだろうか。心臓発作、脳梗塞、急性アルコール中毒。もしかして部屋に潜んでいた強盗に襲われ、頭をぱっくりと割られたかもしれない。傷口から血が流れ落ち、虫たちが這い出しているのかもしれない。牧原の手に汗が滲んだ。ある存在に起こったことは同時にあらゆる存在にも起こっているのです、そんな誰かの言葉が思い浮かんだ。誰なのかは思い出せなかった。ただ加治木を襲ったのはまるで牧原自身であるかのような感触だけが手の中で渦巻いていた。
加治木の自宅アパートへは何回か路線を乗り換えないといけない。牧原は事務所を出ると、大通りまで駆けていき、タクシーを止めた。そして加治木が住むアパートの住所を運転手に伝えた。道路が混んでいなければ二十分ほどで着けるはずだった。牧原は後部座席のシートにもたれ、スマーフォンに視線を落とした。加治木へのメッセージに既読マークは付いていない。大きく息を吐いてから、窓の外に目を向けた。遅々として進まない道路状況ではなかったが、工事によって何ヵ所か車線規制されており、合流地点ではどうしてもスピードが落とされた。安全第一と書かれた黄色と黒色のフェンスが何枚も続いている。あてもなく眺めているうちに、牧原はスマホに視線を戻した。叶井真言とやりとりをしていたメッセージ画面を表示させた。大手町のビル下のベンチで待ち合わせようという提案に、承知しましたという叶井の返信で途切れている。新たにメッセージを入力する空白のスペースを見つめながら、牧原は迷った。叶井にメッセージを送る必然性など見当たらなかった。何と言葉を打てばいいのかわからなかった。しかしざわめいていた。ベアリングボールのような硬いざわめきが扉を叩いていた。鍵の掛かったドアノブをがちゃがちゃと回している。強引な波に先導されるかのように、牧原はゆっくりと文字を入力した。仕事の依頼があります、そうあてもなくメッセージを送信した。
加治木のアパートは細い路地の奥にあった。それ以上車が進入できない場所で牧原はタクシーを降り、その後は路地を歩いて進んだ。なんとなく昭和末期に建てられた佇まいの二階建てアパートで、鉄柱は錆びつき、外壁は紅葉したような様々な色の染みに覆われ、サドルのない自転車が植えこみの中に打ち捨てられていた。牧原はスマホに転送した住所の部屋番号を確かめ、二階への外階段を上った。一歩ずつ足を踏み上げるたびに踏み板が不吉に軋み、細々とした屑が小さく舞った。加治木の部屋はいちばん端だった。表札には誰の名前も掲げられていない。牧原はインターフォンを押した。耳を澄ましても、部屋の中から呼び出し音は聞こえてこなかった。それでも何回か続けて押してみたが、やはり電線が切られたように何の反応もない。ドアノブを回しても、鍵が掛かっていてびくともしない。牧原はドアを叩いた。ドアに向かって加治木の名を呼び、自分の名前を告げた。返事はなかった。すでにそこには誰も存在していないことを重く伝えるような沈黙が牧原の声を反響させていた。
加治木が会社に来ることはもうないのかもしれない、そんな予感がドアを叩いた拳に滲んでいた。もしかしたら加治木はこのまま自分に顔を見せることなく、自分の人生から姿を消していくのだろう、なぜかそんな予感が胸に湧きあがってきた。牧原はスマホを取り出した。加治木に電話を掛けてみたが、やはりコール音は鳴り続ける。次の取るべき行動は警察への通報だった。だが指はためらわれた。叶井に依頼した一件を思い出し、牧原はスマホの画面からしばらく視線を外せなかった。たかがFAXの書類を紛失したぐらいで保健所は盗難届を提出していないはずだ。おそらく事件沙汰にはなっておらず、警察と詳しい話を交わしても何の疑いも持たれはしないだろう。しかし何かが引き止めている。自分はただ偶然によって会社代表という立場にいるにも関わらず、いざ手に入れたものが失われそうになると、保身を図ろうとする牧原が牧原を引き止めていた。ドアの前から立ち去ろうと一歩後ずさった。その瞬間、スマホが震えた。加治木にぐっと肩を掴まれた気がした。しかし加治木が返信してきたわけではなかった。メッセージを送信してきたのは叶井真言だった。
火急の案件でしょうか、叶井はそう書いていた。牧原は目の前に立ちふさがる薄汚れたドアを見つめた。表面には引っ掻いたようないくつもの傷が走り、塗装を強引に剥がした痕もある。鍵に意味などないのよと叶井は言っていた。鍵に意味がないとしても、これは開けられるべきドアなのか、開けられることに意味があるドアなのか、牧原はそんなふうにドアを見つめていた。だがやはりスマホを操作した。社員が自宅の部屋で倒れているかもしれない、返事がなくドアが開かない、とメッセージを送信した。住所は? と叶井が訊ねてきたので、アパートの住所をペーストして送った。
生憎ですが、と叶井は少し間を置いて返してきた。私はすでに東京にはおりません。仙台にもおりません。東京から遠く離れた土地にいます。だから牧原さんのご依頼に今すぐ対応することはできかねるのです。申し訳ありません。ちなみにドアの向こうにいるかもしれない社員さんは、牧原さんと一緒に仙台に来た人ですか? 違います、もう一人の社員ですと牧原は返信した。ならば請求書を失くした方の人ですね。そうですか、叶井はそこで送信を止めた。そして考えをまとめたかのように再び文章を送ってきた。警察へ通報しにくいのはわかります。管理会社に連絡してみてはいかがでしょうか。もし警察がやってきたとしても、どのみち鍵を開けるために管理会社を呼ばないといけません。それが状況を前に進ませる合理的で迅速な選択だと思います。
今どこですか、と牧原は訊ねた。叶井はすぐに返信してきた。申し訳ありませんが、私は今そちらに向かうことはできません。もし対応できる状況だとしても、仕事のご依頼なので、事前に料金の話をしておく必要があります。決して安くはない額です。残念ながらそちらのドアをすぐに開放するために、今の私では距離も時間も遠く及びません。
もし本当に叶井さんにとって鍵に意味がないとしたら、距離にも時間にも大して意味はないんじゃないですか、と牧原はただ反射的に思いついたことを送信した。反応はなかった。返事の文章を何度も書き直しているのかもしれない。叶井が返信してくる前に、牧原は続けてメッセージを送信した。叶井さんは今この瞬間、一体どこの場所からメッセージを送っているんですか。牧原はアパートの階段を下りた。江津の畑が頭の中に浮かんでいた。大きな川の土手で耕された桑畑の木々の間を、叶井が足音を立てずに歩いている光景が浮かんでいた。叶井から返信が届いたのは、引っくり返った自転車が再び視界にあらわれたときだった。
今は島根の江津にいます、叶井はそう書いていた。
大通りでタクシーを捕まえて、事務所に戻った。ドアを開けると、ひんやりとした空気に一瞬身震いをしたが、暖房をつけることはしなかった。自分のパソコンの前に座り、代理店には明日いっぱいまでは連絡がつきにくいとメールを送信して、コールセンターと発送センターには何かあれば携帯番号に連絡をするようにと電話で伝えた。十五分ほどで鞄を手にして事務所を出ると、地下鉄を乗り継いで羽田空港に向かった。車内では部活の試合を終えたと思われる学生たちが騒いでいたので、窓の外をひたすら眺めていた。
空港のカウンターで石見空港行きのチケットを購入した。次のフライトは四時すぎで、その日最終の便ということだった。とりあえず保安検査場を通過し、搭乗口付近のソファに座っていることにした。石見空港への乗客は少ないせいか、搭乗口は羽田空港の広大なスペースのいちばん奥に割り当てられていた。人の姿はまばらで、土産売り場では店員の女が退屈そうに伝票の整理をしていた。
ソファに深々と体を沈ませ、店員の手の動きをぼんやり眺めながら、わざわざ航空券を正規料金で買って、島根まで移動しようとしている自らについて訝しんでいた。加治木の行方はわからない。だが警察にも管理会社にも連絡するのは面倒臭く、たとえ叶井にドアの鍵を開けてもらうにしても、なぜ自分が島根に行かなければならないのか。なぜ強引にでも叶井を東京へ呼び戻さないのか。金の話など後でいくらでもできるはずだ。土産売り場の女はじっとこちらを見つめていた。制服である青色の上着を着て、胸元からは白いブラウスが覗いている。気づくと、女は叶井の顔をしていた。伝票の束を放り出し、叶井の長い髪を肩の後ろにさらりとはねのけ、叶井の目でこちらに視線を向けている。そういえば請求書は紛失されたのではなかった。叶井によって盗まれていた。あの夜に鉢合わせをする以前に、叶井はすでに事務所に侵入していたのだ。
本当は加治木のことなんてどうでもいいんだろう、牧原にそう囁いた。扉の向こう側から囁いた。だってテープ台であいつの頭を叩き割ったじゃないか。連絡もすぐにしなかった。付き合いの長さなんて関係ないさ。それに会社の経営もどうだっていいんだろう。解散したって構わないし、結局どこで野垂れ死んでもいいと思っている。ただ、叶井に会いたいだけなんだ。島根に行って、桑畑で叶井の姿を目にしたいだけなんだ。スマホが震えた。叶井が自らの詳しい位置情報を送信してきた。仕事を依頼したいから桑畑の場所を教えてほしいというメッセージに対してのものだった。今からそこに行くんだなとまた囁いた。畑まで行って何をするんだ。まさか叶井が一糸纏わぬ姿で待っていると思っているわけはないよな。忘れちゃいけない。自分は1型糖尿病だと叶井は言っていた。普段の生活にある程度の制限がかかる疾病だ。そんな女に盗みなんて仕事が本当にできるものなのかな。本当に叶井は糖尿病なのかな。そもそも糖桑茶は本当に糖尿病に効くのかな。
次第に人が多くなり、土産売り場のレジには列ができていた。商品のバーコードを手早く読み取っている女はもう叶井ではなかった。そういえばいつから牧原は煙草を吸っていないのだろう、苛立ちを覚えながら女から視線を外した。コールセンターからスマホに着信があったが、応答することはしなかった。
石見空港に着いたのは六時すぎだった。飛行機に乗っている間はほとんど眠っていた。到着ロビーに降り立っても、頭の中は定まっておらず、足元も覚束なかった。そばを子どもが追い越していった。どこかでもらったような見本用の葉書を手にしていた。何も書かれていない、二つ折りに圧着されているタイプだった。子どもは両手で葉書を裂くようにぴりぴりと圧着面を開封した。そして今乗ってきた飛行機のように手を伸ばして舞わせた後、たまたまそばにあったごみ箱の中に投げ捨てた。
子どもの後を進み、なんとなくごみ箱の中を覗きこんでから自動ドアを通り抜けて、タクシー乗り場に向かった。外気は冷えこんでいた。年の瀬が迫った夜空を吹き抜ける風に上着のボタンを留めた。一台だけ停まっていたタクシーに乗りこみ、叶井から送られてきた住所を伝えた。運転手は首を捻った。耳の上には白髪が混じり、ハンドルを握る指には水分が搾り取られたように何重もの皺が刻まれていた。結構掛かりますが構いませんか、と運転手は訊ねた。たぶん一時間は掛からないだろうけど、そのあたりは詳しくないもんでね。運転手の息は少し臭った。問題ないので向かってください。ただできるだけ飛ばしてもらえれば助かります。人を待たせてるもので。わかりました、と運転手は前を向いた。一応ナビに入力させてもらいますね、まあルートは何本もないでしょうが念のためです。もう一度ゆっくりと住所を運転手に伝え、カーナビの画面に目的地付近の地図が表示された。×印が付いた地点は川のすぐそばだった。おそらく江の川だろう。まわりを囲む緑色は山々だった。おそらく街灯もほとんど立っていない場所で叶井は待っているのだ。すんませんがシートベルトをお願いします、と運転手は車を発進させた。その瞬間、後ろから光が射しこんだ。振り返ると、停車したタクシーのヘッドライトだった。羽田からの客を乗せるためではなく、今から羽田に向かう客を降ろしている。ヘッドライトは遠ざかり、運転手はラジオの音量を少し小さくした。
今、石見空港を車で出ました、そう叶井にメッセージを送り、スマホを上着のポケットにしまった。そして窓の外の夜景に視線を向けた。車はしばらく木々に挟まれた静かな道路を進み、信号をいくつか曲がると、片側一車線の国道に入った。道路沿いには住宅や工場やファミリーレストランなどの店舗が点在していて、ときどき対向車とすれ違った。カーナビの音声案内どおりに角を曲がった運転手は、しばらく国道をまっすぐ進むことに肩の力を抜いたのか、それとも仕事終わりに長距離の客を乗せたことに嫌気が差しているのか、赤信号を見上げながら大きく溜め息をついた。
煙草吸っていいですか、と訊ねてみた。運転手は首を少しだけこちらに回した。すんませんねお客さん、禁煙なんですよ。よく見ると、運転手の鼻に吹き出物ができている。外光を微かに受け、ほんのり赤く浮かび上がっている。窓開けてもだめですか、と吹き出物に向かって続けてみた。ええ、煙草は遠慮してもらってます。だってほら、灰皿ないでしょ。もしどうしてもって言うなら、コンビニ寄りますんで、そこの灰皿で吸ってください、運転手はそう前に向き直り、アクセルを踏みこんだ。背もたれに体を押さえつけられながら『やくそくの環』の表紙をふと思い出した。様々な色の波が重なり合っているイラストが描かれていた。たとえばこの運転手との扉を開くことはできるのだろうか。もし扉が開放され、互いを行き来できるようになれば、たぶん後部座席に座りながら、ハンドルを握って運転することになる。煙草を吸いながら、その煙に眉をひそめることになる。鼻の吹き出物に不気味さを感じながら、鼻の吹き出物など気にしないことになる。叶井のもとへ急ぎながら、早く家に帰って晩酌をしたいというふうに居ても立ってもいられなくなる。そんな入り乱れた状態を受け入れられるのだろうか。自分と運転手の二人が絡み合うだけでも文脈はたやすく崩壊する。それなのにあらゆる存在に一つの大きな環が流れこむとすれば、世のあらゆる小説のページが解かれて混ざり合うことと同じだ。きっとそれぞれの存在が存在すること自体に耐えられなくなる。ならばあらゆる扉を開放させるという鍵に意味なんてあるのだろうか。
だからそのために叶井に会いにきたんじゃなかったのか、そう牧原の隣に座って言った。牧原はこちらを振り向かない。フロントガラスの向こうをまっすぐ見据えたままだ。それでもその強張った横顔にノックをする。牧原が叶井になり、叶井が牧原になり、文脈なんてものを崩壊させるためにわざわざ島根まで飛んできたんじゃないのか。叶井になって、叶井の手を使って、自分の腹にインスリン注射を打つんじゃなかったのか。もし次に会うことができたら、今度こそ環心の手繰り寄せだという叶井の言葉を真に受けたんだろ。牧原は叶井を求めている。自分でも気づかないぐらい、とても激しく求めている。スマホを確認してみるが、叶井からの返信は届いていない。それでも牧原は揺らぐことなく、それを再び上着のポケットにしまう。実際に顔を合わせたのは三回。一体叶井の何が自分をそれほど動かしているのか、牧原にはわかっていない。いつの間にか自分の扉がひっそりと解錠され、その内側に叶井が棲み着こうとしていることにもまだ気づいていない。車の窓の向こうを宗教団体の看板が通り過ぎる。叶井が属している会の看板だった。町の自治会館ほどの小さな建物で、窓に明かりが灯っている。だが牧原は気づかない。ただ後部座席に深く腰を沈めている。フロントガラスの景色に集中しているわけではない。それとは全く無関係の、赤い光に包まれる景色を牧原は思い浮かべていた。
やがて山道に入った。道路の片側には木々が生い茂る斜面が続き、もう片側にはガードレールと底の見えない闇の斜面が続いていた。ひび割れた路面のせいで車は上下に振動し、急カーブを曲がるたびに牧原は手すりを掴む手に力をこめた。かつて訪れた桑畑がこんな山奥にあったのかどうか、牧原は憶えていなかった。糖桑茶に使用されている桑の畑とは別の畑に叶井はいるのだろうと思っていたが、そもそもなぜ叶井は桑畑などを見たいのだろうか、牧原は体をじっと固くしていた。もうすぐ着きますよ、運転手はハンドルを回しながらそう言った。牧原は何も答えずに、窓の外の闇を見つめている。闇の中でときおり光っていた。一級河川の江の川ではなく、沢のような小さな流れがあった。そこに何かの姿を見出そうとしているのか、牧原の首は白く伸びていた。耳の下に鋭利な刃を当てれば血が滲み出そうなほど不用心な首筋だ。まさかタクシーの中で首を切られることなど牧原自身は予想もしていないのだろう。
タクシーが停車したのは、直線に伸びている道路だった。すぐそばには二階建ての日本家屋が一軒ぽつりと建っていた。瓦屋根で、玄関の前には軽トラックと高級セダンが並べられている。お待たせしました、と運転手はサイドブレーキを引き、料金メーターの精算ボタンを押した。牧原は財布を取り出し、クレジットカードを差し出した。カードリーダーに通されて、通信回線が情報を送受信し、簡易的なプリンターから領収書が吐き出されるまでの間、牧原と運転手は一言も言葉を交わさなかった。誰もいない山中の国道で二人の目はただ小さな一つの機械を眺めていた。ドアが開かれ、牧原が外に出ると、運転手はすぐに車を発進させた。右に大きくハンドルを切り、一度バックへ切り返してから、これまで走ってきた道を勢いよく戻っていった。
あたりは広く開かれていた。道路沿いに点々と続く電灯よりも、空に浮かぶ月の方が煌々と輝いている。牧原は道路を横切り、ガードレールの下を覗きこんだ。草野球が何試合もできるぐらいの敷地が広々と見渡せた。そこに整然と植えられているのは人の背丈よりも少し高い、何百もの桑の木だった。葉はすべて落ち、ごつごつとした枝を平気で冷気に晒している。強く冷たい風が吹きつけると、桑畑というよりも地中から剥き出しになった古代の骨のようにも見えた。桑畑の向こうでは流水が反射していた。その光は江の川であり、まわりを取り囲む山々は月光に淡く照らされている。牧原はガードレールに腰を掛けて、スマホを取り出した。叶井からの返信は届いていなかった。それでも、今桑畑に着きました、それだけを送信した。
牧原の目の前の日本家屋に住んでいるのは桑畑の農家なのだろう。今頃家族で夕食を終えて、風呂に入り、テレビでも見ているのかもしれない。そんな家の中から叶井が玄関の戸を開けて、姿をあらわすとは想像できなかった。だが牧原はガードレールに腰掛けたまま、上着のポケットに手を入れ、白い息を吐いて、瓦屋根に付けられたアンテナあたりを見上げていた。叶井が送ってきた位置情報なのだから、ここで待つことに何も間違いはないのだというふうに。
しかしあたりに人の姿は見当たらない。定規で引いたような道路が闇の奥まで続いているだけだ。切り裂くような風の音が聞こえてくるだけだ。そんな場所でただ待っていると、煙草を吸いたい気持ちがすでに消えていることに気づいた。牧原は鞄の中から煙草を取り出し、ライターで火をつけた。煙を何度か吐き出した。それはただの白い息であり、ただの二酸化炭素だった。煙草の先端に火は灯っていない。煙草を吸っていいですかと牧原は空中に向かって呟いた。運転手はだめですよと答えていた。牧原は再び煙草をくわえ、肺いっぱいに吸いこんだ。暗闇に赤い点がほのかに浮かびあがる。なぜなら牧原の肺から吐き出されるのはただの二酸化炭素だからだ。牧原は指に挟んだ煙草を道路に投げ捨てた。先端に火は灯っておらず、一筋の煙が立ち昇っている。
どこからか口笛が聞こえてくる。子どものような途切れ途切れの口笛が、昔の懐かしいメロディを引き寄せ、繋げようとしている。きっと牧原が子どもの頃にテレビから流れてきた曲だ。牧原は目を閉じ、耳を澄ます。一体何の曲だったのかを思い出そうとする。メロディには聴き憶えがあるのに、付随する情報を思い出せない。口笛を吹いているのは牧原自身だったのに、何のメロディなのかという情報は牧原に属していない。牧原は唇を尖らせて、死にかけた鳥のように二酸化炭素を吐く。音らしきものは鳴る。音階らしきものは連なる。そして牧原自身は空っぽだった。
もちろん俺自身も牧原と同じだった。牧原が煙草を吸ったら俺も煙を吐き出すし、牧原が洗面台の前に立ったら俺も洗面台の鏡に映りこむ。だがいつからかトレース紙はわずかにずれた。食べたいと望んだものとは別のものを食べていたり、電車の中で小説のページをめくろうとしたときにはページを閉じていたり、誰かを好きになろうとしたときにすでに好きではなくなっていたりした。あるのはずれだった。ずれが引っかかりを生んだ。引っかかりはいつか牧原の首筋に爪を立て、牧原を死なせるのだろうと思っていた。しかし牧原は生き続けた。いつしかずれなど存在しないかのように生き続けた。ずれが存在しないというのは俺も牧原も存在しないのと同じはずなのに。
牧原はガードレールから腰を離し、地面にしゃがみこんだ。少し先の白線あたりに視線を向けている。俺は牧原の脳天を見下ろしていた。鞄の中に硬いものは入っていなかった。あたりを見回すと、道路から欠けたアスファルトの塊が転がっている。牧原から離れて、アスファルトの塊を持ち上げる。しっくりと手の中におさまり、骨を軋ませる重さが肩まで伝わってくる。何よりも強引に引きちぎられたような鋭角な断面が気に入った。牧原のもとに戻りながら、断面を上に向け、うまく力が伝わる握り方に持ち変えた。牧原はしゃがんだままスマホを取り出していた。視線を手元に落として、ちっぽけなブルーライトに集中している。電灯に照らされた不用心な脳天だった。中身はたやすくぶちまけられるだろう。灰色の塊を力の限り握りしめる。深く息を吸いこみ、ゆっくりと肩を上げて、狙いを定めたとき、しかし塊を振り下ろそうしているのは牧原だった。地面にしゃがんでスマホの画面に集中しているのは俺だった。俺はすかさず立ち上がり、後ろを振り向いた。足元にアスファルトの塊なんて転がっていないことを確かめる。牧原はまだスマホの画面から目を離さない。そこにはメッセージ着信の通知が届いていた。加治木からだった。
今日はすみませんでした。ついさっき目が覚めたところです。正直こんなことは初めてで、まだ自分でもよく理解できていないんですが、とにかくカーテン開けたら外はもう真っ暗でした。酔っ払いすぎですね。すみません。さっき冷たい風がすうっと入りこんできたような気がして、目が覚めたんです。何度も着信をもらったのに、全然気づきませんでした。本当に申し訳ありません。今日はこのまま寝ないで、明日は朝イチできっちり出社します。
明日は出社する、牧原は最後の一行を読み返した。加治木が出社する場所を思い浮かべた。そこが古びたビルに入居する事務所だと思い当たり、明日加治木はその事務所へ電車で向かって、朝から仕事をするのだという事象を一つずつ辿った。ところで自分は明日そこに行かなければならないのだろうか、最後の一行を見つめたまま牧原はそう疑う。加治木が出社するという古びた事務所で、自分も仕事をすることになるのだろうか。結局、加治木はアパートの部屋の中で眠っていた。体調を崩したわけでも強盗に襲われたわけでもなく、鍵の掛かった部屋でただ眠っていたのだ。牧原は溜め息をついた。煙草を吸いたくなり、上着の内ポケットを探ったが、空っぽだった。さっき取り出した一本をくわえて、火をつけたはずなのに。ズボンのポケットにも入っておらず、あたりを見回すと、少し離れたアスファルトの地面に煙草の箱が落ちているのが目に入った。牧原は歩を進めて、煙草の箱を拾い上げた。ふたを開けて、ライターが収まっているのを確かめる。叶井真言からの通話着信がスマホを震わせたのは、握りしめたライターに着火させたときだった。
連絡が遅れて申し訳ありません、耳にあてたスマホの向こう側で叶井はそう言った。なるべく急いだものですから。
急いだ? 急いだのは牧原の方だった。飛行機の最終便へと駆けこみ、タクシーを飛ばして人気のない桑畑までやってきたのだ。
私はもう江津の桑畑にいます、と牧原は言った。叶井さんが送ってくれた住所までタクシーで運んでもらい、今叶井さんが来るのを待っているんです。
叶井はしばらく沈黙していた。何を言うべきか考えているような間だった。どこかを歩いているのか、ときどき短い呼吸音が聞こえた。扉を開けました、叶井はそう自分自身に確かめるように言った。もう連絡があったかもしれませんが、牧原さんの会社の社員さん、無事なようです。たぶん眠っていただけなんでしょう。
眠っていたというのは加治木のはずだった。なぜ叶井が加治木のことを話しているのか。叶井さん、あなたが今いるところはどこなんですか、と牧原は訊ねた。
だから東京です、叶井はそう答えた。東京と牧原は繰り返し、そうですと叶井は言った。牧原さんが送ってきたでしょう。自分のところの社員が部屋の中で倒れているかもしれないって。あの後、私タクシーを呼んで、空港まで行って、急いで羽田行きに飛び乗ったんです。そして電車を乗り継いで、送信してもらった住所まで行きました。こういったケースは初めてのことでしたが、とにかく無事で良かったです。やっぱり環心の手繰り寄せだったのかもしれません──
牧原は通話を切った。
喉がひどく渇いていた。唇同士が粘ついた糸を引き、吐く息からは嫌な臭いが漂った。体が震え始めたが、寒さのせいかどうかはわからなかった。そして、なぜ叶井がここにいないのかもわからなかった。呼吸は早く、肩が上下に揺れていた。揺れるたびに、何かと一つに合わさっていく感覚があった。扉は開放され、向こうからこちらへ、こちらから向こうへ、互いに重なり、混じり合うような力が生まれた。あらゆる存在を空っぽにさせる力だった。
歩き出してすぐに、ガードレールに途切れている部分があるのを発見した。その裂け目からは細い坂になっており、桑畑へ下りられるようになっている。坂の途中には枯れ葉や小枝の他に、新聞紙やビニールの切れはしや割り箸などが落ちていた。それらのごみを無造作に拾いながら坂を下りていった。
桑の木は人間に見えた。どこかの村から集められた長身の種族が立ち並んでいるみたいだった。肉は削げ落ち、関節は折れ、それでも骨だけの体はなんとか動き出そうとしていた。桑の間を進み、足元に横たわる柔らかな土は人間の腹の上を踏みしめていく感触だった。ときどき後ろを振り返った。次第に日本家屋の明かりが見えなくなり、屋根のアンテナの先が完全にガードレールに隠れた地点で立ち止まった。電灯の光は届かず、乾燥した夜空に広がる月光だけが桑の頭頂部を淡く浮かばせていた。
一本の桑の根元へ、手にしていたごみを投げ捨てた。まわりに落ちていた枝や枯れ葉も拾い集めて、ゴミの中へ次々と投げ入れた。たまたまそこに落ちていた枯れ葉を手にして、投げ入れただけだ。そんな意味のないものたちがうず高く積み上げられている。叶井と出会ったことも偶然だ。加治木が明日出社することも偶然だ。もし言い換えるなら、環心がただ偶然に手繰り寄せたものと呼べるかもしれない。
あらゆる扉を開け放つことなどたやすいのだ、そう啓示のように一瞬頭の中が白くなった。確かに鍵は一つしかなく、鍵に意味などない。ごみの中を漁って、汚れた麻紐を取り出した。保管するために正しく縛られている状態で、頻繁に使われていた形跡はない。たった一つの鍵として適している。まず桑の木のまわりに新聞紙を敷いて、その上に枯れ葉や枝を散らし、桑の木の根元に寄せ集めた。さらに捻った新聞紙で外側を固めた。最後に残ったごみは適当に上からばら撒いた。上着の内ポケットから煙草の箱を取り出し、ライターだけを抜き取って、煙草も丸ごと投げ捨てた。箱から飛び出た数本の煙草は女の細い指に見えた。麻紐を解いて、ごみの山のまわりに円状に垂らしていき、あとはちっぽけなライターで火をつけるだけだった。
桑の木はまだ枝打ちされておらず、枝先がところどころで隣の木と絡み合っている。さらに風がときおり強く吹いた。火を広く行き渡らせるには悪くない条件に思われた。そう思ったときには、すでに火を麻紐の先端につけていた。最初、紐に吸着した湿気で火は燻っていたが、しつこく着火を繰り返すと、安定した火が麻紐に燃え移った。同じ要領で、他の箇所にもいくつか火をつけていった。それぞれの火は麻紐をゆっくりと燃やしていった。同時に捻られた新聞紙に燃え移り、枯れ葉と小枝を渇いた音を立てて燃やし、ビニール袋や割り箸の燃えかすを細かく風に舞わせた。やがて炎として一つの塊に変貌したときには、桑の幹肌は黒く焦げ、細かく分かれた枝が燃え始めていた。
燃える木から後ずさり、立ち昇る火と煙にしばらく目を細めていた。風で火の粉が舞い、近くの木や土の上に降り注いだ。木が一本燃え落ちるまでにどれくらいの時間が掛かるのだろう、そう思いながら道路に上がる坂へと戻っていった。ここからは見えない。叶井が説いていた世界を目にすることはできない。坂を一歩ずつ踏みしめて上がっていくときも視線を落とし、あえて炎の方には振り返らなかった。
やはり道路に人の姿はなかった。暗闇が深々と遠くまで続いている。車が通りそうな気配もない。ガードレールに近づき、桑畑を見下ろした。赤い流れは眩しく蠢いていた。風に揺さぶられ、もどかしそうに形を変えながらも、整然と立ち並ぶ木々へ流れこもうとしていた。最初に燃やした木はすでに輝きを失いかけていたが、まわりの木々が新たに燃えあがり、炎によって一つに繋がろうとしていた。一つに繋がったときに桑の木は燃え、糖桑茶は燃える。東京の古びた事務所は燃え、加治木は燃える。コールセンターは燃え、商店街の食堂も燃え、違法も合法も先導する者も先導される者も、みんな同じように燃えることになる。燃えていないのは自分だけだった。炎が木の上を次々と流れ渡り、やがてガードレールの下まで近づいたときに、その中へと身を投げこむつもりだった。そうすることであらゆるものが何もない者同士として一つに繋がることができる。
闇の中で火の粉が明滅していた。日本家屋の窓は赤味を帯びて反射している。やがて窓は開けられる。警察を呼ぶ電話が掛けられる。あるいは車が通りかかる。やはり警察を呼ぶ電話が掛けられる。俺と牧原はそのときがくるのを感じながら、足元に迫ろうとする赤い流れを見下ろしていた。
〈了〉2023年作
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
