
◆読書日記.《ヴィリエ・ド・リラダン『未來のイヴ』》
※本稿は某SNSに2020年12月20日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
ヴィリエ・ド・リラダン『未來のイヴ』(東京創元社版)読了。
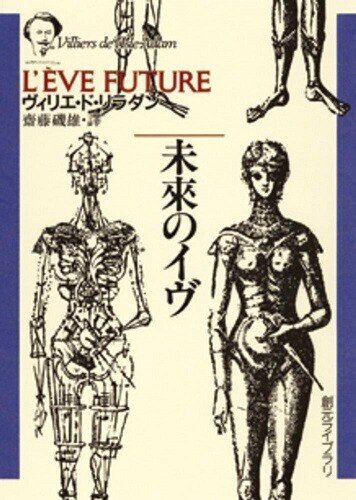
19世紀フランスの大貴族の末裔であるリラダン伯爵の代表的長編小説。
ポオとボードレールに影響を受け、マラルメと親友付き合いをし、ユイスマンスにも激賞されていたが生前は全く一般受けしなかった異端の作家。
本作はそんな伯爵の独自の情熱が籠った異色長編である。
大貴族の末裔とは言え定職には就かず、数々の文学サークルに入り、一族の財産だけを頼りに作家活動をしていたが、この『未來のイヴ』の執筆時期は既にその資産も底をつき、資金的な依存先であった叔母が亡くなった事で赤貧の生活をしていたという。
本作は、そんな伯爵が家具のない部屋で床に腹ばいになって書いたという伝説的な一作。
<あらすじ>
あるとき世界的な発明王・トーマス・エジソンの元に、イギリスの青年貴族セリヤン・エワルド伯爵が悩みを打ち明けに来る。
彼の恋人であるミス・アリシア・クラリーの事であった。アリシアは全く完璧な容姿と神秘的な肉体を持った理想的な美貌の女性で、エワルド伯爵は彼女にぞっこん惚れこんでしまった。
だが、アリシアとつきあう事となって彼は大いに幻滅するのである。
アリシアは確かに圧倒的に完璧な美貌を持ってはいた。だが彼女はその実、偽善的で偏狭な知性を持ち、鈍感で、愚劣で俗悪な精神を持った女だったのだ。
つまりアリシアは完璧な容貌を持っていながら、内面は唾棄すべき俗悪な精神を宿していたのだ!
「ああ!誰かがあの肉体からあの魂を取り除いてくれないかなあ!」――「私は、恋する男ではなくて、囚われ人です」――「私にはもう人生がどうでもよくなったということなのです……」。
彼はアリシアへの執着心と、彼女の内面への憎悪とに心引き裂かれ、人生に絶望するほどにまで思い悩んでいたのである。
エジソンはこの悩める青年に対し、「私はその女からその固有の存在を奪い取ってしまいましょう」と提案する。
エジソンはエワルド伯を自分の実験室に招き入れ、自分が開発した人造人間「ミス・ハダリー」を紹介する。
そしてエジソンは、エワルドに二十一日間、自殺を猶予して待つように言い聞かせるのである。
その期間でこの金属の鎧をまとったような乙女を、あのアリシアそっくりの姿かたちに仕上げてみせようというのだ。
エジソンは、それができるという証明の一つに、自分が開発した人工的な筋肉の上に皮膚を張り付けた、生きた人間の腕にしか見えない驚異的な発明品を見せる。
エワルドは徐々に心変わりし始めて……というお話。
<感想>
あらすじから見て、これを普通のSF長編だと思って読むとだいぶ痛い目にあうのではないかと思う。
ある意味、この長編は「過剰」なのである。
確かに、ユイスマンスが注目しただけある「異端の作」と言えるだろう。
本書の訳者のスタイルが正漢字・歴史的仮名遣いなので文章も非常に印象的である。
実は本書の前半分辺りまでは、読んでいて非常に胸糞悪いと思ったものだった(笑)。
あらすじでもその感じが少しお分かりになったかと思うが、この物語の前半は、とんでもない女性差別的な悪口雑言を、エワルド伯爵とエジソンが延々と並べたてるのである。
これは女性にはお勧めできないとすぐに思った(笑)。
と言うか、本書の前半部分のほとんどは、著者のリラダン伯爵による「女性憎悪哲学」のようなもので成り立っているのである。
なんだこりゃ?といったようなあからさまな罵詈雑言。――皆さまも胸糞悪くなるかと思うが、その雰囲気の一端でも理解してもらうために、本書の中からそういった部分を一部引用してみよう。
「頭の単純さというものを全く持ち合わせていない女などは、怪物以外の何ものでしょうか。《才女》と呼ばれるあの厭わしい存在ほど、人の心を暗くし世を毒するものは他にありますまい。最もそのお相手の巧言令色の徒を除けば、の話ですがね。世俗的な意味の才気なるものは、知性の敵です」
「ある女が、慎み深く、信心で、いささか頭が単純で、しかも謙遜であり、その不思議な本能の力で、ある言葉の意味をまるで薄紗を通す光のように理解するとします。そういう女こそ、無常の宝であり、真の伴侶であって、これと逆の女はどうにも手の施しようのない災厄となるのです!」
――といった感じでリラダン伯爵の筆致は時として苛烈に女性を攻撃する。
上に挙げたのはまだごく一部で、特に男を堕落させるような類の女性に対しては「毒婦」だとか「あばずれ女」だとか「そもそもこういう女たちは、事実に於いて、我々人間よりも遥に獣類に近いのです」等とボロクソに言う(笑)。
これは、この時代はまだ男尊女卑の考え方が根強かったのだろうか?
それともリラダン伯爵の個人的なルサンチマンだろうか?
たぶん、両方の事情が重なっているものだと思える。
実際、リラダン伯爵のプロフィールを確認すると、過去「ルイーズ」と呼ばれる淫婦(?)と同棲して、親族からこっぴどく叱られたらしい。
それ以後も、リラダン伯爵は金を稼ぐこともせずに文学に打ち込んでいたためか、まともな女性との縁談が全く上手く纏まらず、女性には苦労したようなのである。
いや、たぶん女性に対する恨みつらみがあったのだろう。
でなければ、あれだけ大量のページを割いて「女性憎悪哲学」をぶったりはしないだろう。
さて、そういう感じで本書を読み始めた当初はこういった男尊女卑の塊のような演説が延々と続いてゲンナリとしていたのだが、読み進める内にこの雰囲気は何かに似ていると感じるようになった。
マルキ・ド・サド侯爵の『閨房哲学』である。――「男は放蕩せよ、女は淫乱であれ!」という、あれである。
世間とは全くかけ離れたおのれの性癖と倫理観を、世間から迫害されたそのルサンチマンを目一杯に込めて、歪んだ性道徳を高らかに宣言する、あのサド侯爵の長編小説『閨房哲学』である。
リラダン伯爵の『未來のイヴ』における「女性憎悪哲学」には、サド侯爵的な「箱庭の中の歪んだ楽園」があるかのように思えるのだ。
そう考えればまさに箱庭的世界観を描いた『さかしま』のユイスマンスがリラダンを激賞したというのも、近縁的な作風を感じたからなのかもしれない。
で、このリラダン伯爵の「女性憎悪哲学」はどこに行き着くのだろうか?――理想的な外見の女性から魂を抜き、お人形のように従順な「恋人ロボット」に至るのだ。
これは現代も「現実の女の子に絶望した非モテ」なんかがよく妄想する「ぼくがかんがえたりそうのメイドロボット」的なアレである。
花沢健吾の長編マンガ『ルサンチマン』や田中ユタカ『愛人―アイレン―』なんかでも真剣に主題化されたテーマだ。これを19世紀の没落貴族が大真面目にやったのだ。
だが、本書はその手の作品に多く見られる通俗的な娯楽作品と思ってはいけない。
非常に広範な知識によって真剣に「男性はいかに容易く女性に騙されるのか」的な議論を行い、トーマス・エジソンがまだ存命だった時代の科学力を持って、どのようにしてアンドロイドを実際に作るのか、という科学的な議論を大真面目に検討する。
人間の歩行運動を再現するにはどのような機工が必要なのか?
ロボットと対話するにはどのような条件が必要なのか?
女性の筋肉を表現するにはどうするべきか?瞳はどう再現するのか?
髪の毛は?
皮膚は?
――頭の天辺から爪先まで、エジソンは念入りにこの人造人間の構造を説明する。
そうしてやっと悩める青年・エワルド伯が決心をしてエジソンに「お願いします」と頼む所まででこの物語のだいたい五分の四は使われる。
つまり、この物語は「科学的な議論や説明」であったり「哲学的な議論」であったりという「理屈」の部分が圧倒的な割合を占めているのである。
おそらく、そういう「理屈」や「議論」を抜いてストーリーのみを抽出すると、この物語は短編小説程度の分量しか残らないだろう。
要は、この物語は「ストーリー」が重要なのではない、「理想的な女性をいかに作り上げるか?」という問題をいかに成立させるか、その真剣な検討こそがこの物語の本質だったのだ。
「男性にとって理想的な女性とはどのようなものか」――という、このテーマを本当に真剣に突き詰めていくと、けっこうどの作品も似たような「幻想性」を表すことになるのかもしれない。
――人造人間ミス・ハダリーは、最終的に「ロボット」という枠組みさえも超越して、もはや超科学的な幻想性を纏ったその正体を露わにするのである。
「男性にとって理想的な女性」――それを突き詰めてしまうと、最終的には人間の手には届かないような超存在になってしまうようだ。
ラカンが言う 「女なるものは存在しない」、または女性は男性原理からは理解不能である――といったテーゼは、意外とこういう物語に表現されているのかもしれない。
