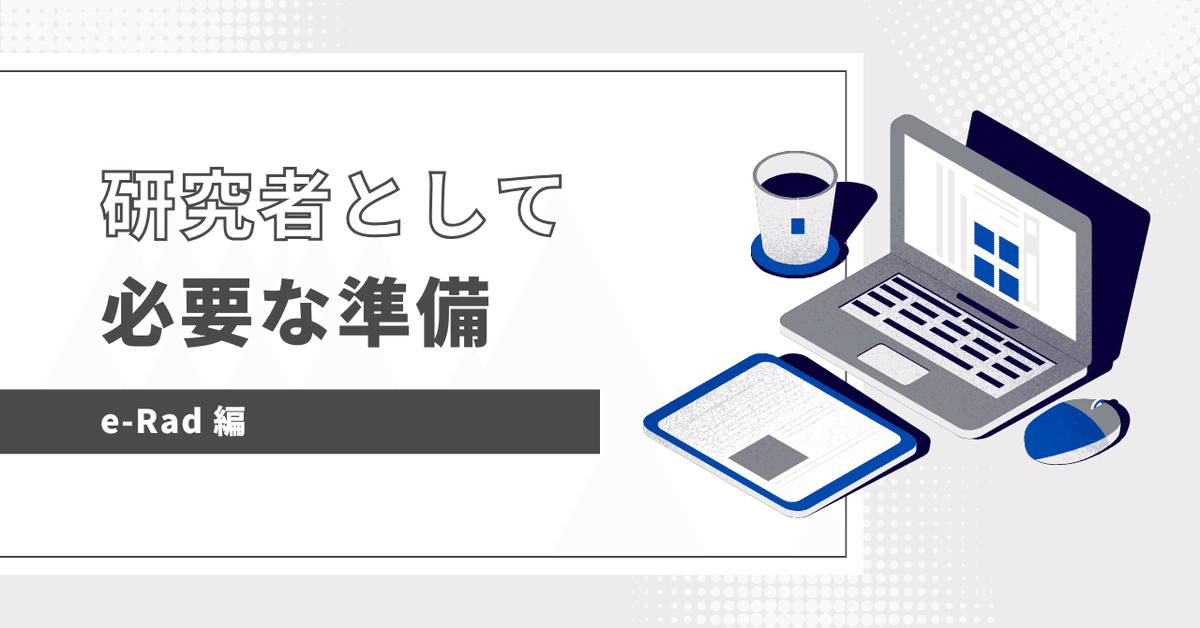
研究者として必要な準備〜e-Rad編〜
はじめに
研究者として活動する上で、国や大学の助成金に応募するための必須ツールが「e-Rad(いーらど)」です。e-Rad(府省共通研究開発管理システム)は、日本の科学技術政策を支えるための基盤となるシステムであり、研究者の情報を一元的に管理します。本記事では、e-Rad登録に必要な条件や、医療機関に所属する研究者としての登録のポイント、登録後にできることを解説します。
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)とは、競争的研究費制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省横断的なシステムです。
Research And Development(=科学技術のための研究開発)の頭文字からなる「Rad」に、Electronic(電子)の頭文字を冠し、「e-Rad」としました。
e-Rad登録で可能になること
e-Radへの登録後、以下の機能を利用できます:
• 助成金への応募
科学研究費補助金(科研費)など、日本政府が提供する研究助成金に応募可能になります。
• 研究者情報の管理
研究者としての基本情報を登録することで、政府や機関によるサポートを受けやすくなります。
• 他研究者との連携
登録者データベースを活用することで、共同研究の機会が増加します。
e-RadとResearchmapの連携
e-Radに登録すると、Researchmap(日本の研究者情報共有プラットフォーム)とも情報を連携できます。Researchmapは、研究業績を公開し、他の研究者と交流するための重要なツールです。
Researchmapとは
研究者による業績管理のデータベースです。研究者ごとのサイトに自分の業績をまとめられます。さらに共同研究者やフォローなどの研究者間の関係構築にも繋がりますし、一般公開もされます。
researchmapは、研究者が業績を管理・発信できるようにすることを目的とした、データベース型研究者総覧です。
簡単な登録で自身の研究者サイトを作成することができ、研究成果として、論文、講演・口頭発表、書籍、産業財産権、Works(作品等)、社会貢献活動などの業績を管理し、発信することができます。また、研究コミュニティなど、様々なツールを研究活動に活用できます。
とある研究者のResearchmapのサイトです。所属や論文の業績集、研究内容などが閲覧できます。
ここに「研究者番号」が書いてあり、これがこの研究者のe-Rad番号になります。
連携によるメリット
• 研究業績の自動反映
e-Radに登録した研究助成金情報がResearchmapに自動的に反映されるため、手動での入力作業を削減できます。
• 可視性の向上
Researchmapは国内外の研究者が閲覧するため、e-Radでの活動が広く認知されるきっかけになります。これにより、共同研究や新たなプロジェクトへの参加がしやすくなります。
• 統一された情報管理
e-Radの研究計画や成果情報がResearchmapに統合されることで、情報の一元管理が可能になり、研究者自身の負担を軽減します。
e-Rad登録の必要条件
e-Radに登録すると研究者番号が付与されます。研究者番号はその後の研究者の所属機関の変更によらず、継続して使用するものです。そのため、複数の機関に所属する場合でも、一人の研究者には一つの番号しか割り当てられません。また過去に登録された事がある場合でも、過去の番号を継続して利用できます。
研究機関に所属している場合
所属研究機関を通して研究者登録を行います。所属機関にはe-Rad事務担当がおりますので、その方へ依頼して登録してもらいます。
研究者の新規登録方法は、研究機関に所属しているかどうかによって異なります。e-Radにおける研究機関とは、以下のとおりです。
・府省内外局、国立試験研究機関、特殊法人及び特別認可法人、独立行政法人
・大学、高等専門学校、大学共同利用機関
・公益法人(財団法人、社団法人、その他)
・民間企業
・その他、科研費機関番号を有する研究機関
研究機関に所属していない場合
以下の書類が必要です
必要書類
・研究者登録申請書
・本人確認証明書の画像
登録はWebで行い、最大2週間で登録が完了します。
医療機関への所属とe-Rad登録
医療従事者の場合、e-Rad登録には所属機関との連携が重要です。
• 医療機関との連携
医療機関に所属している場合、研究費の申請は機関を通じて行われます。これにより、研究倫理の遵守や助成金の管理がスムーズに進みます。
• 職務と研究の兼務
医療業務と研究を並行する際には、e-Radを活用することで助成金の適切な管理が可能になります。
まとめ
e-Radは、日本の研究環境において不可欠なシステムです。特に医療従事者として研究を行う場合、助成金の取得や研究計画の立案において大きな助けとなります。登録手続きを早めに進めることで、研究活動の幅を広げ、効率的にプロジェクトを進める基盤を整えましょう。
