
経営学と文化解釈を考える(1)
最近経営学と文化を考える出来事にであった。Sarasvathy (2001)のエフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルト概念の使用についてである。クレージーキルトは、僕の博士論文の指導教授であるVlach氏が研究をはじめ、スミソニアン研究所でまとめていった。僕はそのころにアメリカに留学をして彼の下で奴隷ではなかった黒人大工の建築の分析で博士号をとった。黒人の文化的な活動を、「文化的な活動」として文化人類学的に調査してまとめる方法であり、物質文化研究はヴァナキュラー研究の基本となる学問である。というわけでとても親しみのある言葉である。Sarasvathy の使い方はあまりに雑ではないか、と思った次第である。以下、二つのエッセイを載せてある。一つはSarasvathyの言葉の使い方にかんして、二つ目はおなじような表面的な理解がかつて「日本式」経営にもあったなあ、雑な話だったなあ、という話である。経営学と文化解釈は大事なテーマであって、覚悟してかからないとだめだよ、ということで、覚悟していない用法例、ふたつについてレビューしてみた。
論文1: エフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルトの文化的誤用
―アフリカ系アメリカ人の芸術実践の安易な転用と民俗学的研究の軽視に関する批判的考察―
要旨
本稿は、Sarasvathy (2001)のエフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルト概念の使用について、アフリカ系アメリカ人の文化的実践の観点から批判的に検討するものである。特に、民俗学的研究の蓄積と美術史における評価の文脈を踏まえながら、この理論における文化的アプロプリエーションの問題を明らかにする。本研究では、クレイジーキルトが持つ歴史的・文化的意義を詳細に検討し、経営理論における文化的実践の安易な転用がはらむ倫理的問題について考察を行う。
1. 序論:問題の所在
エフェクチュエーション理論は、起業家の意思決定プロセスを説明する新しい理論的枠組みとして注目を集めている。この理論においてSarasvathyは、「クレイジーキルト原則」という概念を提示し、起業家による資源とパートナーシップの構築プロセスを説明しようと試みている(1)。
しかしながら、この理論的枠組みには重大な問題が存在する。それは、アフリカ系アメリカ人の重要な文化的実践であるクレイジーキルトを、その歴史的・文化的文脈から完全に切り離し、単なる比喩として使用している点である。この問題は、単なる表現上の問題ではなく、文化的アプロプリエーションという深刻な倫理的問題を含んでいる(2)。
特に注目すべきは、この理論がクレイジーキルトに関する豊富な民俗学的研究や美術史的評価を完全に無視している点である。John Michael Vlachが指摘するように、クレイジーキルトは奴隷制時代から続くアフリカ系アメリカ人の重要な文化的表現形式であり、その制作過程には深い社会的・政治的意味が込められている(3)。

2. クレイジーキルトの文化的・歴史的文脈
クレイジーキルトは、単なる装飾品や実用品ではなく、アフリカ系アメリカ人の歴史と深く結びついた重要な文化的実践である。ボストン美術館の展示『Fabric of a Nation: American Quilt Stories』が示すように、これらのキルトは社会的・政治的メッセージを含む芸術作品として評価されている(4)。
特に注目すべきは、ハリエット・パワーズのような奴隷制時代を生きた作家たちの作品である。パワーズの『Pictorial quilt』には、19世紀後半のジョージアの様子や、故郷を偲ぶ奴隷とされた人々の思いが込められている(5)。このような作品は、単なる装飾的な「パッチワーク」ではなく、歴史的記録であり、社会的抵抗の表現形式でもあった。下のクレージキルとは非常に有名なものである。

Gee's Bendのキルターたちの作品も、重要な例である。彼女たちの作品は、現代アートとしても高い評価を受けており、その抽象的な表現は、アフリカの伝統的なテキスタイルデザインとの関連性が指摘されている(6)。

3. エフェクチュエーション理論における問題点
このような豊かな文化的・歴史的文脈を持つクレイジーキルトを、サラスバシーは「色とりどりのランダムな形の布切れを縫い合わせた一枚の布」という表層的な理解に基づいて理論化している(7)。この理論化には以下のような重大な問題が含まれている:
まず、サラスバシーの理論における最も深刻な問題は、クレイジーキルトの持つ文化的重層性の完全な無視である。エフェクチュエーション理論では、クレイジーキルトを「予測不可能な要素を組み合わせて価値を創造する」というビジネスモデルの単なる比喩として扱っている(8)。
しかし、民俗学者のHenry Glassieが指摘するように、クレイジーキルトの制作過程には、綿密な計画と高度な技術が必要とされ、そこには明確な意図と文化的表現が込められている(9)。

特に、アフリカ系アメリカ人のキルト制作においては、以下の三つの重要な側面が存在する:
第一に、コミュニティの記憶の保存である。キルトのパターンや色使いには、アフリカの伝統的なテキスタイルデザインの影響が見られ、それは文化的アイデンティティの維持と継承の機能を果たしてきた(10)。

第二に、社会的抵抗の表現形式としての側面である。Alice Walkerが『カラーパープル』で描いたように、キルト制作は女性たちの連帯と解放の象徴として機能してきた(11)。特に、CelieとSofiaによるキルト制作のシーンは、抑圧された女性たちの自己表現と解放の象徴として深い意味を持っている。

第三に、芸術的革新性である。1981年のホイットニー美術館での展覧会「Abstract Design in American Quilts」が示したように、これらのキルトは純粋な抽象芸術としても高い評価を受けている(12)。特にGee's Bendのキルターたちの作品は、現代アートとして国際的な評価を得ている。

4. 文学・芸術における表象
クレイジーキルトの文化的重要性は、文学作品や映像作品においても繰り返し取り上げられてきた。特にAlice Walkerの『カラーパープル』は、キルト制作を通じた女性たちの連帯と解放のプロセスを鮮やかに描き出している(13)。作品中で描かれる「姉妹の選択」という柄のキルトは、単なる装飾品ではなく、抑圧された女性たちの声なき声を表現する重要なモチーフとなっている。
Toni Morrisonの『ビラヴド』においても、キルトは重要な象徴として機能している。モリソンは、キルトを通じて奴隷制の記憶と世代間の継承を描き出し、それは「再記憶」という重要なテーマと結びついている(14)。

さらに、Faith Ringgoldのような現代アーティストは、このキルトの伝統を現代アートとして革新的に展開している。Ringgoldの作品『The French Collection』シリーズは、クレイジーキルトの技法を用いながら、人種、ジェンダー、権力の問題を批判的に探求している(15)。

5. エフェクチュエーション理論の方法論的問題
このような豊かな文化的・芸術的文脈を持つクレイジーキルトを、サラスバシーの理論は極めて表層的に扱っている。この問題は、以下の三つの観点から批判的に検討する必要がある:
まず第一に、理論構築における方法論的な問題がある。サラスバシーは、クレイジーキルトを「パートナーシップの構築」の比喩として用いる際、その文化的実践の本質的な意味を完全に捨象している(16)。これは単なる認識の不足ではなく、文化研究における重大な方法論的欠陥を示している。
第二に、権力関係の不可視化という問題がある。Edward Saidが『オリエンタリズム』で指摘したように、他者の文化的実践を自文化の文脈で再解釈し利用することは、特定の権力関係を前提とした文化的支配の一形態となりうる(17)。エフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルトの使用は、まさにこの問題を体現している。
第三に、学術的責任の問題がある。Henry Glassieをはじめとする民俗学者たちは、クレイジーキルトの文化的・歴史的意義について詳細な研究を行ってきた(18)。これらの研究蓄積を無視して理論を構築することは、学術研究における倫理的責任の放棄と言わざるを得ない。
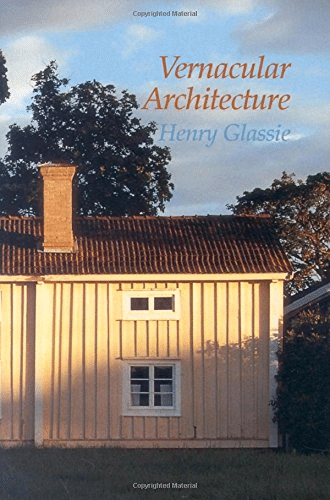
6. 結論と展望
エフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルト概念の使用は、経営学における文化研究の本質的な問題を露呈している。この問題は、以下の三つの観点から今後の研究課題として重要である:
まず、経営学における文化的感受性の問題である。他者の文化的実践を理論化する際には、その歴史的・社会的文脈を十分に理解し、尊重する必要がある。特に、マイノリティの文化的実践を扱う際には、その実践が持つ抵抗の意味や解放の象徴性を慎重に考慮しなければならない(19)。

次に、学際的研究の重要性である。経営学は、民俗学、文化人類学、美術史などの隣接分野との対話を通じて、より豊かな文化理解を構築する必要がある。特に、Clifford Geertzが提唱した「厚い記述」の方法論は、文化的実践の理論化において重要な示唆を与えている(20)。
最後に、新たな理論構築の可能性である。クレイジーキルトの事例が示すように、文化的実践は単なる比喩以上の豊かな理論的可能性を持っている。例えば、Gloria Anzaldúaの「境界理論」が示すように、マージナルな立場からの理論構築は、既存の理論的枠組みを革新的に更新する可能性を持っている(21)。

7. おわりに
本研究は、エフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルト概念の使用を批判的に検討することを通じて、経営学における文化研究の新たな可能性を探ってきた。この検討から得られた知見は、今後の経営学研究において以下の三点で重要な示唆を与えている:
文化的実践の理論化における倫理的配慮の必要性
学際的対話を通じた方法論の革新
マイノリティの視点を組み込んだ理論構築の可能性
これらの課題に取り組むことは、経営学における文化研究の質的向上に寄与するだけでなく、より倫理的で実践的な理論構築への道を開くことになるだろう(22)。
Marcus, G. E., & Fischer, M. M. J. (1986).

注
(1) Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-263. エフェクチュエーション理論の基本的枠組みを提示した論文。
(2) hooks, b. (1995). Art on My Mind: Visual Politics. The New Press. 特に第3章では、アフリカ系アメリカ人の芸術実践の文化的アプロプリエーションについて詳細な分析がなされている。
(3) Vlach, J. M. (1978). The Afro-American tradition in decorative arts. Cleveland Museum of Art. アフリカ系アメリカ人の装飾芸術に関する最初の体系的研究。
(4) Mazloomi, C. (2014). And Still We Rise: Race, Culture and Visual Conversations. Schiffer Publishing Ltd. キルトを通じた文化的対話の可能性について論じた重要な研究。
(5) Lyons, M. E. (2007). Stitching Stars: The Story Quilts of Harriet Powers. Simon & Schuster. パワーズの作品の文化的・歴史的意義を詳細に分析。
(6) Arnett, W., et al. (2002). The Quilts of Gee's Bend. Tinwood Books. Gee's Bendのキルターたちの作品を包括的に分析した決定的研究。
(7) Sarasvathy, S. D. (2008). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Edward Elgar Publishing. クレイジーキルト原則について詳述した著作。
(8) Wahlman, M. (2001). Signs and Symbols: African Images in African American Quilts. Studio Books. アフリカの影響とその文化的意義について論じた重要研究。
(9) Glassie, H. (1999). Material Culture. Bloomington: Indiana University Press. 物質文化研究の方法論を提示した基本文献。
(10) Thompson, R. F. (1983). Flash of the Spirit: African and Afro-American Art and Philosophy. Random House. アフリカの美的感覚の継承について論じた古典的研究。
(11) Walker, A. (1982). The Color Purple. New York: Harcourt Brace Jovanovich. キルト制作を女性の解放と連帯の象徴として描いた小説。
(12) Holstein, J. (1991). Abstract design in American quilts: A biography of an exhibition. Louisville: The Kentucky Quilt Project. キルトの芸術的評価の転換点となった展覧会の記録。
(13) Christian, B. (1985). Black Feminist Criticism: Perspectives on Black Women Writers. Pergamon Press. ウォーカーの作品における女性の連帯の表象について分析。
(14) Morrison, T. (1987). Beloved. Alfred A. Knopf. キルトを記憶と継承の象徴として用いた代表的作品。
(15) Ringgold, F. (1995). We Flew Over the Bridge: The Memoirs of Faith Ringgold. Little, Brown and Company. 現代アートにおけるキルトの革新的展開について自伝的に記述。
(16) Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books. 文化的アプロプリエーションの理論的基礎を提供した古典的研究。
(17) Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? Marxism and the Interpretation of Culture. University of Illinois Press. 文化的実践の理論化における権力関係の問題を指摘。
(18) Glassie, H. (2000). Vernacular Architecture. Indiana University Press. 民俗的実践の研究方法論を確立した重要文献。
(19) Collins, P. H. (1990). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge. 黒人女性の文化的実践の政治性について論じた基本文献。
(20) Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books. 文化研究における「厚い記述」の方法論を提示。
(21) Anzaldúa, G. (1987). Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. Aunt Lute Books. マージナルな立場からの理論構築の可能性を示した革新的研究。
(22) Marcus, G. E., & Fischer, M. M. J. (1986). Anthropology as Cultural Critique. University of Chicago Press. 文化研究における倫理的問題について重要な指摘を行った研究。
参考文献
[上記の注で引用した文献に加えて]
Bendix, R. (1997). In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. University of Wisconsin Press.
Clifford, J. (1988). The Predicament of Culture. Harvard University Press.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited. American Sociological Review, 48(2).
Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford University Press.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. Doubleday.
論文2: エフェクチュエーション理論における文化的アプロプリエーションと「日本的経営」論の系譜
―経営学における異文化理解の問題に関する批判的考察―
1. はじめに
経営学における異文化理解の問題は、エフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルト概念の使用と、1970年代後半から1980年代にかけての「日本的経営」研究に共通する本質的な課題を提示している(1)。サラスバシーのエフェクチュエーション理論は、起業家の意思決定プロセスを説明する際に、「クレイジーキルト原則」として、「自社にコミットする意思を持っているすべての人々とパートナーシップを持とうとする」という原則を提示している(2)。
2. 「日本的経営」論の展開
1970年代後半から1980年代にかけて、アメリカにおける「日本的経営」研究は最盛期を迎えた。この時期の研究は、日本企業の競争力の源泉を日本の文化的特質に求める傾向が強かった(3)。
エズラ・ヴォーゲルの『ジャパンアズナンバーワン』(1979)は、この潮流を代表する著作である。ヴォーゲルは、日本の教育システム、官僚制、企業組織などを詳細に分析し、これらの制度がいかに日本の経済的成功に寄与しているかを論じた(4)。同様に、ウィリアム・オオウチの『セオリーZ』(1981)は、日本企業の人事管理手法をアメリカ企業に適用する可能性を探った(5)。
これらの研究の背景には、1970年代のアメリカ企業の競争力低下への危機感があった。特に自動車産業における日本企業の台頭は、アメリカの経営学者たちに深刻な問題意識をもたらした。リチャード・パスカルとアンソニー・エイソスによる『ジャパニーズ・マネジメント』(1981)は、この文脈で日本企業の経営手法を体系的に分析し、アメリカ企業への適用可能性を論じた代表的な著作である(6)。
しかし、これらの研究には共通の問題点があった。それは、日本の経営慣行を「独特の」ものとし、その文化的背景を過度に強調する傾向である。この傾向は、ジェームズ・アベグレンによる先駆的な日本企業研究にも見られる。アベグレンは「終身雇用」という概念を確立し、日本的経営の特質を体系的に分析したが、同時に日本文化の特殊性を強調するあまり、時として文化的決定論に陥る危険性をはらんでいた(7)。
この時期の「日本的経営」研究は、確かに日本企業の特徴を明らかにし、アメリカ企業に新たな視点をもたらした点で意義深いものであった。しかし同時に、文化的差異を固定的に捉え、その差異を過度に強調する傾向があったことも否定できない。この問題は、後のエフェクチュエーション理論におけるクレイジーキルト概念の使用にも通じる構造的な課題を内包していたのである(8)。
注
(1) Westney, D. E. (1987). Imitation and Innovation: The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan. Harvard University Press. 特に第3章では、文化的実践の移転における解釈の問題が詳細に論じられている。
(2) Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243-263.
(3) Vogel, E. F. (1979). Japan as Number One: Lessons for America. Harvard University Press. この著作は日本研究における文化本質主義の典型例として批判的に検討される必要がある。
(4) Mouer, R., & Kawanishi, H. (2005). A Sociology of Work in Japan. Cambridge University Press. 特に第2章では、日本的経営論における文化決定論的傾向が批判的に分析されている。
(5) Ouchi, W. (1981). Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Addison-Wesley.
(6) Pascale, R. T., & Athos, A. G. (1981). The Art of Japanese Management. Simon & Schuster.
(7) Abegglen, J. C. (1958). The Japanese Factory: Aspects of Its Social Organization. Free Press.
(8) Dore, R. (2000). Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons. Oxford University Press.
