
学校じゃない教育の仕事~森のようちえん~
こんにちは!
学校じゃない教育の仕事プロジェクトの米田と言います。
学校じゃない教育の仕事プロジェクト
今読んでいただいているあなたは、
学校じゃない教育の仕事に興味がありますか?
子どもを対象とした仕事をしたいけど、『学校の先生になりたい?』って聞かれると、なんだか違う気がする。教育学部ではないけれど、教育に興味があるんです。学校以外の教育の仕事ってどんなものがあるのだろう?
そんな学校じゃない教育の仕事に興味を持っているあなたのためのプロジェクトです。
学校じゃない教育の仕事をされている方々をゲストにお呼びして、オンラインで実践されている教育のお話や現在のお仕事に至った経緯などを参加者の方と作り上げていくオンラインイベントになります。
初回は、森のようちえん『里山ようちえん ふえっこ』

未就園児の親子を対象にした親子クラスと3~5歳の幼児を対象にした幼児クラスを開校する里山ようちえん「ふえっこ」は、笛路村(山南町谷川11区)の豊富な自然を生かし親子がのんびりと散策したり、村のおじちゃんおばちゃんたちから楽しみながら暮らしの知恵を学びます。
森のようちえん園長は、大阪からの移住者!?

ゲスト講師:竹岡郁子さん(里山ようちえん『ふえっこ』)
京都府長岡京市出身。2014年8月に結婚を機に丹波市へ移住。丹波市山南町にある笛路村の竹岡農園にて農家の嫁として暮らす傍ら、10年間大阪で保育士として働いた経験を活かしてふえっこを開校している。
おうちから森のようちえんを体験しよう!
オンラインイベント当日は、実際に森のようちえんが活動しているエリアを実際に案内していただきながら、皆さんからの質問にもお答えしていただきます。

ゲストに質問をぶつけよう!
・森の中のようちえんって、どんなことをしているのでしょうか?
・どんな子どもたちが来ているのでしょうか?
・なぜ、森のようちえんを立ち上げたのでしょうか?
そんな参加者の皆さんと共に作るオンラインイベントです!
イベント概要
日程:8/15(土)10:00~12:00
場所:オンライン(Zoomを利用します。)
定員:15名
内容:里山ようちえんふえっこ のオンライン探検
ゲストトーク、質疑応答
参加費:無料
お申し込みはこちら
↓ ↓ ↓
⬇︎You tubeチャンネルで子どもたちの様子が見られます⬇︎
⬇︎Twitterでも情報発信をされております⬇︎
自分が農家の嫁として、食べ物を種から育てること・食べてもらうことを通して、土に触れる楽しさや作物を育てることの喜びを実感することができました。
— 竹岡郁子@ふえっこえんちょう (@fuekkoikuko) March 23, 2020
今でも自分が子どもたちよりも自然に興味を持ち、楽しむことを大切にしています(^-^)
この自然に触れる面白さを保育士目線でつぶやきます♪ pic.twitter.com/9q6YbLU9J0
〜〜〜〜HPより引用〜〜〜〜
都会での保育士の生活から、
丹波の中山間地域の農家へ嫁ぎました。
百姓の嫁の傍ら、何か丹波でできることはないか、
自然が豊かなところで保育ができたら、
子どもたちと里山を活かした遊びがしたいという思いから、
平成28年4月NPO法人丹のたねの元、
里山ようちえんふえっこを立ち上げました。
結婚を機にこの場所に住み、フィールドを与えていただいたことで、自分にできることはないか?と考えました。
そして、幼稚園に勤めている間、砂場でずっと遊んでいる子、
用務員のおじさんについて回る子、
季節の変わり目にいち早く気がついて教えてくれる子、
(食べれる木の実や花の匂い、果物の収穫など)たちがいて、
ここで暮らすようになって、本来人間がもっている感性というか、
意識せずに行ってきたことが、子どもたちはもっているんだ、
畑で土を触る機会が増えて、砂遊びが好きな理由(自分自身が落ち着く)がわかったような気がしました。
こどもたちの本来もっている感性、ありのままの人間らしい姿、
ここでならこどもたちがそういう風に育っていってくれるのではないか、
また、ここには里山の大自然のすばらしい教材、
笛路村の温かい住人の方々、この地域資源があり、
それをを活かした保育をすることができたらという思いからです。
あとは、自分自身で
「さあ!私がやってみたいから、やるよ!!」
という感じで始めたのではなく、
この場所と、来てくれる子どもたちがいたから、
『始めてみようか?』
という感じがスタートです。
親子保育から始めたのは、
子どもが楽しい、と感じるにはまずお母さんが、安心して楽しんで、のんびりすごしてもらうことが大切なんじゃないか?と思い、お母さんと子どもとで、一緒に楽しむ親子保育としようとおもったからです。
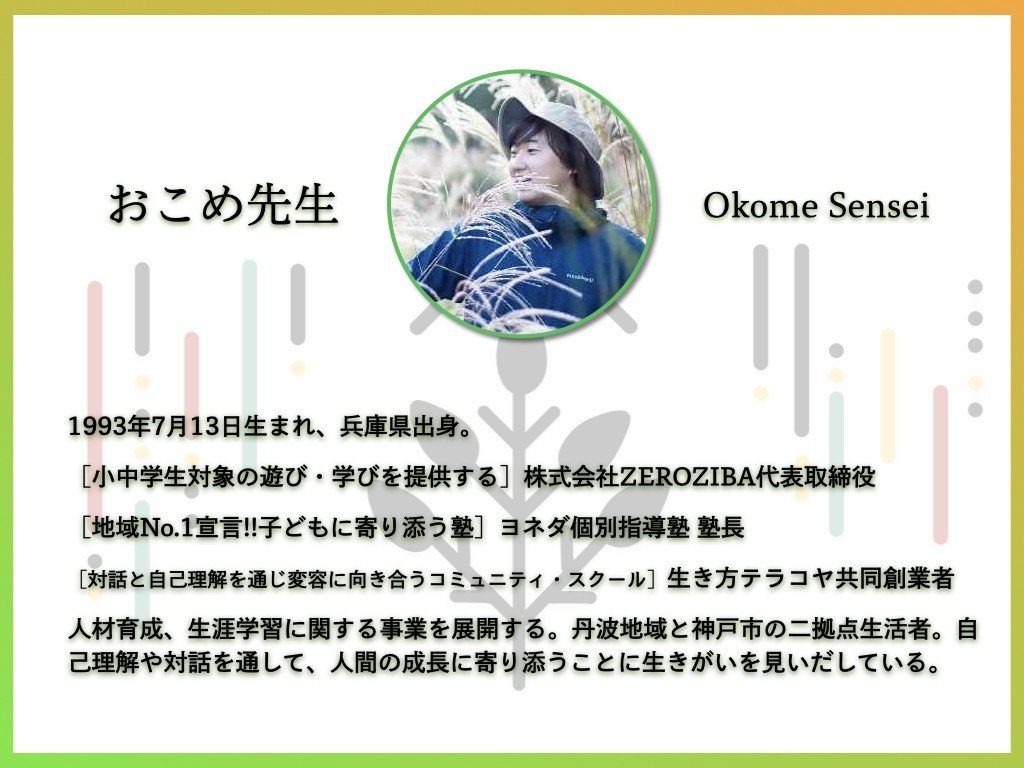
いいなと思ったら応援しよう!

