
講師への道 第1章 1対多数のデリバリースキル②講師自己紹介
研修業界における「魔の11分」とは
航空業界には「魔の11分」という言葉があります。これは航空事故が離陸時の3分間と、着陸時の8分間に集中していることに由来します。
研修業界で言えば「魔の11分」は開始から最初のセッションに入るまでの時間帯のことだと、私は痛感しています。着陸(終了時)は怖くありません。オープニングにはちょうど10分から12分くらいかかりますので、平均するとまさに「魔の11分」と言えそうです。理由は3つあると思います。
第一に、講師にとっての受講者情報が未だ少なく、周波数を合わせている最中だからです。講師固有のキャラクターにどのような味付け(テンション高めか、冷静沈着を貫くかなど)をすれば受講者の波長にフィットするか、未だ分からない時間帯だからです。
第二に、受講者は未だ研修内容についてほとんど未知の状態で、期待やコミットが未だ高まっていないからです。要するに「場が温まっていない」状態です。温まるまでは、気を揉む時間帯となります。
受講者の「敵対心」が、講師に緊張を強いる
そして第三は、講師に対する「警戒心」や「敵対心」が解けていないからです。大袈裟だと、思われますか?
私の経験では、多少感じる程度で済む場合もあれば、稀にあからさまに態度に表れている受講者に遭遇することもあります。
少し大げさに言うと、「忙しいのに無理やり集められて、どうせつまらない研修受けさせられるんだろう。どこの誰だかわからないヤツが、現場実態に即さない教科書的なことや、分かり切ったことを一方的に垂れ流すのだろう」というムードです。トレーニングを「ありがたい機会」と思って参加してくれる企業や個人は少数派です。
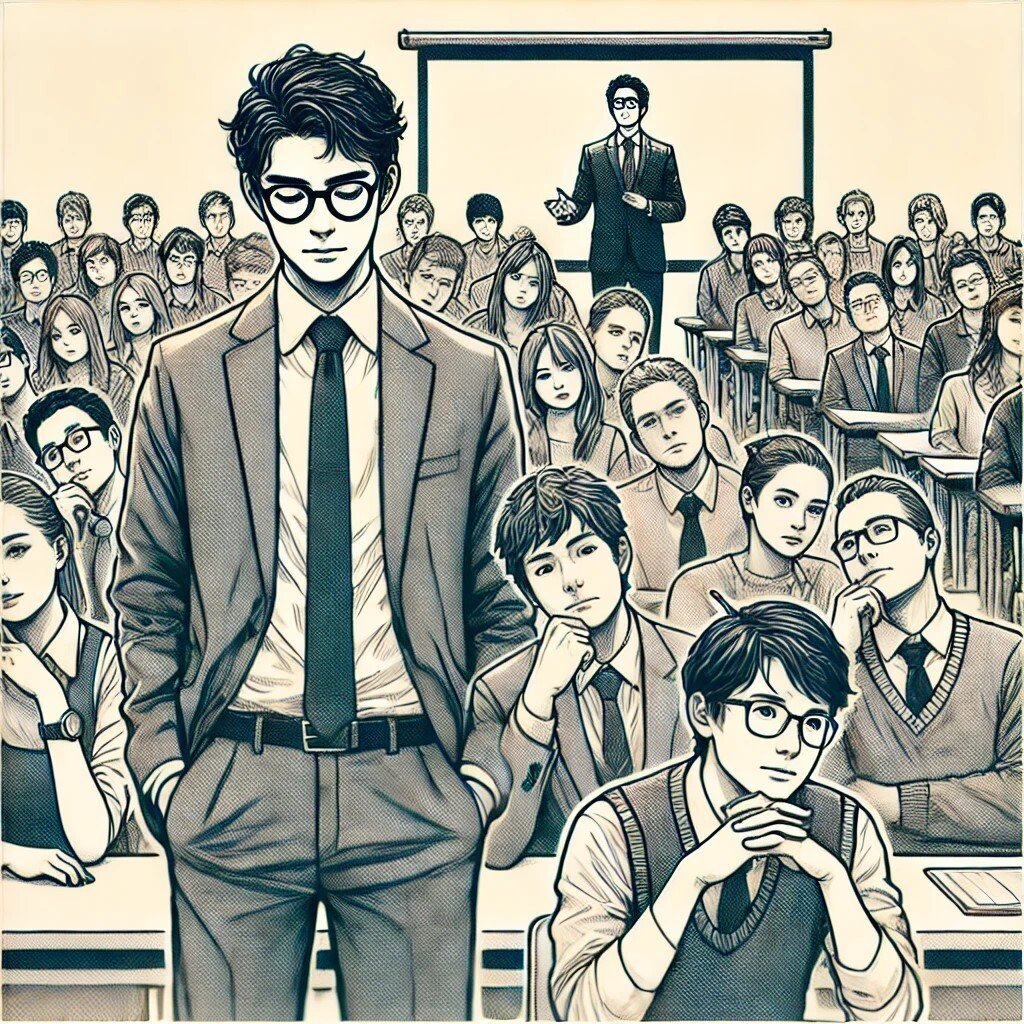
では、これら3つの悪条件をどうやって解消するか。行うべきことは順に以下3点になります。
意図をもって自己紹介を行う
研修のねらいやラーニングジャーニーの全体像を示す
心理的安全性を担保する
1.意図をもって自己紹介を行う
まずとにもかくにも、受講者の貴重な時間を預かる者が「何者なのか」をはっきり伝える必要があります。親近感を感じさせたり、期待感を高めさせたり、できるならば信頼感を少しでも獲得したいです。聴く耳を持ってもらわないと、何も始められないからです。
ですが、冗長になると逆効果です。せいぜい3分から長くても5分以内に収めます。私の場合は、人となりや大事にしている職業観など「自分らしさ」をお伝えできる、アテンションを引く強めのエピソードを複数用意するようにしています。職歴やビジネスでの実績・成果が素晴らしい講師ほど、あえて失敗談から自己開示する方が多い気がします。意図を感じますね(笑)
どのエピソードで自己紹介するかは、研修の中身とのマッチングを考えて仮決めしておきます。そのうえで、受講者から感じ取る雰囲気に合わせてアジャストしています。
なので、事前の準備として顧客企業のビジネスや受講者の日常業務をできるだけ調べますし、対面集合研修なら早めに会場入りした受講者とコミュニケーションを取って情報収集しています。
「そんなことまで知っているのか」というサプライズを受講者に与えられれば、心理的な距離感がぐっと縮まります。もちろん研修冒頭なので「そんなこと」のチョイスは、ポジティブなものとします。
2.研修のねらいやラーニングジャーニーの全体像を示す
次に対面集合にしろオンラインにしろ、「何のために集められたのか」というねらいや意義をはっきり示す必要があります。大抵事前に、事務局様がご案内されていますが、あらためて講師の口からお伝えする必要があります。
ここで奇をてらうのは避けた方がいいと思います。スライドに書いた研修のねらいや目的を丁寧に読み上げるだけでも良いと思います。
もしやるなら、自分もこの研修は大変意義があると思っているということを、講師目線ではなく受講者と同じ一人のビジネスパーソン目線でしみじみ語ることでしょうか。冒頭の自己紹介が上手くいっていて、ある程度の信頼感を獲得できているなら、なお効果的だと思います。

3.心理的安全性を担保する
オープニングの締めくくりは「心理的安全性」の担保です。心理的安全性とは、エイミー C. エドモンドソンが提唱した概念で「組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のこと」です。Googleの実験によると「心理的安全性の高いチームは生産性が高い」と実証されていて、昨今注目されている概念です。この概念は研修の運営にも有効です。
そもそも研修で扱うテーマ、ビジネスにおける成果創出に向けたテーマは、自然科学の領域と違って唯一絶対の正解が存在しにくい領域です(会計学や統計学など一部を除く)。
誤解を恐れずに言えば、自分がそうだと信じて実行し、成果が上がるならばそれでよいのです。もちろん再現性は高くなければなりません。各人が意見や考えを率直に交換し合って、刺激し合って、気づきが得られればよいのです。
その状態に持っていくには、性別、年齢、職歴、職場における上下関係すら一旦脇に置いて、意見交換や議論が活性化しなければなりません。そうでなければ、集まる理由がなくなるからです。
講師は以上のことをオープニングで高らかに宣言し、体現する必要があります。さらに受講者にも心理的安全性の高い場づくりを促し、もしそれが損なわれる場面があれば、介入する必要もあります。

以上、「魔の11分」を乗り切る工夫です。11分間、ほぼ一方的にしゃべることになりますので、最初のセッションはアイスブレイクとしてのグループ内自己紹介か、軽めのテーマでのグループ討議など、参加のハードルがさほど高くない、動きのあるセッションにつなげていきます。その理由は、第4章 インストラクショナルデザイン(ID)で詳述いたします。
