
#5 ACPについて僕の思うこと
先週、私はまた自分の利用者が亡くなりました。
ご飯が食べたい想いの強い、非常に低栄養で虚弱状態の方でした。
呼吸が苦しいと言うことで入院し、そのまま病院で亡くなられました。
私はその方と長い付き合いという訳では無かったので、
そこまで深くその利用者様の「死」の時の話はできていませんでした。
付き合いとしては2ヶ月程度とかなり短い期間でしたが、
私としても思うところがたくさんあったご家庭でした。
本日はACP(Advance Care Planning):アドバンスケアプランニングについて、
私が普段、訪問看護の現場で感じることについて述べたいと思います。
ACPとは?
ACPの本質としているところ
ACPの実際
ACP(アドバンスケアプランニング)とは
定義について少し前提を整理していきたいと思います。
ACPについては厚生労働省の資料にて説明されています。
2018年にはACP愛称選定委員会が「人生会議」として愛称を打ち出し、
この取り組みを広めようと取り組んでいますね。
医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、 人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思を その都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人と の話し合いが繰り返し行われることが重要である
(人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインより抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf
そして、ACPにおけるプロセスの中で、「リビングウィル」という言葉(文書)も登場します。ここも整理しておきます。
回復の見込みがなく、すぐにでも命の灯が消え去ろうとしているときでも、現代の医療は、あなたを生かし続けることが可能です。人工呼吸器をつけて体内に酸素を送り込み、胃に穴をあける胃ろうを装着して栄養を摂取させます。ひとたびこれらの延命措置を始めたら、はずすことは容易ではありません。生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから、医療者が躊躇するのです。
「あらゆる手段を使って生きたい」と思っている多くの方々の意思も、尊重されるべきことです。一方、チューブや機械につながれて、なお辛い闘病を強いられ、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」と思っている方々も多数いらっしゃいます。「平穏死」「自然死」を望む方々が、自分の意思を元気なうちに記しておく。それがリビングウイル(LW)です。
https://songenshi-kyokai.or.jp/living-will
(公益財団法人日本尊厳死協会ホームページより抜粋)
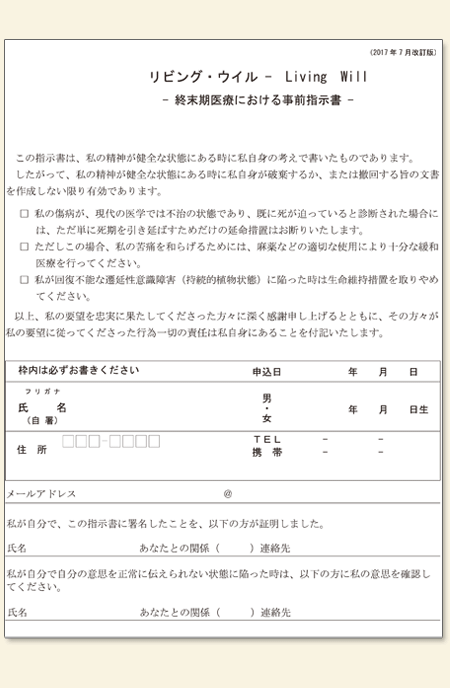
自分が意思表示できなくなった状況で、意に添わない、ただ単に死の瞬間を引き延ばす延命措置を受けずに済むように、人生の最終段階(終末期)を迎えたときの医療の選択について事前に意思表示しておく文書のことです。
表明された意思がケアに携わる方々に伝わる様に、自分らしく誇りを持って最期を生きられる様にするものです。
ACPの本質とするところ
よし、分かりました!
じゃあ悪化した時は人工呼吸器はつけませんね?胃瘻は入れませんね?
んで、無理な心臓マッサージなしの延命処置なしと。
OK了解です!ではまたお大事に!
↑
こんなポップな先生いないと思いますが、こんな感じの診察だったら嫌ですよね。。
そして、これだけ決めればいいんでしょ、と言うようなことでもない様に思います。
ACPは、
前もって受けたい医療やケアの内容を話し合っておく「プロセス全体」のことなんです。
なので、人工呼吸器をつけるか?胃瘻を作るか?最後どこで死にたいのか?
それを明らかにすること自体は目的ではありません。
作家の開高健氏の著書で、「輝ける闇」と言う書籍があります。
その中で開高氏は、
「ライオンはライオンと名付けられる前は、得体の知れない凶暴な恐怖であった。けれど、それをライオンと名付けた時、凶暴ではあるが一個の四足獣にすぎないものとなった」
と述べています。
そのことに対して、腫瘍内科・緩和ケア内科医の西智弘先生は、「死」に関して先生の著書の中でこう語られています。
昔から「死」は人間にとって凄まじい恐怖でした。
先人達は極楽浄土と言う概念を作って、絵を用いたりストーリーを描いたりして、
何とか人間の意識の中で、「死」と言うものを扱える様に格闘してきました。
しかし、いくら「死」と言う言葉を当て嵌めても、
私たちは全くこの「死」と言うものを取り扱えるようになってはいません。
https://pluscare.thebase.in/items/29980417
私は西先生のお話を聞いてから、この著書を拝読し、非常に納得しました。
私は終末期の利用者様と向き合う時、めちゃくちゃ悩んで苦しんで辛いと思っていました。今でもそうです。
でもなるほど、それでもいいんですねと思える、少し救われる著書でした。
人間が「死」の恐怖との格闘の歴史の中で、たくさんの言葉が生まれた結果が、
この「死」と言う言葉なんですね。
そして、「死」と言う言葉があるから意識の中にはイメージできるようになったけど、その概念は未だ取り扱えてはいないと言うのが西先生の考えです。
「死」が取り扱えない概念である以上、そこに向かっていくプロセスも明確にできないはず。
だから、何かを決めておくと言うのは
悪くはないけども、本質的なことではないんです。
なぜなら、刻一刻と状況は変わって、気持ちも変わるからです。
人生の最終段階に近づくほど、終わりが見えてリアリティのある判断が要求されるからです。
文書を取ることはメモの様なものです。
何も解決できない苦しい時間もあるだろうけど
何をするべきか曖昧なこともあるだろうけど
その曖昧な時間に耐えて
たくさんの話し合いの中で
価値観や人生観を共有して
一緒に最後まで歩んでいきましょう
これが本質かなと思っています。
ACPの実際
冒頭の私の利用者様は、果たして納得できる「死」だっただろうかと、
今非常に悩ましく思っています。
奥様は「そんなに腹減ったなら餅でも食って死んじまえっ!!」
なんて発言が飛び出るくらい、ストレスの絶頂でした。
本人はゼリーでもなんでもいいから、口から何か食べたい。
私が関わり始めた時には既にその事ばかりで、まともに物事を判断できる状態ではありませんでした。
そして入院ししばらくは持続点滴で療養していた様ですが、
3ヶ月程で肺炎を起こし亡くなられました。
私はこの方のように
弱るまで方針決めていない→弱ったら本人意思表示不可→急変時は蘇生しないと家族がいう→でもやれる範囲でやって欲しいから点滴で長期療養→肺炎で病院内で死亡
みたいなケースをよく目の当たりにします。
ここにもっと早く、自分の人生の幕の終わり方について考える機会があれば、
自分らしい死に方、死に場所が選択できたのかもしれない。
そう思ってしまいます。
日本人は意思表明を鮮明に打ち出さない独特の精神風土があります。
「家族に任せる」
と言うやつです。
しかし振られた家族は大抵「お医者さんにお任せします」となります。
「家族の死を自分が決めたくない」という心情もあるでしょう。
そうなれば延命措置に走ることは必然ですよね。本人にとっては意にそぐわない余計な苦しみを味わう結果になる可能性があります。
私の担当していた利用者様がどの様な最後を迎えたのか、
関係が途絶えてしまった今は知ることができません。
しかし、ご本人の意にそぐわない形に向かってしまう事がなるべく無いようしたいものです。
振り返りの方法としては「デスカンファレンス」と言う取り組みもあります。
私の所属している訪問看護ステーションでも行います。
こういった振り返りの機会をとり、
日々利用者様とあとで後悔しないように向き合っていきたいものです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
岡田壮司
