
【もしや丸文字のルーツ!?】難道開通!万歳!摩崖刻『開通褒斜道刻石』
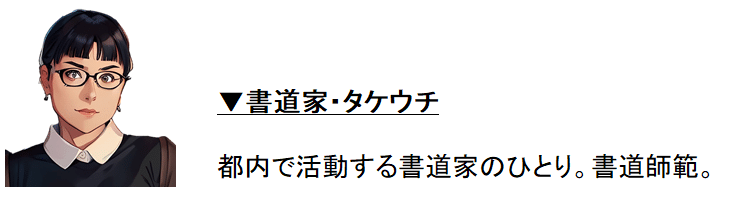

書道超有名古典シリーズ↓↓↓
「九成宮醴泉銘(欧陽詢)」「蘭亭序(王羲之)」「祭姪文稿(顔真卿)」
今回はちょっとマニアック古典!「開通褒斜道刻石」!
開通褒斜道刻石との出会い
開通褒斜道刻石、かいつうほうやどうこくせき、と読みます。
まずは筆者の秘蔵?写真をお見せしましょう↓↓

拓本は、石碑に墨を塗ってその陰影を写し取ったもの。この拓本にずきゅんと来てしまったのが筆者・タケウチであります。
書道、と言うと、
どでかい筆でビチャっとやっているか、
険しい顔つきで無言で漢文を書いているか、
はたまた雅に和歌をサラサラっと書いているか、
いずれにしても格調高めの面をしてやってくるイメージがあるのではないでしょうか。
でもこんなのあるよ!とお伝えしたい可愛らしい文字が「開通褒斜道刻石」であります。
大学の書道学科の学生さんたちに、特に人気のある古典なんだとか!
この話のYouTube版はこちら↓↓
開通褒斜道刻石プロファイル
時代:後漢(25-220年)西暦66年の刻(永平9年←文の出だしに書いてある)
※日本は弥生時代(文字の存在すら微妙な頃)
大きさ:130.8×263.2cm(1字は15cm~18cmほど)
書体:隷書体(古隷)
※草書体が作られ始めた頃。楷書体はまだ存在しない。
内容:蜀に至る難道を、四年がかりで延べ76万人を動員して完成したのを記念したもの(文字通り開通記念)
文字量:16行(1行は5字~11字)
※発見されたのは刻された時から1000年以上も後のため、剥落して解析不能な文字もある。
下の画像は、天来書院さんが拓本からペンで書き起こしたもの。(見やすい!わかりやすい!やっぱりカワイイ!)

摩崖刻(まがいこく)
何だか怪物でも登場しそうで禍々しいですが、摩崖刻とは岩壁に刻まれた絵や文字のこと。「開通褒斜道刻石」は摩崖刻です。
この頃、筆と墨は存在していたと考えられていますが、一般的な紙と呼ばれるものがちょうど発明されるかどうかのところ。無論紙はまだまだ普及していないため、文字を残すのは石に直接彫り付けるのが主流でした。
岩壁は当然ながら平面ではなく、ごつごつとした岩肌。そこに文字を彫りつけるので、文字の大きさや1行の文字量が不揃いであると考えられます。
開通褒斜道刻石の現在
1970年代、ダム建設により水没してしまうとのことで、岩を切り出して漢中市博物館に移されています。
遺跡発掘!文字が出てくる喜び!
「開通褒斜道刻石」は1200年頃に初めて発見され、一旦忘れ去られて、またその600年後の1700年代後半に再発見されました。
そもそも初発見でも作られてから1000年以上、そしてまた600年・・・随分と放置されたものです。そしてよく残っていてくれた!
しかし、遺跡発掘隊からすれば、切り立った岩に文字を発見するのは無類の喜びであることが筆者には容易に想像できます。だって、絵は概念的なものを伝えるけれど、文字は記号そのものなので、書いてある内容が分かる!すなわち、古代の人の言っていることが分かる!ということ。(古代の言葉を理解できる人なら、だけれども)
自分と同じ種類の動物・人間が成したものがそこにある。何なら発見者はそれを触ることもできただろう。なんだかそれだけでも感動的な気持ちがしませんか。

こんな味わい深く温かみと可愛らしさのある文字を発掘したい!
ちょっと違うけれど、漫画「賭博黙示録カイジ」の鉄骨渡りのシーンを思い浮かべてしまいます。

オレは…佐原を救えない……佐原もオレを救えない……
絶望的に離れ離れだ……!
なのに……なんだ……?この温もりは……!
胸から湧いてくる……この温かさ……感謝の気持ちは……
佐原が……佐原がただ……そこに在るだけで……救われる……!
奴が目の前にいないその寒々しさを考えたら……
今……見える存在はまさに救い……!希望そのもの……!
1980年代に一世を風靡した丸文字に通ずる!?
こちらをもう一度見ていただくと分かると思いますが、昔1980年代頃に流行った丸文字に似ている気がしませんか?

こんな感じの↓↓

昭和50年代。女子の文字は丸文字。文字も可愛く書きたーい♪ってことで流行した。聖子ももちろん一発で分かる独特の丸文字。でも神田正輝と離婚するころには普通の字になってた。聖子も大人になったのだと思ったw明菜の昔の丸文字もインパクトあったな。画像の三枚とも聖子、最後は参考画像。 pic.twitter.com/LN4xPtamjM
— 懐かしい昭和時代(女性) (@natsukashi__) July 5, 2019
丸文字は基本が横書きでノートの罫線の幅にきっちり収める(つまり文字の縦幅がほぼ一定)特徴があり、それは「開通褒斜道刻石」の文字とは異なりますが、角が取れた丸っこく可愛らしい字体という点では似ています。
当時の女子中学生、女子高校生たちは「開通褒斜道刻石」を知っていた・・・!?わけは無いと思いますが、何だか近しい雰囲気や精神性を感じるのは筆者だけではないのではないでしょうか。
うーん、やっぱり好きだなあ「開通褒斜道刻石」
noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!
フォローも感謝感激!
※毎週火曜19時更新
『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いたします↓↓↓
○YouTube
noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!
フォローも感謝感激!
※毎週火曜19時更新
『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓
○YouTube
いいなと思ったら応援しよう!

